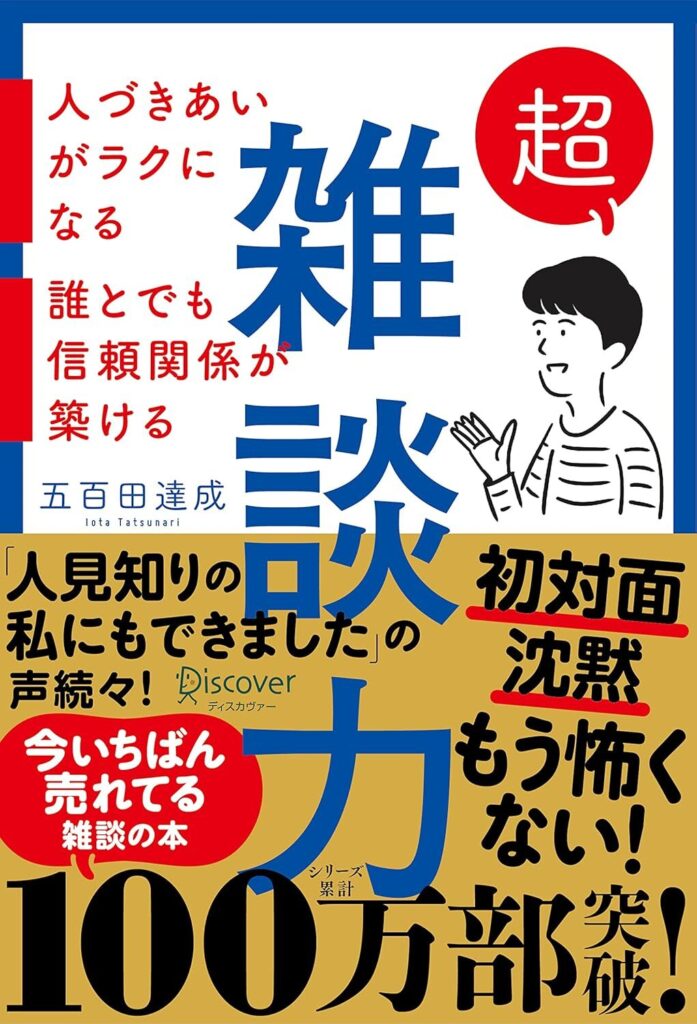
「沈黙が気まずい」「話が続かない」「何を話せばいいのかわからない」――
そんな“雑談の悩み”を抱える人にこそ手に取ってほしい一冊があります。
五百田達成(いおた・たつなり)氏によるベストセラー『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける』は、シリーズ累計100万部を突破し、テレビやYouTubeでも話題となった「雑談の教科書」。本書は、話し上手になるための本ではありません。むしろ、「話さなくても、うまくいく技術」を身につけるための実用書です。

雑談がうまくできないのは、あなたのコミュニケーション能力が低いからではなく、「雑談には、雑談ならではのルールがある」ことを知らなかっただけ。
本書では、誰でもすぐに実践できる“7つの基本ルール”を軸に、初対面・知人・ビジネスシーンなど、場面別のテクニックを多数紹介しています。
話すことが苦手な人も、人見知りの人も、読後には「これなら私にもできそう」と思えるはず。
雑談の苦手意識を手放し、人との関係をラクに、そして自然に築いていけるヒントが、ここにはあります。

合わせて読みたい記事
-

-
会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力
「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...
続きを見る
書籍『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける』の書評

人との関係を円滑に保つには、「話し方」や「伝え方」以前に、場に応じた適切な“距離感”と“空気の読み方”が求められます。特に、沈黙が気まずくなりやすい微妙な関係性――初対面の相手、職場の上司、義両親、ママ友、取引先の担当者など――との「雑談」は、多くの人がうまくこなせずに悩んでいるテーマです。
本書は、そんな「何気ない会話なのに、なぜかうまくいかない」状況に答えを出してくれる、極めて実用的な会話指南書です。以下の4つの視点から、その全体像を詳しく掘り下げていきます。
- 著者:五百田 達成のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
これらの要素を理解することで、本書がなぜ今、これほどまでに評価されているのかが明確になるでしょう。
著者:五百田 達成のプロフィール
五百田達成(いおた・たつなり)氏は、東京大学教養学部(アメリカ研究)を卒業後、角川書店で編集者としてキャリアをスタート。さらに広告業界最大手の博報堂や、そのシンクタンクである博報堂生活総合研究所でプランナーとして活躍しました。つまり、出版・広告という「人に伝える・動かす」最前線で研鑽を積んできた人物です。
その後、心理カウンセラー(GCDF認定キャリアカウンセラー)として独立し、現在は作家・講演者・メディア出演者として幅広く活動。恋愛、夫婦、親子、職場など、さまざまな人間関係におけるコミュニケーション課題をテーマにした著作を数多く出版しています。代表作に『察しない男 説明しない女』『話し方で損する人 得する人』『ベスト・パートナーの話し方』などがあり、累計発行部数は120万部を突破。
五百田氏の強みは、アカデミックな心理学の知見と、現場主義的な観察・分析が見事に融合している点にあります。頭でっかちな理論ではなく、誰でも現実のコミュニケーションに応用できる「型」として整理されていることが多くの読者に支持されている理由です。

本書の要約
『超雑談力』の核心にあるのは、「雑談は、普通の会話とはまったく違う」という明確な定義です。これはつまり、日常的なおしゃべり(友人との気楽なトーク)や、仕事上の報告・議論とは別に、第三の会話ジャンルとして“雑談”を切り分けて考える必要があるという提案です。
多くの人が雑談を苦手に感じるのは、無理に面白い話をしようとしたり、会話を情報交換の場と誤解したり、ビジネス会話のように正確さを重視したりするからです。しかし、そうしたやり方では雑談が不自然になり、相手との距離感も縮まりません。
そこで本書は、「雑談には雑談に適した技術と姿勢がある」として、NG例とOK例のペア解説という実践的な構成で、誰でも学べるように設計されています。
たとえば以下のような例が典型です。
- 「がんばって面白い話をしよう」はNG → 「会話のラリーを続ける」がOK
- 「天気やニュースを話す」はNG → 「自分のエピソードや経験談を語る」がOK
- 「なぜ?(WHY)」で理由を聞くのはNG → 「どう?(HOW)」で気持ちや背景を聞くのがOK
こうした改善点を少しずつ取り入れていくことで、誰とでも自然な距離で、ストレスなく雑談ができるようになるのです。

本書の目的
この本が目指しているのは、「雑談を上手くすること」ではありません。それは、会話を通じて“信頼関係を築ける人”になることです。つまり、話のうまさではなく「人との距離を縮める力」を育てることに主眼が置かれています。
人は、あらかじめ親しい人とであれば、会話がうまくいくのは当たり前です。しかし本書が取り扱っているのは、親しくもなく、仕事仲間でもない、どちらつかずの関係性の相手。たとえば初対面の相手、義実家、ママ友、上司などです。こうした関係では、誰しも一定の“緊張”や“気まずさ”を感じがちで、そのストレスが人間関係全体を苦しいものにしてしまいます。
そこで重要になるのが、「雑談の設計図」。本書は、どのタイミングで何を話し、どのようにリアクションを取り、どう切り上げればいいのかまでを“型”として整理しています。話題を変えるフレーズ、身振りの使い方、否定せずに共感する技法など、会話に不安がある人でも実行可能な内容です。
つまり、雑談を“才能”ではなく“スキル”として身につけることが、この本の最大の目的なのです。

人気の理由と魅力
『超雑談力』がここまで広く受け入れられ、ベストセラーとして長く読み続けられているのには、以下のような理由があります。
NG/OKの構成で理解しやすく、真似しやすい
多くの会話本が“理論”や“原則”を語る一方で、本書は「こんな言い方は避けよう」「代わりにこう言おう」という具体的な場面で構成されており、読んだその場で使えるレベルの実用性があります。
誰もが経験しているシーンが題材
雑談にまつわる困りごとは、特別な人に限らず誰しもが感じていることです。だからこそ、「あ、これ自分もやってる……」という共感ポイントが多く、読みやすく、気負わずに読了できる点が大きな強みです。
メディア露出による信頼性と話題性の高さ
2024年には日本テレビ『千鳥かまいたちアワー』や、登録者145万人を超えるYouTubeチャンネル『PIVOT』でも紹介され、「面白いのにためになる」と話題に。口コミやSNSでも広まり、“会話に悩んでいた人の人生を変えた一冊”として評価されています。
「凡人」と「達人」の比較で自己診断しながら読める
単なる情報提供ではなく、読者自身が「自分はどのタイプか?」を振り返りながら進められる点も好評です。まるで診断テストを受けるような感覚で読めるため、能動的に学びが進む仕組みになっています。
実践→実感→定着の流れが短い
実際のレビューには、「読んだ直後のランチミーティングで実践してみたら、空気が柔らかくなった」「“あいうえお”リアクションで盛り上がった」など、読後すぐに効果を実感した声が多数寄せられています。

本の内容(目次)

本書『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける』は、雑談を「第3の会話」として定義し、その技術を誰でも身につけられるように段階的に解説した実践書です。読者の状況や人間関係の種類に応じて、全4章の構成となっており、それぞれに実用的な会話術が詰め込まれています。
以下の章立てで展開されており、場面ごとに異なる悩みに応じた対処法が学べるのが本書の魅力です。
- 第1章 基本の7ルール これさえ知れば怖くない!
- 第2章 初対面編 もう緊張しない。ドギマギしない。
- 第3章 知人/飲み会編 人づきあいがラクになる!
- 第4章 職場/ビジネス編 小さな会話が信頼につながる
どの章も、NG行動とそれに代わる実践的な対応が対比形式で紹介されており、読みながら即座に「これは自分の課題だ」と気づき、改善できる設計になっています。
それぞれの章の内容については、次項以降で順に詳しく見ていきましょう。
第1章 基本の7ルール これさえ知れば怖くない!
この章では、雑談をうまく行うために必要な「型」を7つのルールとして明確化しています。特徴的なのは、「面白い話をしよう」「話を広げよう」といった一般的な発想を真っ向から否定している点です。代わりに提示されるのは、会話のリズムを心地よく保ち、相手との関係性を自然に築いていくという戦略です。
たとえば、笑わせる必要はない、情報を提供する必要もない、と明言されます。大事なのは、共感を軸にした応酬のテンポと、気まずさのない終わらせ方です。また、話が途切れたときは別の話題に切り替えるのではなく、自分の経験など身近なトピックに“戻す”ことで、会話の流れを保ちやすくなるというアプローチも紹介されています。
言い換えれば、雑談は「盛り上げる」より「繋げる」、そして「伝える」より「共有する」ことが重視されるのです。ルールを知ることで、雑談の場面で自信を持てるようになります。

第2章 初対面編 もう緊張しない。ドギマギしない。
この章は「初対面の相手との雑談」に特化しており、最も多くの人がつまずく“会話の入り口”をスムーズにするためのノウハウが詰まっています。
まず強調されるのは、ありきたりな「はじめまして」や「趣味は何ですか?」といった定型的な質問では、心の距離は縮まらないという点です。かわりに、「こんにちは」「最近ハマってることはありますか?」など、相手のパーソナリティが表れる問いを用いることで、自然なやりとりが始まります。
さらに、「共通の話題」よりも「相手が語りやすいテーマ」を探ること、あいづちは“さ・し・す・せ・そ”ではなく感情に訴える“あ・い・う・え・お”リアクションを使うこと、など独自のアプローチが豊富に紹介されています。
雑談の目的は“情報の交換”ではなく“空気を合わせる”ことだと知るだけで、初対面での緊張はかなり軽減されるでしょう。

第3章 知人/飲み会編 人づきあいがラクになる!
ある程度顔なじみのある相手や、飲み会などの緩やかな社交シーンでの雑談を円滑にする技術が紹介されるのがこの章です。親しさの段階が中途半端であるがゆえに生まれる気まずさや誤解に、どのように対処すればよいのかを具体的に解説しています。
「相手の話にアドバイスを返すのではなく、共感を優先する」「記憶が曖昧な話題は曖昧に続けず、素直に聞き直す」といった姿勢が推奨されており、気を使いすぎるよりも、率直で穏やかな応対のほうが関係性を良好に保てると示されます。
また、話題を常に前に進めようとせず、状況に応じて話を戻すことで、相手の気持ちや話の深掘りにつながるという“リズム感”のある対話術も紹介されています。雑談において主導権を握ろうとせず、空気を温める立場に徹することが、むしろ場をうまく回す鍵となります。

第4章 職場/ビジネス編 小さな会話が信頼につながる
最終章では、職場やビジネスの場面での雑談がテーマとなります。ここでの会話は「成果を出す」ためのものではなく、「関係性を築く」ための潤滑油としての役割が重視されています。いわゆる“仕事以外のひとこと”が、相手との心理的な距離を大きく左右するという視点です。
たとえば、部下や後輩との会話ではフラットに話すよりも、一定の上下関係を保ちながら安心感を提供する態度が有効だとされます。また、雑談の場として飲み会ではなく、ランチやお茶の場が推奨されるのも特徴的です。これは「閉ざされた場」よりも「開かれた場」での対話が、より自然で信頼感を生みやすいからです。
さらに、話題を変える際には「話変わりますけど」というワンクッションを入れる、返答を曖昧に保留せず即答するなど、細やかな言語技術も数多く提示されています。細部にこそ、プロフェッショナルな信頼構築のヒントが隠れているというメッセージが本章の要です。

対象読者

本書は、「雑談」という一見ささいに思える行為に対して、戸惑いやストレスを抱えている人たちに向けて書かれています。会話のテクニックやノウハウを紹介するだけでなく、読者それぞれが直面する具体的な悩みに応じて、使えるアプローチを提案しています。
とくに、次のような方々にとって、本書は実践的な助けとなるでしょう。
- 雑談が苦手で沈黙に気まずさを感じる人
- 営業や接客での雑談に悩んでいるビジネスパーソン
- 義実家・ママ友・上司との世間話にストレスを感じている人
- 初対面で何を話せばいいか困る人
- 会話を盛り上げたいが話題の選び方がわからない人
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
雑談が苦手で沈黙に気まずさを感じる人
誰かと話していて急に沈黙が訪れると、不安や焦りを感じてしまう。そうした場面が苦手で、できれば避けたいと感じている人にとって、本書は「沈黙に動じない話し方」のヒントが満載です。
著者は、雑談とは“普通の会話”とはまったく異なる独自の技術であると明言します。だからこそ、うまくいかないのは当然であり、自己否定する必要はありません。
沈黙を避けようと無理に話題を変えるのではなく、少し間を空けてから“自分に近い話題”に引き戻す。そんな具体的なやり方が紹介されており、会話の途切れを恐れずに自然に対応できるようになります。

営業や接客での雑談に悩んでいるビジネスパーソン
仕事上の関係者と話す際、業務とは関係ない雑談が求められることがあります。とはいえ、「おもしろい話」をしようとして空回りしたり、「話すことがなくて沈黙が続く」などの経験は誰にでもあるでしょう。
本書では、商談の合間や打ち合わせ前後に自然な関係を築くための「雑談力」を、シンプルなルールに分解して説明しています。とくに、“情報交換”よりも“気持ちのやりとり”を重視する考え方は、心理的な距離を一気に縮める上で非常に有効です。
相手に「この人と話すのは心地いい」と思わせることが、結果的に信頼関係と成果を生み出します。

義実家・ママ友・上司との世間話にストレスを感じている人
適度な距離感を保ちたいけれど、無視もできない。そんな相手との雑談ほど、精神的に消耗しがちです。義実家では無難な話題を探し、ママ友には気を使いすぎ、上司との会話は一語一句に神経を尖らせる……。
本書では、そのような関係性で役立つ“柔らかくて攻撃性のない話し方”を提示します。具体的には、「事実ではなくニュアンスで話す」「共感は短く、反論は避ける」「会話を進めるよりも“戻す”」といったアプローチが紹介され、いずれも心理的負担を軽減する工夫に満ちています。
無理をせずに“関係をつなぐ”方法がわかることで、気まずさや気疲れから解放されます。

初対面で何を話せばいいか困る人
はじめて会う人と何を話せばいいか分からず、緊張して空気が固まってしまう。その不安を解消したい人にとって、本書の「初対面の雑談マニュアル」は極めて有効です。
“名前の由来を聞く”“共通の興味を探る”“趣味ではなく「最近ハマっていること」を聞く”など、よくある会話のテンプレートを“心の距離を縮める型”に変えるテクニックが丁寧に解説されています。
また、いきなり相手に話を振るのではなく、「少しだけ自分の話をしてから相手に戻す」方法も紹介されており、プレッシャーを軽減しながら自然な会話の流れを作ることができます。

会話を盛り上げたいが話題の選び方がわからない人
「もっと会話を盛り上げたいけれど、何を話せばいいか毎回悩む」——そんな人にとって、本書の提案は非常に具体的で使いやすい内容です。
まず、本書では“面白さ”よりも“共感”や“共通の感覚”に重点を置くよう勧めています。そのため、天気やニュースのような無難な話題よりも、“最近の自分の小さな体験”や“相手の何気ない仕草へのポジティブなコメント”の方が効果的です。
また、“盛り上げる”とは、会話のテンポとラリーを保つことだと定義されており、「質問の投げ方」や「共感の返し方」にも実践的な指針が示されています。

本の感想・レビュー

雑談に「第3の会話」という視点
私は普段、営業職で多くの人と接しています。話すこと自体には抵抗がないものの、なぜか“雑談”となると気が重くなる。打ち合わせの冒頭や終了後、アイスブレイクとして話しかけるべきだと頭では分かっているのに、いざとなると何を話していいか分からない、会話が続かない、気まずくなってしまう——そんな悩みをずっと抱えていました。
そんな中でこの本と出会い、冒頭に出てくる「雑談は、普通の会話とはまったく違う“第3の会話”」というフレーズに衝撃を受けました。これまで私は、雑談も「友達との楽しいおしゃべり」か「ビジネスライクな話」の延長線にあるものだと思い込んでいたんです。でも、それではうまくいかないのは当然だったんですね。
「雑談には雑談なりの型がある」と知ってから、自分がなぜ失敗していたのかが明確になりました。「型のない会話」に型を持ち込む発想がとても新鮮で、まさに“発見”でした。今では「失敗するのが当たり前だったんだ」と割り切れたことで、気持ちもずいぶん楽になりました。
苦手意識がスッと和らぐ
私は内向的な性格で、昔から人づきあいに苦手意識があります。特に、初対面の人との何気ない会話——いわゆる雑談になると、とたんに緊張してしまい、言葉が出てこなくなることもしばしば。職場やママ友の集まりなど、気を使う場面ではなおさらで、「私、こういうの向いてないな」と落ち込むことが多かったです。
そんな私にとって、この本の語り口はとてもやさしく感じられました。「雑談は誰でも苦手で当たり前」とはっきり書いてくれていたのが、まず嬉しかったですね。なんだか自分だけがコミュニケーション下手なんじゃないかと思っていたので、その一言に救われたような気持ちになりました。
本を読み進めるうちに、「技術として学べばいいだけ」「才能ではなくスキル」と考えられるようになり、少しずつ自信が湧いてきました。心が軽くなった、という表現が一番しっくりきます。今では、雑談の時間が“避けるもの”ではなく“ちょっと試してみようかな”と思える場になってきています。
実例が豊富で即実践できる
比較的論理的に物事を考えるタイプで、何かを学ぶときは「理論よりも実践」「抽象より具体」が合っています。そういう意味で、この本の構成は自分にとって非常にしっくりくるものでした。
例えば、「こういう質問はNG」「こう言い換えると会話が弾む」という具体的な会話例がとにかく豊富に盛り込まれていて、読んでいるだけでシミュレーションができるんです。しかも、「初対面の相手」「取引先との打ち合わせ前後」「飲み会での会話」など、シチュエーション別に整理されているから、自分の悩みにピンポイントで対処法が見つかるのもありがたかったです。
読んだその日から、職場で実践してみました。すると、なんとあの無口だった上司が、ぽつぽつと話してくれるように。自分でも驚くほど効果がありました。「こう言えば反応が変わる」という確信が持てたことで、自分の話し方にも少しずつ自信が出てきました。
「陽キャ」じゃなくても大丈夫
私はどちらかというと人見知りな性格で、学生時代も今の職場でも、積極的に話しかけるタイプではありません。「陽キャ」に見られる人たちが簡単に場を盛り上げているのを見ると、「自分には無理」と引いてしまっていました。
でも『超雑談力』を読んで驚いたのは、そういう“社交的な性格”と“雑談がうまいこと”とはまったく関係がない、という指摘です。本書のなかには、「性格を変える必要はない」「雑談力は型で身につく」と何度も繰り返されています。これがすごく心強かった。内向的な自分を責めなくてよくなるというのは、それだけで安心できるんです。
むしろ、感受性の強い人や、観察眼のある人のほうが「共感型の雑談」には向いているという話もあって、「私にもできるかもしれない」と思えました。本書は“明るく元気に”を目指す会話術ではなく、“誰でもできる再現可能な方法”を丁寧に示してくれています。その姿勢がとてもありがたかったし、だからこそ、今まで「どうせ向いてない」と避けていた雑談にも、ようやく挑戦してみる気持ちになれました。
「続ける会話」が主役になる
これまでの私は、「雑談=面白い話をすること」と思い込んでいて、常に“ネタ探し”に追われていました。ですが、この本の中で「雑談は、話題の面白さではなく、会話が続いているかが大事」という説明を読んで、まさに目からウロコでした。
確かに、相手と気持ちよく会話を続けられたときって、内容が特別面白かったわけじゃなくても、「話してて楽しかったな」と感じることが多いですよね。今まで私は、面白い話をしようとするあまり、話す前から緊張して、結果的に不自然な空気を作っていたんだと思います。
「会話を止めずに、ラリーを続けることに意味がある」——このシンプルだけど本質的な考え方に触れたことで、自分の中の雑談の定義がまったく変わりました。今では「何か面白いことを言わなきゃ」というプレッシャーから解放され、自然体で会話に臨めるようになりました。
雑談が「苦行」から「資産」になる
私は今までずっと、雑談というものを「義務」としてとらえてきました。人間関係の潤滑油だから仕方なくやる、話しかけられたら適当に返す、気を使って疲れる——そんな風に、雑談は“消耗するもの”というイメージが強かったんです。
でも、この本を読み終えたとき、心の底から「雑談って、こんなに価値があるんだ」と思いました。雑談には、相手との距離を縮め、信頼を築き、長期的な人間関係を育てる力がある。そのことを明快に、そしてやさしく伝えてくれる一冊でした。
しかも、雑談は訓練すれば誰でも身につけられるスキルであり、一度習得すれば一生モノの“資産”になる——この考え方には大いに希望を感じました。これまでは雑談の時間が苦痛でしたが、今は「人との信頼をつくる練習の場」ととらえられるようになり、自分の成長の機会だと思えるようになりました。
雑談は“苦行”ではなく“資産”。その逆転の発想に出会えたことが、私にとって最大の収穫です。この本と出会えたことで、人と話すことが怖くなくなりましたし、これからの人生が少し楽しくなったようにすら思えます。
「おもしろさ」より「共感」が大事
長年、接客業に従事している私にとって、“会話を盛り上げる”というのはまさに自分の仕事の一部でした。でもそのプレッシャーがしんどい。お客様を笑わせないとダメだとか、話をオチまで持っていかなきゃとか……気を抜く暇がありませんでした。そんな中、本書で出会った「雑談に必要なのは共感であって、おもしろさではない」という考え方は、私の中でまさに革命的でした。
お客様が求めているのは、笑える話ではなく、「共感してもらえた」という安心感や親しみやすさ。これは仕事だけでなく、日常生活でもまったく同じことが言えると感じます。本書が教えてくれるのは、相手に合わせて無理をするのではなく、「自然体で反応すること」の大切さです。
これまで、「私は話が面白くないからダメだ」と思い込んでいた自分にとって、この価値観の転換は本当に救いになりました。「相手の感情に寄り添うだけでいい」「共感を軸に会話を組み立てればいい」——そう思えるようになってから、雑談が少しずつ楽になってきました。無理にウケを狙わなくても、その場の空気を温かくできる。それが雑談力の本質なんだと、心から納得できました。
職場の空気が変わった気がする
私は事務職で、同僚や上司との何気ない会話が苦手なまま数年過ごしてきました。無口だと思われているのも、自分の評価に影響しているのでは?と不安に思うこともありました。
そんな時にこの本を読み、特に第4章の「職場/ビジネス編」に多くのヒントがあることに気づきました。「上下関係の中では、先生と生徒のようなスタンスで雑談をする」という考え方や、「得意なジャンルではなく、得意な視点を持つ」という視点は、私にとって非常に新鮮でした。
実際に、相手に話を振られたときに「なるほど、それってどういう視点ですか?」とリアクションをしてみたら、想像以上に反応が良く、そこから会話が広がるようになったんです。最近では、「話しやすくなったね」と言われるようになり、少しずつですが職場での居心地がよくなってきました。あの小さな雑談の変化が、職場の空気まで変えるとは、自分でも驚いています。
まとめ

本書『超雑談力』は、雑談に悩むすべての人へ向けて、「話し方」ではなく「関わり方」を根本から見直す機会を与えてくれます。読後には、実生活でどんな変化が期待できるのか、そしてその変化をどう活かしていくかが気になるところでしょう。
そこで最後に、以下の3つの視点から、本書を通じて得られる価値を振り返ります。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの項目で、実際に得られる効果や行動へのヒントを具体的にご紹介します。読み終えたあとに“読んだだけで終わらせない”ための導きとして、ぜひチェックしてみてください。
この本を読んで得られるメリット
雑談が苦手だと感じる人にとって、『超雑談力』は、単なるノウハウ集にとどまらず、「人との関係構築」の本質を学べる貴重な指南書です。読むことで得られる効果は、仕事でもプライベートでも活用できる汎用性があり、誰でも実践可能なアプローチが満載です。
以下のようなメリットを得ることができるでしょう。
雑談に対する苦手意識がなくなる
本書では、「雑談は普通の会話とは違う」という前提に立って、その性質を明確に定義しています。だからこそ、読者は「なぜうまくいかないのか」を理論的に理解し、「自分が悪いのではなく、やり方が合っていなかっただけ」と気づけます。その結果、雑談に対する苦手意識が徐々に薄れ、自信をもって人と向き合えるようになります。
日常のコミュニケーションがラクになる
あいさつや世間話といった、特別ではないけれど避けられない会話シーンが、本書を通じて大きく変わります。たとえば「天気の話」や「最近どう?」といった定番の導入がうまく機能しない理由を学び、代わりに使える具体的なフレーズやテーマを知ることで、日常のちょっとした会話もストレスなくこなせるようになります。
職場や取引先との信頼関係が深まる
雑談は、ただの雑談ではありません。本書は、ちょっとしたやり取りの中に信頼を生むエッセンスがあることを教えてくれます。ビジネスの現場では、相手と信頼を築くうえで形式ばらないやり取りが重要ですが、その際に必要となるリアクションや距離感を本書で学べば、相手からの印象がぐっと良くなり、関係性も円滑に進展します。
雑談力が「一生モノの武器」になる
本書の最大の強みは、「一度身につければずっと使える会話の型」を提案している点です。ルールやフレーズは誰でも再現できるよう平易に設計されており、慣れてくれば自然と口をついて出てくるレベルにまで落とし込めます。つまり、短期的な効果だけでなく、長期的に使えるスキルとして定着するのです。

読後の次のステップ
『超雑談力』を読み終えたあと、内容を「知識」で終わらせるのではなく、「行動」に変えることで、真の効果が現れます。本書の魅力は、読むだけで納得する内容にとどまらず、実生活で再現可能な会話術として活用できる点にあります。
ここでは、読後にどのようなステップで行動すれば良いかを解説します。
step
1苦手な場面を明確にしよう
まずは、自分がどのような雑談の場面に苦手意識を持っているのかを整理することから始めましょう。たとえば「初対面で緊張する」「義両親との沈黙がつらい」「上司と何を話せばいいかわからない」など、場面ごとの不安要素を可視化することで、どの章・どの技術を優先的に取り入れるべきかが明確になります。本書は場面別に技術がまとめられているため、自分に必要な箇所だけを重点的に読み返すという使い方も有効です。
step
2OKパターンを一つだけ実践してみる
いきなりすべての会話術を実践しようとすると、かえって不自然な会話になってしまう可能性があります。そこで重要なのは、「ひとつだけ」に絞って取り組むこと。本書で紹介されているOK例のなかから、自分が「これならできそう」と思えるものをひとつ選び、実際の雑談で試してみましょう。たとえば、「共感だけで会話を続ける」「天気ではなく自分の体験から話し始める」など、小さな変化が実感を生み出し、次の行動の原動力になります。
step
3成功・失敗の記録をつけてみる
雑談力は、経験を通じてブラッシュアップされていく能力です。うまくいった会話、逆に気まずくなってしまったやりとり、それぞれを思い出してメモしておくことが大きな学びになります。とくに「どう反応したら相手が笑顔になったか」や「どんな言葉に詰まってしまったか」など、感情や反応に注目して記録すると、自分の癖や強みが見えてきます。それが次の雑談の成功率を高めてくれるのです。
step
4雑談チェックシートで習熟度を確認する
本書には電子書籍限定で「雑談力7つのルール チェックシート」が付いています。これは読者が自分の実力を客観的に確認するためのツールとして非常に有効です。7つの基本ルールをもとに、自分の現在地と伸びしろを把握することで、次にどのポイントを意識するべきかが明確になります。単なる知識の蓄積ではなく、「使える力」へと転換させるための道標として活用できます。

総括
『超雑談力』は、「雑談は得意な人が自然にできるもの」という従来の思い込みをくつがえし、誰でも再現可能なスキルとして体系化した点で非常に画期的な一冊です。著者・五百田達成氏が提案するのは、会話のセンスに頼らず、具体的なルールと場面ごとの対応例をもとに、確実に習得できる「雑談の型」です。
この本の核心は、雑談を「第3の会話」と定義している点にあります。つまり、仕事での論理的な会話でも、親しい間柄での砕けた会話でもない、微妙な関係性のなかで相手との距離をはかる特殊なコミュニケーション。だからこそ従来の会話スキルでは通用せず、専用の技術が必要なのです。
内容の実践性も非常に高く、場面ごとのOK例・NG例を豊富に掲載しているため、自分の行動を客観的に見直しやすい構成になっています。しかも、全体のトーンは決して堅苦しくなく、著者のユーモアと共感がにじむ語り口によって、最後まで楽しく読み進められます。
読後には、雑談が苦手だった理由が明確になり、「どうすればいいか」という具体策が手元に残ります。これにより、読者は自己流の“あてずっぽう”の会話から脱却し、場の空気や相手との関係に配慮した“意図のある雑談”ができるようになります。結果として、日常生活でも仕事でも、人間関係のストレスが大きく軽減されるでしょう。

本書は、ただ会話が得意になるためのテクニックではなく、人と気持ちよくつながるための「心のスキルブック」として、一生役立つ価値をもった一冊です。
雑談に自信がない人はもちろん、すでにある程度話せる人にとっても、自分のやり方を見直すきっかけとなり得る内容になっています。
読者の会話観そのものを、やさしく、でも確実に変えてくれる良書です。
会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング
- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける
- 頭のいい人が話す前に考えていること
- 人は話し方が9割
- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術
- 話し方で損する人 得する人
- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる
- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ
- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身
- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術
- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術

