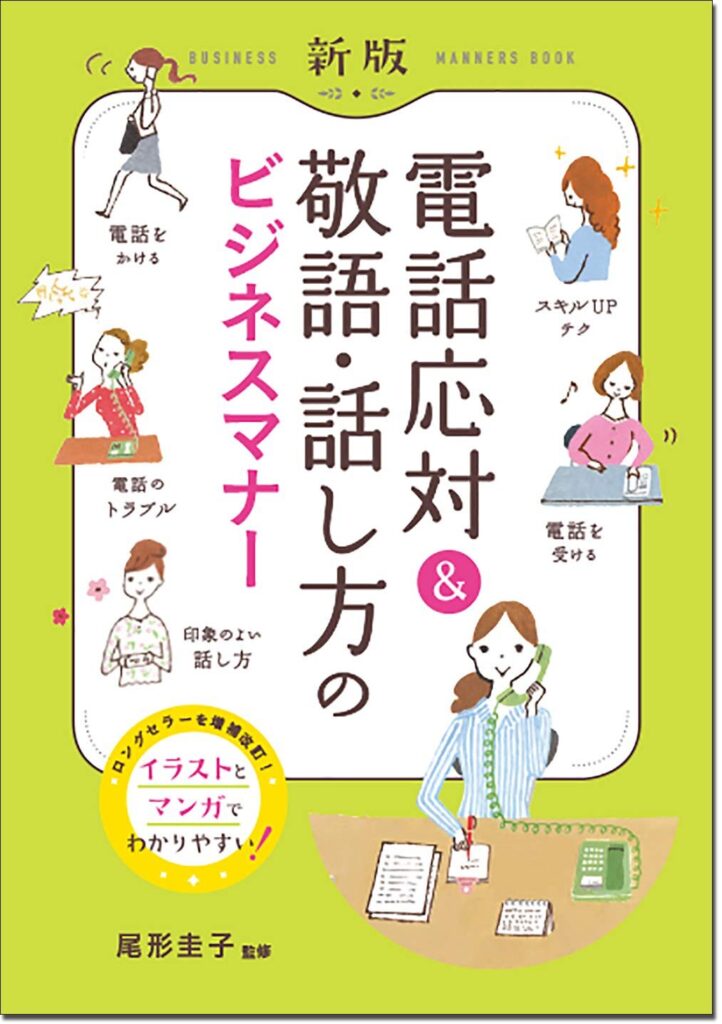
社会人にとって「電話応対」や「敬語の使い方」は、第一印象を左右する大切なスキルです。
しかし、実際の現場では「緊張して声が上ずってしまう」「敬語の使い分けに自信がない」「クレーム対応で何を言えばいいかわからない」といった悩みを抱える人が少なくありません。

『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』は、そうした不安を解消し、誰でも安心して実践できるように構成された一冊です。
令和の時代に合わせてリニューアルされた本書は、オールカラーのイラストやマンガで分かりやすく解説され、電話だけでなくチャットや携帯電話など現代のコミュニケーションツールにも対応しています。
持ち歩きやすいB6サイズで、社会人一年目の新入社員から、マナーを見直したい中堅社員、さらに人材育成を担う研修担当者まで、幅広く活用できる内容が詰まっています。
マナー本という堅苦しさを感じさせず、日常の会話や仕事の現場ですぐに使える知識を楽しく学べることが、この書籍の大きな魅力です。

合わせて読みたい記事
-

-
電話応対について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
電話応対は、社会人にとって避けて通れない大切なスキルです。 声のトーンや言葉遣いひとつで、相手に与える印象が大きく変わります。 しかし「緊張してしまう」「敬語に自信がない」といった悩みを抱える人も少な ...
続きを見る
書籍『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』の書評

電話応対は「声だけで接客する仕事」です。名乗り・要件確認・復唱・終話までの一連の流れに、敬語の精度や“間(ま)”の取り方が重なって、相手の印象が決まります。本書は、その流れをイラストと手順で見える化し、初心者でも迷いなく再現できるように設計された実用書。
まずは全体像を立体的に掴むため、以下の4つの観点から整理します。
- 監修:尾形圭子のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれの項目を順にたどることで、なぜこの一冊が“現場で効く”のか、背景と価値を深く理解できます。
監修:尾形圭子のプロフィール
尾形圭子氏は、本書『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』の監修を務めています。彼女は航空会社での勤務を皮切りに、接客やOJT指導の現場を経験し、その後大手書店チェーンにて社員教育や人材育成を担当しました。これらのキャリアは、接客業や販売の最前線で“実際にどのような言葉や態度が信頼を生むのか”を肌で学んだものです。
独立後は企業研修や講演活動を中心に、電話応対・接遇・クレーム対応・顧客満足(CS)の分野で研修プログラムを提供。監修者として関わる著作も多く、読者に「机上の空論ではなく、現場で役立つマナー」を届け続けています。加えて、マナーインストラクターやアンガーマネジメント関連の資格を保持しており、専門的な教育理論と現場感覚の両方を兼ね備えています。
また、尾形氏の特徴は「人と人との関わりを多角的に捉える視点」にあります。接客・ビジネスマナーの枠を超えて、人間関係全般をより円滑にするための方法を研究しており、それが研修や書籍の随所に反映されています。

尾形氏の強みは“現場経験×教育スキル”の掛け算です。
だからこそ、理論的に正しく、かつ実務で即使える知識を体系化できているのです。
本書の要約
『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』は、社会人に必須とされるコミュニケーションスキルを、実務に直結する形で整理した実用書です。従来のマナー本と異なり、単なる「知識の蓄積」ではなく「実際にどう動けばよいか」を体系化している点が特徴的です。特に電話応対や敬語表現は、知識を持っていても瞬発的に使いこなすことが難しい分野です。そのため本書は、場面ごとのフローやフレーズを具体的に提示し、読者が迷わず対応できるよう設計されています。
内容は7つのパートに分かれ、基礎から応用、さらにはトラブル対応や高度な会話術まで幅広くカバーしています。例えば、最初のパートでは電話応対の基本姿勢や緊張を抑える方法が解説され、次のパートでは「電話を受ける」際の流れや取り次ぎの仕方、伝言メモの取り方など、日常業務に直結するスキルがまとめられています。その後は「電話をかける」「クレーム対応」「英語での応答」「チャットアプリでのやり取り」など、現代のビジネス環境に欠かせない実践的なノウハウへと進んでいきます。
また、イラストやマンガを交えることで、文章だけでは理解しにくい場面を視覚的に再現しているのも大きな特徴です。読者は、単に文字を追うのではなく「実際に目の前で起こっているような場面」をイメージしながら学習できるため、実務での再現性が高まります。こうした構成により、初心者から経験者まで、自分の課題に応じた読み方ができる柔軟な一冊になっています。

電話や敬語は“型を覚える”ことが先決。
本書はその型をわかりやすく示し、初心者でも短期間で“正解”を再現できるよう設計されています。
本書の目的
本書の目的は、社会人にとって避けて通れない電話応対や敬語表現における“不安”を取り除き、誰もが安心して業務に臨めるようにすることです。電話は、対面と違って相手の表情や反応が見えないため、不安や緊張を感じやすい場面です。そのため新人社員にとっては特に大きな壁となります。本書では、そんな状況でも落ち着いて対応できるように、手順とフレーズを「型」として示し、再現性を高めています。
また、単に“正しい”言葉を並べるのではなく、“どう受け止められるか”に重点を置いているのも大きな特徴です。例えば、断るときに「できません」と言うのは正しい表現ではありますが、印象としては冷たく響きがちです。そこで本書は「恐れ入りますが」「あいにくですが」といったクッション言葉を紹介し、相手の気持ちに配慮しながら自分の意図を伝える方法を提案しています。こうした工夫は、単なる知識ではなく“信頼を築く技術”を学ぶことにつながります。
さらに本書は、現代的な働き方に合わせてチャットや留守番電話の活用についても触れています。これは「電話だけがすべて」ではなく、状況に応じてツールを選ぶ判断力を養うことを意図しています。つまり目的は、“社会人に必要な言葉遣いの基礎固め”と“時代に即した柔軟な対応力の育成”の両立にあるのです。

マナーは“相手を不快にさせない最低限のルール”であると同時に、“信頼を積み上げるための手段”でもあります。
本書の目的は、この両方を自然に習慣化させることです。
人気の理由と魅力
『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』が長年にわたり支持され続けるのは、単なるマナー本を超えた多面的な魅力を備えているからです。まず第一に、全ページオールカラーで、イラストやマンガを多用している点が挙げられます。これにより、従来のマナー本にありがちな「堅苦しくて読みづらい」という印象を払拭し、誰でも楽しく学べる仕立てになっています。特に新人や若手社員にとっては、イメージを伴って理解できることが学習のハードルを下げています。
次に、内容が非常に実用的である点です。NGとOKを比較する解説、シーン別のフレーズ集、チェックシート、ケーススタディなど、読者が現場で直ちに役立てられる具体例が豊富に盛り込まれています。実際に「電話で相手が不在だったとき」「クレームを受けたとき」「英語で電話がかかってきたとき」など、現場で誰もが遭遇しうる場面を再現しており、単なる座学では得られない実践感覚をつかむことができます。
さらに、令和版へのリニューアルで加わった「チャットマナー」は、若い世代にとって特に共感度の高いテーマです。メールや電話だけではなく、チャットを使ったやりとりが日常化した現代の職場において、これを学べることは大きなアドバンテージとなります。
そして、持ち歩きやすいB6サイズという仕様も見逃せません。デスクや鞄に常備しやすく、困ったときにすぐ開いて確認できる“お守り”のような存在として機能します。この利便性は、日常的に参照するビジネスマナー本として大きな魅力です。

人気の理由は“楽しく学べる”と“すぐに使える”を両立させていること。
見た目はやさしいのに、内容は現場仕様という二面性が、幅広い読者の心をつかんでいます。
本の内容(目次)

この書籍は、基礎から応用、さらにトラブル解決や上級の会話力までを段階的に学べるように整理されています。各パートが一冊の中で有機的に結びついており、読み進めることで自然にスキルが積み上がっていく設計になっています。
全体の流れは次の通りです。
- Part1 電話応対の基本
- Part2 電話を受ける
- Part3 電話をかける
- Part4 電話トラブルの解決法
- Part5 基本のビジネスコミュニケーション
- Part6 仕事がうまく進む会話術
- Part7 ワンランクアップの話し方
それぞれの項目は、単なるマナーの知識にとどまらず、実務で直面する場面に即して解説されているのが特徴です。
以下で詳しく見ていきましょう。
Part1 電話応対の基本
この章では、社会人としてまず押さえておきたい土台を学びます。電話は「会社の窓口」とも言える存在であり、受け答え一つで企業全体の印象が変わります。そこで冒頭では、電話に出るときに守るべき基本動作が紹介され、緊張しやすい人のために「あがりを防ぐ工夫」も解説されています。
続いて、声の出し方や話し方の工夫に焦点が当てられています。人は言葉そのものよりも、声のトーンや間の取り方で印象を受け取ることが多いため、相手に安心感や好印象を与える話し方が求められます。また、この章では「敬語の基本」や「立場に応じた言葉の使い分け」が体系的に整理されており、自分の言葉遣いを確認する「NG例と正しい表現の比較」も用意されています。
さらに、日常的によく使う「クッション言葉」や「敬意を示すフレーズ」も紹介されます。これらは相手との距離を和らげ、会話をスムーズに進めるための重要なツールです。特に新人や若手社員は、言葉選びに迷うことが多いため、この一覧を参考にするだけでも自信を持った応対ができるようになります。

電話応対は“声の表情”で信頼を築く技術。
敬語と同時に“声の演出”を意識することで、相手の印象は格段に変わります。
Part2 電話を受ける
この章では、受電時に必要な一連の流れが具体的に示されています。電話が鳴ってから受話器を取るまでのスピードや第一声の言葉選びなど、相手に「安心して話せる雰囲気」を与えるための基本動作が丁寧に解説されています。また、電話の切り方や声のトーンを保つ重要性にも触れており、最後まで気を抜かない姿勢が求められます。
特に詳しいのが「取り次ぎ」に関する解説です。単に電話を回すだけでなく、相手への気配りや社内での正確な伝達をどう行うかに重点が置かれています。不在時の言い回しや、伝言を受け取る際のメモの取り方、間違いを防ぐ復唱の技術など、実務でありがちな悩みをカバーする具体例が満載です。
さらに、問い合わせ対応やクレームの初期対応など、受け手として直面する難しい場面についても触れられています。単なるフレーズ集にとどまらず、相手の気持ちに配慮した「言葉の柔らかさ」が強調されているため、機械的な対応ではなく信頼を得るコミュニケーションが自然に身につきます。

受電対応は“第一印象を決める玄関口”。
フレーズの正しさよりも、相手に“誠意が伝わる声”を届けることが最も大切です。
Part3 電話をかける
発信の場面では、まず準備の大切さが語られます。相手の名前や要件を整理してからかけることで、会話がスムーズに進み、無駄な時間を取らせずに済みます。この段階で不十分だと、相手に余計な負担をかけることになり、信頼を損ねるリスクが生じるため、事前の計画は欠かせません。
会話の運び方では、初めての相手と二度目以降の相手ではアプローチを変える必要性が説明されています。初めての相手には、特に礼儀を重視した挨拶と自己紹介が求められます。一方で、二回目以降は相手の負担を減らすため、簡潔に要件を伝えることが重視されます。また、携帯電話にかけるときの注意点や、相手が出られなかった場合の留守番電話への残し方も、具体例とともに紹介されています。
さらに、現代のビジネスシーンに合わせた「チャットでの連絡マナー」も掲載されています。電話だけに頼らず、チャットやメールと併用することで、相手にとって負担の少ない連絡が可能になることが解説されています。状況に応じた最適な手段を選ぶ力が、現代社会人には必須であると強調されています。

発信は“相手の時間を奪う行為”であることを意識するのがマナーの基本。
準備と配慮が、効率と信頼を同時に生み出します。
Part4 電話トラブルの解決法
この章は、電話応対の中でも最も難易度が高いトラブル対応を扱っています。特にクレーム対応については、冷静に進めるための流れが具体的に示されており、「5つのステップ」に従えば、パニックにならずに落ち着いた対応が可能になります。具体的なフレーズ集も掲載されており、困ったときにすぐ役立つ“実務用の引き出し”として機能します。
また、誤った言葉遣いが事態を悪化させることがあるため、「NGワード」とその代替表現も整理されています。例えば「できません」という断定的な言葉を「確認いたします」と言い換えることで、相手の受け取り方が大きく変わるといった実例が紹介されています。こうした配慮が、相手の感情を落ち着かせる第一歩となります。
さらに、英語での応対やセールス電話、間違い電話やイタズラ電話など、日常的に発生しうる特殊なケースもカバーされています。状況に応じて上司に引き継ぐ判断基準や、クレーム対応チェックシートも用意されており、個人のスキルだけでなく、組織全体で共有できるノウハウとして活用できます。

トラブル対応は“火消し”ではなく“信頼回復の機会”。
適切な言葉と手順で、むしろ顧客満足を高める可能性があります。
Part5 基本のビジネスコミュニケーション
この章では、電話以外にも社会人として欠かせない日常的なやり取りが整理されています。最初に取り上げられるのは挨拶です。初対面での挨拶や日常的な声掛けは、ただの儀礼に見えて実は信頼関係を築く大切な行為です。ここでは「目を見て、相手より少し先に声を出す」といった細かなテクニックも解説されており、第一印象をより良くする工夫が示されています。
次に扱われるのは、名刺交換や来客対応といった、ビジネス上の基本的な場面です。名刺を差し出す順番や角度、来客を案内する際の立ち位置など、細かい動作が「相手への敬意」を可視化する方法として解説されています。これらはマニュアル的に見えますが、実際には「相手に安心感を与える共通言語」として大きな意味を持ちます。
さらに、敬語の活用についても詳しく触れられています。単なる言葉遣いではなく「相手の立場を尊重する姿勢」を伝える手段としての敬語であり、誤用を避けることが信頼構築の基盤になると強調されています。こうした視点から、日々の小さなやりとりが積み重なって長期的な関係性を形成していくプロセスが示されています。

形式的に見える挨拶や名刺交換も、実は“信頼を見える化するツール”。
おろそかにすると信頼残高を減らす原因になります。
Part6 仕事がうまく進む会話術
ここでは、業務を円滑に進めるための会話力に焦点が当てられています。冒頭では「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」の基本が取り上げられ、正しく行うことで上司や同僚との間に余計な誤解や摩擦を生まない方法が解説されています。
次に、謝罪や感謝の伝え方が詳しく解説されています。ビジネスの現場では失敗やトラブルは避けられませんが、誠実に謝罪できるかどうかで信頼が大きく変わります。また、感謝の言葉も「ありがとう」だけでは不十分で、具体的に何に対して感謝しているのかを明確に伝えることで、相手に「理解されている」と感じさせることができます。
さらに、部下や後輩への指導、打ち合わせでの説明方法、相手への依頼や催促の工夫なども取り上げられています。これらは単なる会話のテクニックではなく、組織の生産性を高めるための重要な要素です。適切な言葉を選ぶことで、相手のモチベーションを下げずに協力を得ることが可能になります。

会話力は“潤滑油”ではなく“組織を動かすエンジン”。
言葉の精度が高まるほど、仕事の効率は飛躍的に上がります。
Part7 ワンランクアップの話し方
最後の章では、基本を超えてより洗練されたコミュニケーションを実現するための方法が解説されています。ここで扱われるのは「あいづちの工夫」「角を立てない断り方」「誤解を受けたときの切り返し」など、相手との関係をより深めるためのテクニックです。
特に強調されているのは、「言いにくいことをどう伝えるか」という難しい場面での言葉選びです。否定的な内容であっても、言い回しを工夫することで相手に不快感を与えずに意図を伝えることができると示されています。また、苦手な相手や話しにくい人とのコミュニケーションを乗り越える方法も取り上げられており、実務だけでなく人間関係全般に役立つ内容になっています。
さらに、コミュニケーションの悩みを解決するヒントも数多く盛り込まれており、読者が自分の課題に照らし合わせて応用できる工夫が施されています。単なるマナー本を超えて「人間関係の改善書」としても活用できる一章となっています。

言葉は“相手を動かす力”を持っています。
ワンランク上の会話術は、ビジネスだけでなく人生全体を豊かにするスキルです。
対象読者

この書籍は、社会人として成長する過程で直面するさまざまな課題をサポートする実践的な内容になっています。読者の立場ごとに異なる悩みに対応できるように、複数の層を想定して構成されています。
以下のような人たちに特におすすめです。
- 電話応対に不安を感じる若手社員
- 敬語や言葉遣いに自信がない人\
- クレーム応対や接客業務に携わる人
- マナー研修や人材育成に携わる担当者
- 就活生や転職活動中の人
それぞれの立場に応じて役立つポイントがまとめられており、読者が自分自身の課題に即したヒントを見つけやすいよう工夫されています。
電話応対に不安を感じる若手社員
初めて社会に出たとき、最も大きなハードルの一つが電話対応です。相手の顔が見えない中で会話を進めなければならず、声のトーンや言葉遣いだけで印象が決まります。本書は、電話を取る手順や話すときの基本を具体的に示しているため、不安を抱える人が安心して取り組める実践的なガイドとなります。
さらに、緊張を和らげるための心構えや、好印象を与える話し方のコツも盛り込まれており、単なる「手順書」以上の価値があります。若手社員が自信を持って電話に出られるようになるための、一歩先を行く支えになるのです。

新人が電話に不安を感じるのは自然なことです。
大切なのは、正しい型を知り、繰り返し練習して体に覚えさせること。本書はその型を提供してくれます。
敬語や言葉遣いに自信がない人
社会人として避けて通れないのが敬語の習得ですが、多くの人が尊敬語・謙譲語・丁寧語の使い分けに苦手意識を持っています。本書は、ありがちな誤用を取り上げながら、正しい言い換えや自然な表現方法を解説しており、短期間で改善につなげることができます。
さらに、クッション言葉やシーン別の表現集が掲載されているため、単に間違いを減らすだけでなく、相手との距離を縮める話し方を身につけることができます。日常的に「敬語に自信がない」と感じている人にとって、安心して実践できる支えとなるでしょう。

敬語は正しいルールを暗記することよりも、状況に合わせて適切に使えることが大切です。
その練習を体系的にできる点が、本書の強みです。
クレーム応対や接客業務に携わる人
顧客と直接接する仕事では、クレーム対応が避けられません。感情的な場面で冷静さを保ち、正しい言葉を選べるかどうかが信頼を左右します。本書には、クレーム応対の流れや避けるべき言葉、さらに実際に使える具体的なフレーズが整理されているため、現場で迷わず対応できます。
ケーススタディが豊富に掲載されている点も強みです。シチュエーションごとに適切な対応を疑似体験できるため、机上の知識ではなく「現場で使えるスキル」として身につけられます。接客やサービス業の担当者にとっては必携の一冊と言えるでしょう。

クレーム対応は「顧客を失うリスク」ではなく「信頼を高めるチャンス」と考えることが重要です。
本書はその発想を支える実務的な知恵を与えてくれます。
マナー研修や人材育成に携わる担当者
人に教える立場にある人にとっても、この本は頼れる一冊です。イラストやマンガが多く使われているため、受講者が飽きずに学べる教材として最適です。理論よりも実例が豊富な点は、研修参加者にとって「自分ごと」として理解しやすい効果をもたらします。
また、電話対応だけでなく、名刺交換や来客応対といった基本マナーまで網羅しているため、研修プログラム全体を支える総合教材として活用できます。担当者が一から資料を作る負担を減らしつつ、効果的な教育を実現できるでしょう。

教育の成果は「理解」だけでなく「行動に移せるか」で決まります。
本書は学んだ知識を実践につなげる設計になっている点で優れています。
就活生や転職活動中の人
就職活動や転職活動において、電話や言葉遣いは面接以前に評価されるポイントです。特に企業担当者との電話応対は、社会人としての基本姿勢を確認される場でもあります。本書は、正しい言葉選びや対応の流れを網羅しているため、安心して企業とやり取りできる力を養えます。
また、社会人マナーをあらかじめ理解しておくことで、面接やグループワークなどの場面でも落ち着いて振る舞えるようになります。短期間で印象を高めたい学生や転職希望者にとって、即効性のある実用書となるでしょう。

採用の場面では、専門スキル以上に「この人は基本ができているか」が見られます。
本書はその基盤を整える最適な一冊です。
本の感想・レビュー

クレーム対応のフレーズ集が心強い
私は普段から電話でのクレーム対応に緊張してしまうタイプですが、この本のフレーズ集には本当に助けられました。実際のやり取りを想定した表現が整理されていて、そのまま口に出すだけで場をつなげる安心感がありました。
読んでいると「自分だけが困っているのではないんだ」と感じられるほど、よくある状況が丁寧に取り上げられていました。言葉に迷って時間が空いてしまうことがなくなり、結果的に相手への印象も改善できた気がします。
このフレーズ集は、一人で悩み込んでいた自分にとって大きな味方になりました。電話に出るときの恐怖心が少しずつ和らいだのは、この本のおかげだと思います。
クッション言葉の使い方が分かりやすい
電話や対面でのやり取りでは、相手を不快にさせない言葉の工夫が欠かせません。この本には「シーン別クッション言葉の使い方」がまとまっていて、とても参考になりました。今まで何となく使っていた表現が、実はより柔らかく伝えられることに気づきました。
たとえば依頼や断りをするときに、ワンクッション置くことで印象が大きく変わります。相手に配慮しつつ自分の意図を伝えられるので、会話がスムーズに進むのです。私自身、相手の反応が変わったときに、この学びの効果を実感しました。
読んで終わりではなく、日常業務にすぐ活かせるのがこの本の魅力です。気づかないうちに失礼になっていたかもしれない表現を見直す機会にもなり、コミュニケーションの質を上げるきっかけになりました。
NG例→OK例の比較が分かりやすい
読み進めていて特に印象に残ったのが、NG表現とOK表現を並べて解説しているページでした。単に「これは間違いです」と指摘されるだけだと納得感が薄いのですが、正しい言い回しと比較することで理由まで自然に理解できました。
自分が無意識に使っていた言葉の癖が可視化され、「これでは相手に失礼に聞こえるのか」と気づかされる瞬間が何度もありました。言葉は普段の習慣で出てくるものだからこそ、こうした比較は学習効果が大きいのだと実感しました。
ページをめくるたびに「すぐに直してみよう」という気持ちがわき、日常会話の中で少しずつ修正できるようになったのが大きな収穫です。
取り次ぎや折り返し対応の流れが明快
会社の代表電話を取るときに最も困っていたのが取り次ぎや折り返しの対応でした。この本ではその流れがステップごとに整理されていて、まるでマニュアルのように分かりやすかったです。
読む前は「どう言えば丁寧で、どう言えば失礼になるのか」が曖昧だったのですが、実際のフレーズや具体的な対応手順が載っていたことで、自信を持って行動できるようになりました。
今では電話が鳴っても慌てずに対処できるようになり、同僚からも「安心して任せられる」と言ってもらえるまでに成長できたのは、この本で学んだ流れを実践できたからだと感じています。
ホウレンソウ(報告・連絡・相談)の解説が役立つ
この本の後半で紹介されているホウレンソウの解説は、自分の働き方を見直すきっかけになりました。単なる言葉として知ってはいましたが、具体的にどう実践すべきかを詳しく書いてある本は意外と少ないように思います。
特に、報告の仕方や相談のタイミングについて細かく触れられている点は実用的で、日々の業務にすぐ役立ちました。上司とのやり取りがスムーズになり、以前より信頼を得られるようになったと実感しています。
仕事を円滑に進めるための基本的な考え方を再確認できたことで、「電話応対の本」という枠を超えて、ビジネスマナー全般を学べる良書だと強く感じました。
言いにくいことの伝え方が参考になる
この本で特に印象に残ったのは、「言いにくいことをどう伝えるか」というテーマでした。仕事をしていると、相手に不快感を与えずにこちらの立場を理解してもらう必要がある場面は少なくありません。ここでは、相手に配慮しながら自分の意見を伝えるための工夫が丁寧に書かれていて、実際に役立つ実感がありました。
読み進めていく中で、ただ柔らかく言い換えるだけではなく、「誤解を避けながら核心を伝えること」の大切さに気づきました。あいまいにしてしまうと問題が長引くこともあるので、適切な言葉の選び方が身につく点が非常に実用的でした。
研修担当者からの評価が高い
職場で研修を担当している立場から読んでみると、この本の使いやすさに感心しました。イラストやフレーズ集が豊富に盛り込まれていて、受講者が理解しやすい構成になっているため、実際の研修教材としても非常に適しています。
特に、電話応対の流れやNG例・OK例が明確に示されている点は、実習の場で説明する際に効果的でした。抽象的な説明ではなく、すぐに現場で使える内容なので、新入社員への指導に自信を持てるようになりました。
これまでさまざまな研修資料を試してきましたが、この本はその中でも群を抜いて実践的で、受講者からも好評を得やすい一冊だと感じます。
あいづちや印象アップの工夫が実用的
会話の流れを円滑にする「あいづち」や、好印象を与える話し方について書かれている部分は、とても実用的で親しみやすかったです。形式ばった説明ではなく、日常の会話にも取り入れやすい工夫が多く紹介されていて、すぐに試してみたい気持ちになりました。
実際に意識して取り組んでみると、相手の反応が以前と違うことに驚きました。小さな変化でも「話しやすい人」と思ってもらえるようになり、会話全体の雰囲気が柔らかくなったと感じます。
本を読む前は些細なことだと思っていた点が、相手の印象に大きく影響することを知り、ビジネスに限らず人付き合い全般に役立つ知識だと実感しました。
まとめ

この記事の最後に、本全体を振り返りながら、読者の方が理解しやすいように整理しておきましょう。
本書がもたらす価値や読後に取り組むべき行動、そして全体の総括を記していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
このように整理することで、読者が「読む前に期待できる効果」と「読み終えた後の行動指針」、そして「全体の位置づけ」を一目で理解できるようになります。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、この一冊を手に取ることで得られる主な効果について整理してみましょう。
自信を持って電話対応ができるようになる
社会人にとって電話対応は避けられない業務ですが、慣れるまでは緊張や不安を感じるものです。本書では、受け答えの基本フローや適切な言葉選びを具体的に解説しているため、初めての対応でも迷わずに行動できるようになります。結果として、安心感と自信を持って電話を受けたりかけたりすることが可能になります。
敬語の正しい使い分けを習得できる
敬語は「知っているつもり」でいても、実際の現場では間違った使い方をしてしまうことが多い分野です。本書では、尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎的な整理から、立場に応じた応用表現までを丁寧に解説しています。自然な言葉遣いを身につけることで、相手から信頼を得るコミュニケーションが可能になります。
クレーム対応力が身につく
クレームは誰にとっても避けたい状況ですが、適切に対応できる人材は組織にとって大きな価値を持ちます。本書には、事例ごとの解決方法や実際に使えるフレーズが掲載されており、トラブルを冷静に処理するための実践力を磨けます。これにより、顧客満足度の向上や信頼回復につなげるスキルを養うことができます。
現代的なマナーを理解できる
近年は電話だけでなく、チャットやメールを活用する場面も増えています。本書では、こうしたデジタルコミュニケーションにおけるマナーについても紹介されており、時代に即した実践的な知識を学ぶことができます。若手社員だけでなく、すでに現場で働いている人にとってもアップデートの機会となるでしょう。

ビジネスマナー本の中には理論中心で読みにくいものもありますが、本書はイラストや漫画を交えて直感的に理解できる構成になっています。
そのため、初心者でも挫折せず最後まで読み切れる点が、学習効果を大きく高めているのです。
読後の次のステップ
本書を読み終えた後に大切なのは、得られた知識を頭の中にとどめておくだけではなく、日々のビジネスシーンで実際に活用することです。学んだ内容を実践に移すことで初めて、本当の意味で「自分のスキル」として身につきます。
ここでは、読了後に取り組むべきステップをいくつか紹介します。
step
1学んだ知識を日常業務に活かす
まず取り組むべきは、本書で得た知識を実際の仕事の場に落とし込むことです。電話応対や敬語表現をすぐに試してみることで、自分の癖や改善点に気づくことができます。特にクレーム対応や依頼の仕方などは、緊張しているときにこそ役立つものなので、実務で繰り返し使いながら体に覚え込ませることが重要です。
step
2自分なりの応対マニュアルを作る
次におすすめなのが、自分専用の「電話・会話マニュアル」を作ることです。本書のフレーズや解説を参考にしながら、よく使う言葉や場面を整理して手元にまとめておくと安心です。仕事中に慌てたときでも、そのメモを見ることで落ち着いて対応できるようになります。こうした「自分用のツール」を作ることで、学んだ知識が定着しやすくなります。
step
3継続的なトレーニングを心がける
電話応対やビジネス会話のスキルは、一度覚えたからといってすぐに完璧に使いこなせるわけではありません。繰り返し練習することで自然に言葉が出てくるようになります。職場での会話を意識的に練習の場とし、同僚や先輩からフィードバックを受けることで、さらに精度の高いコミュニケーション力を磨いていけます。
step
4習慣化して自然なスキルにする
最終的なゴールは、マナーや言葉遣いを「意識せず自然にできる状態」にすることです。本書で学んだ知識を反復して日常に取り入れ、毎日の仕事に溶け込ませていくことで、気づけばそれが自分のスタイルとして定着していきます。

学びを定着させるためには「知識→実践→改善」の循環を作ることが不可欠です。
これは教育学や心理学でも指摘される学習プロセスであり、特にビジネスマナーのような技能的な分野では反復とフィードバックが成果を左右します。
総括
『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』は、社会人として避けて通れないコミュニケーションの基礎を体系的に学べる一冊です。電話応対から始まり、敬語、クレーム対応、さらには人間関係を円滑にするための話し方まで、幅広いテーマをカバーしています。特に、イラストやマンガを多用した解説は初心者にも理解しやすく、難しさを感じさせない工夫が随所に施されています。
本書の最大の強みは、「現場ですぐに役立つ実用性」と「誰でも手軽に取り組める分かりやすさ」を兼ね備えている点にあります。実際の業務で直面しやすいケーススタディやフレーズ集が豊富に盛り込まれており、読者は単なる知識習得にとどまらず、そのまま実践に活かせる形で吸収できるのです。これは、多忙なビジネスパーソンにとって非常に大きなメリットといえるでしょう。
また、時代の変化に即した内容が盛り込まれていることも重要なポイントです。従来の電話応対マナーに加え、チャットアプリを用いたやりとりや英語での対応方法など、現代のビジネスシーンに欠かせないスキルにも触れています。単なるマナー本にとどまらず、現代的なコミュニケーション力を養うための総合的なガイドとなっているのです。

新社会人はもちろん、スキルの見直しを図りたい中堅社員や教育担当者にとっても有益な存在です。
マナーを身につけることは相手への思いやりを形にする行為であり、それが信頼関係を築き、仕事の成果を高める基盤となります。
『新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー』は、その第一歩を確実に支えてくれる良書であると結論づけられます。
電話応対に関するおすすめ書籍

電話応対について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 電話応対について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー
- 電話応対、これができればOKです!
- ソツのない受け答えからクレーム対応まで [新版]一生使える「電話のマナー」
- どんなに苦手でもうまくいく電話応対
- ゼロから教えて電話応対
- 電話応対はこわくない! 知っておきたい仕事のルールとマナー
- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー
- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる
- 敬語「そのまま使える」ハンドブック
- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート

