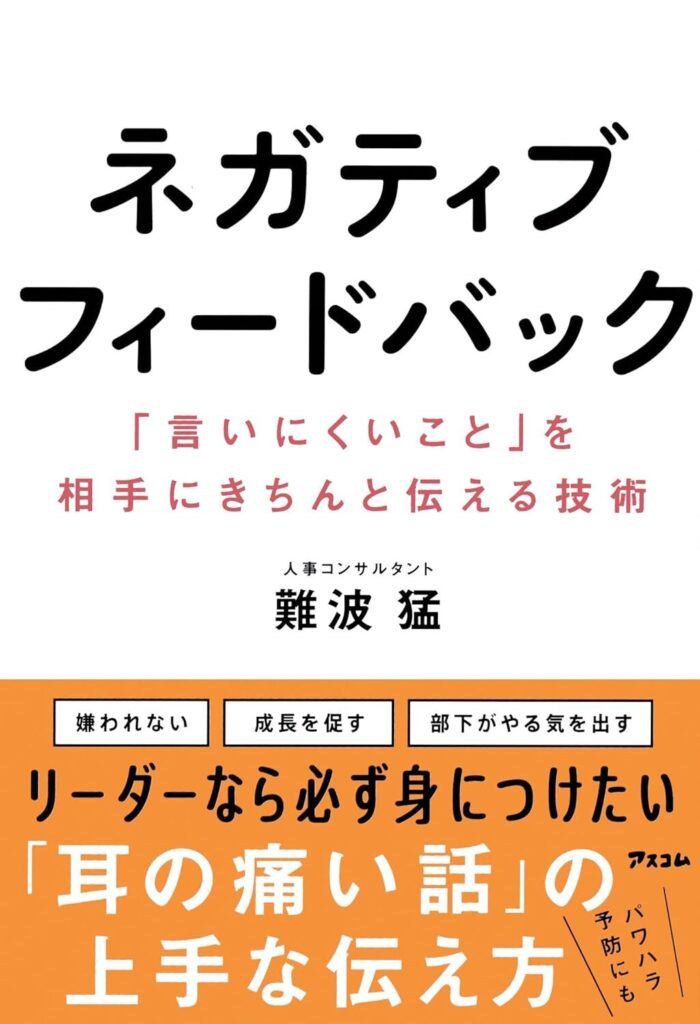
人間関係を壊さずに、相手に変化を促す──。
職場でもプライベートでも、本当は伝えたほうがいい「言いにくいこと」を胸にしまい込んだまま、モヤモヤした経験はありませんか?
この本は、そんなあなたにこそ読んでほしい一冊です。

ネガティブフィードバックは、ただ相手を指摘することではありません。相手の行動を変えるきっかけを作り、より良い関係と成果を生み出すためのスキルです。
本書では、心理学や行動科学の知見をベースに、部下や同僚、上司、さらには家族や友人にまで使える「伝え方の技術」を具体的に解説しています。
「言いづらい」「嫌われるのが怖い」「パワハラと思われたらどうしよう」──そんな不安を乗り越え、建設的な対話を実現する方法が、この1冊に凝縮されています。
言葉を変えれば、人も関係も変わる。勇気を出して伝えるための実践的ヒントが、ここにあります。

合わせて読みたい記事
-

-
新しい知識やスキルが身に付く、おすすめのビジネス書 14選!人気ランキング【2026年】
ビジネスの世界で成功を収めるためには、知識の幅を広げるだけでなく、実践的なスキルや思考法を身につけることが欠かせません。 しかし、数多くのビジネス書の中からどれを選べば良いか迷ってしまうことも多いでし ...
続きを見る
書籍『ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術』の書評

本書は、ビジネスリーダーが部下との関係を損なうことなく、あえて困難な話題を伝える手法を学ぶための一冊です。多くの上司が避けたがる「耳の痛い話」を、むしろ部下の成長を促す機会に変える技術が丁寧に構成されており、実務現場で再現可能な内容が特徴です。
以下の視点で本書の構造と価値を掘り下げます。
- 著者:難波 猛のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれを丁寧に見ていくことで、この本の本質がはっきりと浮かび上がります。
著者:難波 猛のプロフィール
難波 猛氏は、人材育成と組織改革を専門とするコンサルタント兼研修講師で、幅広い実務経験を持つプロフェッショナルです。大学を卒業後、編集や企画の仕事を経て人材サービス大手に転身し、2007年以降は同社でキャリア支援や研修を推進してきました。累計では個人へのキャリアカウンセリングが3000件超、管理職研修が2000名以上と広範囲にわたる実績があり、部下育成における指導と心理学の知見を両輪に現場で活かしてきました。
さらに、プロティアン・キャリア協会アンバサダーや日本心理的資本協会理事などを務め、理論と実践の橋渡しを行う社会的リーダーとしても知られています。自身が理論を深めるだけでなく、それらを企業現場に導入する活動にも精力的に取り組んでいます。

本書の要約
この書籍は、職場でのコミュニケーションにおいて特に難しいとされる「ネガティブフィードバック」を、建設的かつ前向きに伝えるための方法を体系的に解説した実践書です。ネガティブフィードバックとは、部下や同僚に対して行動改善を促すために伝える“耳の痛い情報”のことを指します。多くの上司が「言わないと改善しない」と理解しつつも、関係性の悪化を恐れて踏み込めない課題を解消するための知識と技術が詰め込まれています。
本書ではまず、相手のやる気を損なわずにフィードバックを行うための基本フレームとして「WILL/MUST/CANモデル」が紹介されます。これは、本人がやりたいこと(WILL)、組織が求めること(MUST)、実際にできること(CAN)の3つを整理し、対話を通じて行動改善に結びつけるアプローチです。単なる叱責ではなく、相手の可能性を引き出す形で伝えることが重要であると強調されています。
さらに、言葉選びや表情、タイミングといった非言語要素の重要性についても深く掘り下げています。例えば、同じ内容を伝える場合でも、強い口調で言うか穏やかに言うかで受け取り方がまったく異なることを実例とともに示しています。オンライン面談のケースや、パワハラと受け取られないための注意点など、現代の多様な働き方に即した具体的な場面別アドバイスがあるのも特徴です。

本書の目的
本書の狙いは、管理職やリーダーが「言いにくいことを適切に伝えるスキル」を身につけ、組織全体の生産性と人間関係の質を同時に高めることです。単なるコミュニケーションマニュアルではなく、信頼関係を壊さずに部下の成長を後押しする「建設的なネガティブフィードバック文化」を根付かせることが大きな目的となっています。
著者は、ネガティブフィードバックが避けられる背景に、伝える側の心理的不安があると指摘します。「嫌われたくない」「雰囲気を壊したくない」といった感情が、必要な指摘を遅らせ、結果としてチーム全体のパフォーマンス低下を招いているのです。本書では、まず伝える側が自身のメンタルを整えるための方法が示され、心の準備をした上で建設的な対話ができるようステップを踏むプロセスが紹介されています。
このアプローチは、従来のトップダウン型の指導方法から一歩進み、相手の主体性を尊重しながらも明確な方向性を示す、新しい時代のマネジメントスタイルといえます。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者から支持されている背景には、理論と実践を両立した内容構成があります。心理学的な根拠に基づいた説明によって、なぜ従来のフィードバックが機能しないのかを明確に理解できるため、読者は根本原因に納得したうえで改善策を学ぶことができます。
また、抽象論ではなく、実際の職場で使えるフレーズや対話例が豊富に掲載されているため、読了後すぐに日常業務に応用できる点も魅力です。「こう言えば良い」といった具体例が提示されることで、読者が迷わず実践に移しやすくなっています。
さらに、指摘という行為自体をポジティブに再定義したことも支持の理由です。これまで「ネガティブフィードバック=嫌われるもの」という思い込みを持っていた人にとって、「信頼を深め、未来を良くするための前向きな手段」と捉え直せる視点は衝撃的で、読者の価値観を大きく変えるきっかけになっています。

本の内容(目次)

この書籍は、部下の成長を促すために必要なフィードバックの方法を、多角的な視点から解説しています。単に良い点を褒めたり、悪い点を叱ったりするだけでは、人材の力を最大限に引き出すことはできません。心理学や組織行動学の理論をベースに、現場ですぐ活用できるアプローチが体系的に紹介されています。
主な章立ては以下の通りです。
- 第1章:部下は「叱る」だけでも「ほめる」だけでも成長しない
- 第2章:ネガティブフィードバックが難しいのはなぜ?
- 第3章:ギャップを整理するフレームワーク「WILL」「MUST」「CAN」
- 第4章:「何を言うか」より「誰が言うか」が重要(日常のマネジメント)
- 第5章:ネガティブフィードバックを成功させる心の整え方(5つのマインドセット)
- 第6章:ネガティブフィードバックを成功させる技術(5つのスキルセット)
- 第7章:パワハラにならない伝え方のポイント
- 第8章:「ぶら下がる年上部下」「すぐ辞める若手部下」への向き合い方
- 第9章:部下から上司へフィードバックする(ボスマネジメント)
各章を通じて、耳の痛い内容をどう伝えるか、相手を萎縮させずにどう改善を促すか、そして上司自身がどのように成長すべきかまで、具体的なノウハウが詰まっています。以下から章ごとの内容を詳しく見ていきましょう。
第1章 部下は「叱る」だけでも「ほめる」だけでも成長しない
近年、部下に対して厳しいことを言えない上司が増えているといわれています。背景には、パワハラ防止や心理的安全性への過剰な配慮があり、部下との関係が悪化するのを恐れるあまり、上司が耳の痛いフィードバックを避ける傾向が強まっています。しかし、部下の成長を促すには、ただ「叱る」だけ、あるいは「ほめる」だけでは不十分です。
部下にネガティブフィードバックを与える目的は、単にミスや問題を指摘することではなく、「理想とのギャップ」を明確に示し、今後どう変化していくべきかを一緒に考えるきっかけをつくることです。叱るだけでは、部下は防御的になり、改善の余地を見つけにくくなります。一方、ほめるだけでは、現状に甘んじて成長の機会を逃すこともあります。
部下が自ら「変わりたい」と思うまでには、まず現状を認識し、その後に危機感を持ち、行動を変えたいという意欲を育み、最終的に自発的な行動につなげるという4つのフェーズを経る必要があります。ネガティブフィードバックには、現状を認識させる価値、危機感を持たせる価値、方向性を示す価値、そして自発的行動を促す価値の4つが含まれています。

第2章 ネガティブフィードバックが難しいのはなぜ?
ネガティブフィードバックが難しいのは、単に上司のスキル不足が原因ではありません。社会的背景には、パワハラ防止や心理的安全性の確保、働き方改革などがあり、上司が耳の痛い話をすること自体がリスクとして認識されやすくなっています。また、若手の早期離職を防ぐために「できるだけ摩擦を避けたい」という心理が働くケースも少なくありません。
さらに、部下側も耳の痛い話を歓迎することはほぼなく、上司側も相手に不快感を与えることを好まないため、双方が避けがちなコミュニケーションになっています。その結果、「やり方を知らない」のではなく「やらないことを選んでいる」という状態に陥りがちです。
しかし、ネガティブフィードバックを避ければ、部下は成長の機会を失い、チーム全体の生産性が低下します。一方で、適切に実施すれば、短期的なストレスはあっても長期的には信頼関係の構築とパフォーマンスの向上につながります。重要なのは、「面倒くさい」「やらされている」という感情が表情や態度から9割伝わるため、上司自身が腹をくくって行うことです。

第3章 ギャップを整理するフレームワーク「WILL」「MUST」「CAN」
ネガティブフィードバックを有効にするには、単なる叱責や指示ではなく、「何がズレているのか」を明確に伝える必要があります。そこで有効なのが、ギャップを「WILL(やりたいこと)」「MUST(やるべきこと)」「CAN(できること)」の3つの軸で整理する方法です。
まず、「WILL」は部下が本当にやりたいこと、達成したい目標を指します。これが不明確なままでは、フィードバックは押し付けに感じられ、行動が続きません。強制的に引き出すのではなく、上司と部下が対話を通じて共有することが重要です。
次に、「MUST」のズレは、期待される業務水準や役割の認識に食い違いがあるときに発生します。そして「CAN」は、スキルや環境、リソースが不足している場合に行動が止まる要因となります。これらを整理し、ギャップを具体的に可視化すれば、部下が自発的に行動を変えるきっかけをつくれます。

第4章 「何を言うか」より「誰が言うか」が重要(日常のマネジメント)
フィードバックは、内容の正しさだけではなく、「誰が言うか」が大きな影響を及ぼします。信頼関係が築けていない状態で耳の痛い話をすれば、逆効果になることもあります。研究によると、38%のフィードバックは逆効果となり、否定され続けることで部下に「学習性無力感」が生まれるとされています。
ポジティブとネガティブの比率は「4:1」が理想とされており、「ほめるところがない」と感じるのは上司や人事の評価スキルの問題であることが多いです。結果ばかりをほめ続けると、部下は過程を軽視し、結果のみに執着する傾向が強まります。
耳の痛い話をする場合でも、信頼関係があることで受け止めやすくなります。定期的な面談は、月1回1時間よりも週1回15分を4回行う方が効果的です。フィードバックは一度に多く詰め込まず、1回につき1つの行動改善に絞ることが原則です。

第5章 ネガティブフィードバックを成功させる心の整え方(5つのマインドセット)
ネガティブフィードバックを行う上司自身の心構えが整っていなければ、内容が正しくても相手に響かず、逆に関係を悪化させるリスクがあります。重要なのは以下の5つのマインドセットです。
- 嫌われることを覚悟する:耳の痛い話をすれば一時的に嫌われる可能性は高いですが、それを恐れていては部下の成長を阻害します。
- 期待するが期待しない:成果を期待しつつ、相手がすぐに変わらないことを受け入れる冷静さが必要です。
- 感情をこめるが感情的にならない:熱意は必要ですが、怒りや苛立ちをぶつけるのは逆効果です。
- 真剣に業務に取り組む:上司が真剣さを示さないと、フィードバック自体が軽んじられます。
- 自分で決める:誰かにやらされて行うのではなく、自分の意思でフィードバックするという主体性が大切です。

第6章 ネガティブフィードバックを成功させる技術 (5つのスキルセット)
ネガティブフィードバックを成功させるためには、単に正論を述べるのではなく、相手の心理状態を理解し、変化を促すための適切な技術を駆使する必要があります。まず重要なのは、「ギャップが存在している」ことに対して相手の合意を得ることです。上司だけが「改善すべき点がある」と認識しても、部下がそれを自覚していなければ行動変容は起こりません。そのためには、現状と理想の違いを客観的なデータや事実をもとに示し、共通認識を作ることが第一歩となります。
次に、人は認知的不協和、つまり現状と理想のズレを強く意識したときに初めて変化を望むようになります。上司は、この不協和を適切に生み出す質問や指摘を行う必要があります。ただし、これが相手を責める言葉になってしまうと、防御反応が生じ、逆効果になることもあるため、注意が必要です。
さらに、「きれいに終わる面談」には注意が必要です。表面上は円満に終わっても、肝心の行動変容に結びついていないケースが多いため、時には面談を中断し、冷却期間を設けることが効果的な場合もあります。面談中は「話すより聴く」姿勢を徹底し、部下が自分自身の課題に気づくきっかけをつくることが重要です。そして、最終的に改善が見込めない場合には「諦める(明らかに見極める)」ことも必要であり、リソースの無駄遣いを防ぐために決断を下すことが求められます。
また、オンラインでのフィードバックは非言語的要素が伝わりにくいため、特に注意が必要です。画面越しでも誠意が伝わるように表情や声のトーンに気を配り、誤解を招かないように面談を5段階構造で整理して臨むことが効果的です。

第7章 パワハラにならない伝え方のポイント
ネガティブフィードバックを行う際、誰もが気になるのが「パワハラにならないか」という問題です。実際、上司の多くがこの懸念を抱いています。パワハラを避けるためには、相手の「性格」を攻撃せず、「行動」と「事実」に基づいて話すことが鉄則です。例えば、「君はだらしない」という言い方ではなく、「会議の開始時間に3回連続で遅れてきている」という具体的な事実を指摘することで、攻撃的にならずに問題を伝えることができます。
また、いくら論理的に正しい指摘でも、相手を追い詰めてしまうような言い方はNGです。「もうあなたには期待していない」といった言葉は、改善意欲を根こそぎ奪ってしまいます。優しすぎる上司が陥りやすいのは、相手を傷つけたくないあまり、問題を放置してしまうケースです。結果的にそれが部下の成長を妨げ、チーム全体に悪影響を及ぼします。
初回の面談は特に感情的になりやすく注意が必要です。お互いに構えてしまい、会話がヒートアップすることもあります。自分がどのような場面で怒りやイライラを感じやすいかをあらかじめ把握し、感情をコントロールできるよう準備しておくことが重要です。

第8章 「ぶら下がる年上部下」「すぐ辞める若手部下」への向き合い方
職場にはさまざまなタイプの部下がいます。特に、年上のベテラン社員がやる気を失い「ぶら下がり状態」になっているケースや、若手社員がすぐに退職を選ぶケースは、多くの上司が直面する問題です。
ベテラン社員の中には、「あと数年で定年だから」と成長を諦めているように見える人がいます。しかし、年齢に関係なく、人は誰しも「認められたい」「ほめられたい」という欲求を持っています。実際には「WILL(やりたいこと)」が見えにくくなっているだけで、適切なコミュニケーションを取れば再びやる気を取り戻す可能性があります。
一方で、若手社員の中には「成長の余地がない」「環境が合わない」と感じるとすぐに退職を選ぶ人が増えています。ここで大切なのは、上司側の価値観や物語(ナラティブ)と、部下側のナラティブが食い違っていることを前提に話すことです。相手の背景や考えに共感し、まずは理解する姿勢を見せることで、関係性は驚くほど改善します。

第9章 部下から上司へフィードバックする(ボスマネジメント/受ける側のポイント)
フィードバックは上司から部下に与えるだけではなく、部下から上司に伝えることも大切です。ネガティブフィードバックは「貴重なギフト」であり、関係性を良くするチャンスでもあります。例えば、上司の行動がチームに悪影響を与えている場合、陰口を言うのではなく、思い切って「表口」で伝えることが、組織改善の一歩となります。
上司に望ましい行動を促す技術は「ボスマネジメント」と呼ばれます。上司を正面から批判するのではなく、建設的な意見として伝えることがポイントです。クライアントやコミュニティ、友人関係においても同じで、相手が受け入れる準備が整っていない場合には、無理に指摘せず静観することが大切です。タイミングと伝え方が整えば、フィードバックは信頼感を高め、より良い関係を築くきっかけとなります。

対象読者

この書籍は、職場での人間関係やコミュニケーションに課題を感じている方に向けて書かれています。特に、部下や上司との関わり方に悩んでいる方が、より良い関係性を築き、チームの成果を高めるためのヒントを得られる内容です。
具体的には、次のような立場や悩みを持つ方におすすめです。
- 管理職・リーダークラスの上司
- 部下との信頼関係構築に課題を感じている管理職
- パワハラを避けつつ指摘したい上司層
- 年上部下を持つ上司
- 部下から上司へフィードバックをしたい人
それぞれの立場がどんな悩みを抱きやすいのか、またどんな状況で役立つ知識が必要になるのか、詳しく見ていきましょう。
管理職・リーダークラスの上司
この書籍は、組織やチームを率いる立場にある管理職やリーダークラスの上司にとって、非常に有用な一冊です。多くのマネジメント層が抱える課題のひとつに、部下に対して「伝わるように」言葉を届ける難しさがあります。自分の意図が正しく伝わらず、指示や方針が理解されないまま進んでしまうと、チームのパフォーマンスが低下したり、モチベーションが下がる要因となります。
本書では、リーダーとしてチームを動かすための言葉の使い方を具体的に示しています。例えば、メンバーに仕事を任せるときの表現や、会議で発言する際の言い回し、チームの雰囲気を前向きに導く声かけのポイントなど、実践的なノウハウが豊富に紹介されています。これらの内容は、管理職として日常的に直面する場面に直結しており、すぐに使えるのが特徴です。
さらに、部下が安心して意見を言える関係づくりや、やる気を引き出す声かけの方法についても丁寧に解説されています。本書を通じて、リーダーが持つ言葉の力を最大限に活かすことで、より強いチームを作り上げるための一歩を踏み出せるでしょう。

部下との信頼関係構築に課題を感じている管理職
部下との関係がうまく築けず、会話が表面的になってしまったり、報告や相談が少なくなることで悩んでいる管理職は少なくありません。信頼が欠けた状態では、どれほど指示を出しても思うように動いてもらえず、チーム全体の成果にも影響が出てしまいます。
この書籍は、そうした状況を改善したい管理職に役立つ内容が詰まっています。本書では、まず部下が安心して話せる空気を作ることの重要性を強調しています。そして、そのためには「伝え方」が非常に大きな役割を果たすと解説しています。
信頼が築かれると、部下が自発的に動くようになり、チームの雰囲気も良くなります。本書の知識を実践することで、上司と部下の関係が一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションへと変わっていくでしょう。

パワハラを避けつつ指摘したい上司層
必要な指摘や注意をしたいのに、パワハラと受け取られることを恐れて言えない──そんなジレンマを抱える上司層は少なくありません。厳しく注意しすぎると関係が壊れる一方で、何も言わなければ部下の成長が止まってしまう。この難しいバランスに悩む方に、本書は強くおすすめです。
本書では、相手を傷つけず、改善点をしっかり伝えるための方法を具体的に示しています。人格を否定せず、あくまで行動や事実にフォーカスした指摘の仕方、冷静さを保ちつつ建設的なアドバイスをするためのフレーズなどが紹介されており、指摘を受けた側が前向きに行動できるようになる工夫が学べます。
また、誤解を生みにくい表現や、相手の立場を尊重した話し方を心がけることで、職場の人間関係を壊さずに改善を促せるようになります。こうしたスキルは、管理職として部下を育てる上で欠かせないものです。

年上部下を持つ上司
自分より年齢が上で経験豊富な部下に指示を出すことに、気を遣う上司は多いものです。立場上は上司であっても、相手の経歴や年齢を考えると、思ったことをストレートに言えず、結果として遠回しな指示になってしまうことがあります。
この書籍では、そうした難しい状況をうまく乗り切るための「伝え方」に焦点を当てています。相手のプライドを傷つけずに指示を出す方法や、経験を尊重しながらも必要な改善点を伝えるテクニックが紹介されています。これにより、年齢差による気まずさを減らし、円滑に仕事を進められるようになるでしょう。
また、年上部下の強みを活かしつつ、上司としてのリーダーシップを発揮するバランスの取り方についても解説されており、現場でそのまま活用できる内容になっています。

部下から上司へフィードバックをしたい人
上司に対して自分の意見や改善提案を伝えることは、多くの部下にとって勇気が必要な行動です。関係が悪化したり、誤解を生むのではないかと不安を感じて、言うべきことを飲み込んでしまうケースは少なくありません。
本書では、そうした状況を打開するための安全で建設的なフィードバック方法を紹介しています。相手を否定することなく、自分の意見を冷静に伝えるフレーズや、上司が受け入れやすいタイミング・話し方の工夫が詳しく解説されています。
このスキルを身につけることで、上司と部下の関係がよりオープンになり、職場全体のコミュニケーションが活性化します。結果として、チームが協力的に動けるようになり、組織全体の成長にもつながります。

本の感想・レビュー

統計や理論に裏づけされていて納得
私はビジネス書を読むとき、著者の主張が感覚や経験談に偏りすぎていないか、根拠のある内容になっているかを重視しています。この本は冒頭から、心理学や行動科学の研究成果をベースにした解説が多く、読み進めるほど納得感が増していきました。特に、フィードバックが相手にどう受け止められるかを決める要素について、データや過去の研究結果を交えて説明している部分が印象的でした。
これまで私は、「部下が落ち込んでしまったらどうしよう」「言葉がきつすぎて嫌われたら困る」と感覚的な不安を抱きながらフィードバックをしていました。しかしこの本では、その不安の裏にある心理メカニズムをきちんと明らかにしてくれるため、「これは感情論ではなく、脳や心理の仕組みによる自然な反応なのだ」と理解でき、必要以上に気を使いすぎることがなくなりました。
さらに、ネガティブフィードバックを受け入れやすくするための条件や、相手が防御反応を示す場面の特徴を統計的に説明している章は、私の中の「経験頼りの曖昧な感覚」を整理し、実務で活かせる理論的な軸を持たせてくれました。
「嫌われる覚悟」のメッセージが胸に刺さる
私はこれまで、部下に指摘をする場面になると、できるだけやわらかい言葉を選び、相手が傷つかないようにと気を遣いすぎるあまり、伝えるべきことを曖昧にしたり、最終的に言わないまま終わらせたりすることが多かったのです。
しかし、この本を読み進めるうちに、そうした態度が相手の成長を妨げている可能性があると気づきました。本当に相手の未来を考えるなら、多少嫌われるかもしれないリスクを受け入れてでも、正直に伝える勇気が必要だと書かれており、そのメッセージは胸に深く突き刺さりました。
読み終えた後は、自分がこれまで避けてきた場面を思い返し、「あのとき逃げずに伝えていれば、あの人はもっと良い方向に進めたかもしれない」と悔しさを覚えるほどでした。同時に、これからは嫌われることを恐れるよりも、相手の未来に責任を持つフィードバックをしていこうと決意させられた一冊です。
心理法則の解説が具体的でわかりやすい
私は心理学の知識がほとんどないため、専門用語が並ぶ本はどうしても読みにくく感じます。ですが、この本は難しい理論をシンプルな言葉で解説しており、すぐに理解できるのが魅力でした。特に、フィードバックを受け取る際に人間がどのような認知の歪みや感情の反応を起こしやすいのか、その仕組みを具体的に説明してくれている点が印象に残っています。
「なぜ相手は指摘を素直に受け入れられないのか」「なぜ防御反応を起こすのか」を、感情論や性格の問題として片付けるのではなく、心理法則としてわかりやすく示してくれるので、無駄なイライラや誤解が減りました。これまで私は、相手が反発するのは自分の言い方が悪いからだと自分を責めがちでしたが、心理的な仕組みを知ることで冷静に対応できるようになりそうです。
この本を読むことで、相手の気持ちや反応を理解しつつ建設的な会話を進めるための土台ができたと感じています。心理学の知識を実務に落とし込む方法が明快で、とても有益な内容でした。
WILL を自然に引き出す対話手法が参考になった
本書を読んで一番新鮮だったのは、「相手が自分の意志で動き出すためのフィードバック」という考え方でした。私はこれまで、改善点を指摘して「これをやってほしい」と伝えることで仕事を前に進めてきましたが、相手が本心から動きたいと思っているかどうかはあまり意識していませんでした。
この本では、相手のWILL、つまり「自分からこうしたいと思う気持ち」を引き出すための会話の進め方が丁寧に解説されていました。話の聞き方、質問の投げ方、相手が自分の言葉で行動を決められるよう促す方法が具体的に書かれており、読みながら「こうすれば自然に相手が主体的に動けるんだ」と納得できました。
一方的に指摘を伝えるのではなく、相手と同じ方向を見ながら未来を考えるスタンスが重要だと強く感じました。フィードバックを「押し付けるもの」から「相手が自ら選び取るもの」に変えていくためのヒントが満載で、読み終わったあと自分の伝え方を根本から見直したくなる内容でした。
フィードバック頻度を増やす提案が現場向け
日々部下と接していて、フィードバックをするタイミングに悩むことが多くあります。私はこれまで「大事なことがあるときだけ話す」というスタンスで臨んでいましたが、この本では、頻度を増やすことでフィードバックが特別なイベントではなく、自然な対話の一部になると説明されていました。
この考え方を読んだとき、心底納得しました。フィードバックを構えた場でしか行わないからこそ、言われる側は緊張し、防御的になってしまうのだと気づきました。本書では、短くてもいいから日常の中で継続的にフィードバックを行う重要性が書かれており、その積み重ねが信頼関係を築きやすくすると述べられていました。
読んでいる間、これまでの自分のやり方を振り返り、「もっと気軽に、もっと頻繁に話せばよかった」と思う場面が次々に浮かびました。特別な指導の場を設けなくても、日常の中で言葉を交わせる関係を作る大切さを教えてくれた一冊です。
認知的不協和の使い方が目からウロコ
正直、この本を読むまでは「ネガティブフィードバック=嫌なもの、避けたいもの」としか思っていませんでした。しかし、認知的不協和を活用するという考え方に触れ、目からウロコが落ちました。
人が自分の行動や結果と自分の理想像がズレているときに強い動機づけが生まれる、という心理法則をフィードバックに応用できると知り、驚きました。これまで私は、相手に気を遣ってあいまいに指摘してしまい、結果的に行動が変わらないことにモヤモヤしていましたが、この本を読んで、相手が「自分で気づく」よう促す大切さを理解しました。
文章の説明が具体的で、相手の思考を自然に変化へ導く会話の流れが書かれているので、「こうすれば自分の言葉で気づきを持ってもらえるのか」と納得できます。フィードバックをただの指摘ではなく、相手の変化を後押しする機会にできる方法が明快に示されていて、読む前よりも前向きにフィードバックと向き合えるようになりました。
部下の反発を受け入れる視点に安心感
私はこれまで、部下がフィードバックに反発したり、言い訳をしてきたりすると、どう対応すればいいのかわからず、会話がぎこちなくなることが多かったです。この本では、そうした反発が起きるのは自然なことだと書かれており、それだけでも心が軽くなりました。
特に印象に残ったのは、「反発は成長への入り口になる」という視点です。指摘を受け入れる準備が整っていない相手を否定せず、受け止めることで建設的な対話につなげられるという説明がありました。これまで私は、反発されると「伝え方が悪かったのか」と自分を責めたり、「なんで素直に聞けないのか」と相手に苛立ったりしていましたが、この本を読んで、反発を想定内の反応として受け止める余裕が持てそうです。
読後は、フィードバックの場面が怖くなくなりました。反発も含めて前進のためのプロセスだと考えられるようになったのは、この本のおかげだと思います。
パワハラと誤解されないための配慮が具体的
最近はフィードバックの言葉一つでパワハラだと受け取られることもあり、正直なところ、指摘をするのが怖いと感じる場面が増えていました。この本では、その不安に寄り添うように「パワハラと誤解されないための工夫」が具体的に書かれていて、とても助けられました。
特に、フィードバックをする前の関係性作り、相手に対する敬意を示す表現、そして言葉の選び方について細やかな解説があるのが印象的でした。自分の言い方を客観的に見直せるチェックポイントが多く、これなら誤解を防ぎつつ本音を伝えられると感じました。
この本を読む前は、強い表現を避けすぎて結果的に何も伝わらないことも多かったですが、今は「どう言えば安全に伝えられるか」という道筋が見えた気がします。フィードバックに勇気が持てるようになったのは大きな収穫でした。
まとめ

この記事の最後では、この本を通じて得られる具体的な効果や、学んだ知識をどう次の行動に繋げるか、そして総合的な結論を整理します。
ポイントを分かりやすく把握できるよう、以下の内容に沿って解説していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
本を読むだけで終わらせるのではなく、知識を実生活や仕事に役立てる視点を持つことが重要です。それぞれの要素をしっかり理解して、自分の成長や成果につなげていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、読者がこの本から得られる大きな利点を、具体的に紹介します。
ネガティブな内容を「衝突」ではなく「成長の機会」に変えられる
多くの人が「叱る」ことを嫌がる理由は、相手との関係が壊れるリスクがあるからです。本書は、ネガティブな指摘を相手の人格を否定するものではなく、「認識ギャップを埋める行為」として捉え直す方法を提示しています。これにより、言いにくいことも相手を追い詰めず、未来志向の話し合いへ変換できるようになります。
冷静に伝えるための「心の整え方」が身につく
感情が高ぶったまま伝えると、どんなに正しい内容でも反発を招きやすくなります。本書では、嫌われる覚悟を持つことや、自分の感情を整える方法、相手への期待値の調整など、伝える前に必要な心構えを学べます。これにより、フィードバックの場が感情的な衝突ではなく、冷静な対話の場へと変わります。
「伝え方の型」を習得し、迷わず実践できるようになる
多くの人が失敗する原因は、「何をどう言えばいいか」を場面ごとに考えすぎてしまうことです。本書は、WILL・MUST・CANのフレームワークを活用し、認識のズレを整理したうえで伝える手順を明確化しています。この型を使えば、相手を不必要に傷つけず、それでいて曖昧に終わらない建設的な指摘が可能になります。
上司と部下の間に信頼関係を構築しやすくなる
フィードバックがうまくいくかどうかは、内容そのものよりも「誰が言うか」に左右されることが多いとされています。本書は、短い接触機会を日常的に積み重ねる方法を紹介し、信頼残高を増やすことで、耳の痛い話も素直に受け止めてもらえる関係を築く方法を教えてくれます。
相手だけでなく、自分自身も成長できる
ネガティブフィードバックは、相手を正すだけのものではありません。本書を読むことで、伝える側の自己管理力、観察力、対話力が飛躍的に向上します。さらに、相手の反応を受け取りながらフィードバック手法を改善していくことで、自分自身も「信頼されるリーダー」として成長できるようになります。

読後の次のステップ
本書を読み終えた後に大切なのは、知識を頭の中に留めておくだけでなく、実際のコミュニケーションの場で使えるスキルとして身につけることです。
以下では、実践力を養い、さらにスキルを進化させるための具体的なアクションを紹介します。
step
1小さな場面で実践を繰り返す
いきなり大きな問題や重大な場面でネガティブフィードバックを試すと、心理的な負担が大きくなり、うまくいかない可能性があります。まずは日常の些細なやり取り、例えばチーム内の軽微なタスクの進め方や、友人との意見のすれ違いなど、リスクが低い場面で練習を重ねましょう。小さな成功体験を積むことで、伝えることへの抵抗が減り、自然にフィードバックができるようになります。
step
2伝え方のパターンを記録・分析する
実践を重ねる中で、同じように伝えても相手によって反応が異なることに気づくはずです。そのときは、自分が使った言葉や表現を記録し、どのアプローチが効果的だったかを振り返ることが重要です。こうした分析を繰り返すことで、自分なりの“成功パターン”が見えてきて、より相手に合わせた柔軟なフィードバックができるようになります。
step
3信頼関係づくりを日常的に意識する
ネガティブフィードバックは単発で行うものではなく、日々の関わりの延長線上で成り立つものです。本書で紹介されている「承認と改善のバランス」や「話を聴く姿勢」を普段から実践し、相手が安心して耳を傾けられる関係性を築くことが大切です。信頼がある状態であれば、ネガティブな内容もポジティブに受け止めてもらいやすくなります。
step
4定期的に振り返りと改善を行う
ネガティブフィードバックは一度やれば終わりではなく、継続的な対話の中でブラッシュアップされていきます。定期的に自分の伝え方を振り返り、「もっと相手が前向きになれる言い方はなかったか」「タイミングは適切だったか」を検討することで、技術を磨き続けることができます。

総括
本書は、単なる「言いにくいことを伝えるコツ」を解説するだけのハウツー本ではありません。ネガティブフィードバックを、相手を傷つける行為ではなく、信頼関係を強化し、双方の成長を促すための重要なコミュニケーションスキルとして位置づけています。多くの人が抱く“ネガティブフィードバック=対立や衝突を生むもの”という誤解を解きほぐし、建設的かつ前向きに伝えるための実践的アプローチを提示しているのが大きな特徴です。
本書を通じて学べるのは、単に表現方法を改善するだけではなく、自分自身の心構えを整える重要性です。相手の立場を尊重し、信頼をベースに言葉を選び、感情を不必要にぶつけることなく意図を正確に伝えることで、関係を壊すことなく改善を促せるというメッセージが全体を通して繰り返し語られています。これは、日常の人間関係はもちろん、ビジネスの現場でも極めて価値の高い考え方です。
さらに、本書が他の類書と異なる点は、具体的なセリフ例や場面ごとの対応方法だけでなく、「なぜ人はフィードバックを受け入れづらいのか」「心理的安全性がなぜ必要か」といった背景要因まで掘り下げて解説している点です。これにより、表面的なテクニックに頼らず、本質を理解したうえでのアプローチが可能になります。

総じて、本書はネガティブフィードバックを“恐れるもの”から“成長を支えるツール”へと認識を変えるきっかけを与えてくれる一冊です。
読後には、伝えることへの心理的抵抗が軽減され、より誠実で建設的な対話ができる土台が整っているはずです。これは、個人の成長はもちろん、チームや組織全体の関係性向上にも大きく寄与する知識といえるでしょう。
ビジネスに関するおすすめ書籍

ビジネス本に関するおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 新しい知識やスキルが身に付く、おすすめのビジネス書 !人気ランキング
- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか
- 人望が集まる人の考え方
- 実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた
- ビジネスフレームワークの教科書 アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55
- 解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法
- 苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」
- 頭のいい人が話す前に考えていること
- タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ
- サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学
- THINK BIGGER 「最高の発想」を生む方法
- エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする
- プロフェッショナルマネジャー
- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

