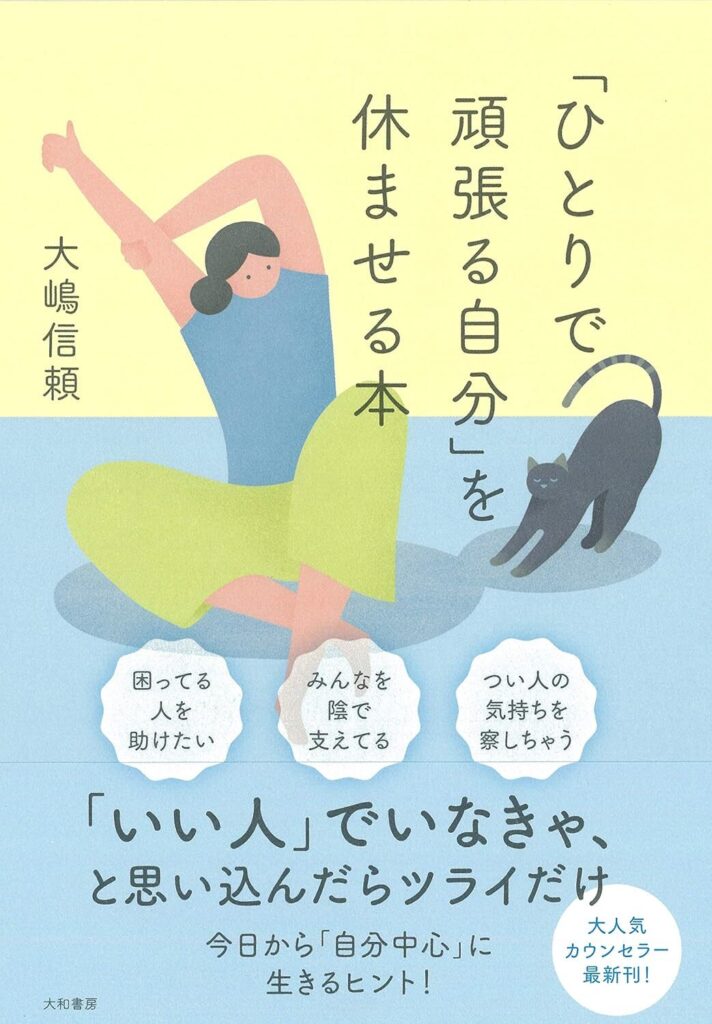
「私がもっと頑張れば、きっと周りが変わるはず」——そう信じて、職場や家庭で「いい人」を続けてきたあなたへ。
その優しさや気遣いが、いつの間にか自分自身を苦しめていませんか?どんなに尽くしても感謝されない、むしろ冷たくされたり、損ばかりしている気がしたり…。そんな経験を抱えたことがある人にこそ読んでほしいのが、本書『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』です。

「頑張っているのに報われない…」そんな思いを抱えている人は、ぜひ本書で、自分らしく輝くためのヒントを見つけてみてください。
あなたの人生が、もっと自由で楽しくなる一歩がここにあります。

合わせて読みたい記事
-

-
努力がテーマのおすすめの本 9選!人気ランキング【2026年】
「努力」をテーマにした本には、私たちの人生を変える力があります。 成功の影にある苦労や挫折をどのように乗り越えるのか、そしてその先にある達成感をどう感じるのか――そんなリアルな体験談や実践的なアドバイ ...
続きを見る
書籍『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』の書評

書籍『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』は、心理カウンセラー大嶋信頼氏による、自己犠牲的な「いい人」から脱却し、健全な「自分中心」の生き方を取り戻すための指南書です。
この書評では、本書を深く理解するために、以下の4つのテーマに分けて詳しく解説します。
- 著者:大嶋 信頼のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:大嶋 信頼のプロフィール
大嶋信頼(おおしま のぶより)氏は、日本屈指の心理カウンセラーとして知られています。米国の私立アズベリー大学心理学部を卒業後、アルコール依存症専門病院や東京都精神医学総合研究所などで経験を積み、心理療法の専門家として活躍してきました。これまでに30年以上のカウンセリング歴と、9万件を超える臨床経験を誇ります。
特筆すべきは、大嶋氏が開発した「FAP療法(Free from Anxiety Program)」です。これは、トラウマや依存症、自己肯定感の低下などに悩むクライアントに対し、過去の記憶や感情を解放し、本来の自分を取り戻す手助けをする画期的な心理療法です。FAP療法は「無意識の領域」に働きかける手法であり、言葉にしづらい不安感やモヤモヤを抱える人々から高い支持を集めています。

本書の要約
本書は、自己犠牲的に「いい人」を演じてしまい、人間関係や自分自身に疲れてしまう人が、自分らしく生きる方法を実践的に学べる内容になっています。全6章構成で、段階的に「いい人」をやめて自分を大切にするステップを紹介しているのが特徴です。
具体的には、人間関係でありがちな「いい人」を演じることで相手が「悪い人」になりやすいという恒常性のメカニズムや、自分の「快・不快」スイッチをオンにして本音を見つける方法、自己肯定感を阻む「万能感」を捨てる重要性、そして「罪悪感」を解消していく過程が詳しく解説されています。さらに、自分の世界の中心に自分を置くことで、人間関係が楽になり、最終的には「嫌われる」ことを怖がらずに生きられるようになるまで、丁寧にステップアップしていく内容です。
本書では、心理学や脳科学に基づいた視点だけでなく、著者が実際に行ったカウンセリングの事例も豊富に盛り込まれているため、現実的かつ実践的なアドバイスが随所に散りばめられています。

本書の目的
本書の目的は、一言でいうと「自己犠牲的な生き方から卒業し、自分を中心に据えて幸せを実感する生き方にシフトする」ことです。そのために、著者は読者が「いい人」をやめるために、無理をして相手に合わせてしまうメカニズムを紐解き、そこから自由になる方法を提示しています。
特に、「快・不快」スイッチという自分の感情のバロメーターを活用し、他人に振り回されるのではなく、自分の本音に従った選択をすることの大切さが繰り返し説かれています。また、「罪悪感」や「万能感」を手放すことで、本来の自分を取り戻し、自分をもっと愛してあげられるようになることがゴールとして描かれています。
この本の目的は単なる自己啓発にとどまらず、実生活の中で実践できるように、著者の豊富な臨床経験に基づいた具体的なステップが紹介されているのも大きな特徴です。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者から高い評価を受けている理由は、大きく分けて3つあります。第一に、著者が心理カウンセラーとして長年培ってきた臨床経験が随所に活かされており、専門的でありながら実践的なアドバイスが豊富に詰まっています。理論だけでなく、「快・不快スイッチ」や「罪悪感の捨て方」など、誰でもすぐに日常で試せる具体的なヒントが満載です。
第二に、専門用語を避け、平易な言葉で書かれているため、心理学初心者でもスラスラと読める点が魅力です。堅苦しさがないので、あまり本を読まない人でも挫折せずに最後まで読み進められます。
そして第三に、実際の事例が豊富に紹介されていることです。「ああ、私もこういうことあるな」と共感しやすく、読み進めるうちに「私にもできるかもしれない」と勇気が湧いてくるような作りになっています。こうした共感と安心感が、多くの読者を惹きつけてやまない理由です。

本の内容(目次)

この本では、自己犠牲的な「いい人」から脱却し、自分を大切にする方法を段階的に学べるように構成されています。全6章を通して、心理学と実践的なテクニックを交えながら、自分を中心にした生き方を提案しています。
以下の項目ごとに詳しく解説します。
- 第1章 「いい人」になるほど嫌われる
- 第2章 「快・不快」スイッチを起動させる
- 第3章 自己肯定感をジャマする「万能感」を捨てる
- 第4章 過去にとらわれる「罪悪感」を消す
- 第5章 「世界の中心」を自分にする
- 第6章 「嫌われる」がこわくなくなる
それでは、それぞれの内容を順に見ていきましょう。
第1章 「いい人」になるほど嫌われる
第1章では、いわゆる「いい人」を演じ続けることで、なぜか周囲から嫌われたり利用されたりしてしまうメカニズムを徹底的に解説しています。ここで重要なキーワードは、心理学でいう「恒常性(ホメオスタシス)」という概念です。これは、本来は人間の体温や血圧などを一定に保つための仕組みですが、人間関係においても同じように「バランスを取ろうとする力」が働くというのです。
たとえば、あなたが「いい人」でいようと頑張りすぎると、そのバランスを保とうとして、周囲の人が無意識のうちに「悪い人」役を演じ始めます。すると、あなたがどれだけ善意で行動しても、「なんだか都合よく使われてるだけかも」「助けているのに感謝されない」といった状況に陥ってしまうのです。
さらに、この章では、職場で他人の仕事を手伝いすぎて自分の負担が増える例や、友人関係でいつも気を遣ってしまい、自分ばかりが疲弊してしまう状況など、実生活での具体的なエピソードがいくつも紹介されています。こうした実例を通して、読者は「いい人」でいることで生じる人間関係の歪みを実感できるようになります。

第2章 「快・不快」スイッチを起動させる
第2章では、「自分の気持ち」を感じることの大切さをテーマに、自分の「快・不快スイッチ」を起動させる方法が詳しく解説されています。「いい人」になりがちな人ほど、他人の気持ちや期待を優先するあまり、自分の感情を置き去りにしてしまう傾向があります。その結果、相手の機嫌や空気を読みすぎて振り回され、「嫌われないためなら何でもしよう」と無意識に頑張ってしまうのです。
本章では、こうした負のループを断ち切るために、まずは「自分が心地よいのか、不快なのか」をしっかり感じ取る練習から始めることが勧められています。たとえば、「頼まれたけど気が進まない」と感じた時、その違和感を大切にして行動を決めるというシンプルなステップです。これは心理学でいう「セルフアウェアネス(自己認識)」を高めるトレーニングでもあります。
また、「親の快・不快スイッチから抜け出す」というテーマにも触れられており、幼少期に親の期待に合わせて行動してきた人が大人になっても無意識に「いい人」を演じ続けてしまう仕組みが具体例を交えて解説されています。これにより、「いい人」をやめることへの罪悪感が自然と軽減されていくのです。

「快・不快スイッチ」は、心理学的に言うと「自己認識」のスタート地点。
自分の心が本当に求めているものをキャッチする第一歩です。
第3章 自己肯定感をジャマする「万能感」を捨てる
第3章では、「自分が何でもできる」と思い込んでしまう「万能感」がテーマです。一見するとポジティブな考え方のようですが、実はこれが「いい人」タイプの人にとっては大きな落とし穴になります。なぜなら、万能感を抱える人は「自分がもっと頑張れば相手の問題も解決できる」と背負い込んでしまい、結果的に自分を責めてしまうという悪循環に陥りやすいのです。
たとえば、仕事でトラブルが起きた時、みんなが困っているのを見て「自分が頑張ればなんとかなる」と無理をしてしまう。あるいは、恋人や家族が悩んでいるときに「私が全部支えなきゃ」と過剰に責任を感じてしまう。こうした行動は、一見「優しい人」ですが、自分自身の限界を無視してしまうので、最終的には疲弊してしまいます。
この章では、「万能感をコントロールしようとしない」というアドバイスが提示されており、「許すだけでいい」というシンプルかつ実践的なステップが紹介されています。特に、「いい人になって救いたいのは、実は過去の自分だった」という一文は、過去の自分を責め続けてきた読者の心に深く響くでしょう。

「万能感」は心理学で言うと「自他境界のあいまいさ」に繋がります。
他人の問題まで背負い込まないことが、自己肯定感アップの第一歩なんです。
第4章 過去にとらわれる「罪悪感」を消す
第4章では、誰しもが抱えがちな「罪悪感」について深く掘り下げています。特に「自分のせいで相手を傷つけたかもしれない」という思い込みが、実は他人からのコントロールの入り口になっていることを解説しています。この章を読むと、過剰な罪悪感を手放すことが、他人の評価や支配から自由になる大きな鍵であることがわかります。
たとえば、同僚に頼まれごとを断っただけで「嫌われたかも」と落ち込む人は多いでしょう。でもそれは、相手が困っているのを自分の責任だと感じる「罪悪感のワナ」にはまっているからです。本章では、「あえて他人の力に乗っかる」という意外な手法で、自分で何もかも背負い込まずに済む具体的なヒントが紹介されています。
さらに、「頼みごとを断った自分を責めない」ことや「ふりをやめれば信頼される」という逆説的なアドバイスもあり、読者は「いい人」を演じ続ける苦しさから抜け出すための心理的テクニックを学べます。

罪悪感は「他人をがっかりさせたくない」という優しさから生まれることが多いんです。
でも、それを抱えすぎると自分の心が潰れてしまいます。
第5章 「世界の中心」を自分にする
第5章では、「自分中心」の生き方がテーマです。ここでいう「自分中心」とは、決して「わがままに振る舞え」という意味ではなく、「自分の感情や快・不快を大切にして選択していくこと」です。自分が幸せでいることで、周りの人間関係も自然に良い方向へ回っていくという心理的メカニズムが説明されています。
たとえば、間違いをしてしまったときに、「私はなんてダメなんだ」と必要以上に反省してしまう人がいますが、本章では「間違いは認めても反省はしない」と割り切ることの大切さを教えてくれます。これは、失敗から学ぶ姿勢を持ちつつも、過度に自分を責めず、前向きに進むための実践的なアドバイスです。
また、「困った人を手助けせずに観察する」という一見ドライに思える提案も、自分を犠牲にしすぎず、相手の問題を相手に返すことでお互いに健全な距離感を保つ方法として紹介されています。こうしたアプローチを実践することで、読者は周囲との関係を楽にしつつ、自分らしい人生を生きられるようになります。

第6章 「嫌われる」がこわくなくなる
最終章では、「嫌われること」が怖くて「いい人」をやめられない人のために、他人からの評価に振り回されずに自分らしく生きる方法が解説されています。特に、「自分中心」になる過程で周りから嫉妬されやすくなるという心理的現象を解説し、その乗り越え方が詳しく語られています。
「足の裏の感覚で嫉妬をやり過ごす」というユニークな方法や、「嫌い」は態度に出てもいいというアドバイスが、読者に安心感を与えてくれます。また、他人への嫉妬や「怖くてできなかったこと」を思い切ってやってみることで、新しい自分を発見できるというメッセージが込められています。
特に印象的なのは、「人の幸せを願いすぎるあなたへ」というセクション。他人の幸せを願うあまり、自分が疲弊してしまう人に向けて「まずは自分の幸せを優先していいんだよ」と背中を押してくれる内容になっています。

対象読者

本書『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』は、心理学と脳科学の視点から、人間関係で「いい人」を演じてしまいがちな方が、自分を大切にしながら周囲とも調和のとれた関係を築けるようになるためのヒントが詰まった一冊です。
特に、以下のような方々に強くおすすめします。
- 人間関係で疲弊している方
- 自己肯定感が低いと感じている方
- 他人の期待に応えようと無理をしている方
- 人間関係でストレスを感じている人
- 自分をもっと大切にしたいと考えている方
それぞれの対象者がどんな悩みを抱えやすいのか、そして本書を読むことでどのような気づきや変化が得られるのかを、順番に解説していきます。
人間関係で疲弊している方
「周りの人の顔色ばかり気にして、気がつけば自分ばかり我慢している」——そんなふうに感じている方はいませんか?職場でも家庭でも、誰かのために一生懸命になってしまう優しいあなたは、知らず知らずのうちに自分の心や体をすり減らしているかもしれません。
本書では、そうした「いい人」になってしまう背景には、人間関係の「恒常性」という無意識のバランス調整があると教えてくれます。例えば、あなたが頑張りすぎると、周りの人が逆に「悪い人」のように振る舞ってバランスを取ろうとしてしまうのです。結果として、「こんなに頑張っているのになんでうまくいかないんだろう」と感じてしまう負のループに陥ります。
そんな人間関係の不思議を知るだけで、「私のせいじゃなかったんだ」と心が少し軽くなるはずです。頑張りすぎて疲れてしまったあなたに、この章は大きな気づきを与えてくれるでしょう。

人間関係の恒常性は、誰かが「いい人」を演じると周りに「悪い人」が必要になるバランスの法則。
これを知るだけでも気持ちが楽になります。
自己肯定感が低いと感じている方
「どうせ私なんてダメなんだ」「頑張ってもどうせ報われない」と、自分を責めることが多い方もいるのではないでしょうか。自己肯定感が低いと、人に嫌われるのが怖くて「いい人」でい続けてしまいがちです。
この本では、そんなあなたに「いい人でいることが自己肯定感を下げてしまう」という意外な真実を教えてくれます。人に尽くしてばかりいると、自分の本音がわからなくなり、自分の存在価値を誰かに決めてもらおうとしてしまうんです。「かわいそう」と思って助けようとする行為も、実は相手を信じていない証拠だと気づけたら、自分を大切にすることの本当の意味が見えてきます。
自己肯定感を育てるには、万能感(私が頑張れば相手を変えられるはずという思い込み)を捨てることが大切だというメッセージは、頑張り屋さんの心に響くはずです。

自己肯定感は、心理学で「自分の存在に価値がある」と感じられる感覚のこと。
頑張りすぎなくても「今の自分で大丈夫」と思えることが大切です。
他人の期待に応えようと無理をしている方
「頼まれたら断れない」「相手に合わせてばかりで疲れる」——そんな人は、この章で大きなヒントを得られるはずです。特に、日本人は「相手を優先しなければならない」と思い込みがち。でもその優しさが、自分の気持ちを押し殺してしまっていることに気づいていますか?
本書では、自分の「快・不快スイッチ」に気づくことで、自然に「やりたいこと」「やりたくないこと」が見えてくると解説しています。「断ることが相手への優しさになる場合もある」と知れば、「断るのが怖い」という思い込みがほどけていくのです。
また、親から受け継いだ「いい人でいなきゃ」という刷り込みを解放するアプローチもあり、自分の心に素直になることで人間関係がラクになる感覚を味わえます。

人間関係でストレスを感じている人
「周りに気を遣ってばかりで疲れる」「どうしてこんなに生きづらいんだろう」そんなモヤモヤを抱えている人も多いでしょう。人間関係がうまくいかないのは、自分に問題があるからではなく、「いい人」でいようとするクセが原因かもしれません。
この本では、人間関係のストレスの正体を解き明かし、「他人のために生きる」のではなく、「自分のために生きる」ことでストレスが減っていく仕組みを教えてくれます。自分中心になることは決してワガママではなく、自分を大切にする一歩です。
「私が我慢すれば丸く収まる」と思い込んでいた方も、本書を読むことで「私だって自分の人生を大切にしていいんだ」と気づけるはずです。

自分をもっと大切にしたいと考えている方
「自分を大切にしよう」と言われても、どうしても罪悪感があったり、相手に悪いなと思ってしまう人は多いものです。でも本書では、「自分を大切にすることが結果的に周りのためにもなる」という新しい視点を教えてくれます。
「自分中心」と聞くと、自己中心的でわがままなイメージがありますが、ここで紹介されている「自分中心」は、むしろ相手を尊重しつつ、自分の幸せも叶えていく生き方。相手に尽くすばかりだった人も、「あ、私も大事にしていいんだ」と思える内容になっています。

「自分を大切にする」とは、心理学的には「自分の心の声を無視しない」こと。
自分の本音を大事にすることで、人生がどんどん楽になりますよ。
本の感想・レビュー

自分の「快・不快」に敏感になれた
これまで、どんな場面でも「人に迷惑をかけないように」「空気を壊さないように」と考えるのが当たり前で、自分の心の声なんてほとんど無視して生きてきた気がします。だけど、この本を読みながら、いつも「なんでこんなに疲れるんだろう」って自分を責めていた理由がやっとわかったんです。
どうやら、私が人の気持ちばかり気にして「いい人」をやっていたから、自分の「快・不快」に気づけなかっただけだったんですね。読んでいくうちに、「あ、これが私の心の声なんだ」と、胸の奥で小さくうずくまっていた自分の本音を少しずつ感じ取れるようになってきました。
最近では、仕事で頼まれたことでも「今の自分は本当にそれをやりたいのかな?」と問いかけるようになり、嫌だなと思ったときは断る勇気も持てるようになったんです。そのおかげで、周りに流されることが減ってきて、心に余裕が出てきた気がします。誰かのために頑張るのも大切だけど、自分の心の声をちゃんと聞いてあげることって、こんなに大事なんだなぁと実感しています。
万能感を手放すことの重要性を理解
家族や友達、職場の人間関係、どこにいても「私がなんとかしなきゃ」と思ってしまう癖がありました。誰かが困っていると、「私が助けなきゃ」「私が解決しなきゃ」と、自分のキャパを超えて動いてしまうんです。
だけど、この本を読んで、「万能感」に支配されていた自分に気づけました。「万能感は許すだけでいい」というフレーズに出会ったとき、心にストンと落ちて、なんだか泣きそうになりました。いつも無理して頑張ってきたのに、結局誰も幸せになれないどころか、自分がどんどんしんどくなっていたんだと気づかされたんです。
今では、相手の問題は相手のもの、私は私の課題だけに集中すればいいと思えるようになってきました。周りから「助けてくれないの?」って言われるんじゃないかと怖かったけれど、それもまた相手の問題なんだと思うと心が楽になりました。この本を通して、自分の生き方が少しずつでも変わっていくのが嬉しいです。
嫌われることへの恐怖が減った
正直、私は「嫌われる」ってことがすごく怖かったんです。どんなに自分が疲れていても、無理してでも笑顔で人に合わせてしまう。相手の機嫌を損ねたら、すぐ「私のせいだ」と思ってしまう。だからいつも周りの目ばかり気にして、本当の自分の気持ちはどこかに置き去りでした。
この本を読んで初めて、「嫌われてもいいんだよ」と背中を押してもらえた気がしました。嫌われるのが怖いのは、自分が「いい人」でいようとしているからなんだと気づかされたんです。少しずつですが、「相手が私をどう思うかは、相手の自由」と思えるようになってきました。
もちろん、まだ完全に吹っ切れたわけじゃないけど、以前よりは確実に、自分の心が楽になったと感じています。嫌われることを恐れて、自分を犠牲にするのはもうやめたい。そう思えるようになったのは、この本のおかげです。
他人の評価に振り回されなくなった
昔から私は、他人にどう見られているかがすごく気になるタイプでした。友達の輪の中で笑っていても、心のどこかで「今の自分、大丈夫かな」「変なこと言わなかったかな」って考えちゃうんです。
そんな私にとって、この本の「いい人でいようとすると、かえって周りに振り回されてしまう」というメッセージは衝撃でした。人に嫌われるのが怖くて自分の意見を飲み込んだり、頼まれたことを断れなかったり、そんな自分をずっと責めていました。
でも、この本を読んでからは、「他人の評価は他人のもの、自分は自分」と割り切れるようになってきたんです。完璧な人間なんていないんだから、少しくらい嫌われても仕方ないって思えるようになって、心がすごく軽くなりました。今は少しずつですが、自分の気持ちを大切にして過ごせるようになった気がします。
自分の感情に正直になれた
これまで、私は自分の気持ちよりも「こうあるべき」とか「みんなに合わせなくちゃ」といった思いで生きてきました。嫌なことがあっても笑顔でやり過ごし、怒りを感じてもそれを押し込める。そんなことを繰り返していたら、いつの間にか自分の感情を感じることすら難しくなっていたんです。
この本を読み進めるうちに、私がずっと「いい人」でいようとして、本音を押し殺してきたことに気づきました。そこから、「自分の感情にもっと素直になってもいいんだ」と思えるようになったんです。
今では、泣きたいときは泣いて、嬉しいときは素直に喜ぶことが少しずつできるようになってきました。完璧じゃないけれど、自分の気持ちに耳を傾けるだけで心が軽くなるものなんだと、この本を通して知りました。
自分の時間を大切にするようになった
この本を読む前は、家事や仕事、人のことばかりを優先して、「自分のための時間」なんて贅沢だと思っていました。毎日、気づけば誰かの期待に応えることばかりで、自分が何をしたいのかもよくわからない。そんな日々が当たり前だったんです。
でも、この本を読んで、「自分の時間を大切にしてもいいんだよ」って背中を押してもらえた気がしました。「自分中心」に生きるという言葉が、初めて心に響いたんです。最近では、ほんの少しだけど、自分のための時間を作ってみています。例えば好きな音楽を聴いたり、読書をしたり。
そうするだけで、こんなに気持ちが楽になるんだとびっくりしました。周りに合わせてばかりだったあの頃の私に、「あなたの時間も大事だよ」って言ってあげたいです。これからは、もっと自分のための時間を増やして、自分の人生を楽しみたいと思います。
自分を責める癖がなくなった
いつも「自分のせいかもしれない」と感じては、自分を責め続けてきた私にとって、この本はまるで救いの手のようでした。誰かに何か言われたら、「私が悪いんだ」と思ってしまうし、何かうまくいかないことがあると、真っ先に自分を責める癖があったんです。
この本を読み進めるうちに、「罪悪感」や「万能感」という言葉がすごく心に刺さりました。知らず知らずのうちに、他人の問題まで自分の責任にしてしまっていたことに気づいたんです。それを手放す勇気をくれたのが、この本でした。
今でも完全に癖がなくなったわけじゃないけれど、前よりは「これは私の問題じゃない」と冷静に分けて考えられるようになりました。これだけでも、自分の心の負担がずいぶん軽くなった気がしています。
人間関係が楽になった
人間関係って、ずっと私にとって悩みの種でした。友達や同僚、家族にまで気を遣って、嫌われないように必死になって。でも、そのせいで逆に相手に振り回されてしまうことが多かったんです。
この本に出会って、「いい人」をやめることが、こんなにも人間関係を楽にしてくれるなんて思いもしませんでした。今まで「いい人」でいることが相手のためだと思っていたけれど、実はそれが自分も相手も苦しめていたんだと知って驚きました。
少しずつ自分の意見を伝えられるようになったし、相手の顔色ばかりうかがわなくなってきたことで、人と関わるのが前よりずっと楽になりました。肩の力を抜いて人と接するって、こんなに楽なんだって感じられるようになったのは、私にとって本当に大きな一歩です。
まとめ

本記事では、『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』の魅力や対象読者、具体的な章構成を詳しく解説してきました。
ここでは最後に、この本を手に取ることで得られる大きなメリットと、読後の行動指針、そして総括として心に留めておきたいポイントをまとめます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれを詳しく説明していきます。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を読むことで得られる代表的なメリットをいくつか紹介します。
人間関係のストレスから解放される
これまで相手の期待や顔色ばかり気にしていたあなたも、この本を読むことで「いい人をやめる」ことの大切さに気づけます。人間関係のバランス(恒常性)を知ることで、「私が頑張ればなんとかなる」と思い込んでいた自分を手放せるようになるのです。頑張りすぎて疲れる日々から解放され、もっと自然体で人と関われるようになるでしょう。
自己肯定感が育ち、自分を信じられるようになる
本書は、他人の評価ではなく「自分中心」で生きることの大切さを教えてくれます。これまで「いい人」でいることでしか自分の存在価値を感じられなかった人も、この本を読むことで「自分にはそのままで価値があるんだ」と思えるようになります。自分を認める力が育ち、心がじわじわと強くなるのを感じられるはずです。
いい人をやめても周りから愛されることに気づける
「いい人」でいることをやめたら人間関係が壊れてしまうんじゃないか——そんな不安が、この本を読んでいくうちに和らいでいきます。実際に「いい人」をやめたことで、むしろ周りから信頼され、チームワークがよくなったエピソードも紹介されていて、読むだけで勇気が湧いてくるはずです。あなたも「そのままの自分」で愛されるんだと信じられるようになるでしょう。
自分の時間と心の余裕を取り戻せる
本書は、「自分中心に生きる」ことの大切さを教えてくれます。「自分中心」と聞くとわがままに感じるかもしれませんが、実はそれこそが自分も周りも幸せにする生き方だと気づけるのです。周りを気にしすぎるあまり、自分の時間やエネルギーを後回しにしてきた人にこそ、この本は「自分のための時間」を取り戻すきっかけを与えてくれます。

心理学的に「いい人」症候群は他者への過剰適応の表れ。
そこから抜け出し、本当の意味で自分らしく生きる方法を知ることが、心の健康にも大切です。
読後の次のステップ
本書『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』を読み終えた後、せっかくの学びを日常生活に活かすために、どのように行動を起こしていけばよいのでしょうか?
読んで「なるほど!」と感じたことを、実際にあなた自身の人生に落とし込むために、具体的なステップをご紹介します。
step
1小さな「いい人」行動をやめてみる
最初の一歩は、これまで無意識にやってきた「いい人」行動の中から、一つでいいのでやめてみることです。例えば、「頼まれたら断れない」という行動パターンがあるなら、ちょっと勇気を出して一度だけ断ってみる。相手の反応が気になっても、「大丈夫、これは練習」と自分に言い聞かせながらトライしてみてください。小さな一歩が、大きな自信につながります。
step
2自分の「快・不快」に耳を澄ませる
本書で学んだ「快・不快スイッチ」を、日常の中で積極的に使ってみましょう。誰かに何かを頼まれたとき、すぐに「イエス」と言わずに、「自分はこれを心地よく思うのか、不快に思うのか」を感じ取ってみる。最初は難しいかもしれませんが、続けるうちに、自分の本当の気持ちを大切にできるようになります。
step
3罪悪感や万能感に気づいたら立ち止まる
もし、「断ったら悪いかも」「私が頑張ればなんとかなる」という思いがふと頭をよぎったら、立ち止まってみましょう。その感情は、本書で解説されていた「罪悪感」や「万能感」の可能性があります。その場で深呼吸して、「これは私の問題?それとも相手の問題?」と問いかけてみることで、無理な責任を手放すきっかけになります。
step
4自分中心の時間を作る
最後に、あなた自身のための時間を意識的に作ってみてください。誰のためでもなく、自分のために過ごす時間を大切にすることが、「自分中心」の生き方の第一歩です。趣味やリラックスタイム、カフェでゆっくり過ごすなど、何でも構いません。大切なのは「これは自分のための時間」と決めて行動すること。こうした時間を持つことで、日常の中で自然と「いい人」から距離を置けるようになります。

総括
『「ひとりで頑張る自分」を休ませる本』は、頑張りすぎてしまうあなたに「もっと肩の力を抜いて、自分の人生を大切にしてもいいんだよ」と優しく語りかけてくれる一冊です。本書を通じて、人間関係の恒常性という心理学的な仕組みから、「いい人」を演じ続けることで自分だけが損をしてしまうメカニズムまで、しっかりと学ぶことができます。だからこそ、「いい人」をやめることが、決してわがままではないという安心感を持っていただけたのではないでしょうか。
また、著者がカウンセリング歴25年、8万件を超える臨床経験の中から導き出した実践的なアドバイスは、理論だけではなく、すぐに行動に移せるものばかりです。「快・不快スイッチ」や「罪悪感の手放し方」「相手の問題と自分の問題の切り分け方」など、どれもが実生活に役立つ知恵として光ります。自分を中心に置きながら、他人も大切にできる生き方のヒントが詰まっているのが、この本の最大の魅力です。
この本を読み終えたあなたは、「いい人でいなければならない」という思い込みを少しずつ手放し、本当の意味で自由になっていく道の途中に立っているはずです。これまでとは違う視点で人間関係を捉え直し、「自分が主役の人生」を歩むための大きな一歩を踏み出せることでしょう。

心理学と脳科学に裏打ちされた確かな知識と、著者の温かい語り口が、きっとあなたの心に寄り添い、「もっと自分らしく生きていいんだ」と背中を押してくれるに違いありません。
これからのあなたが、自分を大切にしながら周りも大切にできる、そんな毎日を過ごせるよう心から願っています。
努力に関するおすすめ書籍

努力がテーマのおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 努力がテーマのおすすめの本!人気ランキング
- 1%の努力
- 努力不要論
- 東大生が知っている! 努力を結果に結びつける17のルール
- 一番効率的な頑張り方がわかる 図解 正解努力100
- がんばらないことをがんばるって決めた。
- 「ひとりで頑張る自分」を休ませる本
- 努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学
- がんばるのをやめたらうまくいった
- 主張したいんじゃない、気づいてほしいだけ! 頑張り屋さんのための心が晴れる本

