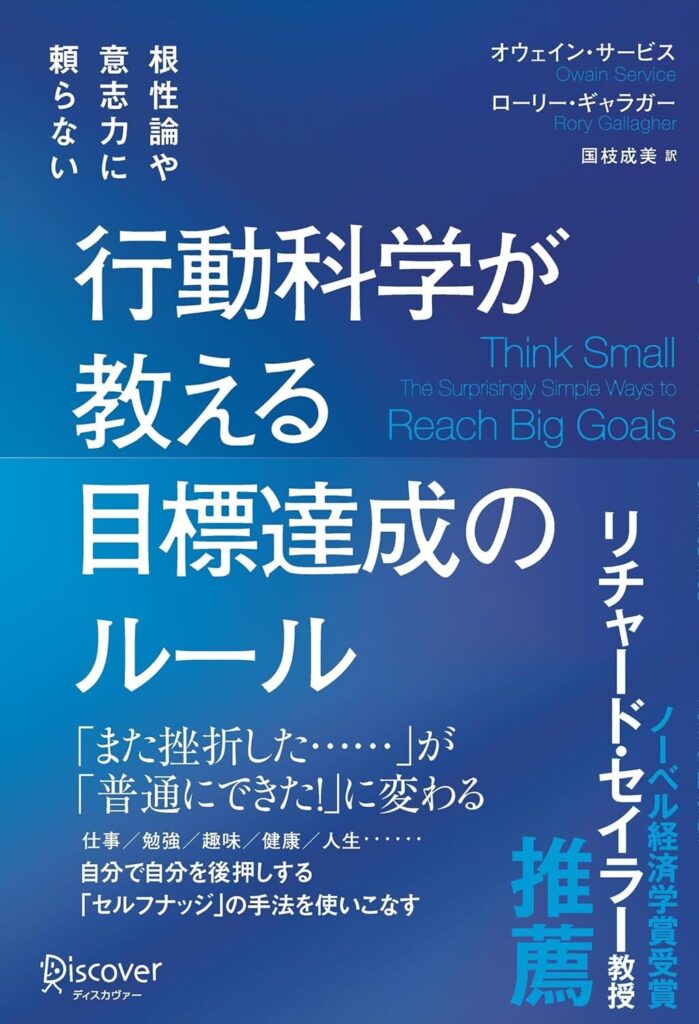
目標を立てても、なかなか達成できない——そんな経験は誰にでもあるはずです。
「もっと努力しよう」「意志の力で乗り切ろう」と考えても、結局続かずに挫折してしまうことは珍しくありません。
しかし、本当に必要なのは「根性」や「意志力」ではなく、科学的に裏付けられた「行動の仕組み」を理解し、適切に活用することです。

本書『根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール』では、行動科学の知見をもとに、目標を確実に達成するための実践的なアプローチを解説しています。
著者のオウェイン・サービスとローリー・ギャラガーは、イギリス政府の「ナッジ・ユニット」での実績を活かし、政府や企業で成果を上げてきた行動変容のメカニズムを一般の読者向けに分かりやすく紹介しています。
「今年こそ新しい習慣を身につけたい」「途中で挫折せずに目標を達成したい」そんな人にこそ、ぜひ読んでほしい一冊です。
意志の力に頼らなくても、科学的に正しいアプローチを取れば、どんな目標も達成できるのです。
今こそ、科学的なアプローチで目標を達成する方法を学び、人生を変える第一歩を踏み出しましょう!

合わせて読みたい記事
-

-
行動力を高めることができるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
「もっと行動力をつけて、自分の可能性を広げたい」「頭では分かっているけれど、なかなか一歩踏み出せない」と悩んだことはありませんか? 行動力は、人生を前に進めるための重要なスキルです。 しかし、意識する ...
続きを見る
書籍『根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール』の書評

この書籍は、目標達成に関する従来の考え方を覆し、行動科学の視点から効果的な戦略を解説した一冊です。
従来の「努力と根性で乗り越える」というアプローチではなく、科学的に裏付けられた方法を用いることで、誰でも目標を達成しやすくなる仕組みを提案しています。
本書の魅力をより深く理解するために、以下のポイントについて詳しく解説していきます。
- 著者:オウェイン・サービスのプロフィール
- 著者:ローリー・ギャラガーのプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
本書がどのような背景のもとで執筆され、どのような読者に向けられたものなのかを、順を追って見ていきましょう。
著者:オウェイン・サービスのプロフィール
オウェイン・サービスは、英国政府によって設立された「行動洞察チーム(ナッジ・ユニット)」の創設メンバーであり、行動科学を実社会に応用する専門家として知られています。
行動経済学や心理学を活用し、政策や企業戦略の改善に貢献してきた実績を持ちます。
彼のキャリアは、多岐にわたる分野での影響力を示しています。
例えば、政府の公共政策では、税金の支払い率を向上させるために「社会的証明(みんながすでにやっている)」という心理学的手法を活用したプロジェクトに関与しました。
また、企業向けには、従業員の生産性向上や健康的な行動を促すための施策を提案し、行動科学の応用範囲を広げています。
さらに、彼は講演活動や執筆を通じて、一般の人々にも行動科学の知見を広めています。
本書もその一環として執筆され、科学的なアプローチを実生活に活かすための実践的な手法を提供しています。

ナッジ(Nudge)とは、選択肢のデザインを工夫することで、無意識のうちに望ましい行動を促す手法です。
例えば、健康的な食生活を促すために、学校のカフェテリアで果物を目立つ場所に配置することなどが該当します。
著者:ローリー・ギャラガーのプロフィール
ローリー・ギャラガーもまた、行動科学の専門家として、政府機関や企業に対して実践的なアドバイスを行っています。
特に、政策設計の分野では、個人の行動変容を促す施策の設計とその効果測定に携わり、多くの成功事例を生み出しています。
彼の研究の中で特に注目されるのが、社会的影響を活用した行動変容の実験です。
たとえば、環境問題への取り組みを促進するために、電気使用量を住民同士で比較できるシステムを導入することで、エネルギー消費を削減する効果が得られることを実証しました。
これは、私たちが周囲の行動を基準に意思決定を行う「社会的比較」の心理を利用した施策です。
また、彼は学術研究だけでなく、ビジネスや教育の分野にも行動科学を応用し、企業のマーケティング戦略や組織運営に役立つ提案を行っています。
本書では、そうした研究と実践の成果を分かりやすく解説し、個人レベルでの応用方法を紹介しています。

「あなたの近所の90%の人がすでにリサイクルを実践しています」という情報が提示されると、人々はそれに倣ってリサイクルを行う可能性が高くなります。
これが社会的証明の原理です。
本書の要約
本書は、行動科学に基づいて目標達成の方法を解説しており、意志力や根性に頼るのではなく、環境や習慣の力を活用することを推奨しています。
目標を達成するためには、「正しい方法で努力する」ことが必要ですが、一般的に「努力」と聞くと、多くの人は自分の意思ややる気を最大限に発揮することを想像します。
しかし、研究によると、モチベーションは長続きせず、目標達成には科学的なアプローチが必要であることが分かっています。
本書では、目標達成のためのステップを7つに分けて解説しています。
まず、目標の設定では、漠然とした理想ではなく、具体的で達成可能なものにすることが重要です。
たとえば、「健康的になる」ではなく、「1日30分の運動を週4回行う」と明確にすることで、実行しやすくなります。
次に、計画の立案では、シンプルで無理のない計画を作ることが求められます。
大きすぎる目標は挫折しやすいため、スモールステップで進めることがポイントです。
コミットメントの強化も重要な要素です。
人は、他人に公言したり、書き留めたりすることで、自分の目標に対する責任感を高める傾向があります。
たとえば、友人に目標を伝えたり、SNSで進捗を報告したりすると、途中で投げ出しにくくなります。
報酬の活用も効果的であり、小さな成功を積み重ねることで、行動を継続しやすくなります。
例えば、運動後に好きな映画を観る、勉強後に好きな音楽を聴くといった方法が考えられます。
さらに、本書では、他者の力を借りることの重要性も説いています。
社会的なつながりを活用することで、行動のモチベーションを高め、習慣化しやすくなるのです。
たとえば、ダイエットをする際に友人と一緒に取り組むことで、お互いに励まし合いながら継続できる可能性が高まります。
また、フィードバックの仕組みを整えることも大切です。
目標達成に向けて、自分がどこにいるのかを確認し、適切な改善を行うことで、より効果的に前進できます。
最後に、本書は、途中で諦めないための戦略についても詳しく解説しています。
成功する人とそうでない人の違いは、失敗したときの対応にあります。
試行錯誤を重ねながら前進し、成功を積み重ねることで、より大きな目標にも挑戦できるようになります。
こうしたプロセスを実践することで、意志力に頼らずとも、自然と目標達成に近づくことができるのです。

「人は合理的に行動するとは限らない」という考えが、行動科学の前提となっています。
だからこそ、自分の意思に頼るのではなく、環境や習慣の力を活用することが有効なのです。
本書の目的
この本の目的は、意志の力ではなく、科学的な仕組みを活用することで、誰もが継続的に目標を達成できるようになることです。
多くの人が目標に向かって努力を続けられない理由は、計画の立て方や環境の整え方に問題があるからです。
本書では、それらの問題を解決するための具体的な方法を提案しています。
一般的に、目標達成には努力ややる気が不可欠だと考えられています。
しかし、研究によると、モチベーションは一時的なものであり、継続するのが難しいことが分かっています。
そのため、モチベーションに頼るのではなく、「行動を自動化する仕組み」を作ることが重要です。
本書では、そのための具体的なステップが紹介されており、誰でもすぐに実践できるようになっています。

目標達成の成功率を高めるには、「意志の力」に頼らず、「環境」と「習慣」をうまく活用することが鍵になります。
本書は、その具体的な手法を明確に示しています。
人気の理由と魅力
本書が多くの読者に支持されている理由の一つは、科学的な裏付けがあることです。
自己啓発書の中には、著者の経験談に基づいたものが多くありますが、本書は行動科学の研究結果を基にしており、実際に効果が実証された方法を紹介しています。
そのため、理論的に納得しながら、安心して実践することができます。
また、具体的なステップが示されている点も魅力の一つです。
「意志力を強くする」「気合で乗り切る」といった抽象的なアドバイスではなく、誰でも再現可能な手法が紹介されているため、実際に試しやすくなっています。
たとえば、目標を小さなステップに分解する、行動のトリガーを設定する、報酬を活用するなど、すぐに実行できる方法が満載です。
さらに、ビジネスや健康、教育など、さまざまな分野に応用できる点も本書の魅力です。
目標達成の技術は、個人の自己管理だけでなく、組織のマネジメントや人材育成にも役立ちます。
企業が従業員のパフォーマンスを向上させるために取り入れたり、学校で生徒の学習習慣を改善するために活用したりすることも可能です。
このように、幅広い場面で応用できることが、本書の価値を高めています。

行動科学の手法を活用することで、努力や根性に頼らず、誰でも目標達成が可能になります。
本書は、そのための実践的なガイドとして、多くの人に役立つ内容になっています。
本の内容(目次)

本書は、行動科学の知見を活かして、目標を達成するための具体的なステップを示しています。
意志力や根性に頼らず、実証された手法を用いることで、持続可能な成果を得ることが可能になります。
本書の目次は以下のようになっています。
- はじめに
- 第1章 目標設定
- 第2章 プランニング
- 第3章 コミットメント
- 第4章 報酬
- 第5章 共有
- 第6章 フィードバック
- 第7章 あきらめない
それでは、それぞれの章の内容について詳しく見ていきましょう。
はじめに
本書の冒頭では、ロンドン郊外のジョブセンターでの実例が紹介されています。
ポールという24歳の若者が、長期間の失業と生活苦に直面し、新たな仕事を見つけるためにジョブセンターを訪れました。
彼の担当となったメリッサは、従来の方法では求職者のモチベーションを高めることが難しいと感じており、新たなアプローチを試みることにしました。
彼女が最初に行ったのは、ポールに「なぜ仕事を得たいのか」を考えさせることでした。
単なる書類の記入をするのではなく、彼自身の目標や理由を明確にすることで、より主体的に動くよう促したのです。
その結果、ポールは「家族を養いたいから」と答え、自分の行動の動機を改めて認識しました。
次に、具体的な目標を設定し、それを小さなステップに分解しました。
例えば、「3カ月以内に建設業界で仕事を見つける」という目標を立て、それを履歴書の改善、求人への応募、業界の知人への連絡といった細かい行動に分けました。
さらに、それらを日々のルーティンと組み合わせることで、確実に実行できるようにしました。
ポールはこの計画に従い、定期的にメリッサと面談しながら進捗を確認し、最終的に3カ月後に建設業界での仕事を獲得しました。
この成功は、単なる努力や根性ではなく、行動科学のアプローチを活用した結果だったのです。
本書では、このような具体的なエピソードを交えながら、科学的に実証された目標達成の方法を解説していきます。

ポールの成功は、目標を明確にし、それを細かく分解することで達成しやすくなることを示しています。
大きな目標も、小さなステップに分ければ実行可能なものになるのです。
第1章 目標設定
目標を達成するためには、適切な目標を設定することが不可欠です。
本章では、行動科学に基づいた効果的な目標設定の方法を解説します。
まず、目標は自分の価値観や興味に沿ったものでなければなりません。
他人の期待や社会的なプレッシャーによる目標では、途中でモチベーションが低下しやすくなります。
行動科学の研究によれば、内発的動機づけ(自分自身の価値観や興味に基づく目標)のほうが、外発的動機づけ(報酬や評価のための目標)よりも長続きしやすいことがわかっています。
次に、目標は具体的であることが重要です。
「健康になりたい」という抽象的な目標ではなく、「半年以内に体脂肪率を3%減らす」といった数値を含んだ目標を設定することで、達成の基準が明確になります。
また、目標は一つに絞ることも効果的です。
複数の目標を同時に追いかけると、注意が分散し、どれも中途半端になりやすくなるためです。
さらに、大きな目標を達成可能なステップに分解することが必要です。
行動科学では、「小さな成功の積み重ね」がモチベーションを維持するうえで重要であるとされています。
例えば、「半年以内に体脂肪率を3%減らす」という目標を、「毎日30分の運動をする」「1週間に3回は野菜中心の食事をとる」といった具体的な行動に分解し、日常のルーティンに組み込むことで、達成しやすくなります。

目標は大きすぎると挫折しやすくなります。
成功するためには、達成可能な小さなステップに分解し、一つひとつ確実にクリアしていくことが大切です。
第2章 プランニング
目標を設定したら、次はその目標を達成するための計画を立てる必要があります。
本章では、効果的なプランニングの方法について詳しく解説します。
まず、計画はシンプルであることが重要です。
あまりに複雑な計画を立てると、途中で挫折するリスクが高まります。
例えば、「週に5回ジムに通い、1時間のトレーニングを行い、さらに食事管理を徹底する」という計画は、一見すると理想的ですが、実行のハードルが高すぎて続かなくなる可能性があります。
それよりも、「週に2回ジムに行き、1回30分のトレーニングをする」といった、シンプルで実行可能な計画のほうが長続きしやすくなります。
また、計画は現実的でなければなりません。
非現実的な計画を立てると、達成できなかったときに自己効力感が低下し、モチベーションが失われてしまいます。
例えば、仕事や家事で忙しい人が「毎朝1時間ランニングする」という計画を立てても、継続するのは難しいでしょう。
それよりも、「朝の通勤前に15分間歩く」といった、小さな行動のほうが続けやすく、結果的に大きな変化につながります。
さらに、計画を習慣化することが成功の鍵です。
習慣化のためには、「既存の習慣と新しい行動を結びつける」ことが有効です。
例えば、「朝のコーヒーを飲む前にストレッチをする」や「帰宅後すぐに英語の勉強をする」といった形で、日常生活の流れに組み込むことで、無理なく継続できるようになります。

計画を立てる際には、無理のないシンプルなものにすることが重要です。
継続できるかどうかを最優先に考えましょう。
第3章 コミットメント
目標を達成するためには、コミットメント(約束)が欠かせません。
本章では、行動科学の観点から、効果的なコミットメントの方法を解説します。
まず、コミットメントは具体的な行動と結びついていることが重要です。
「頑張る」という曖昧な誓いではなく、「毎朝7時に起きて20分のジョギングをする」といった具体的な行動に対するコミットメントをすることで、達成しやすくなります。
次に、コミットメントを紙に書き出し、公にすることも効果的です。
行動科学の研究では、目標を書き出すことで脳の記憶に強く残り、実行の可能性が高まることが示されています。
さらに、友人や家族に共有することで、周囲からのサポートやプレッシャーが働き、継続する意欲が高まります。
また、コミットメントレフリーを任命することも有効な手段です。
レフリーとは、自分の進捗をチェックし、フィードバックを与えてくれる人のことを指します。
例えば、友人と一緒にダイエットの進捗を報告し合うことで、お互いにモチベーションを維持することができます。

人は他者との約束を破ることを嫌う傾向があります。
その心理を活用して、目標達成のためのコミットメントを公にすることで、成功の確率がぐっと高まります。
第4章 報酬
目標を継続的に達成するためには、努力に見合った報酬が必要です。
本章では、効果的な報酬の活用方法について解説されています。
人は、何かを達成した際に報酬があると、それを繰り返したくなるという心理的な傾向があります。
例えば、仕事で良い成果を出したときに上司から褒められると、次も頑張ろうという気持ちが生まれるのと同じです。
本書では、報酬は「意味のあるもの」にすることが重要だと述べられています。
単にお金や物理的なご褒美を設定するだけではなく、達成感や充実感といった内面的な報酬が効果的なこともあります。
たとえば、ダイエットの目標を達成した後に好きな服を買うことも報酬になりますが、体が引き締まり自信を持てるようになること自体が、より大きなモチベーションになることもあります。
また、報酬は「小さくても良い」ことも大切なポイントです。
大きな成果を上げたときだけ報酬を用意するのではなく、日々の小さな努力にも報酬を設定することで、行動の継続がしやすくなります。
例えば、毎日30分の勉強を達成したら好きな音楽を聴いてリラックスする時間を設ける、といった形で、日常的に小さな報酬を用意することが推奨されています。
ただし、報酬の選び方には注意が必要です。
間違った報酬を設定すると、逆にモチベーションが低下することもあります。
例えば、勉強をしたご褒美にゲームをする時間を増やすと、次第にゲームの方が目的になってしまい、勉強の本来の目的が薄れてしまうことがあります。
報酬を設定する際には、目標をサポートするものかどうかを考えることが大切です。

適切な報酬を設定することで、行動の継続がしやすくなります。
ただし、報酬が目的にならないよう、慎重に選ぶことが重要です。
第5章 共有
目標達成には、周囲の人のサポートを活用することが効果的です。
本章では、他者との関わりを通じてモチベーションを維持する方法が解説されています。
人は一人で努力を続けるよりも、他者と協力することで行動を継続しやすくなります。
これは、「社会的つながり」が行動の維持に大きな影響を与えるためです。
本書では、まず「協力を仰ぐ」ことの重要性が述べられています。
例えば、運動の習慣をつけたい場合、一人で行うよりも友人と一緒にジムに通うことで、より継続しやすくなります。
周囲の人に目標を共有し、サポートをお願いすることで、行動を続ける環境を整えることができます。
また、「社会的ネットワークを活用する」ことも有効です。
SNSなどを活用して自分の目標を発信することで、同じ目標を持つ人々とつながることができます。
例えば、読書を習慣化したい場合、読書コミュニティに参加し、進捗を共有することでモチベーションを維持しやすくなります。
さらに、「グループパワーを使う」ことも推奨されています。
人は、集団の中で行動をすると、その行動を継続しやすくなる傾向があります。
例えば、ダイエットを成功させたい場合、一人で頑張るよりも、同じ目標を持つグループに参加することで、互いに励まし合いながら進めることができます。
これは、「仲間意識」が行動の継続に良い影響を与えるためです。

目標を共有することで、モチベーションを維持しやすくなります。
他者とのつながりをうまく活用することが、成功の鍵となるでしょう。
第6章 フィードバック
目標を達成するためには、定期的に自分の進捗を確認することが欠かせません。
本章では、効果的なフィードバックの方法について解説されています。
目標に向かって努力を続ける中で、現在の状況を客観的に把握することができれば、必要に応じて軌道修正をすることが可能になります。
まず、「自分の立ち位置を知る」ことが重要です。
例えば、語学学習をしている場合、単に毎日勉強を続けるだけではなく、定期的に模擬試験を受けたり、実際に会話をしてみたりすることで、自分の成長を確認することができます。
現在の状況を知ることで、次にどのような対策を取るべきかが明確になります。
また、「タイムリーで具体的なフィードバックを受ける」ことも大切です。
例えば、仕事のスキルを向上させたい場合、上司や同僚から定期的にフィードバックをもらうことで、どの部分を改善すべきかを知ることができます。
特に、目標達成に向けた努力が認められると、さらにやる気が高まります。
最後に、「他者と比較することで成長を促す」方法も紹介されています。競争意識を利用することで、自分をより高めることができます。
例えば、ランニングアプリを使い、他のユーザーと走行距離を比較することで、自分の進歩を実感しやすくなります。
ただし、比較がプレッシャーにならないよう、あくまで自分の成長を確認するための手段として活用することが大切です。

定期的なフィードバックを受けることで、自分の進捗を客観的に把握できます。
適切な軌道修正を行うことで、目標達成の可能性が高まります。
第7章 あきらめない
目標を達成するまでには、困難や挫折を経験することが避けられません。
本章では、最後まで諦めずに努力を続けるための方法が解説されています。
特に、途中でモチベーションが低下したときに、どのように乗り越えるかが重要なポイントとなります。
まず、「練習の質と量を高める」ことが求められます。
単に長時間取り組むのではなく、効率的な方法を取り入れることが大切です。
例えば、語学学習の場合、ただ単語を覚えるのではなく、実際の会話の中で使うことで、より定着しやすくなります。
量だけでなく、質を重視することが継続のカギとなります。
次に、「試しながら学ぶ」ことも効果的です。
完璧を求めすぎず、まずは実践してみることで、失敗から学ぶことができます。
例えば、新しいスキルを身につけたい場合、最初から完璧にこなすのは難しいものですが、小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に上達していくことができます。
最後に、「振り返りをして成功を祝う」ことも大切です。
自分がどれだけ成長したのかを確認し、その成果を認識することで、次の目標への意欲が湧いてきます。
例えば、運動を習慣化したい場合、「最初は1km走るのがやっとだったが、今は5km走れるようになった」という変化を実感することが、さらなるモチベーションにつながります。

途中で諦めそうになったときは、自分の成長を振り返ることが大切です。
小さな成功を積み重ねることで、目標達成が現実のものになります。
対象読者

本書は、従来の根性論や意志力に頼らず、科学的アプローチで目標を達成したいと考える人に向けた内容となっています。
著者は行動科学の専門家であり、政府や企業の現場で実際に成果を上げた手法をもとに、個人の目標達成に応用できる実践的な方法を紹介しています。
以下のような人に特におすすめです。
- 目標達成の方法を科学的に学びたい人
- 意志力や根性に頼らず成果を出したい人
- 習慣形成や自己管理を向上させたい人
- マネジメントやチーム運営に役立てたい人
- 行動経済学や行動科学に興味がある人
それぞれの対象読者に向けた具体的な説明を以下で詳しく紹介します。
目標達成の方法を科学的に学びたい人
「努力すれば必ず成功する」「意志が強ければ夢は叶う」といった考え方に疑問を感じている人にとって、本書は画期的な一冊となるでしょう。
目標達成のプロセスを科学的な視点から分析し、意志の力に頼らずに成果を出す方法を紹介しています。
行動科学の研究によって、人間の行動がどのように形成され、どのように変化するのかが明らかになっており、それを実生活に活かすための具体的な方法が本書には詰まっています。
例えば、ダイエットや勉強、仕事のパフォーマンス向上といった目標に向かって努力しても、途中で挫折してしまうことはよくあります。
その理由は、意志力の限界にあります。
本書では、行動科学の理論を活用し、意志力が尽きても継続できるような環境や習慣を作る方法を解説しています。
「気合い」や「根性」ではなく、仕組みや環境を最適化することで、自然と目標に向かう行動が取れるようになります。

科学的に証明された方法を使えば、意志力に頼らなくても目標を達成できるようになります。
本書はそのための具体的な手順を提供してくれます。
意志力や根性に頼らず成果を出したい人
多くの人が「モチベーションが続かない」「意志が弱いから達成できない」と考えがちですが、本書はその考え方自体を根本から覆します。
行動科学の研究によれば、意志力に頼ること自体が非効率であり、持続可能な成功には「環境」や「習慣」の設計が欠かせません。
つまり、意志が弱いのではなく、目標達成に適した仕組みが整っていないだけなのです。
たとえば、運動を習慣にしたい場合、「やる気があるときに頑張る」のではなく、「毎朝、出勤前に運動するルーチンを作る」といった工夫をすることで、自然と続けられるようになります。
本書では、こうした「意志力を使わずに行動を継続する方法」を詳しく解説しており、日常生活や仕事に応用するヒントを得ることができます。

モチベーションが続かないのは、自分の意志が弱いからではなく、適切な環境が整っていないからです。
本書を読めば、その環境の作り方が分かります。
習慣形成や自己管理を向上させたい人
新しい習慣を身につけたいと思っても、なかなか継続できないことは多いものです。
「毎朝早起きをする」「読書を習慣にする」「スマホの使用時間を減らす」など、良い習慣を取り入れようと努力しても、いつの間にか元の生活に戻ってしまうことがあります。
本書では、習慣が形成される仕組みを行動科学の視点から解説し、無理なく新しい習慣を定着させる方法を提供しています。
行動科学の研究によれば、人間は「環境」に大きく左右される生き物です。
たとえば、健康的な食生活を続けるためには、「冷蔵庫にジャンクフードを入れない」といった環境整備が重要になります。
同様に、読書の習慣を身につけるには、「寝る前にスマホを遠ざけ、枕元に本を置く」といった工夫が有効です。
本書では、こうした具体的なテクニックを多数紹介し、日々の生活にすぐに取り入れられる実践的なアプローチを解説しています。

新しい習慣を続けられないのは、意志が弱いからではなく、習慣化の仕組みを知らないからです。
本書を読めば、その方法がよく分かります。
マネジメントやチーム運営に役立てたい人
本書の内容は、個人の目標達成にとどまらず、ビジネスや組織運営にも応用できます。
特に、チームのモチベーションを高め、効率的に成果を上げる方法を探しているマネージャーやリーダーにとっては、非常に役立つ内容となっています。
個人の意志力に頼るのではなく、チーム全体が自然と高いパフォーマンスを発揮できるような仕組み作りが重要であり、本書ではその方法を具体的に解説しています。
たとえば、社員の生産性を向上させるためには、「報酬」や「評価制度」の設計が重要です。
しかし、単に高額なボーナスを用意すればよいわけではありません。
行動科学の研究によれば、人は「即時報酬」や「社会的評価」に強く影響を受けることが分かっています。
そのため、「短期的な達成感を得られる仕組みを作る」や「チームメンバー同士で成果を共有する」といった施策が効果的です。
本書では、こうしたマネジメントのヒントが多数紹介されています。

個人の意志力ではなく、チーム全体の仕組みを整えることで、自然と成果が出る組織を作ることができます。
本書はそのための実践的な手法を教えてくれます。
行動経済学や行動科学に興味がある人
本書は、行動科学や行動経済学に興味がある人にとっても、非常に興味深い内容となっています。
行動科学は、私たちの日常の意思決定にどのような影響を与えるのかを研究する分野であり、その知識を活用することで、より賢く目標を達成することができます。
たとえば、人間は合理的に判断していると思いがちですが、実際には多くのバイアスに影響されています。
本書では、こうした「意思決定の癖」を理解し、それをうまく活用することで、より良い結果を得る方法が紹介されています。
行動科学に興味がある人にとって、本書は単なる自己啓発書ではなく、科学的な視点で人間の行動を分析する実践的なガイドとなるでしょう。

行動科学を学ぶことで、自分自身の行動をより効果的にコントロールすることができます。
本書では、その知識を実生活に応用する方法が詳しく解説されています。
本の感想・レビュー

科学的アプローチの有効性
本書を読んで最も印象に残ったのは、目標達成に関するアプローチが「科学的な知見」に基づいていることでした。
一般的な自己啓発書では、成功者の体験談や精神論が中心になりがちですが、本書はそうした感覚的なアドバイスとは一線を画しています。
実際のデータや研究結果をもとに、どのような方法が効果的なのかを具体的に説明している点が、とても信頼できると感じました。
本書では、「意志力や努力に頼るのではなく、行動そのものを変える仕組みを作ることが重要である」と繰り返し強調されています。
この考え方は、心理学や行動科学の研究結果と一致しており、人間がいかに環境や習慣の影響を受けるかを論理的に説明していました。
読んでいて「なるほど」と納得できる部分が多く、ただ感情的に「頑張る」だけではなく、合理的に行動を変えていくことの大切さを実感しました。
具体的な事例の豊富さ
本書が単なる理論書で終わらず、実際の事例を豊富に紹介している点も非常に魅力的でした。
行動科学の理論は興味深いものの、それをどのように実生活に適用すればよいのかが分からなければ、単なる知識として終わってしまいます。
しかし本書では、個人や組織がどのように行動変容を成功させたのか、具体的なエピソードを交えながら解説されており、読者が自身の状況に置き換えて考えやすい構成になっていました。
特に印象的だったのは、イギリスのジョブセンターで行われた取り組みの事例です。
求職者の行動を変えるために、単に「頑張れ」と励ますのではなく、目標を細分化し、達成までのステップを具体的に設定することが大きな効果を生んだことが示されていました。
この事例を読んで、「人の行動はちょっとした工夫によって大きく変わるのだ」と実感し、自分自身の目標管理にも応用できると感じました。
また、日常生活や仕事の場面でも活用できるエピソードが多数紹介されており、「この方法なら自分でも試せる」と思えるようなものが多かったのも良かったです。
理論だけでなく実践的な内容が充実しているため、すぐに行動に移したいと感じさせてくれる一冊でした。
実践的なフレームワークの提供
本書の魅力のひとつは、目標達成に向けた具体的なフレームワークが明確に示されていることです。
ただ抽象的な概念を説明するだけではなく、読者が実際に活用できる形でステップごとに整理されているため、非常に実践的な内容になっていました。
目標を設定する際には、単に「何を達成したいのか」を考えるのではなく、それをどのように細分化し、具体的な行動に落とし込むかが重要だと説明されています。
さらに、その行動を習慣化するための仕組み作りや、途中で挫折しないための対策なども詳しく述べられており、「これなら自分にもできそうだ」と思える構成になっていました。
特に、コミットメントを高めるために「公言する」ことや「フィードバックを受ける」ことの重要性が強調されていた点が印象的でした。
これまで、目標を立てても途中で諦めてしまうことが多かったのですが、本書のアドバイスを読んで、自分の行動を変えるための具体的な戦略を考えることができました。
自己啓発書としての新鮮さ
本書は、従来の自己啓発書とは異なる視点から目標達成について語られており、非常に新鮮な印象を受けました。
多くの自己啓発書では、「ポジティブな思考」や「強い意志」が成功の鍵であると説かれていますが、本書では「意志の力ではなく、環境や習慣を整えることが重要である」とされています。
この考え方は、従来の自己啓発の枠組みとは異なり、より実践的で再現性の高い方法論を提供しているように感じました。
特に、「人間の行動は意識的な努力よりも、無意識の習慣や環境によって決まる」という考え方には強く共感しました。
これまで、目標達成には強い意志が必要だと思っていましたが、本書を読んで、その前提を見直すきっかけになりました。
また、本書の方法論は「一部の成功者だけが実践できるもの」ではなく、「誰にでも応用できる普遍的なもの」として紹介されているため、読みながら「自分にもできる」と思える点が非常に良かったです。
従来の自己啓発書とは一線を画す、新しい視点を提供してくれる一冊だと感じました。
行動科学の知見の活用
本書を読んで、行動科学が目標達成においていかに有効な手段となるのかを改めて実感しました。
これまで、目標を達成できないのは「自分の意志が弱いから」と考えていたのですが、それは単なる思い込みであり、人間の行動は環境や習慣に大きく影響を受けるものなのだと気づかされました。
特に印象的だったのは、「ナッジ(Nudge)」という概念です。
これは、人の行動を自然に促すように環境を設計する手法で、政府や企業が政策やビジネス戦略の中で活用しているものです。
本書では、このナッジを個人の目標達成にも応用できることが示されており、意志の力に頼るのではなく、行動しやすい仕組みを整えることの重要性が説かれています。
目標達成への新しい視点
本書を通じて、目標達成に対する考え方が大きく変わりました。
これまで、「目標は努力して達成するもの」と考えていましたが、本書では「目標は、仕組みや習慣の中で自然に達成されるもの」として捉えられています。
これは、従来の「根性論」とは大きく異なるアプローチであり、非常に新鮮でした。
特に、目標を達成するためには「継続できる方法」を選ぶことが重要であるという考え方には深く共感しました。
これまで、目標を掲げても途中で挫折してしまうことが多く、それは「自分の努力が足りないから」だと思い込んでいました。
しかし、本書を読むことで、それは単に「方法が適切でなかったから」なのだと理解することができました。
小さな変化の重要性
本書を読んで、「小さな変化こそが、最終的に大きな成果を生む」という考え方の重要性を改めて認識しました。
これまで、何かを変えるのであれば「劇的な変化を起こさなければ意味がない」と考えていましたが、その思い込みこそが目標達成を妨げていたのだと気づかされました。
人間の脳は、大きな変化をストレスと捉える傾向があるため、一気に変えようとすると無意識のうちに抵抗が生まれるそうです。
そのため、変化を習慣として定着させるには、「無理なく取り入れられる小さなステップを積み重ねること」が鍵となるのだと学びました。
この考え方を知ったことで、「すぐに成果を出さなければならない」というプレッシャーから解放され、焦らずに取り組めるようになりました。
また、すぐに結果が出なくても、日々の小さな行動が最終的には大きな成功へとつながるという点も非常に納得感がありました。
本書を読むことで、「急ぐ必要はなく、続けることが何よりも大切なのだ」と思えるようになり、日々の行動に対する捉え方が変わったように感じます。
長期的な成果の追求
これまで、目標を立てると「短期間で成果を出さなければならない」と焦ることが多かったのですが、本書を読んで「長期的に継続することが何よりも重要である」と考えられるようになりました。
本書では、「一時的な成功よりも、続けられる仕組みを作ることが大切」という考え方が一貫して示されており、それが非常に説得力を持っていました。
今までは「目標を設定し、それをクリアすること」が最も重要だと思っていましたが、本書を通じて「一度達成しても、それを維持できなければ意味がない」と理解できました。
また、短期的な成果を求めるあまり、無理をして途中で挫折することが多かったのですが、本書では「小さな習慣を積み重ねることで、最終的に大きな変化を生む」という考え方が紹介されており、それが非常に納得のいくものでした。
これまでのやり方を振り返り、「続けられる方法を選ぶことが、結果的に最も効率的なのだ」と考えられるようになったことが、大きな収穫だったように思います。
まとめ

本書を通じて、読者は目標達成に関する新しい視点を得ることができます。
意志力や根性に頼るのではなく、科学的なアプローチを用いて確実に成功へと近づく方法が紹介されています。
ここでは、本書を読んで得られるメリット、読後の次のステップ、そして総括について解説していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
本書では、目標達成に必要な考え方や方法が具体的に紹介されています。
単なる精神論ではなく、行動科学に基づいた実践的なアプローチが豊富に解説されているため、日常生活やビジネスシーンで役立てることができます。
以下に、本書を読むことで得られる主なメリットを紹介します。
目標達成の成功率を飛躍的に向上させる
目標を立てても途中で挫折してしまう人は少なくありません。
本書では、「小さな成功体験を積み重ねることが、最終的なゴールへの道を開く」という考え方を基本とし、成功しやすい環境を作る方法を解説しています。
具体的には、目標を細かく分解し、達成しやすい形にすることで、途中でモチベーションが下がるのを防ぐ方法が紹介されています。
例えば、「英語を話せるようになりたい」という漠然とした目標ではなく、「毎日10分、英単語を3つ覚える」といった具体的な行動に落とし込むことで、達成感を得ながら続けることができます。
意志力に頼らず、習慣化するスキルを身につける
多くの人は「目標達成には強い意志が必要」と考えがちですが、実は人間の意志力には限界があります。
本書では、意志力に頼るのではなく、習慣化によって自然と目標達成に向かう仕組みを作る方法を紹介しています。
例えば、行動のトリガー(きっかけ)を設定することで、意識しなくても継続できるようになるのです。
「朝のコーヒーを飲んだら英単語を3つ覚える」など、日常の行動と結びつけることで、努力を意識しなくても習慣が形成されていきます。
科学的に証明された行動変容のテクニックを学べる
本書は、行動科学や行動経済学の研究成果を基に構成されており、エビデンスに裏付けられた実践的な手法を学ぶことができます。
例えば、「ナッジ理論」と呼ばれる手法では、「選択の仕方を工夫するだけで行動が変わる」という概念を紹介しています。
具体的には、健康的な食生活を促進するために、スーパーのレイアウトを工夫して野菜を手に取りやすい位置に配置することなどが挙げられます。
このようなアプローチを個人の目標達成にも応用することで、無理なく行動を変えることが可能になります。
フィードバックを活用してモチベーションを維持できる
人は、進捗が見えるとモチベーションを維持しやすくなります。
本書では、フィードバックの重要性について詳しく解説されており、適切なフィードバックの取り方が紹介されています。
例えば、ダイエットを続ける場合、ただ「体重を減らす」という目標を掲げるのではなく、「毎日体重を記録する」「写真を撮って変化を確認する」といった方法を取り入れることで、進捗を可視化し、継続しやすくなるのです。
また、自分一人ではなく、他者からのフィードバックを活用することで、より効果的に行動を継続できます。
「続かない」ことに対する罪悪感がなくなる
目標を達成できないと、「自分は意志が弱い」と責めがちですが、本書ではその考え方自体を変えることができます。
行動が続かないのは意志力の問題ではなく、環境や習慣の設計に原因があるのです。
つまり、「ダメな自分を変えよう」とするのではなく、「自分が自然と行動できる環境を作ろう」と考えることで、ストレスなく前に進めるようになります。
このマインドセットの変化こそが、本書を読む最大のメリットの一つです。

本書を読むことで、目標達成に必要な仕組みづくりができるようになります。
根性論や意志力に頼らず、科学的なアプローチを活用することで、無理なく確実に成果を出す方法を身につけましょう。
読後の次のステップ
本書を読んだ後、学んだ知識を実践に移すことが重要です。
目標達成のためには、単に理論を理解するだけでなく、実際の行動を変えることが不可欠です。
本書で紹介された行動科学のアプローチを活用し、具体的なステップを踏みながら、自分の目標に向かって進んでいきましょう。
以下に、読後の実践的なステップを紹介します。
step
1具体的な目標を設定する
まず、本書で学んだ「適切な目標設定の方法」を活用し、実際に自分の目標を明確にしましょう。
目標は漠然としたものではなく、できるだけ具体的にし、達成期限や到達点を設定することが重要です。
例えば、「運動を習慣化する」という目標ではなく、「週に3回、30分のウォーキングをする」といった形で、行動レベルに落とし込むことが効果的です。
step
2目標達成のための行動プランを立てる
次に、設定した目標を達成するために、具体的な行動計画を作成します。
このとき、本書で解説されている「シンプルなプランの作り方」や「実行可能なプランの立て方」を活用しましょう。
たとえば、運動を習慣化する場合、「毎週月・水・金の朝7時に近所の公園をウォーキングする」というように、具体的なタイミングと場所を決めることで、実行しやすくなります。
また、「習慣化するための工夫」として、ウォーキングの後に好きな音楽を聴く、コーヒーを飲むといった小さな報酬を設定するのも効果的です。
step
3コミットメントを強化し、実行を継続する
目標を達成するには、決めた行動を継続することが不可欠です。
そのために、「コミットメントを公にする」「サポートしてくれる人を見つける」など、本書で紹介された方法を活用しましょう。
例えば、家族や友人に「週3回ウォーキングをする」と伝え、報告することで、途中で挫折しにくくなります。
また、行動を記録する習慣をつけるのも良い方法です。
日記やアプリを使って、自分の進捗を可視化することで、モチベーションを維持しやすくなります。
step
4フィードバックを受け取り、調整する
行動を継続する中で、「思うように進まない」「モチベーションが下がる」といった壁にぶつかることもあります。
そうしたときに重要なのが、適切なフィードバックを受け取り、計画を柔軟に調整することです。
本書で紹介されているように、目標までの進捗を定期的にチェックし、「どこまで達成できたのか」「何が障害になっているのか」を振り返る習慣を持つと、継続しやすくなります。
例えば、「ウォーキングの頻度が減ってしまった理由」を分析し、天候が影響しているなら「屋内でできる運動に切り替える」といった調整を行うことで、行動を続けやすくなります。
step
5小さな成功を祝い、モチベーションを維持する
目標を達成する過程で、小さな成功を積み重ねることが大切です。
本書では、「成功を振り返り、自分を評価することの重要性」についても解説されています。
たとえば、「1か月間、週3回のウォーキングを継続できたら、新しいスポーツウェアを買う」といった報酬を設定すると、楽しみながら取り組むことができます。
また、成功体験を記録し、過去の自分と比較することで、「できるようになったこと」に目を向けると、さらに継続しやすくなります。

本書を読むことで得た知識を、実際の行動に落とし込むことが大切です。
目標を具体的に設定し、行動計画を作り、小さな成功を積み重ねることで、無理なく継続することができます。
総括
本書『根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール』は、目標を達成するために、単なる意志力や根性に頼るのではなく、科学的なアプローチを活用することの重要性を説いています。
著者たちは、行動科学の最新の知見をもとに、人間がいかに目標を持続可能な形で達成できるのかを、シンプルかつ実践的なフレームワークにまとめています。
多くの人が目標を立てたものの途中で挫折してしまうのは、決して「努力が足りないから」ではなく、目標達成のプロセスが適切に設計されていないからです。
本書は、その課題を解決するために、「目標設定」「プランニング」「コミットメント」「報酬」「共有」「フィードバック」「あきらめない」という7つのステップを体系的に解説し、読者が実生活の中で取り入れやすい形で提示しています。
この本の最大の魅力は、「小さな変化を積み重ねることで、大きな成果を生む」という考え方にあります。
多くの人は、目標達成には劇的な努力や大きな改革が必要だと思いがちですが、本書では、日常の中に組み込める小さな工夫こそが長期的な成功につながると説いています。
例えば、目標を達成しやすくするために、「環境を整える」「習慣化する」「他者と共有する」などの方法を活用し、無理なく行動を変えていくことが推奨されています。
また、本書は、単なる理論の解説にとどまらず、実際の成功事例や研究結果を多数紹介することで、読者が納得しやすい形で知識を伝えています。
たとえば、イギリスのジョブセンターでの求職支援の成功事例や、ナッジ理論を活用した政府の施策などが具体的に紹介されており、これらの手法がいかに効果的かを実感できます。
こうした実例を交えることで、読者は「自分にもできるかもしれない」と感じやすくなり、行動を起こすモチベーションを高められます。
本書を読むことで、「意志の力に頼るのではなく、仕組みを変えることで行動を持続できる」という視点が身につきます。
そして、それを実際の生活や仕事に応用することで、より効果的に目標を達成できるようになります。
たとえば、ダイエットや運動習慣の継続、キャリアアップのためのスキル習得、チームマネジメントの改善など、さまざまな場面で活用できる考え方が詰まっています。

本書が伝えたいメッセージは、「大きな成果を生むために必要なのは、少しずつでも確実に前進すること」だという点に集約されます。
私たちは、目標を立てるときに「一気に変わらなければならない」と思いがちですが、実際には、小さな行動の積み重ねが最も強力な変化を生むのです。
行動力に関するおすすめ書籍

行動力がテーマのおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 行動力を高めることができるおすすめの本!人気ランキング
- やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ
- すぐやる! 「行動力」を高める”科学的な”方法
- 0秒で動け 「わかってはいるけど動けない」人のための
- どんなことでも「すぐやる」技術
- 根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール
- 嫉妬を今すぐ行動力に変える科学的トレーニング
- 突き抜ける人は感情で動く 結果を出すためのメンタルと行動力のつくり方
- 行動力神メソッド55:潜在意識に働きかけて「すぐやる人」になる!
- ゼロ秒思考[行動編]―――即断即決、即実行のトレーニング
- やる気はあっても長続きしない人の「行動力」の育て方 自分を変える「7+1の習慣」

