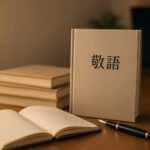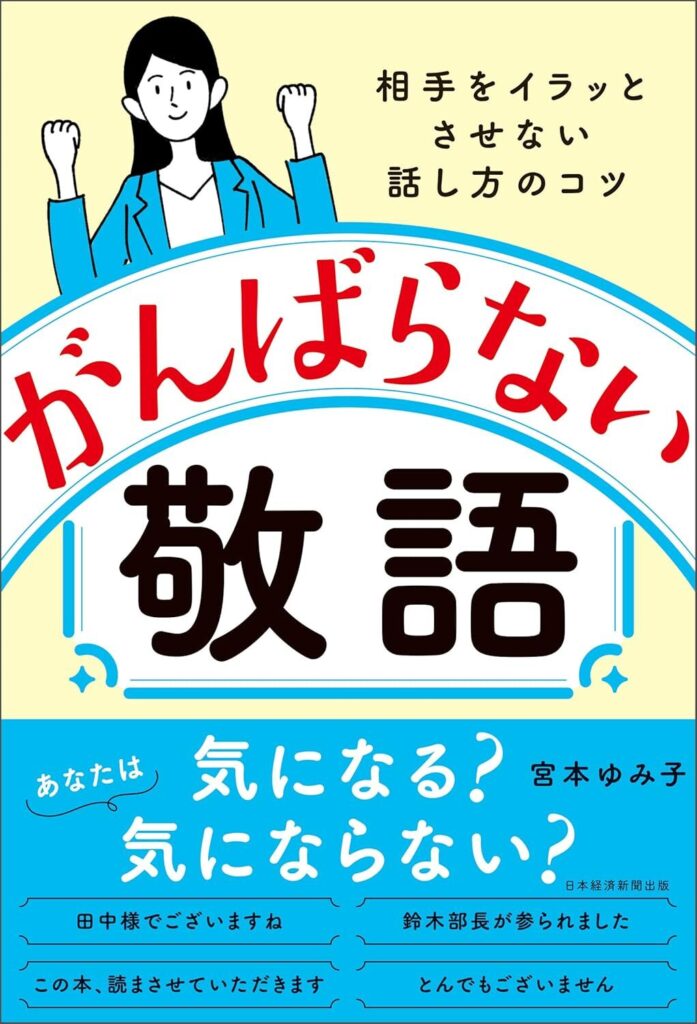
敬語を話すとき、つい「これで合っているのかな?」と不安になったことはありませんか。
丁寧にしようとすればするほど言葉が不自然になったり、相手に距離を感じさせてしまったりする――そんな経験をした人は少なくないはずです。

書籍『がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ』(著:宮本ゆみ子)は、「正しいかどうか」に縛られるのではなく、「気持ちが伝わるかどうか」を重視した新しい敬語の指南書です。
20年以上アナウンサーとして人前で言葉を扱ってきた著者が、シンプルで自然体の表現を豊富な事例とともに解説しています。
本書を手に取れば、「上下関係だから敬語を使う」という従来の発想から離れ、相手との距離感を大切にした言葉の使い方を学べます。
肩の力を抜いて、誰とでも心地よくコミュニケーションできるヒントが詰まった一冊です。

合わせて読みたい記事
-

-
敬語について学べるおすすめの本 13選!人気ランキング【2026年】
上司や取引先へのメール、電話、面接の受け答え――ふと「この敬語、合ってる?」と不安になる瞬間は誰にでもあります。 正しい言い回しが身につけば、伝わり方も印象も一気に変わるはず。 1位 敬語の使い方が面 ...
続きを見る
書籍『がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ』の書評

この本を深く理解するためには、まず著者がどのような経歴を持ち、どんな狙いで執筆したのかを知ることが大切です。さらに全体のエッセンスや目指す方向性、そして多くの人に受け入れられている理由を整理しておくと、本の価値が立体的に見えてきます。
以下の4つの観点から見ていきましょう。
- 著者:宮本ゆみ子のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれを丁寧に確認していくことで、ただの「敬語ハウツー本」とは違う特徴が分かるはずです。
著者:宮本ゆみ子のプロフィール
宮本ゆみ子氏は、大阪大学人間科学部を卒業後、FM石川でアナウンサーとしてキャリアをスタートさせました。その後、K-mix(静岡エフエム放送)や群馬のFM局などを渡り歩き、二十年以上にわたりラジオの現場で第一線を走り続けています。現在は調布FMでも番組を担当し、フリーアナウンサーとして活動中です。
加えて、ビジネスマナーや話し方を指導する研修講師としても活躍。新入社員向け研修から管理職向け研修まで幅広く対応し、企業や自治体で「言葉の使い方」「相手に伝わる表現力」をテーマに指導を行っています。また、書籍の執筆やライターとしても豊富な実績を持ち、三十冊近い本に関わってきました。
こうした多彩な活動を一貫して支えるのは、「話し言葉と書き言葉は表裏一体であり、どちらも人に伝えるためのツールである」という信念です。その視点があるからこそ、敬語を単なるマナーではなく「人間関係を心地よくする技術」として解説できるのです。

アナウンサー経験が長い人ほど、発声や正しい日本語の訓練に意識が集中しがちですが、宮本氏は“どう聞こえるか”“どう受け取られるか”を重視する点が特徴です。
つまり形式美よりも「伝わる」ことを優先する姿勢です。
本書の要約
『がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ』は、従来の「正しい敬語を覚えること」に重点を置いた指南書とは異なり、「いかに自然に敬意を伝えるか」に焦点を当てた実用的な一冊です。敬語を無理に操ろうとすると、かえって不自然な言い回しや誤用を生み、相手に違和感を与えてしまう――著者はこの問題意識を出発点にしています。
本書では「上下関係」を基準に考えるのではなく、「内側と外側」という人間関係の距離感を基準にする方法を提案しています。例えば、身近な関係性では肩の力を抜いた言葉が心地よい一方で、まだ親しくない人には少し丁寧な言葉を選ぶ。この切り替えを身につけることで、過剰に形式ばった表現を避けつつ、適度な敬意を示せるようになります。
構成は六章から成り、最低限押さえるべき基礎表現の整理から始まり、誤用されやすい例の指摘、クッション言葉を用いた柔らかい表現の紹介、敬語の使いすぎによる不自然さへの注意、違和感を覚える日常的な日本語の解説、そして最後には敬語の基礎知識を練習問題で確認できる内容になっています。実践的かつ理論的に「がんばらない敬語」を身につけられる構成となっているのが特徴です。

本書の目的
この本の狙いは、単に「正しい日本語」を習得させることではありません。むしろ、相手に不快感を与えず、自然に思いやりを届ける言葉遣いを身につけることに重点を置いています。敬語を「社会的な武器」と考えるのではなく、「相手との距離感を調整する道具」として活用する考え方を広めようとしているのです。
実際、敬語を使いこなそうとするあまり過剰になったり、間違えたりしてかえって相手を戸惑わせてしまうケースは多くあります。著者はそこに警鐘を鳴らし、「シンプルで丁寧」を軸に据えることで、誰でも無理なく実践できる方法を提案しています。このアプローチは、社会人だけでなく日常的な人間関係でも役立つものです。

人気の理由と魅力
この本が支持される理由は、第一に具体例が豊富である点にあります。単なる解説ではなく、実際に使われている誤用や日常的なやりとりを例に挙げているため、読んだその日から実践に移せます。次に、従来の敬語教育が持つ「正解探し」のプレッシャーから読者を解放してくれる点も大きな魅力です。無理に背伸びをせずとも「自然体でいい」と思えることで、心理的な負担が軽くなります。
さらに、ビジネスの現場に直結する内容が多いのも特徴です。付録にはビジネスメールでよく使うフレーズが整理されており、社会人1〜2年目が直面しやすい「メールで何を書けばいいか分からない」という悩みを解消してくれます。そして、著者がアナウンサーや研修講師として実績を重ねてきた信頼性も、読者の安心感につながっています。
結果として、この本は単なる敬語の参考書ではなく「自然で気持ちのよいコミュニケーション」を可能にする実践書として、多くの人に選ばれているのです。

本書の魅力は、言語学的な正しさよりも「相手にどう届くか」に重点を置いている点にあります。
これはコミュニケーション論としての敬語の活用法であり、単なるマナー本を超えた価値を持っているのです。
本の内容(目次)

この書籍は、敬語を「正しさ」だけで縛るのではなく、実際に人と接するときにどう使えば自然かを体系的に整理しています。各章ごとに焦点が異なり、読み進めることで、言葉遣いの幅が広がるよう構成されています。
以下のような流れで展開されています。
- 第1章 「敬語」は、がんばらなくていい
- 第2章 まずはこれだけ覚えよう 「ございます」「いらっしゃいます」
- 第3章 「敬語」でなくても“うやまう気持ち”を表す表現がある
- 第4章 使いすぎの敬語に注意
- 第5章 よく耳にする違和感ニホンゴの正体
- 第6章 もっと知りたい人のために~敬語の基礎
それぞれの章は、理論だけではなく実例や実践問題を交えて解説されており、初心者でも段階的に理解できるよう配慮されています。
このあとでは、各パートの中身を順に見ていきましょう。
第1章 「敬語」は、がんばらなくていい
最初の章では、「敬語は上下関係を表す道具ではなく、人と人との距離を調整するための表現である」という考え方が示されています。難しい敬語を無理に使うことでかえって相手を不快にさせるより、自然で心のこもった言葉を選ぶ方が大切だと強調されています。
また、いわゆる「バイト敬語」や「慇懃無礼」のように、表面的には丁寧でも違和感を与える表現が例として挙げられています。正しいかどうかを過度に気にするのではなく、場の雰囲気や相手の立場に応じた柔軟な対応が求められるという点がわかりやすく解説されています。
さらに、「郷に入れば郷に従え」という言葉の通り、職場や地域ごとの習慣を理解し、自然に溶け込むことの大切さも語られています。言葉は常に変化するものだからこそ、間違い探しをするのではなく、心地よいコミュニケーションを意識する姿勢が重要だと示されています。

敬語の本質は「正誤」よりも「相手にどう届くか」です。
形式美にとらわれすぎると、かえって本来の目的である“敬意の共有”が失われます。
第2章 まずはこれだけ覚えよう「ございます」「いらっしゃいます」
この章では、敬語の中でも特に誤用が多い基本表現の整理が行われています。とりわけ「ございます」と「いらっしゃいます」の使い分けについて、日常の具体的なシーンを想定しながら丁寧に解説されています。
例えば、身内や自分に関わる場合には「ございます」を用い、外部の人や相手を敬うべき状況では「いらっしゃいます」を使うのが基本です。このシンプルな区別を知ることで、混乱しやすい場面でも迷わず表現できるようになります。
また、上司を社外の人に紹介する場合や、複雑な「いらっしゃいます系」と「ございます系」の境界についても触れられています。こうした実践的なケーススタディを通じて、ただ知識を覚えるのではなく、状況に即して正しく使える力が養われます。

第3章 「敬語」でなくても“うやまう気持ち”を表す表現がある
この章は「敬語=難しい言葉」ではなく、「相手を思いやる姿勢を示すための工夫」として表現を紹介しています。特に「クッション言葉」と呼ばれる前置きのフレーズは、依頼やお願いを柔らかく伝える効果があります。
例えば「恐れ入りますが」「お手数ですが」といった言葉を添えるだけで、相手に与える印象は大きく変わります。また、謝罪の表現や「かしこまりました」「何卒よろしくお願いいたします」といった定型文の使い方についても、背景にある配慮が解説されています。
さらに、メールの誤字脱字を防ぐことや、イントネーションに気を配ることも「敬意の表現」として扱われています。これは単に言葉の選び方だけでなく、伝え方全体が礼儀を形作るのだという視点を学べる内容です。

言葉そのものよりも「伝える態度」が敬意を示します。
声の調子や文章の丁寧さも立派な敬語表現です。
第4章 使いすぎの敬語に注意
この章では「丁寧にしようと頑張るほど不自然になる」という敬語の落とし穴が解説されています。「させていただく」や「お召し上がりになられましたか?」など、二重敬語や過剰表現がその典型例として紹介されています。
また、スピード感が求められるビジネスチャットなどでは、前置きを長く書くよりもシンプルに用件を伝えるほうが適切な場合があると述べられています。過剰に丁寧な表現は、むしろ相手に距離を感じさせたり、逆に負担を与えることがあるのです。
「マナー」と「ビジネスマナー」の違いについて触れられている点も特徴的です。場面や文化によって期待される表現は変わるため、「正しい敬語」よりも「場にふさわしい表現」を選ぶことが重視されています。

敬語を「足す」ほど丁寧になると考えるのは誤解です。
引き算の意識を持つことで、すっきりとした好印象を与えられます。
第5章 よく耳にする違和感ニホンゴの正体
この章では、私たちが日常で耳にする「微妙におかしい日本語」の正体を明らかにします。「すいません」や「よろしかったでしょうか」といった表現は、使う人が多い一方で不自然さを覚える人も少なくありません。
著者は、こうした言葉がなぜ違和感を持たれるのかを分析しつつ、「とんでもございません」や「感謝しかありません」といった言い回しも取り上げます。実際に正しいかどうかよりも、言葉が相手にどう受け取られるかを重視する姿勢が示されています。
また、「ら抜き言葉」についても言及があり、現代では違和感が薄れつつある一方で、場面によってはマイナスの印象を与えることがあると説明されています。こうした変化を理解することで、より柔軟に言葉を使えるようになります。

第6章 もっと知りたい人のために~敬語の基礎
最後の章では、体系的に敬語を学びたい人に向けて基本の整理がなされています。尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・美化語・丁寧語といった分類が説明され、基礎を押さえることで全体像を理解できるようになっています。
さらに、練習問題が用意されており、自分の理解度を確認しながら学べる仕組みになっています。教科書的な知識だけでなく、日常生活やビジネスでどう活かせるかを意識できる内容になっています。
この章は「もっと学びたい」という読者に向けた深掘りの位置づけですが、実際には全体を支える土台にもなるため、基礎から積み上げたい人には特に有用です。

敬語は「理論」と「実践」の両輪で習得するものです。
体系を学んだ後に現場で試すことで、はじめて血肉化します。
対象読者

この本は、特定の立場や状況にある人にとって特に役立つ内容が多く盛り込まれています。敬語に苦手意識を持つ人だけでなく、日々のコミュニケーションに悩みを感じている人にとっても実践的な助けとなるでしょう。
主な対象は以下の通りです。
- 新入社員・社会人1〜2年目の人
- ビジネスメールや接客など敬語を日常的に使う人
- 敬語を使うことがストレスになっている人
- 言葉遣いに自信がないが、印象を良くしたい人
- 上司・後輩・取引先との距離感で悩んでいる人
いずれも共通しているのは、「形式よりも相手に伝わる表現を大切にしたい」という思いを持っている点です。
この本は、その気持ちを形にし、自信を持って人と向き合うための大きな助けとなります。
新入社員・社会人1〜2年目の人
社会に出たばかりの時期は、正しい敬語を使おうと意識するあまり、不自然な表現や過剰な言い回しになってしまうことが多いものです。本書は「上下関係」ではなく「内側・外側」という距離感で敬語を捉える視点を提示しており、複雑なルールにとらわれずに自然な言葉遣いを身につけられます。
また、誤用例や実際の会話シーンを豊富に示しているため、現場での戸惑いを減らし、自信を持ってやりとりができるようになります。入社初期から「自然で失礼のない表現」を体得することは、信頼関係を築くうえで大きな武器になるでしょう。

新社会人がつまずきやすいのは「正しいかどうか」よりも「自然かどうか」。
本書はその違いを明確に教えてくれます。
ビジネスメールや接客など敬語を日常的に使う人
顧客対応やメール業務で敬語を日常的に使う人にとって、言葉は信頼の基盤です。小さな誤用でも「雑」「不親切」と受け取られるリスクがあり、ミスを避けるためのストレスも増えがちです。本書では、よく使う表現を中心に整理しているため、業務に直結するフレーズを効率よく学ぶことができます。
さらに、接客や営業では「感じが良い」と思われることが成果に直結します。形式ばかりを追わず、相手に寄り添うやわらかな表現を身につけることができる本書は、現場で即戦力となるツールとなるでしょう。

顧客との接点では「言葉遣い=企業の顔」。
そのため現場職にこそ、本書の実践的アプローチが必須です。
敬語を使うことがストレスになっている人
「間違えたらどうしよう」と不安を感じ、会話そのものが重荷になっている人は少なくありません。本書は「上下関係」という硬直した発想から離れ、「内と外」というシンプルな視点で敬語を捉えることを提案しています。これにより、不要な緊張を和らげ、リラックスして会話できるようになります。
結果として、敬語を「苦手意識を強める壁」ではなく「人間関係を円滑にする橋」として活用できるようになります。心理的負担を減らすことで、対話そのものがスムーズになり、相手に自然体の好印象を与えることが可能です。

過剰な自己監視は会話不安を悪化させます。
本書は敬語を簡素化することで、心理的安全性を高める実践書といえます。
言葉遣いに自信がないが、印象を良くしたい人
「自分の敬語は合っているのか」と不安を抱きつつも、少しでも印象を良くしたいと考える人には、本書の「相手を敬う気持ちを形にする表現」が役立ちます。完璧な文法よりも、誠意が伝わる言い方を優先する姿勢が紹介されており、安心して使える表現が身につきます。
わずかな言い回しの工夫で、相手の受け止め方は大きく変わります。本書の事例を取り入れることで、自信がなくても「感じが良い人」と思われる言葉選びができるようになるのです。

印象形成の研究では「正しさ」より「親しみやすさ」の影響が大きいとされます。
本書はまさにその視点を補強します。
上司・後輩・取引先との距離感で悩んでいる人
立場の違う相手との関わりで「堅苦しすぎても冷たい」「砕けすぎても馴れ馴れしい」といった悩みはよくあります。本書は、立場ではなく関係性の「近さ」を基準に敬語を調整する考え方を提示しており、このジレンマを解消します。
この柔軟な発想を実践することで、上司との信頼、後輩との協力、取引先との良好な関係を自然に築くことができます。形式的に上下を意識するのではなく、相手を尊重しつつ適切な距離を保つバランス感覚が養われるのです。

言語学のポライトネス理論でも「心理的距離」が丁寧さの基準とされています。
本書はそれを日常会話に落とし込んでいます。
本の感想・レビュー

敬語の「上下関係」から「距離感」への転換が新しい
敬語といえば「上司に対してどう言うか」「年上にどう話すか」という上下関係の意識が当たり前でした。けれども、この本に書かれていた「内側と外側」という考え方は、従来の発想を大きく変えてくれるものでした。近しい人には肩ひじ張らない言葉を、距離のある相手には丁寧な表現を、とシンプルに整理できる視点は、とても腑に落ちます。
読んでいるうちに、自分がこれまで「目上だから」と無理にかしこまっていたことが、むしろ不自然さを生んでいたのではないかと気づかされました。距離感を軸にすることで、余計な緊張が減り、相手と自然に会話ができるというイメージがつかめました。
実際に本を閉じた後、家族や職場でのちょっとした会話を思い出して、「これは内側」「あの人は外側」と頭の中で仕分けするだけで、言葉選びが楽になりました。上下関係という枠組みから解放されるだけで、敬語が身近に感じられるようになったのです。
過剰敬語や間違い敬語の具体例が多く、実践に活きる
読み進めていて驚いたのは、自分が「正しい」と思い込んでいた言葉が、実は誤用や過剰表現として挙げられていたことでした。たとえば「読まさせていただきます」や「お召し上がりになられましたか?」といった言い回しは、日常の中でよく耳にするものです。それが「使わない方が良い」と明快に説明されていて、なるほどと納得しました。
また、誤りを指摘するだけではなく、「ではどう言えば良いのか」という代替表現が一緒に提示されているので、すぐに実践できる点がありがたかったです。単なる知識ではなく、実際の会話やメールの中に落とし込める形で解説されているのは、非常に実用的だと感じました。
読後に自然と「自分が使っている表現を一度振り返ってみよう」と思わせてくれる力があります。知らない間に誤った敬語を身につけてしまうことは誰にでもあることですが、その修正方法をわかりやすく教えてくれるのが、この本の大きな価値だと実感しました。
初心者でも読みやすい言葉遣いと構成
普段、語学やマナーの本は少し堅苦しくて途中で読むのをやめてしまうことが多いのですが、この本は最後までストレスなく読み進めることができました。著者がアナウンサー出身ということもあってか、リズム感のある言葉遣いで、まるで会話をしているような感覚で学べました。
内容も難解な理屈ではなく、日常の場面を切り取った具体例をベースにしているので、初心者でも置いてけぼりになりません。「ああ、このシーンで使う言葉なんだな」と自然に想像できる構成になっていました。
また、章立ても独立性が高いので、最初から順番に読まなくても理解できるのが便利です。仕事の合間や通勤時間に気になる章だけ読むというスタイルでも、十分に役立つ知識が得られるところに、この本の懐の深さを感じました。
“心がこもっている”言葉と“形式的な敬語”の違いに気づかされる
これまで私は「正しい言葉を選ぶこと」ばかりを優先してきました。そのため、形式的には正しくても、どこかよそよそしいと感じられることがあったのです。本書を読んで初めて、敬語は形ではなく「相手を敬う気持ち」が中心にあるべきだと実感しました。
どれほど完璧な表現を並べても、心がこもっていなければ相手に響かない。その一方で、多少くだけた表現でも、思いやりが伝われば不快にはならない。この違いを、事例を通してわかりやすく解説してくれているため、改めて言葉の本質に立ち返ることができました。
言葉を磨くことは大事ですが、もっと大切なのは「相手と心を通わせること」だと気づかされた瞬間でした。形式にとらわれて息苦しさを感じていた人ほど、この視点に救われるのではないかと思います。
ビジネスメールにも応用できる表現が付録で便利
特に役立ったのは、巻末に収録されているビジネスメールでの言い回しでした。普段のやり取りの中で迷う定型文が整理されており、実際にそのまま使える表現が多いのです。読むだけでなく、実務で即応用できる点は非常に実用的だと感じました。
しかも単なるフレーズ集ではなく、どういう場面でどの言葉を選ぶのがふさわしいのかも説明されています。そのため、単に「書き写す」のではなく、状況に合わせて適切に使えるようになる導き方がされています。
読み終えたあと、自分のメール文を見直すと、無駄に堅苦しかった部分を自然に修正できるようになりました。形式張った文章よりも、相手に伝わるやさしい敬語表現を選べるようになったことは、大きな成果です。
感情を害さずに丁寧さを保てるテクニックが多数
この本を読んで一番ありがたかったのは、相手に余計なストレスを与えず、それでいて丁寧さをきちんと表現できるテクニックが紹介されていたことです。敬語はどうしても過剰になったり、逆に軽くなりすぎたりして相手に不快感を与えてしまう危うさがあります。そのバランスの取り方を丁寧に解説してくれている点が安心感につながりました。
特に印象的だったのは、相手に配慮しつつも、過剰にへりくだらない方法が紹介されていたところです。読んでいて「なるほど、これなら言いやすいし、聞く側も気持ちよく受け止められる」と納得できました。単なる理屈ではなく、実際のやり取りを想定した実践的なアドバイスだからこそ、説得力があります。
著者のバックグラウンド(アナウンサー・ライター)からくる説得力
著者がアナウンサーとして長年活動してきたという経歴を知ると、文章や内容に説得力がある理由がよくわかりました。声で伝える仕事に携わってきたからこそ、「どう聞こえるか」「どう伝わるか」に敏感で、その視点が本全体に生きています。
さらに、ライターとしても活動しているため、言葉を文字で扱う経験も豊富です。話し言葉と書き言葉の両方を自在に扱える人だからこそ、敬語の解説が単なる知識の羅列ではなく、実際の場面でどう響くかに焦点が当てられています。読んでいると、理論と実践が自然に結びついているのを感じました。
経歴を背景にした言葉は、単なる専門家のアドバイス以上の重みがあります。長年の経験からにじみ出るリアルさがあり、この人の言うことなら信じられると思わせてくれる一冊でした。
言葉の「がんばりすぎ」が不自然さを生むと気づける
これまで私は、敬語は「なるべく丁寧に」「間違えないように」と気を張って使うものだと考えていました。しかし本書を読んでいくと、その「がんばりすぎ」がかえって不自然さを生んでしまうのだと気づかされました。二重敬語や過剰な表現が、相手にとっては逆に居心地の悪さを生むという指摘には、思わずハッとしました。
本書に出てくる「慇懃無礼」という言葉は、とても印象に残りました。どんなに正しくても、あまりに堅苦しさを感じさせる言い回しは、結局は相手に壁をつくってしまうのです。私は今まで、正確さばかりに意識を向けていましたが、実はシンプルさや自然さこそが相手に伝わる敬語の鍵なのだと学びました。
それ以来、自分が話すときも「丁寧にしよう」と力むのではなく、「自然に伝わるかどうか」を基準に考えるようになりました。過剰な敬語を避けることは、相手との距離を近づけ、自分自身もリラックスできる方法だと実感しています。
まとめ

ここまで紹介してきた本のポイントを振り返ると、実践的でありながら肩の力を抜いて敬語を学べる仕組みがよく分かります。
最後に、このセクションでは整理された形で確認してみましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
整理した視点を押さえることで、読者は「本書を読むと何が変わるのか」を一目で理解できるはずです。
そして、その学びを今後の日常やビジネスシーンにどう活かしていけるかもイメージしやすくなります。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、読者が得られる具体的な利点を整理してみましょう。
自信を持って言葉を使えるようになる
本書では、敬語を「上下関係」ではなく「内側と外側」という距離感の発想で捉える方法が紹介されています。従来の複雑なルールを暗記するのではなく、相手との関係性に合わせて言葉を選ぶスタイルは、初心者にとって理解しやすく、実際に使いやすいものです。これにより、過剰な敬語や不自然な言い回しに悩むことなく、自信を持って会話やメールを行えるようになります。
信頼を築けるコミュニケーション力が身につく
敬語を正しく使うこと自体が目的ではなく、「相手に敬意を伝える」ことが本質であると説かれています。そのため、形だけの表現にとらわれず、相手に不快感を与えないシンプルで誠実な言葉遣いを実践できるようになります。こうした態度は、上司や同僚、取引先など、さまざまな人との信頼関係を築く基盤となり、仕事の成果にも直結するでしょう。
実践的なスキルをすぐに活用できる
本書では、「ございます」と「いらっしゃいます」の正しい使い分けや、クッション言葉のバリエーション、メールにおける敬語の注意点など、現場で即活用できる具体的なフレーズが多く紹介されています。知識だけで終わらず、日々のやり取りに直結する表現を学べるため、読むほどに実用的な引き出しが増えていきます。
敬語に対するストレスが減る
「頑張れば頑張るほど間違えてしまう」という敬語のジレンマを解きほぐし、必要以上に力を入れずとも自然な表現で十分伝わることを教えてくれるのが、この本の大きな特徴です。これにより、緊張や不安を感じがちな人でも肩の力を抜いて言葉を使えるようになり、対人関係におけるストレスが大幅に軽減されます。

読後の次のステップ
本書を読み終えた後に大切なのは、知識を知識のまま終わらせず、日常に落とし込んでいくことです。敬語は机上の学問ではなく、人と関わる中で初めて意味を持つスキルだからです。
ここからは、学んだ内容を定着させ、さらに発展させるための行動指針を紹介します。
step
1実際の会話で試してみる
本を読んだだけでは敬語の感覚はなかなか身につきません。まずは日常の会話や職場のコミュニケーションで、学んだフレーズを意識的に使ってみましょう。たとえば、取引先に電話をかける場面や上司に報告する場面など、身近な実践の場を選ぶと自然と習慣化につながります。繰り返すうちに、無理をせずとも言葉が口から出るようになります。
step
2自分の言葉を振り返る
実践のあとは、自分の使った表現を振り返ることも大切です。メールやチャットの文面を見直したり、会話のやりとりを思い返したりするだけでも、自分の癖や改善点が見えてきます。誤字脱字を防ぐ習慣もここで身につき、相手に対する敬意が一層伝わりやすくなります。
step
3少しずつ表現を広げる
基礎となる表現を定着させたら、クッション言葉や柔らかい言い回しを取り入れて幅を広げていきましょう。たとえば「恐れ入りますが」「念のためご確認ください」といった表現は、堅苦しさを和らげつつも丁寧さを損ないません。小さな一歩の積み重ねが、自分らしい敬語スタイルを築いていきます。
step
4周囲の反応を観察する
言葉は相手あってこそ成り立つものです。自分が発した表現に対して、相手が安心しているのか、距離を感じているのかを観察することで、より適切な言葉遣いが磨かれていきます。相手の笑顔やうなずきといった非言語的な反応も、敬語の効果を測る大切な手がかりになります。

言語習得の定着には「実践」「フィードバック」「拡張」の3段階が必須です。
本書の学びを行動に移すことで、単なる知識が実践的なスキルへと昇華します。
総括
『がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ』は、従来の「正しいかどうか」に縛られる敬語学習から一歩踏み出し、相手を思いやる姿勢を中心に据えた新しいアプローチを提示しています。敬語を上下関係の道具として扱うのではなく、心地よい距離感を作るための表現として再定義している点が、他のビジネス書にはない大きな特徴といえます。
本書の内容を通じて、私たちは「正確さ」よりも「伝わりやすさ」を優先すべき場面が多いことに気づかされます。無理に難しい言葉を駆使しなくても、相手に尊敬や配慮が届けば十分に良好な関係は築けるという考え方は、日常のコミュニケーションを大きく軽やかにしてくれます。
また、本書が示す「内側と外側」という距離感の考え方は、社会人にとって非常に実用的です。相手を上下ではなく関係性の近さで捉えることにより、状況に応じて適切な言葉を自然に選べるようになります。これにより、無理をして敬語を装うのではなく、自分らしい表現で相手を尊重できるようになります。

この本が伝えているのは「敬語にがんじがらめにならなくても大丈夫」という安心感です。
読者はこのメッセージを通じて、自分自身の言葉に自信を持ち、ビジネスや日常生活においてよりリラックスしたコミュニケーションを実現できるでしょう。
敬語に関するおすすめ書籍

敬語について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 敬語について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 敬語の使い方が面白いほど身につく本
- がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ
- 敬語と言葉づかい マナーの便利帖 新装版
- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー
- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる
- 誰もここまで教えてくれない 一生使える「敬語&ビジネスマナー」
- その敬語、盛りすぎです!
- 敬語再入門
- これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識
- 敬語「そのまま使える」ハンドブック
- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート
- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー