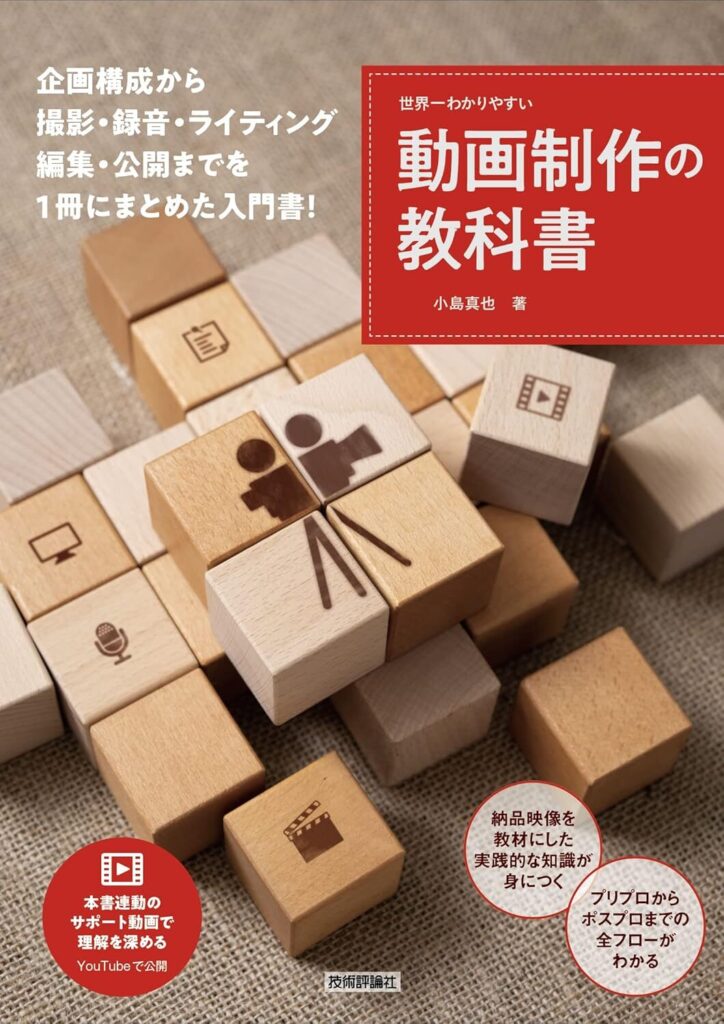
動画は今や、ビジネスや教育、さらには店舗や観光のプロモーションに欠かせない表現手段となっています。
しかし、実際に制作しようとすると「何から始めればいいのか分からない」「思い描いた通りの映像にならない」といった壁に直面する人は少なくありません。
本書『世界一わかりやすい動画制作の教科書』は、そんな悩みを抱える方々に寄り添い、企画から完成までの全体像を体系的に学べる一冊です。

本書の特徴は、映像制作を「企画」「撮影」「編集」という3つの工程に分け、ワークフローに沿って具体的に解説している点にあります。
専門的な理論や技術も、初心者が理解できるように噛み砕いて紹介されており、さらに実際の企業案件を題材にした企画書や台本の実例が豊富に掲載されています。
机上の知識にとどまらず、現場で使えるスキルを身につけられる構成になっているため、読んだその日から実践につなげられるのが大きな魅力です。
また、書籍と連動したYouTube動画による解説が用意されており、テキストだけでは伝わりにくいカメラワークや編集のニュアンスを視覚的に確認できます。
文字・図解・映像を組み合わせて学べるため、初心者でも理解が深まりやすく、上達スピードも飛躍的に高まります。
これから動画制作に挑戦したい方にとって、本書は確かな羅針盤となるでしょう。

合わせて読みたい記事
-

-
動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本 7選!人気ランキング
YouTubeやTikTokなどで動画を作っていると、「もっと視聴者に楽しんでもらいたい」「再生数や登録者を増やしたい」と感じることはありませんか? 動画制作はアイデアから撮影・編集、発信に至るまで幅 ...
続きを見る
- 書籍『世界一わかりやすい動画制作の教科書』の書評
- 本の内容(目次)
- chapter 01 動画制作の企画書づくり & 調査
- chapter 02 動画作品の構成づくり
- chapter 03 撮影台本とナレーション原稿づくり
- chapter 04 撮影/映像の技術的な基礎
- chapter 05 撮影/カメラワークの基本
- chapter 06 撮影/編集で困らないための撮影
- chapter 07 撮影/ストーリーを意識した撮影
- chapter 08 録音/映像を支える音声収録
- chapter 09 ライティング / 光の知識と実践技術
- chapter 10 編集 / 動画編集の基本と事前準備
- chapter 11 編集 / 映像的演出とつなぎの基礎知識
- chapter 12 編集/音声の編集
- chapter 13 編集 / テロップとタイトル
- chapter 14 編集 / カラーグレーディングの基本
- chapter 15 編集 / 納品先メディアと書き出し
- 対象読者
- 本の感想・レビュー
- まとめ
書籍『世界一わかりやすい動画制作の教科書』の書評

この本は、動画制作をこれから始めたい人から、すでに取り組んでいるが「もっと質を高めたい」と考える人まで幅広く役立つ一冊です。単にカメラや編集ソフトの操作方法を解説するのではなく、映像の企画段階から撮影、編集、そして公開・納品までの一連のワークフローを体系的に整理しているのが大きな特徴です。
ここでは以下の4つの観点から、書籍の魅力を深く掘り下げていきます。
- 著者:小島 真也のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれを理解することで、本書が単なる技術書ではなく、映像を通じて「人に伝える力」を育てる実践的なガイドブックであることが見えてくるでしょう。
著者:小島 真也のプロフィール
小島真也氏は1961年、愛知県生まれ。大学で経営学を学んだ後、名古屋ビジュアルアーツで写真・映像の技術を習得し、日本を代表する写真家・篠山紀信氏に師事しました。篠山氏のもとでポートレート撮影や構図の基本を学んだ経験は、その後の活動の基盤になっています。1990年に独立してからは、広告や雑誌を中心にポートレートや商品写真を撮影し、数多くの商業案件を手がけてきました。
2005年、AppleのFinal Cut Studioを導入したことをきっかけに映像制作にも本格的に参入。写真の「一瞬を切り取る力」を生かしつつ、映像の「時間を編集する力」を磨いていきます。2011年には映像制作ユニット「VideographersOnline」を立ち上げ、企画・構成・撮影・編集・カラーグレーディングまで一貫して手がけるワークフローを確立しました。
教育者としても積極的に活動しており、日本写真芸術専門学校で映像授業を担当するほか、映像学院で編集や技術セミナーの講師を務めています。また、Blackmagic Design社のDaVinci Resolve認定トレーナーとして、カラーグレーディングを中心に後処理の専門知識を普及しています。玄光社「コマーシャルフォト」「ビデオSALON」やWebメディアPRO NEWSなどで専門記事を連載し、プロの現場と教育の両面で影響力を持つ人物です。

本書の要約
『世界一わかりやすい動画制作の教科書』は、動画制作をまったく知らない人でも順を追って学べるように構成されています。内容は大きく三つの流れに分かれており、それぞれが有機的につながることで、動画制作全体のワークフローが理解できるようになっています。
第一の流れは「企画・構成づくり」。ここでは、動画制作の方向性を決める企画書の作り方や、構成を固めるための調査方法、さらには撮影台本やナレーション原稿のまとめ方までが丁寧に解説されています。特に、実際の企業案件で使われた企画書や調査シートの事例が紹介されているため、読者は「机上の勉強」ではなく「実務に直結する学び」を得られる点が大きな魅力です。
第二の流れは「撮影・録音・ライティング」。カメラの種類ごとの特徴、レンズやフレームレートの基本、撮影ポジションやカメラワークの工夫など、現場で役立つ知識が豊富に盛り込まれています。また、音声収録や照明の基礎知識も扱われており、単なる映像ではなく「映像と音が調和した作品」を目指せるよう工夫されています。初心者がつまずきやすい「イマジナリーライン」や「ジャンプカット」といった映像文法についてもわかりやすく解説されているのは、本書ならではのポイントです。
最後の流れは「編集と公開」。カット編集やモンタージュの基本原理、音声編集、テロップやタイトルの作成方法、カラーグレーディングなど、仕上げの工程が網羅されています。さらに、完成した動画の納品や公開方法についても具体的な手順が示されており、YouTubeやBlu-rayといった異なるメディアへの対応まで含まれています。このため、本書一冊で動画制作の全体像を把握しつつ、各ステップで必要な実践的スキルを学べるのです。

動画制作を理解するには「部分」ではなく「全体の流れ」を掴むことが不可欠です。
本書は準備から完成までの一連の工程を体系的に学べるよう設計されているため、初心者が迷わず取り組めるのです。
本書の目的
この本の目的は、誰もが手軽に動画を作れる時代において、「単に作ること」ではなく「相手に伝わる映像を完成させること」を可能にする点にあります。動画は、文字や静止画に比べて圧倒的に多くの情報を伝達でき、インパクトも大きいメディアです。しかし、撮影機材や編集ソフトが身近になったとはいえ、作り手の意図が整理されていない作品は、ただの自己満足で終わり、視聴者には響きません。
著者の小島真也氏も、写真家から映像へと活動を広げた初期には、見栄えは良いがメッセージが伝わらない「見せられて困る動画」を作ってしまった経験があると語っています。この失敗から学んだのは、動画制作において重要なのは「ロジック」と「表現手法」の両立だということです。
本書では、製品紹介や観光案内、社内教育や店舗宣伝といったビジネスでの利用を想定し、プロモーション映像として効果的に伝えるための仕組みを体系的に学べるようになっています。つまり、「動画を作れる」から「動画で伝えられる」へと進化するための道筋を示すことが、本書の大きな目的です。

動画制作の本質は「技術」ではなく「意図をどう伝えるか」にあります。
本書はその視点を常に軸に置いているため、単なる操作解説書ではなく、映像表現の教科書としての価値を持っています。
人気の理由と魅力
この本が多くの読者から支持を集めている理由は、理論と実践のバランスに優れている点にあります。多くの入門書は基礎知識に終始しがちですが、本書は実務の現場を踏まえており、実際の企業案件で使われた企画書や台本、撮影プランの事例が数多く掲載されています。そのため、学んだ内容をすぐに仕事に応用できるのが大きな魅力です。
さらに、写真や図解、画コンテ、ソフトのキャプチャ画面が豊富に盛り込まれており、初心者が直感的に理解できるよう工夫されています。特に専門用語や映像文法といった難解な部分についても、噛み砕いた説明が添えられているため、独学でも学びやすい構成です。加えて、YouTubeに連動した解説動画が用意されていることで、紙面だけでは伝わりづらい部分を映像で確認できる点も評価されています。
また、著者自身の失敗談や現場での体験談が散りばめられており、単なる技術解説書ではなく「実務でどう活かすか」にまで踏み込んでいる点も魅力の一つです。特にカラーグレーディングや納品データの作成方法など、一般的な入門書では触れられにくい専門的な領域までカバーしているのは珍しく、現場目線で役立つ情報が満載です。

本書の魅力は「網羅性」と「実用性」の両立です。
全体像を示しつつ、実務ですぐに使えるノウハウに落とし込んでいるため、初心者から経験者まで幅広い層に役立つ一冊となっています。
本の内容(目次)

本書は、動画制作の流れを体系的に学べるように章ごとに構成されています。基礎的な企画から、撮影・録音・編集、そして最終的な仕上げまで、段階的にスキルを積み上げられる仕組みになっています。
各章のテーマは以下のとおりです。
- chapter 01 動画制作の企画書づくり & 調査
- chapter 02 動画作品の構成づくり
- chapter 03 撮影台本とナレーション原稿づくり
- chapter 04 撮影/映像の技術的な基礎
- chapter 05 撮影 / カメラワークの基本
- chapter 06 撮影/編集で困らないための撮影
- chapter 07 撮影 / ストーリーを意識した撮影
- chapter 08 録音/映像を支える音声収録
- chapter 09 ライティング / 光の知識と実践技術
- chapter 10 編集 / 動画編集の基本と事前準備
- chapter 11 編集 / 映像的演出とつなぎの基礎知識
- chapter 12 編集/音声の編集
- chapter 13 編集 / テロップとタイトル
- chapter 14 編集 / カラーグレーディングの基本
- chapter 15 編集 / 納品先メディアと書き出し
このように段階を追って学べる構成になっているため、初心者でも流れを理解しながら実践的な力を養えます。
chapter 01 動画制作の企画書づくり & 調査
動画制作の最初のステップは、しっかりとした企画を立てることです。この段階では「映像の難易度は構成によって決まる」という考え方が強調されます。アイデアがどんなに良くても、筋道がなければ視聴者に伝わりません。そのため、制作の目的やターゲットを整理し、どのようなメッセージを届けたいのかを言語化していく必要があります。ここでは「3T」や「5W2H+1T」といったフレームワークを活用し、企画を具体的な形に落とし込む方法が紹介されています。
また、この章では下調べの重要性についても触れられています。情報収集は主観に偏りやすいため、事前の調査を徹底して先入観を排除する姿勢が求められます。調査シートの作成やリサーチの進め方を具体例を交えて解説しているため、実務での再現性が高いのが特徴です。こうした準備が整っていれば、後の撮影や編集工程がスムーズに進み、最終的なクオリティにも直結します。

企画段階を軽視すると、撮影現場で迷走しがちです。
映像制作は「段取り八分」であり、この章で学ぶ企画書作成の技術が成功の土台になります。
chapter 02 動画作品の構成づくり
企画が固まったら、次に必要なのはストーリーの設計です。この章では「起承転結」や「三幕構成」といった物語の基本法則を動画に応用する方法が解説されています。ストーリー性を持たせることで、視聴者が自然に引き込まれ、最後まで見てもらえる動画に仕上がります。特に、情報を盛り込みすぎず「引き算の思考」で整理することの重要性が強調されています。
さらに、構成を形にするための実践的な方法として「付箋を使ったアイデア整理」や「画コンテの描き方」なども紹介されています。文章だけでなく視覚的に流れを確認できる工夫を取り入れることで、撮影現場での齟齬や迷いを減らすことができます。シンプルで理解しやすい構成が、映像表現のわかりやすさを決定づけるのです。

構成づくりは「情報を削る勇気」がカギです。
すべてを盛り込みたい気持ちを抑えて、視聴者が本当に必要とする要素だけを残すことで、説得力のあるストーリーになります。
chapter 03 撮影台本とナレーション原稿づくり
この章では、構成をもとに実際の設計図を作るステップが解説されています。台本は映像制作の地図のような役割を果たし、撮影現場での混乱を防ぐために不可欠です。ここでは「ロケーションの下見(ロケハン)」や「撮影サイズの指定」といった、現場で必要になる準備の仕方が丁寧に説明されています。
また、ナレーション原稿の作成にも重点が置かれています。映像だけでは伝わりにくい部分を言葉で補うナレーションは、視聴者の理解を助ける重要な要素です。専門的なポイントとして「わかりやすく」「簡潔に」「誤解を避ける」という三つのルールが紹介され、具体的な原稿例も提示されています。さらに、コンテの描き方についても触れられ、文章を映像イメージに変換するプロセスを実際に体験できる構成になっています。

撮影台本は映像制作のナビゲーションシステムです。
事前に用意することで、現場の混乱を最小限に抑え、狙った映像を確実に撮ることができます。
chapter 04 撮影/映像の技術的な基礎
撮影段階に入ると、カメラの特性や映像の基礎理論を理解することが必要になります。この章では、ビデオカメラや一眼レフ、スマートフォンなど、各機材の長所と短所を整理しながら、自分に合った機材を選ぶ指針が示されています。また「焦点距離と画角」「露出の三要素(シャッタースピード・絞り・ISO感度)」「ホワイトバランス」など、映像制作の基本的な理論が具体例を交えて紹介されています。
さらに「フレームレート」や「解像度」「アスペクト比」といった、動画ならではの設定要素も解説されています。これらは聞き慣れない専門用語ですが、本書ではパラパラ漫画を例に「なぜ映像が動いて見えるのか」を説明するなど、初心者でも理解しやすい工夫がなされています。こうした理論を押さえておくことで、意図した映像表現を選択的に作り出すことができるようになります。

映像の基礎知識は、楽譜を読む音楽家にとっての譜面と同じです。
理屈を理解してこそ、狙った表現を自在にコントロールできるのです。
chapter 05 撮影/カメラワークの基本
この章では、カメラの動きやアングルが持つ意味と、その使い方が解説されています。アイレベルや俯瞰、ローアングルといったカメラポジションやアングルは、それぞれ異なる印象を与えます。例えば、俯瞰は対象を小さく、弱く見せる効果があり、ローアングルは迫力や威厳を表現するのに適しています。こうした「視点の操作」によって映像のメッセージ性が大きく変わることが示されています。
また、フィックスショットやパン、ズームといった基本的なカメラワークの解説も行われています。移動撮影の手法(ドリー、トラック、クレーン)など、映画やCMで使われる高度な技術も紹介されており、演出意図に応じて適切に選択できるようになります。初心者が撮影を行う際にも「ただ回す」から一歩進んで、映像表現に意識を持たせることができるようになります。

カメラワークは「視聴者の目線を操る技術」です。
どう見せたいかを意識するだけで、同じ被写体でも全く違う印象を与えることができます。
chapter 06 撮影/編集で困らないための撮影
映像制作において、撮影と編集は密接に結びついています。この章では、後の編集作業で困らないために撮影時に意識すべきルールや工夫が解説されています。例えば「イマジナリーライン」という概念は、人物同士の位置関係を守るための見えない線のことを指します。これを意識せずにカメラを配置すると、編集の段階で不自然なカットつなぎが生じ、視聴者が混乱してしまうのです。
また、編集で避けたい「ジャンプカット」を防ぐ方法も紹介されています。似たような画角で撮影すると映像がぎこちなく見えてしまうため、「20%ルール」や「30度ルール」に従って撮影を工夫する必要があります。さらに、構図のラインを意識した撮影を行うことで、映像にリズムやメリハリを加えることができ、編集作業が格段にスムーズになります。

撮影は編集のための素材作りでもあります。
編集段階を想定してカットを撮り分けることで、後工程の自由度が大きく広がります。
chapter 07 撮影/ストーリーを意識した撮影
単に映像を積み重ねるのではなく、物語性を意識した撮影が求められるのがこの章です。ここでは「1シーン3カット構成」や「5W1Hの要素を盛り込む」といった、撮影を作文のように組み立てる手法が紹介されています。これにより、映像にリズムと流れが生まれ、観る人にとって理解しやすいストーリーになります。
さらに、「アクションカット」「マッチカット」など、場面転換や映像のつながりを自然に見せるテクニックも解説されています。加えて「ディーンの法則」という舞台芸術の理論を映像表現に応用する事例も取り上げられ、伝統的な美学が現代の動画制作にどう生きるかを学べます。撮影を単なる記録ではなく、演出として捉える重要性を実感できる章です。

chapter 08 録音/映像を支える音声収録
動画のクオリティを左右する大きな要素が音声です。この章では、録音の基礎から実践的な収録方法まで幅広く扱われています。音の種類やマイクの特性について詳しく解説され、特にダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違い、指向性の理解といった知識が重要視されています。適切な機材を選ばなければ、どれほど映像が美しくても全体の印象は損なわれてしまいます。
さらに、ノイズを抑えるための環境作りやマイクの扱い方、インタビューやナレーションの収録方法についても具体的に解説されています。特に「宅録」のノウハウは、近年のオンライン動画需要に応える実用的な情報です。自宅でもプロレベルの音声が録れる環境を整えることで、制作の幅が大きく広がります。

映像の質を決めるのは目ではなく耳です。
人間は意外にも映像より音の不自然さに敏感であり、音声品質の高さが信頼感に直結します。
chapter 09 ライティング / 光の知識と実践技術
照明は、映像に立体感や雰囲気を与える最も重要な要素の一つです。この章では「硬い光と柔らかい光」の違いや、点光源と面光源の特徴を解説しながら、被写体をどう照らせば印象的に見せられるかを学びます。光の方向や質を調整することで、同じシーンでもまったく異なる印象を与えることができるのです。
さらに、映像制作で頻繁に用いられる「三点照明」の基本も解説されています。キーライト、フィルライト、バックライトを組み合わせることで、人物を立体的に引き立たせる技術です。また、現場の光を活かす応用的なライティングについても触れられ、限られた機材でも高品質な映像を作る工夫が学べます。

ライティングは「画面の空気感」を作る技術です。
光を意識するだけで、同じ被写体でも高級感や安心感といった異なる印象を自在に演出できます。
chapter 10 編集 / 動画編集の基本と事前準備
撮影が終わったら、次は編集の段階に移ります。この章では「編集とは何か」という根本的な問いから始まり、ポストプロダクションの全体像が整理されています。映像編集は単なるカットのつなぎ合わせではなく、素材を取捨選択し、意図に沿って再構成する作業です。そのため、編集に入る前の準備が極めて重要となります。
具体的には、データの整理やバックアップの仕方、必要な素材を効率的に集める方法など、作業環境を整えるノウハウが解説されています。また、編集に使うソフトウェアの種類や特徴についても触れられており、自分に合ったツール選びの参考になります。下準備を丁寧に行うことで、制作全体の効率と完成度が大きく変わることを強調しています。

編集は「撮影した素材をどう語らせるか」の工程です。
準備を怠らないことが、表現力を最大限に引き出す近道となります。
chapter 11 編集 / 映像的演出とつなぎの基礎知識
映像編集において「どうつなぐか」は「何を撮るか」と同じくらい重要です。この章では、編集の目的を「撮りっぱなしの映像を整理し、メッセージをわかりやすく伝えること」と定義し、具体的な手法を丁寧に解説しています。モンタージュやクレショフ効果といった映画理論も紹介され、単なる技術ではなく視覚心理を利用した表現の奥深さを学ぶことができます。
また、場面転換の方法としてクロスカットやマッチカット、ジャンプカット、ディゾルブやフェードなど、多彩なつなぎ方が紹介されています。それぞれの手法が持つ印象や効果の違いを理解することで、映像にリズムや感情を与えることが可能になります。実際の企業映像の事例を通じて、文法に沿った編集の実践方法がイメージしやすくなる構成です。

編集は「削る作業」ではなく「意味を与える作業」です。
つなぎ方ひとつで観客の感情は大きく変化します。
chapter 12 編集/音声の編集
音の調整は映像の完成度を左右する大きな要素です。この章では、収録した音声を編集でどのように整えるかが解説されています。音声レベルを均一にし、不要なノイズを取り除くことで、聞きやすく視聴者にストレスを与えない仕上がりにすることが基本とされています。BGMの扱い方についても触れられ、映像の盛り上げや雰囲気づくりに効果的な選び方が紹介されています。
さらに、キーフレームを用いた音量の細かな調整や、コンプレッサーを使った安定化処理など、より高度な編集方法も紹介されています。映像と音声を正確に同期させる方法や、エンディングのBGMの切り方といった細部にわたる配慮が、完成度の高さを決める重要なポイントになります。

人は目で映像を見ますが、心で物語を感じ取るのは音声からです。
音の調整は「伝わる映像」の最後の仕上げです。
chapter 13 編集 / テロップとタイトル
映像に言葉を添えるテロップやタイトルは、情報を補足するだけでなく印象を左右する大切な要素です。この章では、見やすい文字の大きさや色、表示時間の工夫など、視聴者が自然に読み取れるデザインの原則が紹介されています。特に、テロップを入れるタイミングは映像の流れと連動させることが重要で、数秒の差が理解度を変えると解説されています。
また、タイトルデザインについては「雛型」を利用した効率的な作成方法や、自分のブランドに合わせたオリジナルタイトルを作成する考え方が提示されています。視聴者に第一印象を与える部分だからこそ、フォントや色、動きの工夫で作品全体の質を底上げすることができます。

テロップは「情報を伝える字幕」ではなく「映像を補完する演出」です。
文字のデザインひとつで、作品の信頼性や世界観が大きく変わります。
chapter 14 編集 / カラーグレーディングの基本
映像の色は、視聴者に与える印象を大きく左右します。この章では、カラーグレーディングの基礎が体系的にまとめられています。色を正しく表示するための環境づくりやカラースペースの理解から始まり、カラーホイールを使ったプライマリー処理の実践方法が紹介されています。
さらに、特定の部分の色を調整する「セカンダリー処理」や、HSLカーブを駆使した高度な調整方法も解説されています。たとえば、空の青を強調して爽やかな印象を与えたり、肌の色を自然に整えることで好感度を高めるといった具体的な活用例が示されています。こうした処理は、映像に映画的な質感や独自の雰囲気を与えるために欠かせません。

色は「見せる情報」ではなく「感じさせる情報」です。
カラーグレーディングは視聴者の感情を無意識にコントロールする強力な手法です。
chapter 15 編集 / 納品先メディアと書き出し
編集が完了した映像は、最終的に配信や納品という形で世に出ます。この章では、完成動画をどのように書き出し、適切な形式で納品するかが解説されています。YouTubeのチャンネル開設から配信の基本、Blu-rayやDVDなど物理メディアでの納品方法まで幅広く網羅されています。
さらに、データ形式や解像度、コーデックの選択といった技術的なポイントが整理されており、用途に応じて最適な設定を選べるようになっています。Web配信用の軽量データから放映用の高画質データまで、目的ごとに適した書き出し方が理解できる構成になっています。実際の現場では、この最終工程がミスなく進められるかどうかが信頼に直結します。

動画は「制作した段階」ではまだ完成ではありません。
適切に書き出して配信・納品することで、初めて人に届くコンテンツとなるのです。
対象読者

この書籍は、立場や目的は違っても「動画を通じて情報をわかりやすく、魅力的に伝えたい」と考えている幅広い人々に向けて書かれています。
特に以下の人々に強くおすすめできる内容になっています。
- 動画制作初心者
- 企業の広報・マーケティング担当者
- 店舗/サービスの宣伝を担当する方
- 社内教育や研修コンテンツを作りたい担当者
- プロモーション動画の基礎を学びたい学生・クリエイター
では、それぞれの読者層にとってどのような価値があるのかを具体的に見ていきましょう。
動画制作初心者
動画をこれから学び始める人にとって、一番の課題は「何から手をつけていいのか分からない」という点です。本書は、企画から撮影、編集、公開までのワークフローを体系的に解説しているため、未経験者でも迷わず学びを進めることができます。しかも、実際の企業案件を題材にした企画書やナレーション原稿が例として示されており、抽象的な理論ではなく、現場で通用する知識を基礎から身につけられるのが大きな魅力です。
また、専門的なカメラワークや編集技法も、初心者の理解度に合わせて噛み砕かれて解説されています。専門用語には補足が添えられているため、初学者が置き去りにならず、順を追ってスキルを積み上げられる構成になっています。これにより、知識の断片をバラバラに覚えるのではなく、「動画制作」という全体像を頭に描きながら学習を進めることができます。

初心者にとって大切なのは「木を見る前に森を見る」ことです。
本書は動画制作の全体像を最初に示してくれるので、迷子にならずに基礎を固められるのです。
企業の広報・マーケティング担当者
企業において動画は、単なる映像作品ではなく、ブランドやサービスを戦略的に伝える武器です。本書では「5W2H+1T」といった企画のフレームワークを用いて、目的を明確にした動画制作の方法を解説しているため、広報担当者が直面する「誰に」「何を」「どう伝えるか」という課題に応えることができます。
さらに、外注に頼らず自社の人材や限られたリソースを活用して効果的な動画を作る方法が紹介されています。これにより、予算を抑えつつ成果を出すことが可能となり、マーケティング活動の効率化に直結します。戦略的思考と実務的ノウハウを両立して学べるのは、本書ならではの強みです。

広報における動画は「完成度」だけでなく「戦略性」が鍵を握ります。
本書は企画の段階から成果を見据えた設計を学べる点で、実務担当者に最適です。
店舗/サービスの宣伝を担当する方
店舗やサービスの宣伝では、短い時間で商品やサービスの魅力を伝える力が求められます。本書では、スマートフォンや身近な機材を用いた実践的な撮影方法が紹介されており、高価なカメラを持たなくても、印象的な映像を作る方法を学ぶことができます。特に「視聴者の目を引く構図の工夫」や「短尺動画の編集テクニック」など、現場で即活用できる知識が充実しています。
加えて、SNSプラットフォームに適した動画形式や投稿方法についても触れられているため、宣伝担当者は「ただ動画を作る」のではなく「見てもらえる」映像を発信することができます。動画とSNSの組み合わせは、集客やブランディングの成果を大きく左右するため、本書は現代の店舗運営に欠かせない実用書といえるでしょう。

店舗宣伝用の映像は“長さ”よりも“瞬発力”が命です。
本書は短時間で視聴者を惹きつける具体的な技術を示してくれる点で、宣伝担当者に強い味方となります。
社内教育や研修コンテンツを作りたい担当者
社内研修や教育コンテンツでは「分かりやすさ」と「正確さ」が最優先されます。本書は、マニュアル映像や研修動画を分かりやすく設計する方法を具体的に紹介しています。構成を工夫して学習者の集中力を維持する方法や、理解を深めるためのナレーション原稿の書き方など、教育的な効果を高める工夫が随所に盛り込まれています。
さらに、編集段階では情報を整理して伝えるためのテロップ活用や、場面転換の工夫など、実務に即したノウハウが豊富です。これにより、教育担当者が専門的な知識を持っていなくても、受講者にとって理解しやすく効果的な動画を制作することが可能になります。

教育用の動画は「どれだけ詳しく説明するか」ではなく「どれだけ分かりやすく伝えられるか」が鍵です。
本書はその視点を常に意識した解説を提供しています。
プロモーション動画の基礎を学びたい学生・クリエイター
将来映像業界を志す学生や、自主制作を通じて腕を磨きたいクリエイターにとっても、本書は大きな価値を持ちます。学校で学ぶ理論に加え、現場での具体的なワークフローを理解することで、より実務に近いスキルを身につけられます。これにより、卒業制作やポートフォリオ作品の質を高めることができます。
さらに、単に映像表現を学ぶだけではなく、目的やターゲットに応じた「伝わる動画」を作る視点が得られるのも特徴です。映像を自己表現の道具にとどめず、社会に向けて効果的に発信する力を養えるため、プロとして活動を始めるための第一歩となるでしょう。

学生や若手クリエイターにとって大切なのは“自己流に固まらず正しい基礎を築くこと”です。
本書はそのための確かな指針を与えてくれます。
本の感想・レビュー

全ての始まりに最適な一冊
最初にこの本を開いたとき、動画制作の全体像をどうやって理解したらいいのかまったくわかっていませんでした。これまでインターネットや動画サイトで断片的に情報を拾い集めていたのですが、それらは点でしかなく、つながりが見えなかったのです。本書は企画から編集、そして公開までを一つの流れとして解説しているため、バラバラだった知識が整理され、頭の中に一本の道筋が通るような感覚を得ました。
さらに、基礎の基礎から順を追って説明してくれるので「今、自分がどこにいるのか」を見失うことがありませんでした。動画制作を始めようとすると、どうしても目先の撮影や編集に気を取られがちですが、この本は最初から最後まで一貫したプロセスを示してくれます。特にプリプロダクションの段階にしっかりとページを割いている点は印象的で、基盤がいかに大切かを改めて実感しました。
読み進めるにつれ、制作を「特別な人だけができるもの」だと思っていた意識が少しずつ薄れ、誰でも段階を踏めば習得できるのだと勇気づけられました。基礎を学ぶための出発点として、まさに最適な一冊だと感じています。
“撮る”の怖さが消える
カメラを前にすると、どう動かせばいいのか、どの位置に立てばいいのかが分からず、撮影自体が怖く感じられることがありました。本書に出会って、その気持ちは大きく変わりました。カメラポジションやアングルの基本、さらには撮影サイズの違いが持つ意味が体系的に説明されているので、これまで感覚に頼っていた部分を理論で理解できるようになったのです。
また、固定ショットやパン、ズームといった撮影方法を段階的に紹介しているのも大きな助けになりました。単に操作方法を羅列するのではなく「この方法にはこういう演出効果がある」と背景を含めて教えてくれるので、ひとつひとつの動作に納得感を持ちながら練習できます。撮影を進める中で「どう撮れば良いのか分からない」という不安が少しずつ解消されていくのを実感しました。
今では、撮影を始めることに抵抗を感じなくなり、むしろ積極的に試してみたいという意欲が湧いています。以前のように「失敗したらどうしよう」と肩に力が入ることもなく、自然体でカメラに向き合えるようになったのは、この本のおかげです。
編集中の迷いを断つ指針
これまで動画編集に挑戦しても、途中で迷って手を止めてしまうことが何度もありました。その一番の理由は「どのようにつなげればいいのか分からない」という漠然とした不安でした。本書を読み進める中で、編集には映像文法やモンタージュといった明確な考え方があることを知り、その迷いが解消されていきました。
編集を「感覚」で行うのではなく、「目的に沿って組み立てる」という視点を持てるようになったのは大きな変化です。例えば、強調したい場面ではどのようなつなぎを使えばよいのか、観客に違和感なく場面を切り替えるにはどう工夫すればよいのか、本書は具体的な理論と実例を通して教えてくれます。読みながら「なるほど、だからこう編集するのか」と納得できる瞬間が何度もありました。
その結果、編集作業はただの試行錯誤ではなく、考えを形にする創造的な時間へと変わりました。これまでに感じていた迷いが、道しるべを得たことで整理され、作品を完成に導く力がついたと強く感じます。
理論だけでない説得力
これまで参考書を読んでも「実際に現場ではどう応用するのか」が見えず、学んだことが自分の中で宙ぶらりんになることがありました。この本は、その弱点を見事に補ってくれます。企業案内や店舗のPRといった実際の動画事例を用いて解説しているので、知識が現実と結びつき、理解が一層深まりました。
理論を学んでいる最中に「だからこういう映像が必要なんだ」と納得できる瞬間が何度もありました。単に正しい手順を暗記するのではなく、その背景にある意図や目的がはっきりと示されているので、自分でも応用できるという実感を持ちながら読み進められます。
こうした実例が随所に差し込まれていることで、読者は「教科書を読んでいる」という感覚よりも「経験者から直接学んでいる」ような感覚を持てるのです。頭で理解するだけでなく、現場のリアリティを伴った知識として自分の中に落とし込める点に、本書の強い説得力を感じました。
光と音で変わる仕上がり
動画を作るとき、どうしても映像そのものにばかり意識が集中してしまい、音や光の扱いを後回しにしてきました。けれど、この本を読んでから「映像を支えているのは目に見えない部分や背景の環境なんだ」と強く感じるようになりました。録音の基礎知識やマイクの種類、ライティングの基本構成などが体系的にまとまっているので、今まで知らなかった“裏方の力”の大きさに気づかされました。
特に印象的だったのは、硬い光と柔らかい光の違いを丁寧に解説していた部分です。同じ被写体でも光のあたり方ひとつで雰囲気がまったく変わることを理解し、「自分が意図する見え方を作り出す」ことが撮影の大事な技術だと知りました。また、録音に関しても環境音をどうコントロールするかや、インタビュー収録での注意点など、具体的な現場に直結する内容が多く、実務で役立つ情報が満載でした。
読み終えた後には「音と光が整って初めて映像は完成する」という言葉が腑に落ちました。これまでは気づかずに流していた部分が、作品の仕上がりを大きく左右する要素だったと理解できたのは、この本を手に取った大きな成果だと思います。
台本が動画を支える骨格
読む前は「台本は形式的なもの」と軽く考えていました。しかし本書を読んでみると、台本やナレーション原稿こそが動画全体の骨格を作るものであり、そこが曖昧では映像全体が崩れてしまうことを痛感しました。企画段階で決めた構成を具体的に落とし込む設計図として台本を活用することで、撮影の効率や完成度が格段に高まることが理解できました。
ナレーション原稿についても「分かりやすさ」「簡潔さ」「誤解を招かない表現」といった実践的な観点がまとめられていて、単なる読み上げの文章ではなく、映像を補強する重要な要素であることに気づかされました。また、画コンテの作成方法についても、映像を撮る前に視覚的に整理することの大切さが丁寧に書かれており、頭の中のイメージを形にするプロセスが明確になりました。
映像を作るうえで台本やコンテを省略してしまうことがどれほど危険か、そして逆にそれらをしっかり準備することがどれだけ安心感をもたらすかを体感できたのは大きな発見でした。この本は「映像はカメラを回す前から始まっている」ということを教えてくれたと思います。
予算が少なくてもプロ並みに
動画制作は高価な機材やソフトが必要だと思い込み、手を出しづらいと感じていました。しかしこの本は、限られた環境でも工夫次第で十分にクオリティを上げられることを示してくれました。高価なカメラを持っていなくても、手元の機材で撮影の基礎を理解すれば十分実践できるという説明に、肩の荷が下りたように感じました。
特にスマートフォンやコンパクトカメラを使った撮影の利点や注意点が整理されていたのは印象的でした。また、ライティングや録音に関しても、現場の環境を活かしながら整える方法が紹介されており、コストをかけなくても工夫ひとつで映像の質が大きく変わることが理解できました。
このアプローチは、これから動画を始めたい人にとって非常に現実的です。「予算がないから無理」と諦めるのではなく、「工夫すればできる」と前向きになれる一冊でした。自分の環境でできることを最大限に引き出す姿勢を学べたのは、大きな収穫です。
手を動かすきっかけになる
読み進めるうちに「自分も実際に作ってみたい」という気持ちがどんどん高まっていく本でした。説明が一方的ではなく、常に読者が実践に移せるような流れで構成されているため、知識が自然と行動へとつながっていきます。ページをめくるたびに「次はこれを試してみよう」と意欲が湧き、机上の勉強だけで終わらないのが魅力です。
特に、各章が一連のワークフローに沿って進んでいくので、途中で迷うことなくステップアップできるのも安心でした。企画から撮影、編集、公開までの道筋がはっきり示されていることで「今の自分がどこにいるのか」を把握しながら学べます。この構成が、自然に手を動かす気持ちを後押ししてくれるのです。
読み終えた頃には、頭の中にあった「動画を作ってみたい」という漠然とした思いが、「次はこれをやってみる」という具体的なアクションへと変わっていました。実践への一歩を踏み出す勇気を与えてくれるという点で、本書はただの参考書以上の存在だと感じます。
まとめ

この記事では『世界一わかりやすい動画制作の教科書』を通じて学べる内容を整理してきました。
最後に振り返りとして、以下の観点から本書の価値を見直してみましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれを掘り下げることで、読者が本書を手に取る意義や、その後の学習や実践にどのようにつなげられるかを明確にイメージできるはずです。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。
ワークフロー全体を体系的に理解できる
企画、撮影、編集、公開という一連の流れを段階ごとに整理して学べるため、読者は自分が制作のどの位置に立っているのかを常に把握できます。特に初心者にとって、全体像を掴むことはスキル習得の近道です。各ステップの役割や目的を理解しながら進めることで、学習の定着が自然と高まります。
実務で役立つ具体的なノウハウを習得できる
本書では理論だけでなく、実際に使われた企画書や台本といった具体的な事例が数多く紹介されています。さらにYouTube連動の解説動画が付属しているため、テキストで得た知識を視覚的に確認しながら学ぶことができます。これにより「知る」から「できる」への橋渡しがスムーズになり、学んだ直後から実際の制作に応用できるのです。
プロの発想法や判断基準を取り入れられる
動画の出来を左右するのは、単なる機材やソフトの操作ではなく、企画段階の構想力や演出の判断力です。本書は著者の豊富な経験に基づき、企画や構成に時間を惜しまない重要性を説きながら、初心者でも取り入れられる思考法を伝えています。そのため、動画制作を単なる作業ではなく「表現のプロセス」として捉えられるようになります。
自信を持って制作に取り組めるようになる
断片的な知識では「この方法で合っているのか」と不安を感じがちですが、本書を通して全体像と実務的な知識を得ることで、制作過程に一貫した自信が持てるようになります。その自信は作品の完成度を高めるだけでなく、依頼や案件を受ける際の説得力にもつながります。結果として、学びが自己満足に終わらず、他者に価値を届ける映像制作へと発展していきます。

動画制作において「部分のテクニック」よりも「全体の設計図」を理解することが圧倒的に重要です。
本書はその設計図を初心者に最適化した形で提示してくれるため、効率的かつ実践的な学びを実現できます。
読後の次のステップ
本書を一通り読み終えた段階で、知識を理解するだけにとどめるのは非常にもったいないことです。動画制作は、座学だけでは決して習得できない「実践型スキル」であり、学んだ内容を実際に手を動かして試してこそ真価が発揮されます。
ここからは、読後に踏み出すべき具体的なステップを紹介します。
step
1実際のプロジェクトに挑戦する
学んだ知識を身につけただけでは、スキルとして定着しません。小規模でも良いので、自分の身近なテーマを題材に企画から編集まで一連の流れを体験することが重要です。例えば、友人のイベント告知や、自分の趣味を紹介する映像を制作すれば、理論と現実のギャップを体感でき、応用力が磨かれます。
step
2専門ソフトの操作を深掘りする
基礎的な編集知識を身につけた後は、ソフトウェアごとの機能を探究する段階に移行します。DaVinci Resolveでのカラーグレーディングや、Adobe Premiere Proを使った高度な編集テクニックに触れることで、表現の幅が格段に広がります。単純なつなぎ編集から一歩進んで、映像に個性や演出意図を加える力を育むことができます。
step
3公開とフィードバックを積極的に活用する
完成した映像は、必ず発表の場に出すことを意識しましょう。YouTubeやSNSにアップロードすれば、視聴者からの反応を得られます。その意見は次回の制作に生かせる具体的な改善点となり、自分一人で学ぶ以上の成長を後押しします。公開を繰り返すことで、自分のスタイルや強みも明確になっていきます。

動画制作は“学習と実践の往復運動”によって確実にスキルが定着します。
本書で得た知識を止めずに動かすことで、初めてプロとしての視点や応用力が身につくのです。
総括
『世界一わかりやすい動画制作の教科書』は、単なる操作マニュアルやテクニック集ではなく、動画制作というプロセス全体を体系的に整理した実践的な一冊です。企画から撮影、編集、公開に至るまでの流れを段階的に解説しているため、読者は「部分的な知識」ではなく「全体像」を確実に把握できます。これは、動画制作を独学で学ぼうとする初心者にとって非常に大きな助けとなります。
本書が特に優れている点は、実際のビジネス現場で使われた企画書やナレーション原稿といった実例が豊富に紹介されていることです。単なる理論や抽象的なノウハウではなく、読者がすぐに実務へと落とし込める具体性を持っているため、「学んだことをそのまま実践できる」という即効性を備えています。さらに、YouTube動画と連動して学習を補完できる点も、理解を深める大きな支えとなっています。
また、著者自身の経験から語られる「企画や構成の重要性」や「表現の工夫」といった思考法は、動画制作を単なる技術習得ではなく「伝えるための創造的プロセス」として位置づけています。そのため、映像を扱うことに不慣れな人でも「なぜこのステップが必要なのか」を腑に落としながら学べるよう設計されています。結果として、読者はただ動画を作るだけでなく、目的を持って効果的に発信するという視点を自然に身につけることができます。

本書は、初心者が最初の一歩を踏み出すための道しるべであると同時に、経験者にとっても制作の基礎を再確認し、応用力を広げるためのリファレンスとなる存在です。
映像がビジネスや教育の場で欠かせない時代において、この一冊を手元に置くことは、確かな制作スキルを育み、自信を持って動画を活用するための大きな力になるでしょう。
動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)に関するおすすめ書籍

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本!人気ランキング
- 今すぐ使えるかんたん YouTube動画編集入門 [改訂新版]
- 1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術
- YouTube完全マニュアル[第4版]
- 伝わる!動画テロップのつくり方
- センスがUPする⤴ 動画編集の教科書 [カットつなぎ・構図・音・色・文字]
- 【超完全版】YouTube大全 6ヶ月でチャンネル登録者数を10万人にする方法
- 世界一わかりやすい動画制作の教科書

