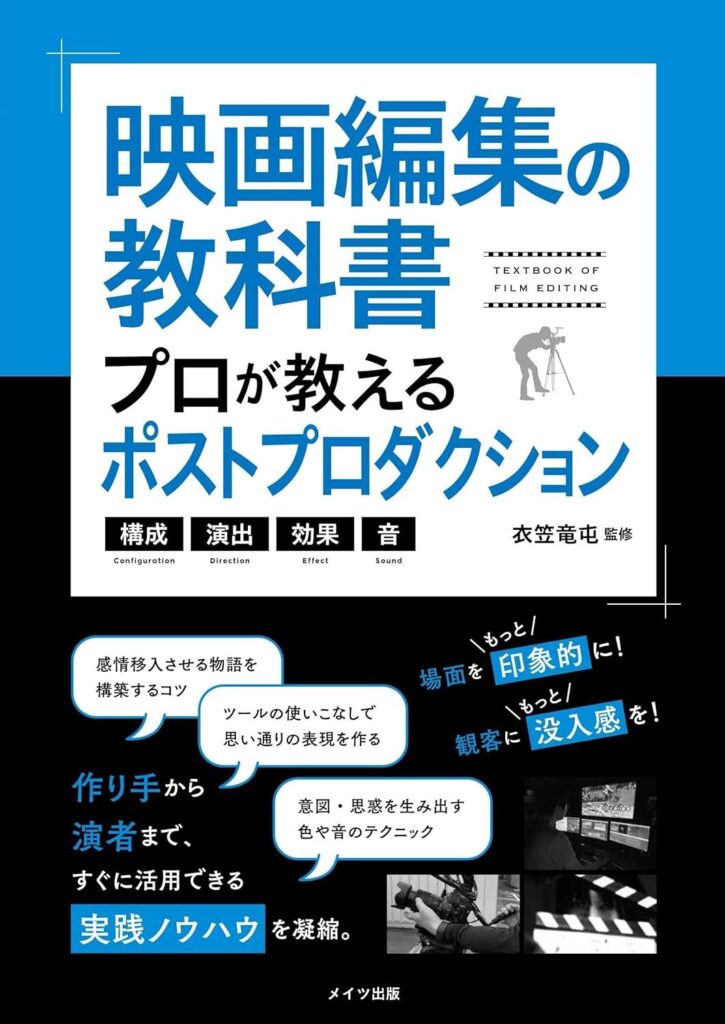
映画を観て「心を動かされた」と感じる瞬間、その裏側には必ず編集の力があります。
シーンの並べ方、音の使い方、色彩の調整――これらはすべて観客の無意識に働きかけ、物語への没入感を生み出す重要な要素です。

『映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音』は、映画編集の基本から実践的なノウハウまでを体系的にまとめた一冊。
単なる技術解説にとどまらず、「なぜ編集が物語を変えるのか」という本質的な問いにも答えてくれる内容になっています。
映像制作をこれから学ぶ初心者はもちろん、現場で経験を積むプロにとっても役立つ知識が詰まった本書。
あなたの作品を「ただの映像」から「心に残る映画」へと導いてくれる、頼れるガイドブックです。

合わせて読みたい記事
-

-
映像制作について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
映画やCM、YouTube動画など、映像は私たちの身近な日常に溢れています。 自分でも映像制作に挑戦してみたい、あるいはプロのスキルを磨きたいと思ったとき、頼りになるのが体系的に知識を得られる「本」で ...
続きを見る
書籍『映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音』の書評

本書は、映画編集をこれから学ぼうとする人だけでなく、現場経験を積んだ映像制作者にも役立つ一冊です。単なるマニュアルや操作手順書にとどまらず、編集の「理論」と「実践」を結びつけることを目的とし、映像作品を観客にどう届けるかという視点まで踏み込んで解説しています。
この書評では、以下の観点から本書の特徴を整理します。
- 著者:衣笠竜屯のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
これらを整理して読むことで、本書の立ち位置や意図、そしてなぜ映像制作者から支持を集めているのかが明確になります。
著者:衣笠竜屯のプロフィール
衣笠竜屯(きぬがさ りゅうとん、本名:衣笠寛之)は、兵庫県神戸市出身の映画作家です。彼が映像制作を始めたのはわずか16歳の頃。友人とともに8mmフィルムを回し、身の回りの出来事を映像作品として形にしていったのが原点でした。当時は今のようにスマートフォンや動画編集アプリがあるわけではなく、撮影から編集までアナログな手法で行わざるを得ませんでしたが、その経験が後の彼の「編集=映画の核」という信念につながっていきます。
1989年には自主映画仲間と共に「神戸活動写真倶楽部 港館」を設立。そこでは学生や社会人が自由に映画制作に取り組める環境を整え、上映会やワークショップを通じて多くの人々に「映画を作る楽しさ」を伝えてきました。この活動は、彼が教育者としての側面を強めるきっかけとなり、後の著作や指導にもつながっています。
映画作りにおける彼の活動領域は非常に広く、監督・編集・脚本・撮影・演出・俳優など、多彩な役割を担ってきました。これは裏を返せば「現場の全工程を体験している人物」であるということ。カメラを回す立場、演技をする立場、編集室で全体を見渡す立場、そのすべてを経験しているからこそ、映画を総合芸術として捉える深い視点を持っています。

本書の要約
『映画編集の教科書』は、映画制作における「編集」を核に据え、映像を完成へと導くための全体像を整理した一冊です。特徴的なのは、映画の物語構造と同じ「起承転結」に沿って構成されている点で、読者は自然な流れに従いながら知識を積み重ねることができます。そのため、初心者でも迷わず学習を進められるよう工夫されており、同時にプロフェッショナルにとっては作業工程を再確認する指針として機能する構成になっています。
内容は、基礎的な機材やソフトの知識から始まり、観客を物語に引き込むための編集技法、映像の色彩や文字による表現、そして音声処理や納品までを包括的にカバーしています。つまり、「編集とは何か」という根本的な問いかけから始まり、「観客に届ける完成品をどう作るか」という実務的な答えに至るまで、一貫して学べるのです。
本書の大きな魅力は、単なる理論解説にとどまらず、実際の編集現場で役立つ具体的なノウハウが随所に盛り込まれていることです。理論と実践の橋渡しがなされているため、読んだその日から自分の制作に取り入れられる内容となっています。また、著者自身の経験やコラムも収録されており、知識だけではなく「映画作りの現場感覚」を追体験できる構成も特徴的です。

本書の目的
著者が本書を通じて目指しているのは、単に編集ソフトの操作方法を伝えることではありません。編集を「映画作りの魔法」と表現するように、観客の心を動かす力を持つ技術として位置づけ、その魅力と本質を伝えることに重点を置いています。
この本を読むことで、同じ素材でも編集の仕方によってまったく違う印象を与えられることに気づかされます。例えば、カットの順序を入れ替えるだけでキャラクターの心情が変わって見えることや、間の取り方によって緊張感や安心感を演出できることなど、映像表現の可能性が広がっていきます。
また、著者は「意図を持って編集を選択する」ことの重要性を強調しています。どのようにカットをつなぐのか、どの場面で音を強調するのかといった判断はすべて観客に伝わるものであり、そこに制作者の意思が宿るのです。本書の目的は、その意思を持って映像を設計できる人材を育てることにあります。
さらに、ソフトやツールを単なる「操作対象」としてではなく、表現を可能にする「道具」として扱う視点を身につけさせることも重要な狙いです。これにより、読者は機材や技術に振り回されるのではなく、作品を表現するために必要な選択を自ら行えるようになります。

人気の理由と魅力
本書が高く評価されている理由のひとつは、初心者でも理解しやすい構成にあります。映画編集というと専門的で難しいイメージがありますが、本書は基礎的な知識を土台にしながら、段階を踏んで理解を深められるように設計されています。動画ファイル形式やソフトの基本操作といった初歩的な部分から始まるため、入門者でも安心して学び進められます。
一方で、本書にはプロが現場で使える具体的なノウハウも豊富に盛り込まれています。時間を操って物語を構築する手法や、観客の錯覚を利用して感情移入を誘う技術、さらには“じらし”や“間”の演出といった心理的効果を引き出す方法まで、実践的なテクニックが数多く解説されています。これにより、学んだその日から編集作業に活かせる知識が得られます。
さらに、映像だけでなく音や文字にまで踏み込んでいる点も大きな魅力です。グレーディングによる映像の色彩調整や、テロップ・字幕による情報伝達、そして音声のバランス調整やBGMの配置までを扱うことで、映画全体を統合的に仕上げる力を養うことができます。ここまで包括的にポストプロダクションをカバーする本は珍しく、読者にとって大きな価値があります。
また、著者が長年培ってきた実務経験に基づいて書かれているため、単なる理論書ではなくリアルな現場感覚が伝わってくるのも特徴です。自主映画から劇場公開作品までを手掛け、さらに教育の場で学生や社会人に映画制作を指導してきた経験が、解説の一つひとつに裏打ちされています。
こうした背景により、この本は「初心者にとっては学びの地図」「経験者にとっては基本に立ち返る指針」として、多くの映像制作者に支持され続けています。

本の内容(目次)

『映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音』は、映画の編集工程を段階的に学べるように章立てされています。それぞれの章は「起承転結」の流れで構成されており、映画の物語と同じように自然に理解を深められる仕組みです。
大きく分けると、以下の4つの章があります。
- CHAPTER I|最強の道具を揃えよう [起]
- CHAPTER II|物語を彩る編集テクニック [承]
- CHAPTER III|色と文字で世界観を操る [転]
- CHAPTER IV|音の調整から納品まで [結]
このように章ごとに役割が明確で、学習のステップを踏みながら知識と技術を深めていける構成になっています。
CHAPTER I|最強の道具を揃えよう[起]
映画編集を始めるうえで最初に直面するのは「道具選び」です。この章では、フィルム時代のパラパラ漫画の例を出しながら編集の基本的な概念を確認しつつ、現代におけるデジタル編集の基盤を築くために必要な知識が整理されています。単なるコンピューター作業ではなく、作品を作るための環境を整えることが編集の第一歩であると強調されています。
続いて、作業環境をどう整えるかについても詳しく解説されています。例えば、映像の再生と編集は同じ環境ではなく、本番での上映や配信を想定した設定が必要であること、入力デバイスを導入することで作業の効率が飛躍的に高まることなどが具体例を交えて紹介されています。また、編集ソフトのインターフェースを理解することは、表現の幅を広げるための第一歩でもあり、操作に慣れることの重要性が強調されています。
さらに、初心者が混乱しやすい動画ファイルの形式やコーデックの違いについても触れられています。これにより、後の作業で不具合やトラブルを避ける基礎知識が身につきます。適切な環境設定は、作品のクオリティを左右する重要な要素であることが理解できる構成になっています。

編集環境は“作業の舞台”です。
舞台装置が不安定だと、どれほど優れた演出も観客に伝わりません。
CHAPTER II|物語を彩る編集テクニック[承]
この章では、映画を「物語」として成立させるための編集技法が中心に取り上げられています。特に強調されているのは、映像の組み合わせによって観客に新しい意味を与える「クレショフ効果」です。ある人物の表情と異なる映像を組み合わせることで、観客がその表情に勝手に意味を見出す心理効果は、映画編集の根幹にある技術といえます。
また、映像のテンポや間を調整することで、観客の心理的な時間感覚を操る方法も解説されています。シーンを長く見せるか短く見せるかによって、緊張感や没入感が変化し、同じ映像でも伝わる印象はまったく異なります。加えて、ショットの順番や省略の使い方、さらにはリバースショットやイマジナリーラインといった基本技法も、具体的な活用例を交えて紹介されています。
さらにこの章では、音の役割についても大きな比重が置かれています。効果音や環境音は映像のリアリティを補強し、BGMは観客の感情を操作する「隠れた演出装置」として機能します。視覚だけでなく聴覚を組み合わせた編集こそが、映画に没入感をもたらす鍵であることが強調されています。

編集は“物語を作る作業”そのものです。
順番や間の操作ひとつで、観客の感情曲線は劇的に変わります。
CHAPTER III|色と文字で世界観を操る[転]
映画の世界観を視覚的に形づくる重要な要素が「色」と「文字」です。この章では、グレーディングやフェード、オーバーラップといった基礎的な手法から、作品全体のトーンを決定づける「ルック」の作り方までが解説されています。映像をただ記録するのではなく、色彩によって雰囲気や感情を強調するための技術が丁寧に説明されています。
加えて、映像の明るさや色調を正確に確認するためのビデオスコープの活用方法や、プライマリ/セカンダリ調整による細やかな色彩のコントロールも紹介されています。これにより、カットごとの色のズレを防ぎ、全体として統一感のある画面を作り出すことができます。特に「色温度」の調整は、撮影環境が異なる素材を組み合わせる際に欠かせないポイントとして強調されています。
さらに、文字の扱いについても深掘りされています。テロップや字幕は単なる情報伝達ではなく、作品の雰囲気やテンポに影響を与える演出要素として機能します。タイトルやクレジットの配置やデザインによっても、観客に与える印象は大きく変わることが示されています。

色と文字は“映像の言語”です。
言葉を発しなくても、画面のトーンと文字の配置だけで世界観を雄弁に語れます。
CHAPTER IV|音の調整から納品まで[結]
映画を完成させる最終段階で大きな役割を果たすのが「音」です。この章では、アフレコの収録から音声のタイミング合わせまで、具体的な作業手順が紹介されています。映像と音のズレは観客の没入感を大きく損なうため、細やかな調整が必要であることが強調されています。
次に、音声の仕上げ作業であるMA(Multi Audio)について解説されます。ここでは、セリフや環境音、BGMなどの音量バランスを整え、全体として自然に聞こえるようにする技術が取り上げられています。イコライザーやリバーブといったエフェクトの使い方、ノイズ除去の方法なども紹介され、音質を高めるための実践的な知識が得られます。
最後に、レンダリングから納品までの工程が説明されています。完成パッケージ(完パケ)の確認や、観客を引き込むための予告編の制作方法も含まれており、作品を「仕上げる」だけでなく「届ける」段階までカバーしているのが特徴です。これにより、ポストプロダクション全体の流れを俯瞰できる内容となっています。

音は“見えない映像”です。
目に映らないからこそ、観客の無意識に作用し、没入感を支える鍵となります。
対象読者

本書は、映画編集という専門的な領域を幅広い立場の人が理解し、実践できるように構成されています。映画を学び始めた人から、現場の第一線で活動しているプロフェッショナルまで、それぞれの段階に応じた学びを得られるのが大きな特徴です。
ここでは、特に想定されている読者層を挙げ、それぞれがどのような形で本書を活用できるかを解説していきます。
- 映像・映画制作を学び始めた初心者
- 映画・映像制作を学ぶ学生
- 自分で動画制作をするクリエイター(YouTuber/Vlog等含む)
- 演者や俳優で編集の意図を知りたい人
- 基礎を見直したいプロの編集者やポストプロダクション関係者
それぞれの立場でどのように本書が役立つのかを詳しく見ていきましょう。
映像・映画制作を学び始めた初心者
これから映像制作の世界に足を踏み入れようとする人にとって、本書は格好のスタート地点となります。編集は難解に見えますが、本書では「パラパラ漫画のように映像をつなぐ」という基本的な考え方から出発しているため、初心者でも理解しやすいのが特徴です。複雑な専門用語も日常的な比喩を交えて解説されており、最初にぶつかりやすい「入り口の壁」を取り払ってくれます。
また、初めて挑戦する人が特につまずきやすいのが、パソコン環境や編集ソフトの設定です。本書は、適切な機材の選び方や動画ファイルの扱い方を一から説明しているので、どんな機材を揃えれば良いのか、どの形式で保存すればトラブルが少ないのかといった基本的な疑問が解決します。これにより、環境づくりに不安を感じる初心者でも安心して学習を進められるのです。
さらに、作品を編集する上で必要となる「観客にどう見せるか」という意識を早い段階から身につけられる点も大きな魅力です。単に技術を習得するだけではなく、観客の感情に働きかける“編集の本質”を掴むことで、基礎を超えた応用への道も自然と開けていきます。

映画・映像制作を学ぶ学生
専門学校や大学で映画を学んでいる学生にとっては、授業で学んだ理論を実際の現場でどう活かすかが大きな課題です。本書は、そうした学びの実践的な橋渡しをしてくれます。例えば、時間を操作する技術や「クレショフ効果」といった理論を、具体的にどのような編集で実現できるのかを実例を交えて説明しており、座学で得た知識を作品制作に直結させることができます。
また、学生の段階では短編作品や課題制作に取り組む機会が多くあります。本書は短い作品であっても効果的に見せるための「テンポ」や「間」の作り方、効果音や音楽を使った演出方法を学べるため、提出作品の完成度を飛躍的に高められる実践的な参考書となります。
さらに、制作の過程で重要となるデータ管理やバックアップの方法、納品の形式といった現場的な知識も含まれているため、将来的にプロの現場に立つことを見据えた準備ができます。これにより、学生はただ作品を作るだけでなく、業界標準の知識を身につけながら学びを深められるのです。

自分で動画制作をするクリエイター(YouTuber/Vlog等含む)
YouTuberやVloggerなど、個人で映像を発信する人にとっても、本書は強力な味方となります。インターネット上で多くの動画が公開される現代において、他と差別化するには編集力が重要です。本書は映像を単に「つなぐ」だけでなく、観客を引き込むためのテンポや音の使い方、色調の工夫といった具体的な技術を提供してくれます。
個人制作の場合、限られた機材や環境で作業することが多いですが、本書は「自分に合った編集環境の整え方」や「効率的な作業の工夫」にも触れているため、プロのような環境を整えるのが難しいクリエイターにとって実用的です。また、環境音やBGMの選び方についても解説されており、動画の印象を大きく変える“音の演出力”を磨くことができます。
さらに、動画発信において重要な「視聴者が最後まで見たくなる編集」を実現するためのヒントが随所に含まれています。これは、エンタメ性やストーリーテリングを重視するYouTuberやVloggerにとって特に価値の高いポイントです。

演者や俳優で編集の意図を知りたい人
俳優や演者にとって編集の知識を持つことは、自身の演技の価値を最大化するために重要です。本書はリバースショットやリアクションカットといった編集技法がどのように観客の感情に影響するかを解説しており、演者が自分の演技の「見え方」を理解する助けとなります。
この知識を持つことで、撮影現場での演技に新たな視点が加わります。カメラの向こうでどのように編集されるかを意識すれば、単なる演技ではなく「編集後の完成形」を想定した表現が可能になります。結果として観客に強い印象を与える演技へとつながるのです。
さらに、監督や編集者とのコミュニケーションにおいても、編集の意図を理解している演者は信頼されやすくなります。共同作業の中で役割をより深く果たせる点で、演者にとって本書を学ぶことは大きな武器となるでしょう。

演者が編集を学ぶことは“演技の幅を広げる最短ルート”。
映像の完成形を意識した演技ができるのは強みになります。
基礎を見直したいプロの編集者やポストプロダクション関係者
すでに編集の現場で活躍しているプロにとっても、本書は基礎を再確認しつつ新しい視点を得られる貴重な資料です。長く仕事をしていると、日常的に行っている技術を「当たり前」として見過ごしてしまいがちですが、本書を通じて改めて基礎に立ち返ることで、自分のスキルをより精度の高いものに磨き直すことができます。
また、最新のデジタル編集環境やAIの導入に関するトピックも盛り込まれており、常に進化を続ける映像業界の動きを把握できる点も魅力です。新しい技術を取り入れる際の考え方や注意点を学べるため、現場の効率化や作品の質の向上につなげることができます。
さらに、制作全体のワークフローを意識した解説がなされているため、編集作業に留まらず、チーム全体での制作フロー改善にも役立ちます。これはプロジェクト全体を俯瞰して動く立場の人にとって特に有用です。

本の感想・レビュー

テクニカルな基礎解説の分かりやすさ
この本を開いてまず驚いたのは、基本的な解説の平易さでした。専門書というとどうしても固い文章で専門用語が並び、初心者には近寄りがたい印象があります。しかし本書では「編集の基本はパラパラ漫画」といったように、誰もがイメージしやすい比喩を交えて解説されており、読んでいて自然と納得できる構成になっていました。
さらに、機材やソフトの仕組みなど一見すると難しそうな部分も、基礎から順序立てて説明されているため、知識ゼロでも無理なく読み進められます。特に動画ファイルの設定やインターフェースの仕組みなど、普段なんとなく使っていたものの背景にある理屈が理解できたのは大きな収穫でした。
読み進めるうちに「基礎を理解することが、結果的に応用力につながる」ということが自然と実感できました。入門書でありながらプロの現場にも通じる知識を盛り込んでいる点は、初心者にとって非常に心強いと感じました。
構成・演出の理論と実践のバランス
本書を読んで印象に残ったのは、理論的な部分と実践的な部分の行き来がとてもスムーズだったことです。映像編集の世界では「理論はわかるけど実際の現場でどう生かすのか」が壁になりやすいですが、本書ではその橋渡しが見事にされていました。
構成や演出の理論についても、抽象的な話で終わらず、実際に映像をつなぐ際にどのような工夫をするのか、具体的な解説が続きます。そのため、読みながら「これは実際の編集作業でこう応用できそうだ」と自然に想像できました。
学問的な知識を一方的に押し付けるのではなく、すぐに手を動かしたくなるように導いてくれる点が好印象でした。理論と実践の両輪がかみ合うことで、学びが「知って終わり」にならず、「身につく学習」になっていると感じます。
色彩調整やグレーディングの具体性
色彩に関する章はとても丁寧で、映像の印象を左右する要素としての「色」の重要性を改めて理解できました。単に美しく見せるためではなく、作品全体の世界観や感情のトーンを決定づけるための手法として解説されており、映像に対する見方が大きく変わりました。
グレーディングや色調整についても、難しい専門用語をそのまま使うのではなく、実際に編集画面を操作するような流れで説明されています。そのため、読むだけでまるで自分が作業しているかのような臨場感がありました。ビデオスコープの使い方や色温度の調整など、普段は曖昧にしていた部分が明確に理解できたのは非常にありがたいです。
この章を読み終えるころには、色の選び方ひとつで観客に与える印象が変わることを強く意識するようになりました。映像編集をするうえで「色を扱うこと」は避けられないテーマだと感じ、本書で得た知識を実際の制作に反映したくなりました。
音・効果音・BGM 使いこなしの章の強さ
音に関する解説がここまで細かく書かれていることに驚きました。映像作品における音は、映像に比べて軽視されがちですが、実際には感情や没入感を大きく左右する重要な要素です。本書では、その重要性を具体的な方法とともに示してくれていました。
特に印象的だったのは、環境音や効果音をどう配置するかでシーンの意味合いが変わるという点です。音楽だけでなく「音の間」をどう作るかという視点も紹介されており、読みながら「これは映像表現の奥深さそのものだ」と感じました。
読み進めるうちに、音を単なる付属的な要素として扱うのではなく、物語を語るもう一つの言語として意識できるようになりました。この気づきは、今後の映像制作において大きな財産になると思います。
演出効果(間・テンポ・じらしなど)の引き込み力
読み進めていると、映像のリズムや呼吸をどう作るかという点に深く踏み込んでいることに気づきました。特に「間」や「テンポ」、さらに「じらし」といった概念が、単なる映像の並べ替えではなく、観客を物語に引き込む強力な武器になることが丁寧に解説されています。これを理解した瞬間、編集そのものがまるで演技の一部であるかのように思えました。
印象的だったのは、映像を切る位置やその前後の繋ぎ方によって、同じ素材が全く異なる印象を与えるという点です。観客が自然に次を見たくなる仕掛けをどう作るか、その工夫がいかに重要であるかが具体的に示されていて、読みながら自分の中で映像の見え方が変わっていきました。
映像編集を「見せ方の調整」程度に捉えていた以前の考えは、この章を読んで大きく覆されました。演出効果を自在に操ることこそが編集者の腕の見せ所であり、それを学べるのはこの本の大きな価値だと実感しました。
読み物としての面白さ・コラムの味わい
専門書でありながら、読み物としての楽しさがあるのも本書の特徴でした。各章に差し込まれたコラムや体験談は、編集の現場に立ち会っているような臨場感を持たせてくれます。特にフィルム時代からのエピソードやAIと映画編集の未来に関する話は、堅い技術書の合間に息抜きとしても、知的刺激としても心地よいものでした。
こうしたコラムは、単に知識を補足するだけではなく、編集という仕事が持つ文化的・歴史的な広がりを感じさせてくれます。読むたびに「編集」という言葉の奥深さを再認識し、単なる技術にとどまらない魅力を味わうことができました。
最後まで退屈せず読み進められたのは、このような人間味のあるエピソードが適度に挟まれていたからだと思います。専門的でありながら、どこか親しみやすさを持たせる工夫が随所に感じられる一冊でした。
写真・図・実例の使い方・ビジュアルの効果
解説を補う写真や図の存在は、この本の理解を格段に深めてくれました。文字だけで説明されると難しく感じる部分も、図解や画面の例を見ながら読むと一気に理解が進みます。特に色調整やショットのつなぎ方の章では、視覚的な説明が非常に効果的でした。
写真や図は装飾として使われているのではなく、内容そのものを支える役割を果たしています。そのため、文章とビジュアルを行き来しながら読むことで、知識が立体的に頭に入ってきます。この構成は、映像というビジュアル表現を扱う分野だからこそ説得力がありました。
実例を伴った解説を通じて、読んでいるうちに「自分も同じようにできそうだ」と自然に感じられるのは大きな魅力です。図や写真が理解の助けになるだけでなく、読者のモチベーションを高める役割を果たしていると思いました。
この本を読んだからできそう・試したくなる実践性
読み終えて最も強く感じたのは、「自分でもやってみたい」という気持ちが湧いてくることでした。理論を学ぶだけでなく、実際の制作に直結する具体的なノウハウが散りばめられているため、手を動かしたくなる衝動に駆られます。
編集の流れやツールの扱い方が丁寧に解説されているので、学んだことをすぐに試せる実践性があります。作業の一つひとつが具体的にイメージできるため、読者は「読む」から「やってみる」へ自然に移行できるようになっています。
この実践性こそが本書の大きな魅力だと感じました。単なる座学では終わらず、学びを自分の映像制作に取り込んでいける内容だからこそ、読者にとって価値の高い一冊になっているのだと思います。
まとめ

ここまで本書の特徴や魅力を見てきましたが、最後に整理しておきましょう。
今回のまとめでは、以下の3つの観点から振り返ります。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの視点を通じて、本書がどのように映像編集の理解を深め、読者自身の制作活動を力強く支えてくれるのかが見えてきます。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的なメリットを整理してみましょう。
映像編集の基礎を体系的に習得できる
初心者がつまずきやすい「道具選び」や「編集環境の構築」といった土台の部分から解説されているため、初めて映像編集に挑戦する人でも全体像を理解しながら学べます。単発的なテクニックに偏らず、編集の仕組みや流れを通して学ぶことで、後々の応用力にもつながります。
物語を魅力的に見せる具体的な技法がわかる
映像作品の魅力は、撮影した素材をどう組み合わせるかによって大きく変わります。本書では「時間の操り方」や「テンポの調整」など、観客を引き込む物語づくりの手法を実例とともに紹介。単にカットをつなぐのではなく、観客の心理を読み解きながら演出を組み立てるスキルが身につきます。
色彩と音響を駆使した表現力が広がる
映像の印象を決定づけるのは、カメラに収めた映像そのものだけではありません。色調の調整やBGMの挿入、環境音の使い方など、作品の空気感を作り出す要素が豊富に解説されています。これにより「ただの映像」から「心に残る表現」へと進化させる力を養うことができます。
実務に直結するノウハウを学べる
単なる学術的な理論ではなく、現場で役立つ実務的なノウハウも数多く盛り込まれています。ファイル管理や納品形式の確認、さらには予告編制作までを網羅しているため、学んだ知識をすぐに自分の作品や仕事に活かすことができます。

編集を学ぶことは、映像を「素材」から「作品」へと昇華させる第一歩です。
本書はその道を迷わず進むための地図の役割を果たします。
読後の次のステップ
本書を読み終えた後は、知識を頭に留めておくだけでなく、実際に手を動かして学んだことを体験へと落とし込むことが大切です。
ここからは、読者が次に進むための具体的なステップを紹介します。
step
1小さな作品で実践を始める
まずは短い映像や自主制作の作品から取り組むことをおすすめします。本書で得た知識を使って実際に編集を試すことで、文字情報だったノウハウが実感を伴ったスキルへと変わっていきます。失敗を恐れずに繰り返すことが、応用力を育てる第一歩です。
step
2他者からのフィードバックを得る
完成した作品は、自分だけで確認するのではなく、周囲の人に見てもらいましょう。観客としての率直な意見は、制作者が気づかない改善点を浮き彫りにしてくれます。批評を受け入れることで、自分の編集の癖や強みを客観的に理解できるようになります。
step
3プロの作品を分析する
さらにステップアップを目指すなら、映画やドラマなどの既存作品を「観客」としてではなく「編集者の視点」で観察することが重要です。どの場面でカットを切り替えているのか、音楽や効果音をどのように重ねているのかを分析することで、プロの編集技術を自分の学びに取り入れることができます。

学んだ知識を現場で使い、客観的な意見を取り入れ、さらに優れた作品を研究する。
このサイクルを回すことが、映画編集のスキルを確実に高める最短ルートです。
総括
『映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音』は、映画や映像制作に関わるすべての人に向けて、編集という工程の本質と実践的な技術を伝える一冊です。単なるマニュアル本ではなく、映像表現の根幹にある「観客の心を動かす仕組み」を明確に解説している点が大きな魅力となっています。
読者はこの本を通じて、編集が単なる作業ではなく、映画全体の印象を決定づける「演出の要」であることを理解できるでしょう。さらに、具体的なツールの使い方や環境構築の方法から、色や音を駆使した高度な表現技法まで、段階的に学べる構成が初心者にもプロにも適しています。
また、本書は実践に直結する知識を惜しみなく提供しているため、読んだその日から実際の映像制作に取り入れられる内容が豊富です。理論と実践の両輪が整っているからこそ、読み終えた後に「すぐ試してみたい」と思える力を持っています。

この本は映像制作を志す人にとってのガイドブックであると同時に、創作活動に迷ったときの道しるべにもなり得ます。
作品をより印象的に仕上げたい、観客に深い没入感を与えたいと願う全てのクリエイターに、自信を持って勧められる一冊です。
映像制作に関するおすすめ書籍

映像制作について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 映像制作について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 映像クリエイターのための完全独学マニュアル
- 映像制作モダンベーシック教本
- 映画制作の教科書 プロが教える60のコツ~企画・撮影・編集・上映~
- マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術
- マスターショット2 【ダイアローグ編】
- filmmaker's eye 第2版
- 映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識
- 図解入門よくわかる最新映像サウンドデザインの基本
- 映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ 心得・法則・アイデア・分析
- 映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音

