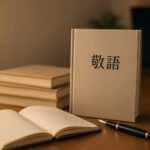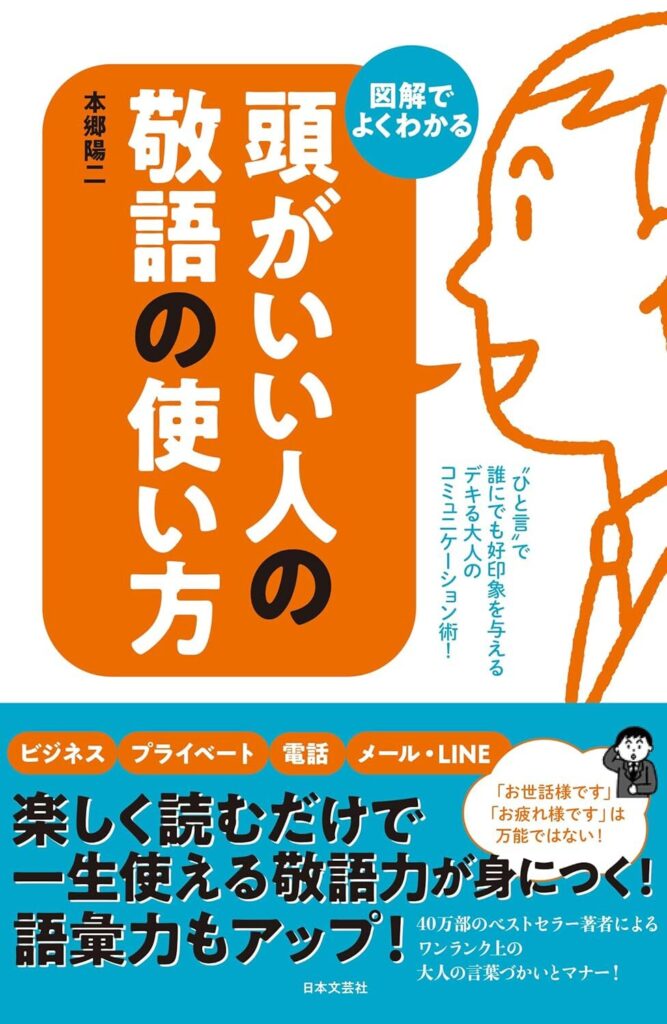
社会人としての第一印象を決める大きな要素は、外見や仕事の成果だけではありません。
むしろ、日々の会話やちょっとしたやり取りの中で自然に使う「ことばづかい」が、相手に安心感や信頼感を与える決め手となります。
とりわけ日本語の敬語は、相手への敬意を表すだけでなく、自分自身の品格や知性を映し出す鏡のような存在です。

しかし実際には、「ご苦労様でした」「とんでもございません」など、気づかぬうちに誤った表現を使ってしまい、知らず知らずのうちに相手を不快にさせているケースも少なくありません。
本書『頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる』は、そんな“うっかり間違い”を正し、誰でも自信を持って使える敬語の実践的なルールを、図解と豊富な事例でわかりやすく解説しています。

合わせて読みたい記事
-

-
敬語について学べるおすすめの本 13選!人気ランキング【2026年】
上司や取引先へのメール、電話、面接の受け答え――ふと「この敬語、合ってる?」と不安になる瞬間は誰にでもあります。 正しい言い回しが身につけば、伝わり方も印象も一気に変わるはず。 1位 敬語の使い方が面 ...
続きを見る
書籍『頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる』の書評

この本は、単なる敬語マニュアル本ではありません。読者が「なぜその言葉が正しいのか」「どうすれば相手により良い印象を与えられるのか」を理解し、実際の会話で自信を持って使えるように構成されています。
以下の観点から読み解くことで、本書の全体像を深くつかむことができます。
- 著者:本郷陽二のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれの要素を順に確認していきましょう。
著者:本郷陽二のプロフィール
本郷陽二氏は、1946年東京都に生まれ、早稲田大学文学部仏文学科を卒業しました。その後、光文社に入社し、編集者としてキャリアを積みます。特に「カッパ・ブックス」編集部では、社会現象ともなった塩月弥栄子の『冠婚葬祭入門』を担当し、冠婚葬祭マナーや日本語表現の分野に深い造詣を培いました。
編集者としての豊富な経験を経て独立後は、編集プロダクション「株式会社幸運社」を設立。ビジネス会話、話し方、人間関係、雑学、スポーツ人物伝など多岐にわたるジャンルで執筆・編集を行い、一般読者に「わかりやすく、すぐに使える知識」を届けることをライフワークとしています。
敬語に関しては『頭がいい人の敬語の使い方』をはじめとする著書が広く支持され、わかりやすさと実用性で高い評価を受けています。特筆すべきは、単なるルールの暗記にとどまらず「人間関係を円滑にする会話術」として敬語を位置づけている点です。

敬語を「語学」ではなく「コミュニケーション設計」と捉える視点は、編集者出身ならでは。
書籍の構成にも「読者がすぐに実践できる導線設計」が反映されています。
本書の要約
『頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる』は、40万部を超えるベストセラーとなった従来版を、さらにビジュアル的にわかりやすく再編集した新版です。大きな特徴は「誤った言い方」「正しい表現」「より印象を高める言葉づかい」という三段階のステップで紹介されていることです。これにより、単に正誤を知るだけではなく、状況に応じてワンランク上の対応ができるようになります。
冒頭では、敬語の基礎を整理することで「なぜ正しい表現が必要なのか」を理解させ、その上で具体的な場面別のケースに入っていきます。第1章では「ご苦労様でした」「役不足」など、日常で誰もが一度は誤って使ってしまう表現を掘り下げます。続く第2章では社内外での対応に焦点を当て、上司への受け答えや取引先とのやり取りを網羅し、職場で即実践できる内容を提供します。さらに第3章では、社会人として避けて通れない電話対応を徹底的に扱い、特にクレーム処理や誤接続の場面など緊張しやすい状況における言葉づかいを解説しています。そして第4章では、日常生活や冠婚葬祭の場にまで踏み込み、家族や親戚、友人との交流の中で敬語をどのように選ぶかを紹介しています。
また、各章の合間には「ビジネスメール」「ビジネスチャット」「クッション言葉」といった現代的なテーマを扱ったコラムが挿入されており、テキストだけでは見落としがちな実務的な要点を補強しているのも大きな魅力です。紙面はイラストや図解を多用し、文章だけでは理解しづらいニュアンスを直感的に捉えられるように設計されています。

本書の目的
この本の狙いは、敬語を単なるルールとして学ぶことではありません。著者が強調しているのは、敬語とは「相手への敬意を表現するツール」であるという視点です。つまり、敬語は文法的に正しいかどうかを競うものではなく、人間関係を円滑にし、信頼を築くために使われるべきものだという考え方に立っています。
本書は文法的な細部に深入りせず、むしろ実例を豊富に挙げることで、読者が「この場面ではこう言えば良い」と自然に理解できるように工夫されています。さらに、「正しいとは言えないが広く使われている」表現についてもあえて取り上げています。これは現実の会話では教科書的な正解だけでは不十分であり、実際のコミュニケーションの場で必要とされる“柔軟性”を養う意図があります。
敬語に苦手意識を持つ人は多く、その多くが「間違えたら恥ずかしい」「正しい言い方がわからない」という不安にとらわれています。本書の目的は、そうした不安を取り除き、読者に「自信を持って言葉を選べる力」を与えることにあります。

敬語は規範を守るだけでなく、相手に安心感や好感を与える心理的効果があります。
本書はその心理的側面に着目し、実用性を高めています。
人気の理由と魅力
本書が長く愛され、多くの人から支持を集めるのには明確な理由があります。まず第一に、従来版からさらに改良された図解とレイアウトにより、難解に感じやすい敬語のルールが直感的に理解できる点です。文字だけの説明ではどうしても抽象的になりがちですが、図やイラストが加わることで、頭にすっと入りやすくなっています。
次に、誤用例を明確に示しながら、その正しい使い方を丁寧に解説している点も評価されています。読者は「これが間違いだったのか」と気づきを得た上で、「こう言い換えれば良いのか」と実践的な知識をすぐに取り入れることができます。この“気づきから学びへ”の流れが自然に組み込まれていることで、読後には言葉遣いへの意識が大きく変わります。
さらに、扱う範囲が広いのも本書の大きな強みです。社内での会話や上司とのやり取りだけでなく、取引先との商談、電話対応、さらには結婚式や葬儀といった冠婚葬祭の場面までを網羅しています。社会生活で直面するあらゆるシーンを想定しているため、どんな立場の人でも「自分に役立つ部分」が見つかるのです。
また、現代的なテーマとしてビジネスチャットやメール対応についてのアドバイスも盛り込まれており、時代の変化に即したアップデートがされている点も支持を集めています。これは、従来のマナー本にありがちな「古臭さ」を排除し、現在の働き方にフィットする実用書としての価値を高めています。
こうした特徴により、本書は新入社員にとっては入門書として、また中堅やベテランにとっては知識の再確認やアップデート用の参考書として、幅広い層に使われています。

本の内容(目次)

この書籍は、大きく4つの章に分けられており、社会人が直面するさまざまな場面を想定しながら敬語の正しい使い方を学べるように構成されています。各章では、具体的な失敗例や改善策、さらに実践に役立つコツが豊富に解説されているのが特徴です。
章立ては次のとおりです。
- 第1章 気づかずに使っているかも!? 間違い敬語
- 第2章 ビジネスシーンですぐに使える敬語
- 第3章 電話対応で役立つ敬語の使い方
- 第4章 日常会話での上手な敬語の使い方
それでは、順に詳しく内容を見ていきましょう。
第1章 気づかずに使っているかも!? 間違い敬語
この章では、普段何気なく使っている表現の中に潜む誤用を取り上げています。例えば、上司に対して「ご苦労様でした」と伝えることは、一見ねぎらいの言葉に聞こえますが、実際には目上の人に使うのは失礼とされています。他にも「役不足」という言葉が「自分の力が足りない」という意味で誤用されやすいことなど、典型的な間違いが具体例とともに解説されています。
さらに、来客や訪問時の応対でも誤用が目立ちます。「○○様が見えられました」と言うと尊敬語が二重に重なり、不自然さが生じますし、「お待ちしてください」といった言い回しは相手への配慮を欠いた印象を与えます。こうした例を通して、「丁寧に言っているつもりが、実は逆効果になっている」という現実を理解できるのです。
また、日常的なあいさつの中にも注意すべき誤りがあります。「とんでもございません」という表現は長年使われてきましたが、文法的には誤りであり、代わりに「とんでもないことでございます」と言うのが正解です。この章を読むことで、社会人として最低限避けるべき言葉遣いを把握できるでしょう。

誤用は恥ずかしさだけでなく、信頼を損なう危険性があります。
正しい表現を知ることは“相手を敬う姿勢”を言葉で形にする第一歩です。
第2章 ビジネスシーンですぐに使える敬語
この章では、職場での受け答えや取引先とのやり取りなど、実務で即活用できる表現に焦点が当てられています。例えば、上司に対して「わかりました」と答えるのは日常的ですが、職場によっては軽い印象を与える場合があり、「承知しました」や「かしこまりました」といった言葉が推奨されます。
また、社外対応における表現の難しさも解説されています。「お世話様でございます」という表現は敬語らしく見えますが、実は不自然で、相手に違和感を与える場合があります。さらに「課長に申し上げておきます」といった一見正しい表現も、使い方を誤ると相手への敬意を欠いた印象になるため注意が必要です。
この章を通じて重要なのは、正しさと同時に相手がどう受け取るかを意識することです。言葉そのものの意味だけでなく、会話全体の流れや相手との関係性を踏まえた表現ができるようになることが、社会人としての信頼につながります。

敬語は“文法的に正しい”だけでは不十分。相手にとって“自然で心地よい”ことが大切です。
本章はその感覚を磨く訓練の場となります。
第3章 電話対応で役立つ敬語の使い方
電話応対は、相手の表情が見えないため言葉遣いがより重要になります。この章では、電話をかける際に使うべき適切な冒頭のフレーズや、相手の声が聞き取りにくいときに失礼にならない伝え方が紹介されています。
特に注目すべきは、取り次ぎや伝言のやり取りに関する具体的な例です。「失礼ですが、お名前を頂戴できますか」といった言い方は一見正しそうですが、相手の立場によっては角が立つこともあります。そのため、場面ごとに適した柔らかい表現が必要とされます。さらに、クレーム対応における最初の一言が相手の感情を左右するなど、緊張感のあるシーンへの備えも含まれています。
また、現代的な要素として、章末ではビジネスチャットに関するコラムも掲載されています。電話と同様に直接顔を合わせないやり取りであるため、丁寧でわかりやすい文章表現が求められます。ここを押さえておけば、電話とチャット双方で一貫した対応力を養うことができます。

第4章 日常会話での上手な敬語の使い方
最後の章では、職場以外の場面、つまり日常生活や冠婚葬祭といった特別なシーンに対応できる表現が扱われています。家庭や友人関係では、形式ばった言葉よりも自然さが求められるため、過剰な「お」「ご」の使用はかえって不自然になることが指摘されています。
さらに、冠婚葬祭における敬語は特に注意が必要です。例えば、結婚式での親族へのあいさつや葬儀でのお悔やみの言葉は、場の雰囲気を大きく左右します。「大往生でしたね」といった不用意な表現は、相手を傷つけかねないため避けるべきです。このような失敗を防ぐ具体例が数多く示されています。
加えて、章末では「クッション言葉」の使い方も取り上げられています。これは、会話を柔らかくするための工夫であり、「恐れ入りますが」「差し支えなければ」といった表現が、日常的なやり取りをスムーズに進める助けになります。場面に応じた適切な言葉選びが、社会人としての成熟を示すのです。

日常の言葉遣いは、その人の人柄を最も表すものです。
本章で学ぶ内容は“マナー”を超え、人間関係を豊かにするための知恵と言えるでしょう。」
対象読者

この本は、敬語に苦手意識を持つ人から、社会人としてより洗練された言葉遣いを目指す人まで幅広く役立つ構成になっています。
特に次のような立場や状況にある人々に向けて、有効なヒントや実践的なフレーズが満載です。
- 新社会人・新入社員
- 接客・営業など顧客対応を行う人
- 電話・メール対応に不安がある人
- 就職活動・転職活動中の人
- 冠婚葬祭や人付き合いで失礼を避けたい人
それぞれの立場に応じたニーズに対して、具体的にどう活用できるのかを解説していきます。
新社会人・新入社員
社会に出たばかりの時期は、知識やスキルよりもまず「基本的なマナー」や「言葉遣い」で評価されることが多いです。特に敬語は、上司や先輩との信頼関係を築く第一歩であり、ここでつまずくと「常識がない」という印象を与えてしまいます。本書は、間違いやすい表現を実例とともに示してくれるため、入社直後から安心して活用できる指針になります。
さらに、新人は日々の報告や相談、会議での発言の機会が多くあります。こうした場面で自然な敬語を使えることは、単なる言葉の選び方にとどまらず、「成長意欲がある」「信頼できる人材」という評価につながります。本書を通じて敬語の基礎を固めておけば、スタートダッシュを切る上で大きな武器となるでしょう。

接客・営業など顧客対応を行う人
営業や接客の現場では、商品やサービス以上に「言葉遣い」が信頼を左右します。どれほど良い提案をしても、相手に不快感を与える表現を使えば成果にはつながりません。本書では、訪問時の挨拶や取引先へのやりとりでよくある失敗例を紹介し、それをどう改善すべきかを具体的に解説しています。そのため、日常的に顧客対応をする人にとっては、現場ですぐに活かせる知識が得られる一冊です。
さらに、顧客との会話では相手の立場に配慮した柔らかい言葉選びが重要です。本書は、単に「正しい日本語」を教えるだけでなく、「どうすれば相手が気持ちよく受け止めてくれるか」という視点も重視しており、営業力や接客力を高めたい人にとって非常に有益です。

電話・メール対応に不安がある人
電話やメールは、相手の表情が見えない分、言葉遣いがそのまま印象を決定づけます。慣れていない人ほど「伝えてくれますか?」など、普段の口調をそのまま使ってしまいがちです。本書では、電話をかける・受ける場面の流れや、よくあるNG表現と正しい言い換えを紹介しているため、不安を抱える人が安心して対応できる力を養えます。
また、クレーム対応や伝言の受け渡しなど、難易度の高い場面でのフレーズも掲載されており、単なる「マナー本」ではなく実務に直結した内容になっています。これにより、経験の浅い人でも落ち着いて対応でき、相手に信頼される話し方を実践できるようになります。

就職活動・転職活動中の人
面接や企業訪問では、知識やスキル以上に「言葉遣い」が評価されることがあります。「ご苦労様です」や「了解しました」といった表現をうっかり使えば、社会経験不足と判断されかねません。本書は、そうした場面での失敗を避けるために役立つ具体例を豊富に収録しており、安心して自己PRできるようにサポートしてくれます。
また、採用担当者に「礼儀正しく、社会人としての基本ができている」と感じてもらうための表現が整理されているため、初めて就活に臨む学生や、転職で面接に挑む社会人にとっても大きな助けとなるでしょう。

冠婚葬祭や人付き合いで失礼を避けたい人
結婚式や葬儀など、人生の節目となる場面では、普段以上に言葉遣いへの注意が求められます。例えば、お悔やみの席で「大往生でしたね」と言ってしまうと、不快に受け止められることがあります。本書では、そうした「やってしまいがちな禁句」と、代わりに使うべき適切な表現をわかりやすくまとめています。
さらに、友人や親戚との日常的なやりとりでも「ありがとう」「すみません」といった基本の言葉を丁寧に言い換える方法が紹介されています。これにより、人間関係をより良好に保ち、相手に気遣いを示すことができるようになります。

冠婚葬祭での言葉遣いは、社会的信用に直結します。
本書を読めば「知らなかった」では済まされない場面で自信を持って振る舞えます。
本の感想・レビュー

敬語の「正解」と「好感度」を両立
私は敬語について「正しいかどうか」だけを基準に考えていました。しかし本書を読み進めるうちに、単に正解を知るだけでは十分ではなく、同時に「相手に好印象を与える」使い方が求められることを痛感しました。正解と好感度の両立という視点は、自分には欠けていたものです。
紹介されているフレーズは、ただ形式的に整ったものではなく、相手の立場や気持ちを考慮したものばかりです。そのため、知識として学ぶというより、人間関係を築くための実践的なスキルを身につけている感覚がありました。文章の端々に、現場で役立つ「言い方の温度」が感じ取れます。
この二つの要素を意識するようになってからは、言葉を発する際に「これで正しいか」だけではなく「これで心地よく伝わるか」まで考えるようになりました。その変化は、コミュニケーションの場で確実に役立っていると感じています。
社外対応の事例が豊富で助かる
仕事柄、取引先や来客と接する機会が多いので、社外対応の具体例が豊富に掲載されているのは非常に助かりました。本書を読みながら、自分がこれまで曖昧な理解のまま使っていた表現が多かったことを実感しました。
特に、相手に依頼をするときや訪問客を迎えるときの言葉は、自分では丁寧なつもりでも失礼にあたるケースがあることを知り、改めて身が引き締まる思いがしました。こうした実例が丁寧に説明されていることで、自分の言葉をすぐに修正しやすくなっています。
社外でのやり取りは一度の失敗が信頼に影響するため、実践的な事例を知っておくことの大切さを強く感じました。この本はその意味で、自分にとって「安心できる支え」になってくれています。
冠婚葬祭の敬語までカバーしていて安心
読んでいて特にありがたかったのは、ビジネス以外に冠婚葬祭の場面にまで触れている点でした。社会人になると避けられない場面でありながら、事前にしっかりと学ぶ機会が少ない部分なので、とても心強い内容でした。
結婚式やお葬式といった特別な場では、普段以上に言葉に気を遣わなければなりません。本書では、その際にふさわしい表現だけでなく、つい言ってしまいがちな誤用や避けるべき言葉についても具体的に示されています。そのため、自分が場を乱すことなく安心して対応できる自信が持てました。
日常や職場にとどまらず、人生の節目にまで役立つ内容が含まれていることで、この本の実用性の幅広さを改めて実感しました。一冊持っているだけで、不安を大きく軽減してくれる存在です。
クッション言葉のコラムが役立つ
読み進める中で特に印象に残ったのが「クッション言葉」を紹介するコラムでした。直接的な表現を和らげ、相手に配慮を伝える工夫として、短い言葉をどう添えるかが具体的に示されています。普段は意識せずに使っていることもありましたが、体系的にまとめてあることで改めて理解が深まりました。
特に、相手に依頼するときや断る場面など、角が立ちやすい状況においてクッション言葉を一言添えるだけで印象が変わることがよくわかります。この部分を読むことで、自分がこれまで無意識にスルーしていた言葉選びに光を当てられたような感覚になりました。
コラムという短い形式でありながら、日常やビジネスの両方で即実践できる工夫が盛り込まれている点は、非常に実用的でした。文章全体の合間に配置されているので、息抜きのように読めるのも魅力の一つです。
図解なので研修教材にも使いやすい
会社の研修用に使えるかどうかという視点で読んでみましたが、この本は非常に有用だと感じました。まず、図解が豊富なので、文字だけでは伝わりにくいニュアンスが視覚的に整理されているのが大きな強みです。敬語のルールは抽象的に語られることが多いですが、図やイラストを通して流れや構造を把握できるので、新人社員にも理解しやすいと実感しました。
また、実際の会話例が段階的に示されていることで、「正しくない言い方」と「より望ましい表現」を比較しながら学べるのが便利です。研修の場で取り上げれば、そのままグループディスカッションやロールプレイに活用できると思いました。単なる知識の暗記ではなく、実際にどう話せば良いかを考えさせる教材として最適です。
読むだけで自信がつく
正直に言うと、敬語に苦手意識があったため、この本を手に取るときも少し不安がありました。しかし、ページをめくるごとに「あ、これなら自分でもできる」という感覚が積み重なり、自然と自信が芽生えていったのです。
難解な理屈ではなく、シンプルな解説と豊富な図解で正しい言い方が整理されているので、頭に入りやすいのが大きな理由だと思います。誤った表現を直すだけでなく、より印象を良くする工夫まで書かれているため、実際に口にするイメージが鮮明にわきました。
読後には「敬語は難しいもの」という先入観が和らぎ、「これなら大丈夫」という安心感に変わっていました。この自信は、実際の人間関係やビジネスの場面でも必ずプラスに働くと感じています。
社会人必携の“敬語の教科書”
最後に全体を振り返って思ったのは、この本はまさに社会人なら一冊手元に置いておくべき「教科書」だということです。基礎から応用まで幅広く網羅されているので、初心者も経験者もそれぞれの立場で学びを得られる内容になっています。
特に、日常会話からビジネス、さらには冠婚葬祭まで、社会人生活のあらゆる場面をカバーしている点は他の書籍にはない特徴だと思います。どんな状況でも迷わず使える表現がそろっているので、いざというときに頼りになる存在です。
「困ったときに開けば答えがある」という安心感が、この本の最大の価値だと感じました。まさに社会人生活を支える道しるべとして、多くの人に薦めたい一冊です。
誤用を直すだけで印象が変わる実感
実際に本で学んだことを取り入れてみると、相手の反応が変わるのをはっきり感じました。大げさな敬語表現をやめたり、誤った言い方を正しく言い換えたりするだけで、会話がすっと通じやすくなり、こちらの印象が明らかに良くなったのです。
間違った敬語を使っていると、無意識のうちに自分の評価を下げてしまうことがあります。そのことに気づけたのは大きな収穫でした。逆に言えば、ちょっと直すだけで信頼度が増すというのは非常に効率的だとも感じます。
敬語を正すことは単なるマナーではなく、相手との関係を円滑にし、自分をより良く見せる武器になるのだと実感できました。この変化を体験したからこそ、継続して使い続けたいと思えます。
まとめ

記事の締めくくりとして、本書を手に取ることでどのような価値が得られるのかを整理しておきましょう。
以下の三つの視点に分けて理解すると、読後の学びがさらに深まりやすくなります。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの観点を踏まえることで、自分にとって本書がどのように役立つのかを明確にイメージできるはずです。
読み進めた知識を実生活やビジネスの現場でどう活かしていくのか、そして今後の成長につなげるためのヒントを見つけるきっかけとして、このまとめをぜひ活用してください。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、この本を通じて得られる大きなメリットを一つずつ解説していきます。
誤用をなくして安心感を持てる
本書では、誰もが一度は口にしてしまう「間違った敬語」を取り上げ、その背景と正しい言い換えを丁寧に解説しています。例えば「ご苦労様でした」という表現は、実際には目上の人に対しては失礼にあたりますが、知らずに使ってしまう人は多いでしょう。本を通じて自分のクセや誤用に気づき、修正できるようになることで、言葉を使う際の不安が軽減し、安心して会話に臨めるようになります。
実践力を育て即戦力になれる
敬語は知識として覚えるだけでは身につきません。本書は日常や職場での会話をそのまま再現するかたちで例文を紹介しているため、読みながら「自分ならこの場面でどう言うか」とシミュレーションできます。これにより、学んだ表現をすぐに実践できる即戦力が身につき、社会人生活のさまざまな場面で役立ちます。
第一印象を改善し信頼を得られる
正しい敬語は単にマナーという枠を超え、相手に「きちんとした人」という印象を与えます。本書で解説されるフレーズは、言葉遣いに品格を添え、相手に信頼感を抱かせる効果があります。特にビジネスや初対面の場面では、会話の最初の数言が人間関係の方向性を決定づけることもあるため、このスキルは大きな武器になります。
あらゆるシーンに対応できる柔軟性が身につく
本書が扱う範囲はビジネスだけではなく、日常会話や冠婚葬祭といったフォーマルな場まで広がっています。たとえば結婚式での親族への挨拶や、弔事の場で避けるべき表現などは、普段の生活ではなかなか学ぶ機会がありません。これらを事前に知っておくことで、いざというときに焦らず、落ち着いた対応ができるようになります。

敬語の学習は単なる言葉の習得にとどまらず、「社会的な自己表現のトレーニング」と位置づけられます。
心理学的にも、人は相手の言葉遣いから「信頼できる人物かどうか」を無意識に判断するとされており、本書を通じて敬語を身につけることは、対人関係全般における信頼資本の蓄積につながるのです。
読後の次のステップ
本を読み終えたときに大切なのは、学んだ知識を「実際の生活や仕事にどう活かすか」という視点です。本書は、読んで理解するだけで終わらせるのではなく、繰り返し練習して習慣化することで真価を発揮します。
ここでは、読後に取り組むべきステップを具体的に紹介していきます。
step
1日常で意識して実践する
本書で学んだフレーズや表現は、まず身近な日常会話の中で積極的に使ってみることが重要です。たとえば、家族や友人との会話で「とんでもございません」ではなく「とんでもないことでございます」といった正しい言い方を取り入れると、自然と体に染みついていきます。実践を通じて自分の言葉の癖が見え、それを少しずつ修正できるのです。
step
2職場や学校でロールプレイする
職場や学校では、同僚や仲間と一緒にシミュレーション形式で練習すると効果的です。電話応対や来客対応のロールプレイを取り入れることで、本番に近い状況で敬語を使う経験が積めます。この方法は緊張感を伴うため、実際の現場で応用する際に迷わず発言できる自信へとつながります。
step
3書き言葉をブラッシュアップする
話し言葉だけでなく、メールやチャットの文面でも敬語力は問われます。読後は、本書で紹介されているビジネスメールの章を参考にしながら、過去に送った自分のメールを振り返って修正してみるのが良いでしょう。書き直しの訓練を繰り返すことで、自然に適切な文面が書ける力が育ちます。
step
4新たな課題を見つける
敬語は場面ごとに異なる難しさを持っています。日常会話では自然さが重視されますが、冠婚葬祭や公式の場では格式や礼儀が求められます。本書を読み終えた段階で、自分が特に苦手だと感じた領域を振り返り、その部分を重点的に強化することが、次のステップとして有効です。
step
5学んだことをアウトプットする
最後に、学んだ内容を他者に伝えることも大切です。後輩や友人に正しい敬語の使い方を教えたり、社内勉強会で共有したりすることで、自分自身の理解が深まります。教える立場に立つことで、自分がどこまで本当に身につけられているのかを確認する機会にもなるのです。

教育心理学の観点では、学習を「インプット」から「アウトプット」へ移行することで記憶の定着率が飛躍的に高まるとされています。
敬語の学びも同様で、読むだけでは一過性の知識にとどまりがちですが、実際に使い、共有することで長期的に保持される「実践知」へと変わります。
総括
『頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる』は、単なる敬語の解説本にとどまらず、社会人として必要な言葉の力を総合的に養える実用書です。誤った表現を正しく直す基礎力から、電話応対やビジネスメールといった具体的な実務スキル、さらには冠婚葬祭などのフォーマルな場で求められるマナーまで幅広くカバーしている点が大きな特徴です。読者は、自分の言葉遣いに自信を持てるようになり、相手からの信頼感を高めることができます。
また、本書はイラストや図解を豊富に用いているため、文字だけでは理解が難しい微妙なニュアンスや場面ごとの使い分けを、直感的に学べる工夫がなされています。これにより、従来の「敬語は難しい」という固定観念を取り払い、初心者でも楽しく学べる内容になっています。特に新社会人や就職活動中の学生にとっては、実践で役立つ即効性のある知識として心強い一冊となるでしょう。
さらに、敬語の習得は個人の印象を良くするだけでなく、職場全体の雰囲気や顧客との関係性を向上させる効果もあります。本書を通じて身につけた正しい言葉遣いは、周囲への配慮や思いやりを伝える手段となり、人間関係を円滑にする潤滑油として機能します。単なるマナーではなく、相手を敬う姿勢そのものを表現できる点で、本書の価値は非常に大きいといえます。

本書は「言葉を変えれば人生が変わる」というテーマを体現する一冊です。
敬語を正しく使えるようになることで、自分自身の評価が高まり、信頼される人間関係が築けるようになります。
これはビジネスシーンに限らず、あらゆる場面で役立つ普遍的なスキルです。
読了後は、身につけた表現を日常的に繰り返し活用し、確実に自分のものにすることで、さらに大きな成長へとつながるでしょう。
敬語に関するおすすめ書籍

敬語について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 敬語について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 敬語の使い方が面白いほど身につく本
- がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ
- 敬語と言葉づかい マナーの便利帖 新装版
- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー
- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる
- 誰もここまで教えてくれない 一生使える「敬語&ビジネスマナー」
- その敬語、盛りすぎです!
- 敬語再入門
- これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識
- 敬語「そのまま使える」ハンドブック
- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート
- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー