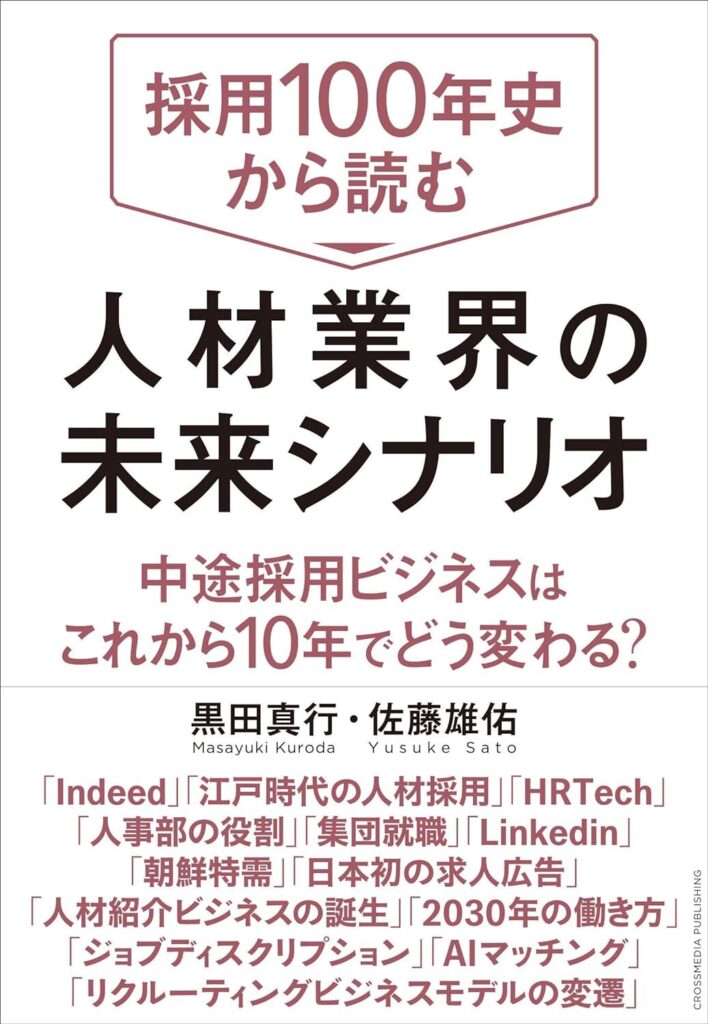
求人広告の誕生から人材紹介、ソーシャルリクルーティング、AI活用型のマッチングサービスまで――本書『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、日本における採用ビジネスの変遷を100年というスパンで紐解きながら、その本質と未来の姿を深く掘り下げた一冊です。

「終身雇用」が当たり前だった時代から、「転職」がキャリアの選択肢として一般化した現在。
そして2030年以降、少子高齢化・テクノロジー・働き方の多様化といった大きな潮流の中で、リクルーティングはどのように再定義されるのか。
リクルートやエン・ジャパン、Wantedly、Indeedなど業界を牽引する企業の取り組みを通して、変革の裏側にある“構造”と“思想”を描き出します。
人材業界に関わるすべての人にとって、過去を理解し、未来への指針を見つけるための「地図」となる一冊です。

合わせて読みたい記事
-

-
優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...
続きを見る
書籍『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』の書評

この書評では、本書を深く理解するために5つの観点から掘り下げて解説していきます。
著者の経歴と視座に始まり、内容の構造やメッセージ、そしてなぜ多くの読者から支持されているのかまで、初めて読む方にもわかりやすく丁寧にご紹介します。
- 著者:黒田 真行のプロフィール
- 著者:佐藤 雄佑のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:黒田 真行のプロフィール
黒田真行氏は、人材業界において長年にわたり実務と革新を両立させてきた希少な存在です。1965年生まれ。関西大学法学部を卒業後、1988年に株式会社リクルートに入社。以後、30年以上にわたり、人材領域における求人広告・転職メディア・人材紹介サービスの企画運営に携わってきました。特に、1990年代から2000年代にかけては、転職情報誌『B-ing』『とらばーゆ』の編集を経て、日本最大級の転職サイト『リクナビNEXT』の編集長としても活躍。リクルート社内における中途採用領域のDX(デジタルトランスフォーメーション)を先導してきた人物です。
その後は、人材紹介サービス『リクルートエージェント』にて、Web集客戦略やユーザー体験設計を担うネットマーケティング企画部長を歴任し、求人メディアと人材紹介の両分野で構造的な知見を蓄積してきました。2014年には独立し、ルーセントドアーズ株式会社を設立。35歳以上の転職希望者に特化した支援サービス「Career Release40」を展開しています。従来は「年齢が高いと転職が難しくなる」とされていた常識に異を唱え、経験豊富な人材が再びキャリアを切り開ける社会づくりを目指して活動しています。

黒田氏の経験は、求人広告・転職メディア・人材紹介という異なる領域を横断的にカバーしており、人材業界の全体像を構造的に理解している稀有な専門家です。
彼のような人物が過去と未来を俯瞰するからこそ、本書には現場感と先見性の両方が込められています。
著者:佐藤 雄佑のプロフィール
佐藤雄佑氏は、企業の人事戦略とキャリア支援を結びつけることを得意とする実務家です。大学卒業後は、まず株式会社ベルシステム24にてマーケティング領域でキャリアをスタート。その後、リクルートエイブリック(現・リクルートキャリア)に転職し、人材紹介ビジネスの現場で法人営業、エリア支社のマネジメント、社内人事、エグゼクティブクラスのキャリアコンサルタントなど、幅広い業務を経験しました。特に、経営視点と現場感覚の双方を活かし、企業が人材をどのように捉え、活用し、成長につなげるかという戦略的課題に長年取り組んできました。
2016年に独立し、株式会社ミライフを設立。以後、企業の働き方改革や人材戦略設計、経営層へのHRコンサルティングを手がけています。単なる採用の枠を超えて、組織そのものの変革支援を視野に入れた活動を展開している点が、従来の人材業界出身者とは一線を画しています。人事と経営の橋渡しができる希少な人材であり、本書でもその視点が随所に生かされています。

佐藤氏の強みは、“採用担当”と“経営者”の両方の立場で物事を考えられる点です。
採用を「組織の一機能」としてではなく、「事業戦略の一部」として捉える視点は、現場志向だけでは得られないものです。
本書の要約
『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、タイトルの通り、日本の人材業界の100年にわたる進化の軌跡をたどりながら、現在の採用市場の構造と、今後のビジネスモデルやキャリア観の変化を展望する内容で構成されています。単に業界の年表をなぞるのではなく、歴史的背景、社会制度、働き方の意識変化などを絡めながら、採用ビジネスが時代に応じてどのように姿を変えてきたのかを立体的に描いています。
本書の前半では、江戸時代の士農工商に基づく職業分類や、明治期の近代産業化による雇用形態の変化を紹介しつつ、戦後の高度経済成長期における終身雇用と年功序列の定着、そして転職へのネガティブな偏見の形成など、人材流動性の乏しかった時代の価値観を丁寧に分析しています。
中盤では、1975年にリクルートが「求人情報誌」という形で市場に新風を吹き込んだ転機を軸に、求人広告、人材紹介、派遣、RPOなど多様なサービスの誕生と分岐を追い、やがて2000年代以降に台頭するソーシャルリクルーティングやAI・アルゴリズムによるマッチング手法といった革新技術の導入がもたらす変化を浮き彫りにしていきます。
最終章では、2030年に向けたリクルーティングビジネスの未来像を提起し、少子高齢化、ライフシフト、インディペンデントコントラクター(独立請負型の働き方)の普及、雇用と業務委託の境界の曖昧化などを前提とした人材サービスのあり方を、具体的なシナリオとして提示しています。

この本は“過去を知る”だけで終わらず、“未来のリクルーティング戦略を構築するための道筋”を論理的に示してくれる点が特徴です。
特定の手法に偏らず、業界全体の構造的なダイナミクスを描いているからこそ、読者は目先の変化に振り回されずに思考の軸を持てるのです。
本書の目的
この書籍が目指すのは、「人材業界に関わるすべての人が、変化の本質を理解し、自らの立場で主体的に未来を描けるようになる」ことです。著者の黒田氏は、リクルートで長年メディアと採用支援の現場に携わる中で、求人広告と人材紹介という二つの世界が、同じ市場に存在しながら交わることなく進んできた現状に強い違和感を抱いていました。そこで本書では、それらを横断的に整理し、採用市場全体を一望することで、業界内部にある分断を乗り越えた視点を提示しています。
また、著者は「変化への対応力は、構造を理解する力に比例する」という信念を持っており、本書ではAI、IoT、ビッグデータ、クローリング、クラウド人材など、テクノロジー主導の業界変化を、単なる流行語としてではなく、どのような原理で既存の仕組みを変えていくのかを丁寧に解説しています。これは、単に目新しいトピックを詰め込んだ情報本ではなく、読者が本質を見抜く力を養う“地図とコンパス”を渡す意図があるからです。
さらに本書は、採用担当者やキャリア支援者だけでなく、経営者や産業政策に携わる人々にも、社会構造の変化の一環として人材ビジネスを理解してほしいという広い視野を持って書かれています。採用とは単なる人集めではなく、企業の未来そのものに直結する経営課題であるというメッセージが随所に込められています。

人材業界を“働く人の人生を支える産業”と捉え直し、その責任と可能性を再認識することが本書の狙いです。
採用という行為が、単なる数合わせではなく、社会と組織の持続性に深く関わる営みであることを、構造的な視点で教えてくれます。
人気の理由と魅力
本書が高く評価され、多くの読者から支持されている理由は、一言でいえば「視野の広さと深さの両立」にあります。単なる歴史の羅列でもなければ、最新トレンドの紹介に終始するわけでもない。その両方を組み合わせたうえで、人材業界が抱える構造的な課題、そして個人と企業の関係性の変化を本質的に問い直している点が、読者にとって新鮮で刺激的なのです。
特に注目すべきは、WantedlyやOpenWork、NewsPicks、Indeedといった実名企業の具体的なケーススタディが豊富に盛り込まれていることです。これにより、読者は抽象的な概念ではなく、実際のビジネスモデルや運用手法を通じて「変化のリアル」を体感することができます。たとえば、求人メディアが単なる掲載枠販売から、ユーザーコミュニティの構築やアルゴリズムによるマッチングへと進化している事例は、読者の視座を確実に広げてくれるはずです。
また、実務に直結する視点が豊富に盛り込まれていることも魅力のひとつです。採用手法やペルソナ設計、広報プロセスの見直しといった現場的課題にも言及されており、経営課題からオペレーションレベルまで幅広く網羅されている点は、現場の担当者にも高い実用価値をもたらします。
さらに、著者2名のバックグラウンドが補完関係にあることも、書籍としての完成度を高めています。黒田氏の“メディアと仕組み”への洞察と、佐藤氏の“個人支援と現場感覚”が融合することで、読む者の立場に応じて多層的な学びが得られる構成となっています。

“歴史×構造×事例×未来”を一冊に凝縮した本書は、単なる知識の羅列ではありません。
現在地を把握し、未来の選択を誤らないための“判断力”を育てる書であり、HR戦略を担うすべての人にとっての“知の資本”です。
本の内容(目次)

本書は、採用という営みが、どのように社会に根付き、形を変えてきたのかを体系的に理解できる構成になっています。章ごとにテーマが明確に分かれており、過去から未来への流れを一貫してたどることができます。読み進めるごとに、人材業界の構造や課題、そしてこれからの可能性がクリアになっていく感覚を得られるはずです。
それぞれの章は以下のようなタイトルで構成されています。
- はじめに
- 序章 採用支援ビジネスをとりまく全体像
- 第1章 職業選択の広がりと採用ビジネスの100年
- 第2章 求人広告と人材紹介 2つの人材ビジネスの誕生
- 第3章 リクルーティングビジネスにおけるビジネスモデル変遷
- 第4章 リクルーティングビジネスの新潮流
- 第5章 人材業界のディスラプター
- 第6章 人事採用部門は変化にどう対応すべきなのか?
- 第7章 リクルーティングビジネスの未来シナリオ
この章立てによって、読者は過去・現在・未来をつなぐ流れを自然に理解できるよう設計されています。
次からは、それぞれの内容を順に解説していきます。
はじめに
冒頭では、日本の人材業界がどのように社会の中で認識されてきたか、その価値観の変遷が語られます。現在では11兆円産業となったこの分野も、1980年代以前はまだ周縁的な存在であり、特に中途採用市場は、困窮者の救済と搾取が紙一重の「人材周旋業」として見られることもありました。転職に対するイメージも悪く、「新卒で入った会社を辞めるのは根性なし」といった固定観念が広く共有されていました。
1970年代後半、そうした価値観に挑戦する動きがリクルートを中心に始まります。求人情報誌の創刊や編集方針には、「転職者を脱落者ではなく挑戦者と見なす」という思想が込められていました。その背景にあるのは、「やり直しができる社会を作る」という理念です。そしてインターネットの登場により、情報の非対称性は徐々に解消されていき、転職市場の可視化が進みました。
現在では情報過多の時代となり、求職者も企業も選択肢の多さに戸惑うようになっています。複数のエージェントから異なるアドバイスを受けたり、求人サイトの多様化により意思決定が難しくなるという問題も浮上しています。一方で企業側でも、AIやRPOといった技術革新に対して「自社はこの変化にどう対応すべきか」といった危機感が広がりつつあります。
このように、過去から現在に至るまでの「採用をめぐる空気感の変化」を俯瞰し、業界が直面する課題と可能性を浮き彫りにすることが、本書の出発点となっています。

“転職=敗北”という過去の価値観が、“転職=自己選択”へと変わった背景には、情報の可視化と信頼性の向上があります。
求人メディアの進化は、単に媒体が増えたという話ではなく、社会全体のキャリア観を変革する装置でもあったのです。
序章 採用支援ビジネスをとりまく全体像
採用支援ビジネスを正確に理解するためには、それがどのような産業構造の中に位置づけられているかを俯瞰する視点が欠かせません。この序章では、人材ビジネス全体の中における「採用支援」の役割を明確にし、求人広告や人材紹介、派遣、アウトソーシングなどの領域が、どのように相互に影響し合いながら成長してきたかを説明しています。
特に注目すべきは、日本特有の新卒一括採用制度の存在です。この制度は、企業が将来の人材を長期的視点で「育成前提」で採用する仕組みであり、欧米の「即戦力型採用」とは大きく異なります。しかし少子高齢化の進行や、テクノロジーの進展による職種の変化により、この新卒中心のモデルは今、構造的な見直しを迫られています。
採用支援ビジネスとは、単に人を紹介する仕事ではなく、労働力を最適に社会に配分する「調整機能」を担う存在でもあります。企業の成長、産業の発展、そして個人のキャリア形成を下支えする仕組みとして、採用支援の意義を再確認することが求められています。

採用支援は“人材獲得”にとどまらず、“人材の最適配置”という経済全体の循環に貢献する社会インフラです。
個別企業の課題に見えて、実は国全体の競争力にも関わる根幹領域なのです。
第1章 職業選択の広がりと採用ビジネスの100年
第1章では、時代ごとの労働観や職業観の変化が採用のあり方にどのような影響を与えてきたかをたどります。江戸時代には士農工商という身分制度が職業選択の幅を狭め、働くとは“生まれに従うもの”とされていました。それが明治維新後の近代化によって、職業の自由度は次第に拡大していきます。
大正から昭和にかけては、戦争と動員体制の中で職業の選択は再び制約を受けることになりますが、戦後はアメリカ型の自由経済の導入とともに、“職業を選ぶ権利”が再び人々の手に戻ってきます。特に高度経済成長期には、大企業が大量の新卒を採用し、終身雇用と年功序列によって安定的なキャリア形成が主流となりました。この時代には、転職はあくまで「例外」であり、再挑戦ではなく“脱落”という否定的なイメージが色濃く残っていました。
この章は、「働く自由」がどのようにして社会に浸透してきたのか、そしてそれがどのように採用市場に影響を与えたのかを理解する上で不可欠な章です。現代のリクルーティングを支える思想や制度は、こうした100年単位の変化の積み重ねの上に成り立っていることを再認識させてくれます。

採用制度は“政策”や“経営施策”だけで生まれるものではありません。
労働観や職業観といった“社会の価値基盤”が根本的な前提として作用しており、その変化を読み解くことがリクルーティングの本質理解につながるのです。
第2章 求人広告と人材紹介 2つの人材ビジネスの誕生
現代の採用支援サービスの源流は、1970年代後半に確立された「求人広告」と「人材紹介」の2つのモデルにさかのぼることができます。この章では、それぞれがどのような背景で誕生し、どのように市場を形成していったのかを具体的に解説しています。
求人広告は、企業が自らの採用情報を広く不特定多数に伝える手段として発展しました。紙媒体からスタートし、やがてWebメディアへと移行する中で、ターゲティング(属性に応じた配信)やメッセージング(応募動機を引き出す表現)の手法が洗練されていきます。一方の人材紹介は、企業と候補者を仲介者がマッチングするサービスであり、個別性と専門性が求められる領域です。
この2つのサービスは、「量の求人(広告)」と「質の求人(紹介)」という補完関係にありながら、事業モデルや収益構造、担当者の役割において大きく異なります。さらに近年では、両者が融合するハイブリッド型の採用支援サービスも登場しており、採用手法は一層多様化しています。

求人広告と人材紹介は、同じ“採用”という目的を持ちながら、アプローチの仕方が全く異なります。
前者は「情報流通業」、後者は「関係構築業」とも言えるほど、ビジネスモデルも運用思想も違うのです。
第3章 リクルーティングビジネスにおけるビジネスモデル変遷
この章では、リクルーティングビジネスの構造がどのように進化し、変遷してきたのかについて、時代の流れとともに詳細に解説されています。特に注目すべきは、ビジネスモデルの視点でリクルーティングを整理している点にあります。求人広告や人材紹介といった手法の違いだけでなく、それぞれの収益構造、集客戦略、マッチング方式、提供価値などを明示しながら、各モデルの本質的な違いと強み・弱みを明らかにしています。
1990年代以降、紙媒体からインターネットへと求人手法が移行する中で、Web型の広告モデルやクローリング型の検索エンジンなど、テクノロジーによってリクルーティングの地図が塗り替えられていきました。その過程で、従来の「広告を出す→応募を待つ」という受け身のモデルから、「適切な人材に届くよう仕掛ける」戦略型モデルへと変化しています。
また、企業と求職者のマッチングにおいて、情報の対称性が高まるにつれ、単なる情報掲示ではなく、カスタマイズされた情報提供や行動予測に基づくレコメンド機能など、より高度な仕組みが求められるようになってきました。これに対応する形で、各社がビジネスモデルをアップデートしていく様子が、本章では詳細に追われています。

ビジネスモデルの違いを理解することは、単なる“手法選び”ではなく、“収益構造”と“価値提供のあり方”を見抜く力を養うことに直結します。
HRビジネスに携わるなら、この視点は欠かせません。
第4章 リクルーティングビジネスの新潮流
採用支援の手法は、近年ますます多様化し、従来型の求人広告や人材紹介だけではカバーしきれない領域が急速に広がっています。この章では、従来の「空白地帯」とされていた分野を掘り下げることで、今まさに変化の渦中にあるリクルーティングの最前線を紹介しています。
たとえば、WantedlyやLinkedInなどのソーシャルリクルーティング系サービスは、企業と個人が“人となり”をベースにした関係性を築く新しい採用文化を形成しつつあります。従来のスペックベースではなく、価値観や思考への共感を基軸にしたマッチングが、特に若年層を中心に広がっているのが特徴です。
また、OpenWorkやNewsPicksなどのメディア型プラットフォームでは、企業文化や従業員の声といった「選ばれる理由」が見える化されており、単なる求人情報だけでは語れないリアリティが、候補者の意思決定を支えています。これらのサービスは、企業と候補者のコミュニケーションを多層的にすることで、“採用体験”の質そのものを変えようとしているのです。

これからの採用競争では、“情報量”ではなく“関係性の深度”が鍵になります。
ソーシャルリクルーティングやメディア型採用は、企業の魅力を“伝える”のではなく、“共感される”状態をどう作るかにフォーカスしている点が新しいのです。
第5章 人材業界のディスラプター
この章では、従来の枠組みを壊すような「破壊者(ディスラプター)」として登場した新興プレイヤーのインパクトを取り上げています。特に、クローリング型求人検索エンジンであるIndeedが、どのようにして求人流通の在り方を一変させたかが中心に語られます。
Indeedは、求人情報をクローリング(自動収集)する仕組みを用いて、求人媒体や企業サイトに掲載されている情報を一覧化・統合化することで、求職者にとっての「求人情報のハブ」となることを目指しています。この構造により、求人情報の可視性が飛躍的に向上し、企業側も新たなリーチチャネルとして活用するようになりました。
しかし、求人情報の拡散力が高まる一方で、質の担保やマッチング精度といった新たな課題も生まれており、従来の人材紹介や求人広告とどう共存するのかという命題が浮上しています。本章では、こうしたディスラプターがもたらす可能性とリスクの両面を冷静に捉え、業界全体が迎える再編の兆しを提示しています。

ディスラプターを単なる“競合”と見るのではなく、“構造変化のトリガー”として分析する視点が重要です。
変革の本質は、プレイヤーの交代ではなく、業界の設計思想そのものに及ぶのです。
第6章 人事採用部門は変化にどう対応すべきなのか?
この章では、採用の現場に立つ人事担当者が、急速に変化する採用市場やテクノロジーにどう対応していくべきかを具体的に論じています。特に焦点が当てられているのは、「誰を採るべきか」という問いへの向き合い方と、それを実現するための仕組みの設計です。
例えば、ペルソナ設計の精度を高めるために、既存社員の行動傾向から理想像を抽出したり、候補者の行動データを分析して“接点の最適化”を図ったりと、科学的アプローチが導入されつつあります。また、「ポータブルスキル」と呼ばれる業種・職種を超えて通用するスキルセットに注目が集まっており、経験よりも“再現性ある能力”が重視される傾向が強まっています。
さらに、採用広報における一貫したストーリーデザインや、選考プロセスの手順化といった“仕組みづくり”の重要性も指摘されており、採用活動を“運用業務”ではなく“戦略プロジェクト”としてとらえる視点が求められています。

優秀な人材を採るには、“欲しい人材の定義”と“その人が魅力を感じる設計”の両輪が必要です。
人事は今、“営業”と“マーケティング”の両方を求められる職能へと進化しているのです。
第7章 リクルーティングビジネスの未来シナリオ
最終章では、少子高齢化やテクノロジーの進化といった社会構造の変化を前提に、2030年以降の人材業界がどう変わるかをシナリオベースで描いています。働き方の多様化、副業や兼業の一般化、個人のキャリアの“人生二毛作”化などがキーワードとなり、企業と働き手の関係性が根本から再構築される時代が到来すると示唆されています。
企業は単に雇用契約を結ぶのではなく、スキルや成果に基づいて柔軟な関係を築く必要があり、採用手法も「長期雇用前提」から「価値創出の単位ベース」へとシフトしていきます。また、業界内では価値の二極化が進み、単なる“人材流通業”ではなく、“戦略パートナー”としての位置づけを築けるかどうかが生き残りの鍵となるとされています。
本章では、未来の働き方がもたらす社会的影響を見据えながら、リクルーティングビジネスがどう進化すべきかを具体的かつ戦略的に描いており、読者にとって「次の一手」を考えるための指針となる内容になっています。

未来のリクルーティングは、“職業”ではなく“価値の流通”を扱う領域になります。
人材業界にとっての課題は、雇用の形式ではなく、“どんな価値を誰に届けるか”という設計思想に移行しているのです。
対象読者

本書『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、単なる採用の実務書ではありません。人材業界の構造的な理解を深め、未来を見据える視座を得るための一冊です。
次のような読者にとって、とくに多くの気づきと学びが得られる内容となっています。
- 採用担当・人事に関わる方
- 転職エージェント・キャリアコンサルタント
- 人材業界を志望する学生・転職希望者
- 転職活動中のビジネスパーソン
- 産業構造の変化に興味があるビジネスリーダー
以下、それぞれの立場に合わせた読みどころや、得られる知見について解説していきます。
採用担当・人事に関わる方
本書は、日々採用の最前線で奮闘する人事・採用担当者にとって、業務の枠を超えて「採用とは何か?」を再定義するきっかけを与えてくれる内容です。採用実務は、時に数値やKPIに追われ、属人的な経験や勘に頼って進めざるを得ない場面も多いものですが、本書を読むことで、採用がどのような背景と歴史の中で成り立ち、今どう変わりつつあるのかを俯瞰して捉えることができます。
とくに印象的なのは、かつての転職が「敗者復活の選択肢」と見なされていた時代から、キャリア形成の戦略的手段へと進化してきた過程を丁寧に解説している点です。自社の採用手法や採用広報、ペルソナ設計に行き詰まりを感じている方にとっては、「なぜ今うまくいかないのか」の根本を理解するヒントが得られるでしょう。

人事・採用の現場を経験で乗り切るだけでは、変化の時代に対応できません。
構造と変遷を理解することが、本質的な人材戦略を導きます。
転職エージェント・キャリアコンサルタント
求職者に対して転職支援を行うエージェントやキャリアコンサルタントにとって、本書は非常に実践的かつ教養的な価値を持ちます。目の前の求職者に寄り添うだけでなく、業界全体の構造やその変遷を把握することで、アドバイスの説得力は格段に増します。たとえば、なぜ人材紹介が「成果報酬型」で定着しているのか、なぜAI型マッチングやクローリングメディアが市場を急速に拡大しているのか――そうした仕組みの成り立ちを説明できるだけでも、支援者としての信頼感は大きく変わるはずです。
また、本書にはWantedlyやLinkedIn、OpenWork、Indeedといった現代のサービスの裏側も多数掲載されており、ツールの使い分けや選定理由に関する知見も得られます。多様化する転職チャネルの中で、どの媒体がどう活用されているかを知ることは、提案力を磨くうえで極めて重要です。

キャリア支援の質は「知識の厚み」に比例します。
業界の歴史や構造を理解していることは、支援の“軸”になります。
人材業界を志望する学生・転職希望者
就職活動やキャリアチェンジを通じて、人材業界への一歩を踏み出そうとしている方にとって、この本は最良のガイドになります。なぜなら、多くの人が「人と企業をつなぐ仕事をしたい」「やりがいがありそう」という漠然としたイメージでこの業界を志望する一方で、業界の仕組みやビジネスモデル、時代ごとの変遷をしっかり理解できている人は決して多くないからです。
本書を読むことで、「なぜ今この業界が注目されているのか」「どんな変化の波が押し寄せているのか」を歴史的視点とデータの両面から学べます。それにより、面接やエントリーシートでも説得力のある志望動機を語れるようになるほか、入社後の業務理解も格段にスムーズになります。実際のサービス事例や企業動向にも触れているため、業界研究の精度も一気に高まるでしょう。

転職活動中のビジネスパーソン
転職活動中の社会人にとって、本書は「求人を見る視点」を変えてくれる一冊です。求人票には書かれていない、企業がなぜそのポジションを募集しているのか、どんな採用戦略をとっているのかといった、背景情報を読み解く力が養われます。企業が何を重視し、どういう文脈で候補者を評価しようとしているのかを知ることは、選考通過率を高めるうえでも極めて有効です。
また、章を追って読むことで、転職市場の成り立ちやチャネルごとの特徴、時代ごとの候補者の動きなども理解できます。結果として、自分がどのタイミングで、どのチャネルを使い、どんなポジションを狙うべきかという“転職の地図”が明確になります。

産業構造の変化に興味があるビジネスリーダー
本書は人材業界に直接関わっていない経営者や事業企画担当者にとっても、価値の高いインサイトを提供します。なぜなら、採用や雇用の在り方は、そのまま組織の設計思想や事業の根幹と密接に結びついているからです。特に「2030年の働き方」や「クラウド人材」、「インディペンデントコントラクター」など、本書が提示する未来像は、単なる予測にとどまらず、新しい経営戦略や制度設計の出発点となり得ます。
また、Indeedのようなディスラプターの登場背景や、大手人材サービス各社の次世代戦略の比較分析など、ビジネスモデルの変革に興味がある方にとっても示唆に富んだ内容です。採用は人材業界だけの話ではなく、すべての企業にとっての「成長の源泉」であり、その未来を構想することは経営者の本質的な仕事でもあります。

採用の未来を読むことは、経営の未来を読むことに直結します。
人事戦略と事業戦略をつなぐヒントが、本書には詰まっています。
本の感想・レビュー

転職が「当たり前」になるまでの歴史
正直、最初はタイトルに惹かれて軽い気持ちで読み始めたんですが、気づけば一気に読み込んでしまいました。私が一番心を打たれたのは、転職という行為が、かつてどれほど社会の中で冷たい視線を浴びていたかという点です。自分が転職を経験したときも、「逃げた」と言われるのではないかとどこか後ろめたさを感じていた記憶があります。でも、この本を読んで、それが社会的な価値観の歴史に深く根差していることを知って、なんだか救われたような気持ちになりました。
江戸時代の身分制度や、戦後の就業構造、そして高度経済成長期の終身雇用の浸透といった歴史の流れの中で、転職がいかに否定され、そして徐々に受け入れられるようになっていったのか。その過程が丁寧に描かれていて、まるで日本社会の「働く」という文化が一皮むけていく姿を見ているようでした。過去を知ることが、今の自分を肯定する手がかりになるなんて、思ってもいませんでした。
求人広告と人材紹介の誕生物語に驚いた
私はマーケティングの仕事に関わっているのですが、この本の第2章を読んで「求人広告」が広告業界や採用業界の中で果たしてきた役割の大きさに、素直に驚かされました。特に、かつて三行広告が当たり前だった時代から、いかにして情報性と信頼性を備えた求人メディアが登場したのか、その歴史的背景が非常に面白かったです。
これまで求人広告は「人を集めるための手段」としてしか見ていなかったんですが、ターゲティングやメッセージングというマーケティング手法がどのように発展してきたかという文脈で読み解くと、求人という枠を超えた広告進化の物語として映りました。人材紹介に関しても、単なる斡旋ではなく、求職者の人生と企業の採用戦略を繋ぐ「社会的装置」としての役割があるという視点にハッとさせられました。
求人業界が抱えるジレンマに共感
僕は今、転職サイトでキャリアアドバイザーとして働いています。この本を読んで一番グサッと刺さったのが、「情報が多すぎて、求職者が混乱している」という部分。実際、現場でも「どのサービスを使ったらいいのか分からない」「エージェントによって言うことが違って困る」という声は日々聞いています。
自分自身も、求職者にとって最適な選択肢を提示しようと努力しているつもりですが、それが本当に正解なのかと自問することも少なくありません。この本では、業界全体が抱えている構造的な課題にまで踏み込んでいて、単なるテクニックやノウハウではなく、根本的な「採用支援の在り方」にまで問いかけてくれます。読みながら何度も立ち止まって、自分の仕事を見つめ直しました。
企業がやるべき「採用広報」の勘所が学べる
広報担当として日々企業のブランディングに携わっていますが、本書で紹介されていた「採用広報プロセス」は、まさに私が求めていた実務に直結する内容でした。これまで採用と広報は別々の施策と考えがちでしたが、ペルソナの設計から、適切なメディア選定、情報発信のタイミングまで、戦略的に設計する視点がしっかり整理されていて、目から鱗でした。
特に、求職者側の「選職行動の変化」についての分析は、自社の採用戦略を見直すうえでの大きなヒントになりました。これまで「良い会社なんだから、きっと分かってくれるだろう」という姿勢だった自分たちにとって、情報発信の仕方そのものを変える必要があると強く感じました。
ミドル層にも希望が持てる内容だった
正直に言って、私はこの本を手に取ったとき「若者向けのキャリア論かな」と思っていました。ところが読み進めるうちに、それがまったくの誤解だったことに気づきました。むしろ、働き盛りの40代・50代にとって、これからのキャリアをどう設計していくべきか、そのヒントが満載の一冊でした。
印象に残っているのは、少子高齢化と働き方の多様化が進む中で、「人生二毛作」を前提にしたキャリア設計が求められているという視点です。もう「一社で定年まで」は過去の話。副業、フリーランス、定年後の再就職……あらゆる働き方の可能性を視野に入れたうえで、自分のスキルや経験を「どう転用できるか」を考える力が重要だと本書は教えてくれました。
年齢を重ねたことがリスクではなく「選択肢の幅」を広げる材料になる。そんなメッセージに背中を押された思いです。
実践できる採用戦略
現在、私は地方の中小企業で人事を担当しています。従業員数は30名ほどで、採用は毎回手探り。そんな私にとって、本書の第6章で紹介されていたペルソナ設計の解説は、本当に目から鱗が落ちるような内容でした。
これまで「こんな人が来てくれたらいいな」と漠然とイメージすることはあっても、それをどう言語化し、戦略的に採用に落とし込むかという視点は持っていませんでした。この本では、優秀な人材を想定し、社内や業界、データの観点からペルソナを作っていく方法が段階的に示されていて、すぐにでも自社の採用活動に取り入れたくなる内容でした。
さらに、採用広報のプロセスや選考手法、ポータブルスキルの考え方など、現場で迷いやすいポイントに対して、非常に具体的なアプローチが紹介されている点もありがたかったです。実務に携わる者として、この本を“読むだけ”にとどめず、“使う本”として、今後も何度も読み返したいと思います。
人材業界が直面する課題を体系的に理解できた
大学で社会学を教えています。人材業界というフィールドを研究対象として扱ううえで、本書ほど体系的に全体像を描いた文献には、なかなかお目にかかれません。江戸時代の職業選択から説き起こし、戦後の高度経済成長、新卒一括採用の台頭、求人広告ビジネスの誕生、AIによる再構築まで――まさに100年の「人と仕事」の変遷を俯瞰できる構成には圧倒されました。
特に興味深かったのは、「労働力調達産業」としての採用支援ビジネスの位置づけが、時代背景によってどのように社会的意味を変えてきたかという点です。採用とは、単なる人員の補充作業ではなく、経済構造や価値観と密接に絡み合う「社会現象」そのものであると実感しました。
本書は実務家向けに書かれたものでありながら、アカデミックな視点からの分析にも十分に耐えうる内容だと思います。
すべての採用担当者の座右の書
私は企業の人事部で10年以上採用に携わっており、これまでに読んできた関連書籍も数えきれないほどあります。そんな中でこの一冊は、間違いなく“座右の書”に加えたいと感じた本でした。
採用業界の100年にわたる歴史を踏まえたうえで、現代の課題と今後の展望まで一気通貫で学べる構成は、知識を再構築したい経験者にとっても非常に有益です。また、最新テクノロジーやマーケットの動向にも触れられており、今後の戦略立案において欠かせないヒントが詰まっています。
読みやすさと専門性のバランスが絶妙で、どの章から読んでも得るものがある構成も魅力です。新たに採用戦略を構築するタイミングや、チームで共通認識を持ちたいときなど、何度でも活用できる一冊だと確信しています。
まとめ

本書『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、100年という長期スパンで人材業界をとらえ直すことで、日々の採用業務やキャリア設計に新たな視座を与えてくれます。
このセクションでは、この一冊を通して得られる具体的な成果や、読後のアクションの方向性、そして総括的なメッセージを示していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの観点から、読者が得られる学びと活用の可能性を掘り下げていきます。
この本を読んで得られるメリット
100年にわたる人材業界の進化と転換点を深く掘り下げたこの一冊は、単なる業界解説書ではありません。現在のビジネスに携わるすべての人に、採用やキャリアに関する実践的な知識と「未来を読む力」を授けてくれます。
以下のような点で、本書は読者に大きな価値をもたらします。
採用や人材育成の判断に「歴史的な背景」という軸を持てるようになる
採用や人材戦略を考えるうえで、どうしても短期的な流行や直近のトレンドに振り回されがちです。しかし本書を読むことで、人材ビジネスがどのような時代的要請によって形成され、どのように社会制度と相互に影響し合ってきたのかを俯瞰する視点が身につきます。これにより、現場での意思決定にも、過去からの流れを踏まえた論理的な軸を持てるようになり、短期視点に左右されない構造的な思考ができるようになります。
変化の本質を見抜き、次に来る波を読み解くための思考法が得られる
リクルーティングビジネスに関わる現場では、テクノロジーの導入や求職者行動の変化に対応する必要があります。本書は、人材業界に起きてきた複数の構造的転換点を丁寧に描くことで、「どのような変化が一時的で、どのような変化が不可逆か」を見極める力を養ってくれます。これにより、目先のトレンドに振り回されず、数年先を見通した採用戦略やキャリアビジョンの設計が可能になります。
自社の採用方針や施策を、社会構造と照らし合わせて再設計できる
企業が人を採用する際、どうしても自社の都合だけで要件やプロセスを考えがちです。しかし本書では、人材の流動性や雇用観の変化を歴史の中で描くことで、現在の求職者の行動や価値観の背景にある「社会的要因」も可視化されます。その理解をもとに、自社の採用要件や広報メッセージ、選考フローをより社会構造にフィットさせた形で見直すことができるようになります。
HRテクノロジーを「ただのツール」ではなく戦略の一部として活用できる
AIやクローリング、クラウド化など、HR領域の技術革新は急速に進んでいますが、ツールを導入するだけで成果が出るわけではありません。本書では、HRテクノロジーの進化が業界構造や求職者の行動にどのような影響を与えてきたかを具体的に示しています。これにより、読者はツールを単なる業務効率化の手段ではなく、「どの局面で、どの技術を、どう活用すればよいか」といった戦略的思考で捉えることができるようになります。
採用業務やキャリア支援に携わる自分の仕事が、社会の中で持つ意味に気づける
人材業界の仕事は、ときに「数字を追うだけ」「求人を回すだけ」といった作業的な側面に捉われがちですが、本書を通して、採用支援という営みが時代と社会をつないできた重要な役割であることが見えてきます。この気づきは、日々の業務に対する意識を根本から変え、自分の仕事に誇りを持つきっかけとなるでしょう。

人材業界に初めて触れる人にとっては“教養書”として、実務に携わる人には“実践書”として、多層的に機能するのが本書の最大の魅力です。
読むことで、歴史・現在・未来を一貫して見渡す俯瞰的な視点が身につきます。
読後の次のステップ
本書を通じて、人材業界の歴史と構造、そしてテクノロジーや社会変化がもたらす未来像に触れた読者は、「知識を得る」だけにとどまらず、「何をすべきか」「どう動くか」へのヒントも手にすることになります。
ここでは、読後に取るべき実践的なアクションの方向性を紹介します。
step
1自社の採用戦略やプロセスを見直し、アップデートする
まず取り組むべきは、これまで当然と考えていた採用手法や評価軸、媒体選定などを見直すことです。本書では、求人広告と人材紹介の機能的な違いや役割の変遷を丁寧に整理しています。これを踏まえれば、例えば「なぜうちの採用はうまくいかないのか」といった問いへの答えを構造的に掘り下げることができます。自社の採用活動を、業界全体の変化と照らし合わせて客観視し、今の市場に合った手法へと見直す絶好の機会です。
step
2人材業界の専門メディアやセミナーで情報収集を続ける
本書をきっかけに、業界の構造や課題への理解が深まったなら、その知識をさらに広げていくべきです。採用やHRテックに関する動向は日進月歩で変化しています。企業の戦略的パートナーになるためにも、HR関連の専門メディア、業界レポート、またはセミナー・ウェビナーなどの情報源にアクセスし続けることが重要です。特にAIやクラウドを活用したリクルーティングの領域は、基礎知識があるだけで情報の質を正しく評価できるようになります。
step
3採用活動に関わる社内外のメンバーと議論を始める
本書の学びは、個人の知見にとどめず、関係者との共有と対話の中で深まっていきます。例えば人事チームや役員層と「わが社はどのチャネルで採用すべきか」「今のターゲット設定は時代と合っているのか」といった議論を行うことで、より実践的な戦略構築につながります。また、エージェントや広告代理店などの外部パートナーとも、本書を土台にした共通言語で話せるようになるため、より建設的で本質的な対話が可能になります。
step
4自身のキャリアプランを見直し、未来志向で描き直す
もし読者が企業の人事やHR業界に属する当事者であるなら、本書は単なる業界ガイドを超え、自らのキャリアデザインにも影響を与える一冊になるでしょう。これまでの人材ビジネスの変遷を知ることで、「次に求められる人材像」や「市場価値の高め方」も理解できるようになります。未来の働き方や人材のクラウド化といったテーマは、自身のスキルアップやポジショニングを見直すうえでの有効なヒントとなるはずです。

知識をインプットしたあとに重要なのは、“行動を伴う学び”です。
本書で得た視点を、実務・転職活動・学習など自分の文脈に落とし込むことで、初めて「読んでよかった」が「変わってよかった」になります。
総括
本書『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、単なる採用ノウハウ本でも、未来予測だけのビジネス書でもありません。過去から現在、そして未来へとつながる人材業界の100年の歩みを丁寧にたどりながら、業界の成り立ちやビジネスモデルの変遷、技術革新による変化、さらに求職者・企業・サービス提供者それぞれの立場から見た課題と展望を、多面的に描いた極めて稀有な書籍です。
読者はページをめくるごとに、「なぜこの業界が今の形になったのか」「何が変わり、何が変わっていないのか」「これから何が必要になるのか」といった問いに向き合うことになります。それは、歴史の記述というより、意思決定の根拠をつくるための知識の積み重ねであり、日々変化するビジネス環境の中で働く人にとって“地に足のついた判断”を支える羅針盤となるものです。
本書が他の書籍と一線を画すのは、その網羅性と実践性の両立にあります。歴史的な視座から未来を読み解く一方で、ペルソナ設計や採用手法の手順化といった現場に即した内容も豊富で、経営層から若手人事担当者まで、どのレイヤーの読者にも“自分ごと”として響く構成になっています。また、HRテクノロジー、RPO、求人メディア、アグリゲーションなどの専門領域にも切り込んでおり、知識のアップデートにも最適な一冊です。
なにより印象的なのは、著者たちが一貫して「人と企業の接点を、より良くする」という思想を持ち続けている点です。売り手と買い手、雇う側と雇われる側、仲介者と当事者という関係を超えて、三者の理解と納得を調和させるには何が必要か。その答えを、歴史に学び、現場に問う姿勢の中に見出そうとする誠実な視点が、全編にわたって貫かれています。

この本は、ただ読むだけで終わらせるには惜しい一冊です。
業界で働く人々にとっては、時代の変化に流されず、むしろその変化を主体的にとらえ直すための“思考の再設計ツール”となるでしょう。
また、これから人材業界に関わろうとする人にとっては、業界全体の地図とコンパスを手に入れるような経験になります。
人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング
- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書
- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ
- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石
- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)
- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則
- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密
- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて
- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法

