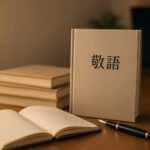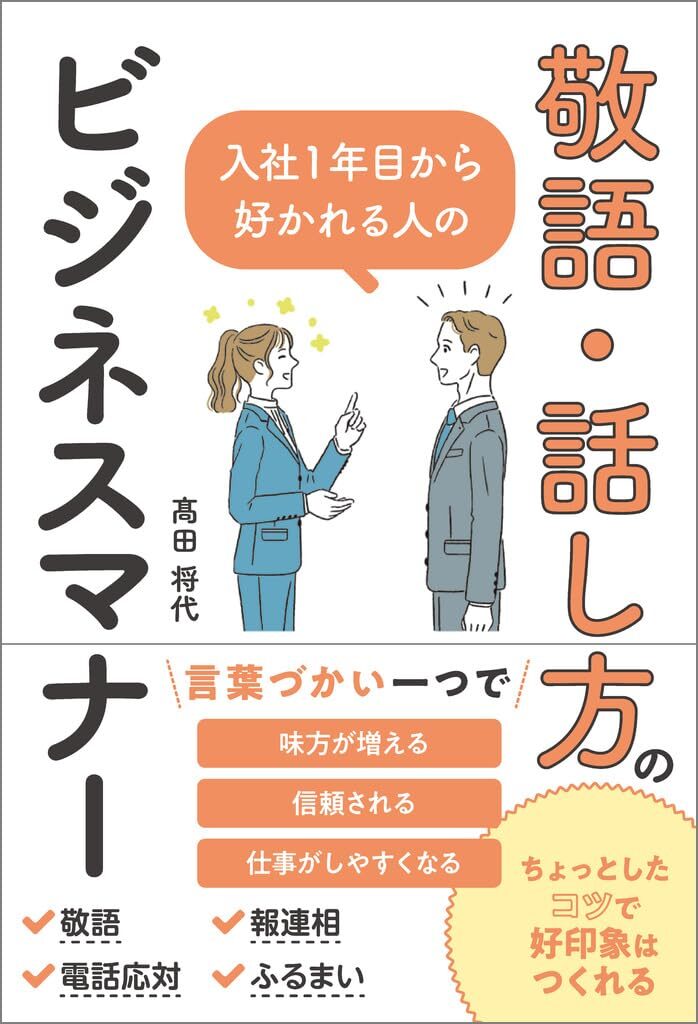
社会人として最初の一年は、仕事の成果以上に「人にどう見られるか」が成長のカギを握ります。
特に敬語や話し方といった基本的なコミュニケーションは、信頼を得るための第一歩でありながら、多くの新入社員がつまずく壁でもあります。

『入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー』は、そんな不安を抱える若手に向けて、挨拶や言葉遣い、電話応対や報連相まで、ビジネスの現場で必要とされる“好かれる振る舞い”を具体的に解説しています。
著者・髙田将代氏が培ってきた豊富な研修経験をもとに、「誰からも応援される人」になるための実践的なメソッドが詰まっています。
愛嬌や特別な才能がなくても大丈夫。正しい言葉選びと少しの気配りで、誰でも上司や先輩、取引先から「この人なら」と信頼される存在になれます。
本書は、社会人としてのスタートラインに立つあなたを一歩先へ導いてくれる、心強いパートナーとなる一冊です。

合わせて読みたい記事
-

-
敬語について学べるおすすめの本 13選!人気ランキング【2026年】
上司や取引先へのメール、電話、面接の受け答え――ふと「この敬語、合ってる?」と不安になる瞬間は誰にでもあります。 正しい言い回しが身につけば、伝わり方も印象も一気に変わるはず。 1位 敬語の使い方が面 ...
続きを見る
書籍『入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー』の書評

この本は、社会人として第一歩を踏み出す若手社員に向けて書かれた実用的な指南書です。単なるマナー解説本ではなく、「どうすれば周囲から応援される存在になれるか」という、仕事での成長や信頼獲得に直結するテーマを扱っている点が大きな特徴です。
理解を深めるために、以下の観点から順を追って解説します。
- 著者:髙田将代のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:髙田将代のプロフィール
髙田将代(たかだ まさよ)氏は、マナーコンサルタント・ふるまいコンシェルジュとして幅広く活動している人物です。奈良・當麻寺に生まれ、幼少期から茶道や華道に親しむことで、自然に「和の所作」や「おもてなしの心」を学びました。大学卒業後に入社した伊藤忠商事では、グローバルな舞台で商談や取引先対応を経験し、実務の中で“本当に役立つマナー”を体得。その後、フィニッシングスクールに通い、国際的な礼儀作法を学んだことが現在の活動につながっています。
現在は「Mエレガンスアカデミー」を主宰し、企業向け研修や学校でのコミュニケーション指導を展開。単に正しい作法を教えるのではなく、「相手から信頼される行動」「好かれる振る舞い」を重視し、心理学や行動科学の知見も取り入れている点が特徴です。
例えば、敬語を「器」として捉え、「中に込める気持ちがなければ意味がない」と説明するスタイルは、従来の形式的なマナー教育とは一線を画しています。こうした指導方針が、受講者から「実践的でわかりやすい」と高く評価されている理由です。

本書の要約
『入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー』は、新社会人が最初に直面する「どう話すか」「どう伝えるか」という課題に対して、実践的かつ体系的な解決策を示している一冊です。単なるマナー解説ではなく、周囲から信頼され、応援される存在になるための“コミュニケーション力”を育てることを目的としています。
本書の構成は、まず第一印象を決定づける挨拶や姿勢、表情など、非言語的な要素から始まります。ビジネスの場においては「見られている意識」が重要であり、笑顔や立ち居振る舞いの基本が、人間関係の土台を築くと解説されています。続いて、尊敬語・謙譲語・丁寧語・美化語といった敬語の基礎を整理し、誤用例を丁寧に指摘。誤りやすい「なるほど」や「よろしかったでしょうか」といった表現についても、なぜ不適切なのかを理由とともに説明しています。
さらに、柔らかな印象を与えるための言い回しや、断り方を円滑にするクッション言葉など、心理的な摩擦を減らすための具体的な方法も紹介されています。電話応対の章では、初めての業務として新人が任されることの多い「電話を取る」ことを取り上げ、基本的な応対からクレーム処理までを網羅。最後には「報連相」を中心とした上司や先輩との関わり方、そして感謝の伝え方や手土産の扱いなど、より好感度を高めるためのふるまいに触れています。
全体を通して共通しているのは、「好かれること=信頼されること」であり、信頼を得られる人こそが最も成長できる、という視点です。この本を読むことで、新人は言葉遣いやマナーを“形式的に守る”のではなく、“信頼を築く手段として使う”という発想を持つことができます。

本書のユニークさは、知識を詰め込むのではなく、すぐに実践できる行動指針を与えている点にあります。
マナーを「型」として覚えるのではなく「信頼を生む手段」として理解できる構成です。
本書の目的
この本の狙いは、若手社員がいち早く「信頼される存在」に成長できるようサポートすることにあります。著者は、基本的な業務は誰でも教わることができるが、その先の“仕事の機微”は上司や先輩からのアドバイスによってのみ学べると指摘しています。しかしそのアドバイスは、誰にでも与えられるわけではありません。困っている姿を見て「助けてあげたい」、努力している様子を見て「育てたい」と思わせる人だけが、その貴重な学びを得られるのです。
つまり、社会人としての成長スピードは、スキルそのものよりも、周囲からどれだけ信頼され、サポートを受けられるかに大きく依存します。そのため本書は、「自分は愛嬌がないから難しい」と感じる人にも、言葉遣いや話し方を磨き、相手への配慮を少し加えるだけで十分に変わることができると伝えています。信頼を得ることは特別な才能ではなく、誰にでも身につけられる習慣なのです。
この目的を達成するために、本書は基礎的な敬語の使い方から、具体的な実践フレーズ、さらには人間関係を円滑にするための気遣いの工夫まで、段階的に解説しています。読者はマナーを「堅苦しいルール」としてではなく、「周囲との信頼関係を築くための道具」として学ぶことができます。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者や企業研修で支持されている理由は、その実用性とわかりやすさにあります。新人社員や学生といった初心者にも読みやすいよう、イラストや事例をふんだんに取り入れながら解説しており、堅苦しさを感じさせません。また、単なる「正しい敬語の暗記」ではなく、誤用されやすい表現を具体的に指摘し、どう改善すれば印象が変わるのかを明示している点が評価されています。
加えて、電話応対や報連相など、新入社員が現場で必ず直面する具体的な場面を想定して解説しているため、すぐに実践できる学びが得られる点も大きな魅力です。さらに、立ち居振る舞いや感謝の伝え方といった人間関係の核心にまで踏み込んでいるため、「ただの言葉遣いの本」ではなく、「信頼を築くための総合マニュアル」として役立ちます。
こうした特徴から、本書は個人のスキルアップにとどまらず、内定者研修や新入社員研修のテキストとして採用されるなど、教育現場でも広く活用されています。読みやすく、実践的で、成果につながるという三拍子がそろっていることが、人気を支えている理由です。

この本が研修や教育の現場で選ばれるのは、「理解→実践→定着」という学習の流れを自然に作れる構成だからです。
マナーを“知識”から“行動”へと橋渡ししているのが魅力といえます。
本の内容(目次)

本書では、社会人として信頼される人になるための要素が、段階的に整理されています。特に新人が最初につまずきやすい部分や、成長の過程で必ず直面する場面ごとに分けられている点が特徴です。
以下のような構成で、読者を導いています。
- 第1章 相手の心をつかむ「話し方」のキホン
- 第2章 好かれる人になるための「敬語」の使い方
- 第3章 柔らかな印象をつくる「言い回し」
- 第4章 「電話応対」ができると社内の味方が増える
- 第5章 上司に好かれる人は「報連相」で差をつける
- 第6章 もっと「好かれる人」になるために押さえておきたい立ちふるまい
これらの章立ては、単に知識を並べるのではなく、実際のビジネス現場で「どう動けば信頼を得られるか」を実践的に学べる流れになっています。
それでは、順を追って中身を確認していきましょう。
第1章 相手の心をつかむ「話し方」のキホン
第一章では、社会人として信頼されるための基盤となる挨拶や姿勢、表情などの基本的な振る舞いについて解説されています。挨拶一つとっても「明るさ」「タイミング」「先手を打つこと」によって印象が大きく変わるとされ、良い第一印象を作ることがその後の関係構築に直結することが強調されています。また、姿勢やお辞儀といった非言語的な要素も、相手に与える印象に大きな影響を与えると説明されています。
さらに、表情や目線の使い方も細かく取り上げられており、「目で感情を伝える日本人特有の文化」にも触れています。話し方においては、声の大きさやスピード、言葉選びに加えて、仕草や態度まで含めた総合的なコミュニケーション力が重要だと説かれています。「聞き上手」になることが相手からの信頼を得る近道である点も、具体的な実践例を交えて紹介されています。
この章を通じて、単なる言葉のやり取りではなく「相手を安心させる空気づくり」がいかに重要であるかがわかります。仕事の成果は一人で完結するものではなく、周囲との協力関係で成り立つため、その土台を築く基本動作こそが評価されるのです。

心理学の「初頭効果」によれば、人は出会って最初の数分で相手の印象を形成し、その後の評価に強く影響します。
本章が挨拶や表情といった基礎を徹底しているのは、この効果を最大限に活かすための実践的アプローチだといえます。
第2章 好かれる人になるための「敬語」の使い方
第二章では、正しい敬語の理解と使い方が詳しく解説されています。尊敬語・謙譲語・丁寧語・美化語といった分類ごとに実例が挙げられ、誤用しやすい場面についても具体的に指摘されています。たとえば「よろしかったでしょうか」のような誤用は、意識せずに使ってしまいがちですが、信頼を損なう危険性があるため、早めに修正すべきと強調されています。
また、敬語を「完璧に使うこと」よりも「相手を敬う姿勢を伝えること」が本質だと述べられています。そのため、言葉を繰り返し口にして習慣化し、「筋トレ」のように身体に馴染ませることが推奨されています。これにより自然に敬語が身につき、相手に対する思いやりが言葉の端々に表れるようになります。
さらに、好感度を高めるための表現も紹介されており、単なる形式的な言葉遣いではなく、相手の心に寄り添う言葉を選ぶことの大切さが示されています。敬語を単なるルールとしてではなく「信頼を築く道具」として位置づける点に、この章の大きな特徴があります。

言語学の観点から見ると、敬語は「ポライトネス理論(Politeness Theory)」に基づく社会的な距離調整の手段です。
本章の指摘は、まさにその理論を実務的に応用し、相手のフェイス(尊厳)を守ることを目的としていると理解できます。
第3章 柔らかな印象をつくる「言い回し」
第三章では、日常的な会話をより円滑にし、相手に柔らかい印象を与えるための表現技法が解説されています。特に「恐れ入ります」「お手すきの際に」といったクッション言葉や大和言葉の活用が紹介され、直接的な表現を避けながらも相手に配慮を示す工夫が強調されています。
また、依頼や断りを伝える場面では、単なる否定表現を避けてポジティブな言い換えを行うことが推奨されています。例えば「できません」ではなく「この条件なら可能です」と伝えることで、相手に否定感を与えず建設的な関係を維持できます。こうした工夫が、職場の雰囲気や人間関係の質に大きく影響するのです。
さらに、言葉選びと考え方は連動しており、前向きな言葉を使うことで自分自身の思考も前向きになり、周囲にも良い影響を与えると述べられています。つまり、言葉は単なる伝達手段ではなく、自分と相手双方の心理状態を変える力を持っているのです。

言葉の「フレーミング効果」により、同じ内容でも表現方法が変われば受け取り方も変わります。
本章での言い換えの工夫は、この効果を利用して対人関係を円滑化する典型的な手法です。
第4章 「電話応対」ができると社内の味方が増える
第四章では、社会人の基本として軽視できない電話応対が詳しく取り上げられています。電話は相手の顔が見えない分、声のトーンや抑揚がそのまま印象に直結するため、元気さや丁寧さを意識することが欠かせません。特に新人時代は、率先して電話を取る姿勢が「頼れる存在」として認識される第一歩になります。
加えて、電話を受ける・かける・伝言を残すといった場面ごとの具体的な手順が示されており、初心者でも実践しやすい形で解説されています。クレーム対応のような難しい状況にも触れられており、相手の感情に寄り添いながら冷静に対処する姿勢が求められることが強調されています。
さらに、電話応対の習熟には「数をこなす」ことが重要であり、繰り返すことで自然にスキルが身につくと説かれています。最初は苦手意識を持っていても、積み重ねによって確実に成長できる領域である点が励ましとなっています。

コミュニケーション学では、電話のような「メディアリッチネスの低い手段」では情報の補完が重要とされます。
本章の指導は、声の表情や言葉選びによって情報不足を補い、信頼を築く実践例といえるでしょう。
第5章 上司に好かれる人は「報連相」で差をつける
第五章では、職場での信頼を勝ち取るために欠かせない「報告・連絡・相談(報連相)」の重要性が取り上げられています。トラブルを未然に防ぐためには、情報を迅速かつ正確に共有することが求められ、特に「朝イチで声をかける」などのタイミングが具体的に示されています。
また、報告は「結論→理由→経過」の順で簡潔にまとめること、連絡はこまめに行い業務の流れをスムーズにすること、相談は課題の共有に加えて必ず結果と感謝を伝えることなど、実践的なノウハウが整理されています。これらは単なる業務遂行ではなく、信頼構築のプロセスとして機能するものです。
章末ではケーススタディも用意されており、資料作成やクレーム対応といった具体的な場面でどう報連相を行うべきかを疑似体験できます。これにより、理論だけでなく実際の行動に落とし込みやすくなっています。

組織心理学において「情報の非対称性」はトラブルの温床とされます。
本章で推奨される報連相の習慣は、このリスクを最小化し、組織全体の信頼関係を強固にする仕組みだと理解できます。
第6章 もっと「好かれる人」になるために押さえておきたい立ちふるまい
最終章では、言葉や話し方だけでなく、日常的な立ち居振る舞いの中に表れる気配りや品格について述べられています。相手の名前を正確に扱う、感謝を繰り返し伝える、手みやげを渡す際に一言添えるといった細やかな行為が、人間関係を豊かにする要素として挙げられています。
また、誰に対しても態度を変えない一貫性や、物の扱い方に表れる人柄の重要性も強調されています。ゆったりとした動作や落ち着いた振る舞いが「心の余裕」として周囲に伝わり、結果的に信頼感を高めることにつながるとされています。
さらに、ご縁を大切にする姿勢も説かれており、出会った人や紹介された相手へのフォローが信頼関係を長期的に支える要因になると述べられています。ここでは単なるマナーを超えて、人としての在り方そのものに触れている点が特徴的です。

社会学でいう「ソーシャルキャピタル(社会関係資本)」は、信頼や互恵関係によって形成されます。
本章の立ち居振る舞いに関する提言は、まさに個人の資本を積み上げ、長期的な人間関係を豊かにするための実践指針です。
対象読者

本書はビジネスマナーの入門書でありながら、実際の現場ですぐに活かせる実践的な解説が豊富に盛り込まれています。そのため、読む人の立場や状況に応じて学べる内容が変わるのも大きな特徴です。
以下のような読者層に特に役立ちます。
- 新入社員
- 敬語や話し方に自信がない人
- 上司や先輩との関係を良好にしたい人
- 電話応対や報連相をスムーズにしたい人
- 就活・内定者研修を控える学生
これらの立場にある人は、本書を通じて「できる人」と思われるための具体的な行動指針を身につけ、周囲から応援される存在へと成長することができます。
新入社員
社会に出たばかりの新入社員にとって、正しい敬語や話し方を身につけることは、仕事の基礎を築くうえで欠かせません。最初の印象がその後の評価を大きく左右するため、挨拶や姿勢といった基本動作から電話応対や報連相まで、早い段階で「できる人」と思われるかどうかが決まります。本書は、その土台を整えるための実践的なノウハウを丁寧に解説しており、新人が自信を持って職場に立てる支えとなります。
さらに、入社直後の時期は上司や先輩から指導を受けやすいため、マナーを意識することでより多くのサポートを得られます。「応援したい」と思われる人材になることは、周囲からの助言や学びを最大化し、同期よりも成長スピードを高める大きな武器となるでしょう。

新入社員に必要なのは「完璧さ」ではなく「吸収力」です。
基本を理解したうえで柔軟に取り入れる姿勢が、最も早く信頼を築く近道になります。
敬語や話し方に自信がない人
社会人としての自覚を持ちつつも、「自分の敬語が正しいか不安」「話すと緊張してしまう」という悩みは多くの人に共通します。本書は、そうした不安を抱える人に向けて、敬語を「難解なルール」ではなく「相手を思いやるための器」として捉え直させてくれます。間違えやすい言葉の修正ポイントも解説されているため、安心して日常に活かすことができます。
また、声の大きさや話すスピードといった非言語的な部分も取り上げられており、「どう伝えるか」を工夫することで印象が改善できることを示しています。これにより、自分は話し上手でなくても、相手に信頼感や安心感を与えることができると理解でき、コミュニケーションに自信を取り戻せるのです。

話し方の不安は、知識不足よりも“経験の少なさ”から生じることが多いです。
本書はそのギャップを埋める練習法を提示し、段階的に自信を育てます。
上司や先輩との関係を良好にしたい人
職場での成功は、上司や先輩との関係性に大きく左右されます。良好な関係を築くためには、報連相を正しく行い、相手に「この人なら安心だ」と思ってもらうことが不可欠です。本書は、報告や相談の適切なタイミングや伝え方を具体的に示しており、相手の立場を尊重したやり取りを学ぶことができます。
こうした習慣を身につけると、指示がより的確に受け取れるようになり、信頼の輪が広がります。その結果、上司や先輩から自然に声をかけられ、アドバイスやサポートの機会が増え、成長を加速させることができるでしょう。

信頼は一度に得られるものではなく、日常の積み重ねによって築かれます。
本書で学ぶ「報連相の精度向上」が、その積み重ねを強固にする最短ルートです。
電話応対や報連相をスムーズにしたい人
電話や報連相は、新人に任される最初の重要な仕事でありながら、多くの人が苦手意識を持つ分野です。本書では、電話を取る際の第一声から、切る前に添える一言、さらにはクレーム対応に至るまで、実務に直結する流れを徹底的に解説しています。
これらの知識を身につけることで、業務の効率が上がるだけでなく、社内外からの信頼を得やすくなります。「電話ができる」「報連相が適切」という評価は、若手社員にとって大きなアドバンテージとなり、周囲から一目置かれる存在へと成長できるのです。

電話応対や報連相は“社会人の登竜門”です。
ここを克服すれば、どんな場面でも動じない安定感を得られるようになります。
就活・内定者研修を控える学生
社会に出る前の学生にとって、この本を読むことは「スタートラインで差をつける準備」となります。面接や研修の場では、言葉遣いや立ち居振る舞いの細かな違いが評価に直結します。基礎を理解しておくだけで、自信を持って振る舞えるようになり、周囲から信頼されやすくなるのです。
また、入社前に敬語や話し方のルールを学んでおけば、社会人としての立ち上がりがスムーズになります。同期が戸惑っている中で自然に正しい対応ができれば、「頼れる人材」として早くから注目され、活躍の場が広がります。

学生時代の準備は、社会人としての“即戦力”を養う時間です。
本書を先に学んでおくことで、最初の一歩を自信を持って踏み出せます。
本の感想・レビュー

敬語の「間違い例」が参考になる
この本を読み進めながら、思わずドキッとする場面がいくつもありました。というのも、普段何気なく使っていた言葉が「誤用」として指摘されていたからです。自分では正しく使えているつもりでも、実際には誤解を招いていた可能性があると考えると、背筋が伸びました。
特に印象的だったのは、身近な会話で使いがちなフレーズが、実は目上の人には不適切だという解説です。日常的に耳にしていた言葉ほど、自分もつい真似してしまうことが多いのだと痛感しました。間違い例が具体的に示されているからこそ、自分の癖を振り返る良い機会になりました。
読み終えてからは、自然と話す言葉に気を配るようになりました。今まで何となく口にしていた言い回しも、「これは正しいのか」と立ち止まって考える習慣が身についたのは大きな変化です。気づきを与えてくれる点で、この章は特に価値が高いと感じました。
言い回しが柔らかくなる実用フレーズ
本書の中で一番役立ったと感じるのは、相手に柔らかい印象を与えるフレーズが豊富に紹介されている部分です。普段の会話では、どうしても直接的な表現になってしまい、結果として冷たく聞こえてしまうことがありました。その改善方法を分かりやすく示してくれたことに感謝しています。
文章を読み進めるうちに、同じ内容でも言葉を少し置き換えるだけで印象が大きく変わるのだと実感しました。これは単なる言葉遣いのテクニックではなく、相手への思いやりをどう伝えるかという姿勢そのものにつながっていると感じます。だからこそ心に響きました。
この本で学んだ表現を意識すると、自然と会話が和やかになり、相手の反応も柔らかくなるように思います。気遣いを込めた言葉選びが、人間関係を円滑にする大きな力になるという実感を持てたことは、自分にとって大きな収穫でした。
報連相の型がシンプルで使える
報連相についての解説は、これまでの自分のやり方を大きく見直すきっかけになりました。どうしても話がまとまらず、要点がぼやけてしまうことが多かったのですが、本書の「結論・理由・経過」という型を知ってからは、自分の伝え方を整理する指標ができました。
具体的な型が示されることで、頭の中の情報を順序立てて話せるようになるのは大きな利点です。これなら相手も聞きやすく、自分も焦らずに伝えられると感じました。シンプルながら実用性が高く、すぐに取り入れられる点が魅力です。
本を読み終えた後、職場で実際にこの型を使ってみると、以前よりも上司からの反応がスムーズになった気がします。自分の伝え方が改善されることで、信頼を積み重ねられるのだと実感しました。報連相の本質を改めて学べたことは、大きな成果だと思います。
電話対応の具体ステップが心強い
電話応対に関する章は、自分にとって特に心強い支えになりました。社会人になってからも電話が苦手で、取次ぎや応答のたびに緊張してしまうのが悩みでした。そんな中、段階的に流れを整理した解説を読むことで、自分の中で具体的な行動イメージが持てるようになったのです。
実際の場面に沿って、声の出し方やメモの取り方まで丁寧に説明されているので、単なる理論ではなく実践的なガイドとして役立ちました。読みながら「自分にもできそうだ」と思える安心感があり、苦手意識を和らげてくれました。
これまで電話が鳴ると身構えてしまっていたのに、本を読んだ後は「試してみよう」という前向きな気持ちになれたのが印象的です。職場での不安を軽くしてくれる内容だったので、同じ悩みを持つ人には特におすすめしたいと思いました。
立ち居振る舞いが信頼感につながる
最後の章で触れられていた立ち居振る舞いの大切さは、私にとって非常に印象的でした。姿勢や動作の細かい部分が、人からの評価や信頼に直結するという解説を読み、普段どれだけ自分が無意識に振る舞っていたかを考えさせられました。
本書では、名前の呼び方や動作の丁寧さなど、細やかな行動が「この人なら大丈夫だ」と思わせる決め手になると示されています。その言葉を読んでから、自分が日常でどんな振る舞いをしているのかを意識するようになり、仕事中も自然と背筋を伸ばすことが習慣になりました。
改めて思うのは、立ち居振る舞いは見た目の美しさだけではなく、相手に対する敬意や心構えの表れだということです。この本を通して、その本質に気づけたのは大きな学びでした。
すぐに真似できるTipsが豊富
読み進める中で感じたのは、「これなら今日から実践できる」と思える小さな工夫が非常に多いことでした。細かい言葉の言い換えや、相槌の工夫など、難しい理論ではなく行動に落とし込みやすい内容が多かったのが助かりました。
特に嬉しかったのは、「自分にもできそうだ」と素直に思えるシンプルさです。気をつけるポイントが具体的に書かれていたので、読んだその日から意識して取り入れることができました。すぐに実践できる点が、この本を読む大きなメリットだと感じます。
振り返ってみると、小さな工夫を積み重ねることが自信につながるのだと実感しました。真似から始めることで、自然と自分のスタイルに変わっていくという流れを本書から学ぶことができました。
研修テキストとして最適
読後に思ったのは、この本が研修テキストとして非常に適しているという点です。体系立てられた章構成と、段階的に学べる流れが、学習教材としてそのまま活用できると感じました。
具体的なフレーズや行動指針が数多く盛り込まれているので、座学で学ぶだけでなく実際のロールプレイにも使えそうです。学びながら実践を重ねることで、理解が定着しやすい形になっています。
会社や学校で導入すれば、多くの人が基本を身につけやすくなるだろうと思いました。一冊の本で基礎から応用までカバーできる点が、研修用教材として大きな強みになると感じます。
イラストや解説がわかりやすい
本を手に取ったとき、すぐに目に入ったのは豊富に盛り込まれたイラストや図解でした。文章だけでなく視覚的に理解できるよう工夫されているため、内容がすっと頭に入りやすかったです。
解説も具体的な場面を想定しているので、読んでいて「この状況でどう話せばよいか」がリアルに想像できました。特に言葉の使い分けに関する部分では、文章とイラストがセットになっていることで理解度が高まりました。
読みやすさと実用性を兼ね備えた構成になっているので、苦手意識がある人でもストレスなく読み進められるのではないかと思います。自分にとっても、繰り返し参照したくなるガイドのような存在になりました。
まとめ

ここまでご紹介してきた内容を整理すると、本書が単なるマナー本ではなく、社会人として信頼を築きながら成長するための確かな指針であることが分かります。
理解を深めるために、このセクションでは以下の観点から振り返ってみましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
これらを意識して読み進めた知識を日々の仕事に落とし込むことで、より実践的に役立てることができます。
単に「読む」だけで終わらせるのではなく、行動の変化につなげることが、自分を成長させる最大のポイントです。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、この一冊を手に取ることでどのような成果が得られるのかを整理してみましょう。
信頼を築ける言葉遣いが身につく
敬語や丁寧語は、ただ「正しい日本語を使う」ための道具ではありません。本書では、言葉に心を込めて伝えることの大切さが強調されています。そのため、読後には、上司や取引先に自然と安心感を与えられる表現力が身につき、人間関係の基盤である信頼構築がスムーズになります。
職場で一目置かれるふるまいを学べる
挨拶やお辞儀、姿勢といった一見すると些細に思える振る舞いも、周囲の評価に大きな影響を与えます。本書では、場面ごとの具体的な立ち居振る舞いが体系的に解説されており、実践することで「この人はできる」と思われる存在に近づくことができます。
実践的なコミュニケーション力が向上する
ただ知識としてマナーを理解するだけではなく、日常業務に即したケーススタディが数多く盛り込まれています。電話応対や報連相など、すぐに現場で役立つトレーニングを通じて、実践力を磨くことが可能になります。その結果、周囲の人と円滑に協力し合える環境が自然と生まれます。
成長のスピードが加速する
「好かれる人」になることは、単に愛されることではなく、周囲からサポートやアドバイスを受けやすい立場になることを意味します。本書を通じて細やかな気配りや思いやりを習得することで、結果的に自分だけでは得られない知見や機会に恵まれ、成長スピードが大幅に高まります。

「信頼」や「好感」は数値化しにくいものですが、心理学やビジネス研究の分野では、職場での昇進や成果に大きく影響することが実証されています。
本書が扱う敬語や立ち居振る舞いは、そうした“見えない評価指標”を確実に高める実践的なツールなのです。
読後の次のステップ
本書を読み終えたときに大切なのは、得られた知識を頭の中に留めておくだけでなく、日常の行動に移していくことです。実際のビジネスシーンで試しながら、自分の成長を体感できるプロセスに落とし込むことで、学びが真の力へと変わります。
ここでは読後に取り組むべき具体的なステップを整理します。
step
1日常の会話に取り入れてみる
まずは本書で紹介されている挨拶や敬語表現を、日々の会話に意識的に取り入れることから始めましょう。特別な場面を待つ必要はありません。朝の挨拶や同僚へのちょっとした声掛けの中で試すことで、自然と自分の言葉遣いが磨かれていきます。
step
2振り返りと改善を習慣化する
一度学んだことを定着させるには、実践後の振り返りが欠かせません。その日のやり取りを思い出し、「もっとこう言えたのではないか」と考えることで、次の場面で修正ができます。小さな改善の積み重ねが、自信につながり、やがて大きな成長を生みます。
step
3信頼できる人にフィードバックをもらう
自己流で続けるだけでは気づけない課題もあります。上司や先輩、あるいは友人に、自分の話し方や立ち居振る舞いを見てもらい率直な意見を求めることで、より実践的な改善点が見えてきます。この外部からの視点が、成長のブレーキを外してくれるのです。
step
4学びを拡張していく
本書で培った基礎は、さらに専門的な分野へと広げることができます。ビジネスマナー全般や交渉術、プレゼンテーションのスキルなど、関連書籍や研修を通じて学びを深めれば、自分のコミュニケーション能力を次の段階に進化させることができます。

行動科学の研究では、「学習の定着率」はインプットだけでは20%未満に留まり、実際の実践と振り返りを繰り返すことで70%以上に高まると報告されています。
本書を読んだ後の行動こそが、成果を左右する最大のポイントといえるのです。
総括
『入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー』は、単なるマナー本にとどまらず、社会人としての基礎を確実に築くための実践的な指南書です。敬語や言葉遣いはもちろん、挨拶やお辞儀といった日常的な振る舞いにまで細かく焦点を当てている点が特徴であり、誰でもすぐに行動へ移せる内容が豊富に盛り込まれています。社会人生活を始めたばかりの人にとって不安の種となりやすい「言葉の壁」を、確実に乗り越えるための足がかりとなるでしょう。
また、本書が強調するのは「好かれること」がゴールではなく、「信頼されること」が本質だという視点です。先輩や上司、取引先から応援される存在になるためには、形式的なマナーを守るだけでなく、相手に寄り添う心や思いやりを持った言葉選びが重要であることを示しています。そのため、ビジネスマナーを学ぶことは単なるスキルアップではなく、人間関係の質を高めるための大切なプロセスであると気づかされます。
さらに、内容は具体的かつ実践的で、場面ごとに「どのように行動すべきか」が明確に提示されています。挨拶の仕方、敬語の使い分け、電話応対、報連相といったシーン別のアドバイスは、日常の業務に直結するため、学んだその日から実践できるのが大きな魅力です。これにより、学びを「知識」で終わらせず、確実に「行動」へと変えていくことができます。

本書は新人だけでなく、改めて自分の言葉遣いやコミュニケーションを見直したい社会人にも大きな価値をもたらします。
敬語や話し方の基礎を固めたい人、周囲との信頼関係を深めたい人にとって、読み返すたびに新しい気づきを与えてくれる一冊と言えるでしょう。
敬語に関するおすすめ書籍

敬語について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 敬語について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 敬語の使い方が面白いほど身につく本
- がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ
- 敬語と言葉づかい マナーの便利帖 新装版
- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー
- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる
- 誰もここまで教えてくれない 一生使える「敬語&ビジネスマナー」
- その敬語、盛りすぎです!
- 敬語再入門
- これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識
- 敬語「そのまま使える」ハンドブック
- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート
- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー