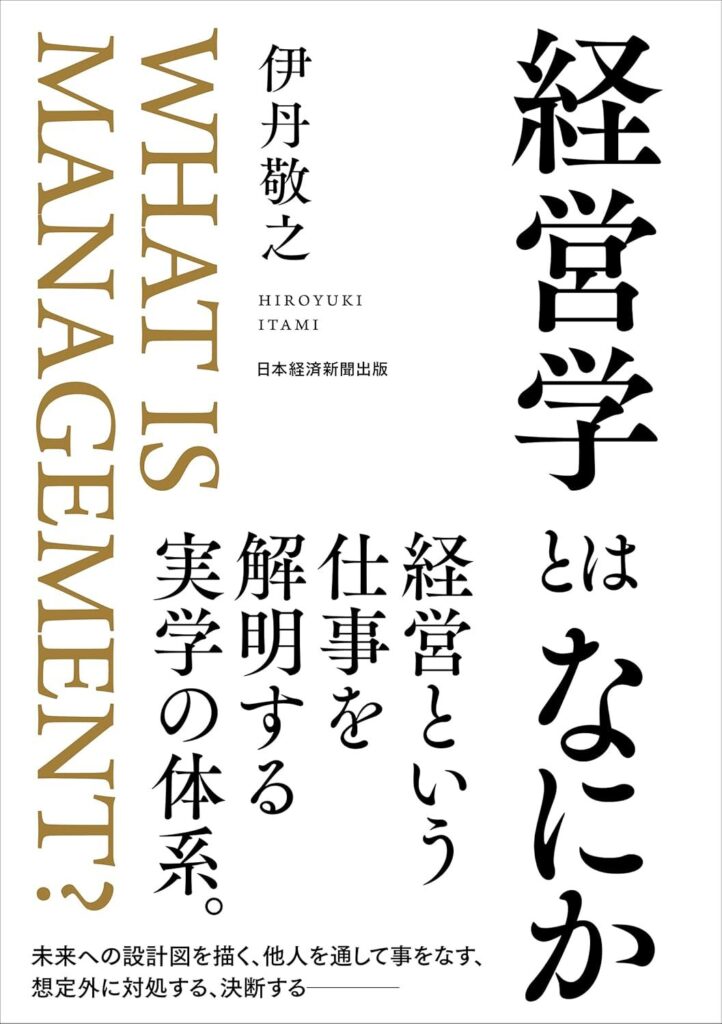
経営とは何か? 企業を動かし、成長させるために必要なものは何か? これらの問いに対する答えを求めるすべての人に向けて書かれたのが、伊丹敬之氏の『経営学とはなにか』です。
本書は、経営学の基本的な枠組みを示しながら、単なる知識の習得にとどまらず、実際のビジネスの現場で役立つ視点を提供しています。

経営学は、理論だけでは成り立ちません。
企業の未来を設計し、組織を動かし、想定外の出来事に対応し、決断を下す。
この一連のプロセスを、リーダーはどのように考え、実行すべきなのか。
本書では、これらのテーマを軸に、経営の本質を紐解いていきます。
経営の初心者はもちろん、企業の経営者、管理職、起業家など、実際に組織運営に関わるすべての人にとって、有益な知識と洞察が詰まった一冊です。
経営の原理を理解し、実践へとつなげるために、本書の内容を深く学んでいきましょう。

合わせて読みたい記事
-

-
経営学について学べるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】
「経営学を学びたいけれど、どの本を読めばいいかわからない…」「ビジネスやマネジメントの知識を深めたいけれど、専門書は難しそう…」そんな悩みを抱えていませんか? 経営学は、企業経営や組織運営、マーケティ ...
続きを見る
書籍『経営学とはなにか』の書評

本書は、経営学の本質と実践を探求し、リーダーが直面する課題に対するフレームワークを提供する一冊です。
伊丹敬之氏の豊富な経験と知見が詰め込まれており、単なる理論書ではなく、経営現場に役立つ具体的な指南書となっています。
この書評では、以下の4つのポイントに分けて解説します。
- 著者:伊丹敬之のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:伊丹敬之のプロフィール
伊丹敬之(いたみ ひろゆき)氏は、日本を代表する経営学者の一人であり、一橋大学の名誉教授です。長年にわたり、日本企業の経営戦略や組織運営について研究し、学問の枠を超えて実務の世界にも深く関わってきました。
1967年に一橋大学商学部を卒業後、1972年にカーネギーメロン大学でPh.D.(経営学博士号)を取得。帰国後は、一橋大学の教授として経営学の教育と研究に従事し、その後、東京理科大学や国際大学でも教鞭を執りました。さらに、スタンフォード大学経営大学院の客員准教授として海外でも活躍し、経営学を国際的な視点で研究してきた経歴を持っています。
また、学問だけでなく、日本企業の実務にも積極的に関わってきた点が特徴です。JFEホールディングスや商船三井など、大手企業の社外役員を務めるなど、実際の経営判断に携わる機会も多くありました。そうした実務経験を活かしながら、経営学の理論と実践の架け橋となる研究を続けてきました。
代表的な著書には、1989年に刊行された『ゼミナール経営学入門』があります。これは、経営学を学ぶ初心者向けの入門書として、多くの読者に親しまれてきました。本書『経営学とはなにか』は、これまでの研究成果を集大成した一冊であり、より実践的な経営学を伝えることを目的としています。

伊丹敬之氏は、経営学の理論だけでなく、実際の企業経営にも深く関与してきた学者です。
だからこそ、現場で役立つ視点を持ち、実践的な経営のあり方を説くことができるのです。
本書の要約
『経営学とはなにか』は、経営の基本原理をわかりやすく整理し、リーダーがどのように組織を動かし、意思決定をしていくべきかを解説した一冊です。大きく分けて二つの部分で構成されており、第一部では「経営行動の原理」、第二部では「企業の本質」について詳しく説明しています。
第一部では、組織の方向性を決めるための「立ち位置の設計」、将来を見据えた「戦略の策定」、効果的に組織を動かすための「影響力の発揮」、現場の自発性を高める「刺激の与え方」、そして経営者が常に直面する「想定外の出来事への対処」、最後に「意思決定の方法」について詳しく掘り下げています。
第二部では、企業という存在の本質を考えます。企業は単に利益を追求する場ではなく、技術や情報を蓄積し、社会に価値を生み出す組織であることが強調されています。また、経営者が企業をどのように統治し、どのように意思決定を行うべきかについても論じられています。
この本の特徴は、単に経営学の理論を説明するだけではなく、それを実際の企業経営にどのように活かせるのかを、具体的な事例を交えて紹介している点です。そのため、経営学の初心者から実務経験のある経営者まで、幅広い読者にとって実践的な学びが得られる内容になっています。

本書は、経営の基本原則をわかりやすく整理し、実際に経営の現場で活かせるように工夫されています。
経営学を初めて学ぶ人にも理解しやすく、経験者にとっても新たな視点を提供する一冊です。
本書の目的
本書の目的は、経営学を単なる理論ではなく、実際のビジネスの場で活用できる実学として提供することにあります。著者は、「経営する」という行為を「組織で働く人々の行動を導き、彼らの行動を生産的であり、成果につながるものにすること」と定義し、経営者が果たすべき役割を明確にしています。
経営を成功させるためには、まず組織の未来を見据えた設計図を描くことが大切です。そのうえで、チームを適切にマネジメントし、組織を円滑に動かすことが求められます。さらに、予測できない事態に柔軟に対応し、最適な意思決定を行うことが経営者にとって重要な役割になります。本書では、これらのポイントを体系的に整理し、読者が実際に経営の場で活用できるように解説しています。
また、本書は経営学の基礎を学ぶ人だけでなく、既に経営の実務に携わっている人にとっても、改めて経営の本質を考える機会を提供してくれます。自分の経営スタイルを見直し、より良い経営判断ができるようになることを目指して書かれています。

経営学は、単なる知識として学ぶだけではなく、実際の経営に応用して初めて価値が生まれます。
本書は、その点を重視し、理論と実践のバランスを考えた構成になっています。
人気の理由と魅力
『経営学とはなにか』が多くの読者に支持されている理由は、その実践的な内容と、著者の豊富な研究と経験に基づいた信頼性の高さにあります。
本書の大きな魅力の一つは、経営学の理論だけでなく、実際のビジネスの現場で使えるフレームワークを提供していることです。経営者や管理職が直面する具体的な課題について掘り下げ、組織の方向性の決め方や、意思決定の方法、リーダーシップの発揮の仕方など、すぐに実務で活用できる知識が多く含まれています。
また、日本企業の実例を豊富に取り入れている点も、本書の特徴です。海外の理論をそのまま適用するのではなく、日本企業ならではの経営環境や文化を踏まえた解説がなされており、日本のビジネス環境に適した経営学を学ぶことができます。

本書の魅力は、理論だけではなく、実践的な経営の知識が詰め込まれている点にあります。
経営者だけでなく、これから経営を学びたいと考えている人にもおすすめの一冊です。
本の内容(目次)

本書では、経営学の基本概念と実践方法を体系的に解説しており、理論と具体例を交えながら、経営の本質について詳しく掘り下げています。
本書は大きく分けて10の章から構成されており、それぞれの章で経営の重要な側面を取り上げています。
- はじめに
- 序章 経営学の全体像
- 第I部 経営行動の原理
- 第1章 組織の立ち位置を――未来への設計図を描く①
- 第2章 未来をめざす流れを設計する――未来への設計図を描く②
- 第3章 組織的な影響システムをつくる――他人を通して事をなす①
- 第4章 現場の自己刺激プロセスを活性化する――他人を通して事をなす②
- 第5章 想定外に対処する
- 第6章 決断する
- 第II部 企業という存在の本質
- 第7章 企業という存在の本質
- 第8章 本質と原理の交差点、そして企業統治
- 終章 経営を考えるための一六の言葉
経営学の理論を単なる知識ではなく、実務に活かす方法を学べる内容になっています。
各章の詳細を見ていきましょう。
はじめに
本書の冒頭では、経営学とは何かという根本的な問いについて考察しています。経営は単に企業を運営するための手法ではなく、組織のメンバーの行動を導き、生産性を高め、成果を生み出すためのプロセスであると定義されています。この考え方をもとに、経営者が果たすべき役割や、企業が持続的に成長するために必要な視点が示されています。
経営の本質は、「未来への設計図を描く」「他人を通して成果を生み出す」「想定外に対処する」「決断する」という四つの行動に集約されると本書では考えられています。これらの行動を適切に実行することが、組織を成功へと導く鍵となります。本書では、経営学の理論をわかりやすく整理しながら、実際の経営の現場でどのように活かせるのかを解説していきます。

経営は、計画通りに進むものではなく、変化に対応しながら組織を運営していくことが求められます。
本書の導入部分では、その基本的な考え方を学ぶことができます。
序章 経営学の全体像
本章では、経営学がどのような学問であり、どのような視点で整理されているのかを概観しています。経営学は、経済学や社会学、心理学といったさまざまな学問と関連しながら発展してきた分野であり、単なる企業の管理手法を学ぶものではありません。
また、本書で提示する経営学の枠組みがどのような特徴を持っているのか、他の学問とどのような関係があるのかについても説明されています。特に、企業の成長や組織運営におけるリーダーシップの役割が重要であることが強調されています。
さらに、本章では経営学を学ぶ意義についても触れています。経営学は、単なる理論ではなく、実際のビジネスの現場で活用できるものであり、経営者だけでなく、組織で働くすべての人にとって有益な学問であることが示されています。

経営学は、単なる知識の習得ではなく、組織をどう動かすかを考えるための学問です。
本章では、その全体像を理解することができます。
第1章 組織の立ち位置を設計する――未来への設計図を描く①
企業が成長し続けるためには、自社の立ち位置を明確にし、そのポジションをどう維持・強化していくのかを考えることが重要です。本章では、企業が市場の中でどのような役割を果たすべきかを検討し、それを実現するための戦略について解説しています。
市場における立ち位置を決める際には、製品やサービスの特徴、ターゲット顧客、競争環境などを総合的に考慮する必要があります。単に売上を伸ばすだけではなく、持続可能な成長を実現するための方針を定めることが重要です。そのため、本章では立ち位置のコンセプト設計、製品・顧客構造の設計、供給力の強化といった具体的な手法が紹介されています。
また、企業の立ち位置を決めることは、組織の方向性を明確にすることにもつながります。経営者やリーダーは、組織全体のビジョンを描き、それを実現するための仕組みを作ることが求められます。本章では、こうした視点から、企業がどのように戦略を立案し、実行していくべきかについて具体的に説明されています。

企業の成功は、「どんな市場で、どのような価値を提供するか」を正しく定義することから始まります。
立ち位置を戦略的に考えることで、持続的な成長が可能になるのです。
第2章 未来をめざす流れを設計する――未来への設計図を描く②
企業が持続的に発展するためには、現在の状況を維持するだけではなく、未来に向けた戦略を明確に描くことが不可欠です。本章では、組織がどのように成長していくのか、そのプロセスを設計するための方法について詳しく解説されています。
企業の成長には、能力の蓄積や市場との関係構築、技術革新への投資が重要な役割を果たします。特に、本章では能力基盤の拡大や情報蓄積を加速する「仕事」の構造設計、イノベーションプロセスの構築といったテーマが取り上げられています。
また、未来を見据えた経営では、単に短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点での成長戦略を描くことが求められます。本章では、「筋のいい技術を育てる」「需要を大きく育てる」といった戦略が紹介され、企業が持続的に発展するために必要な要素が整理されています。
企業の成長戦略を考える際には、市場の変化に柔軟に対応しながら、経営資源をどのように活用していくのかを検討する必要があります。本章では、そうした視点をもとに、企業がどのように成長の流れを作るべきかが詳しく説明されています。

企業が成長し続けるためには、単なる現状維持ではなく、未来に向けた「流れ」を作ることが不可欠です。
流れを意識することで、戦略がより明確になり、成長が加速します。
第3章 組織的な影響システムをつくる――他人を通して事をなす①
経営者やリーダーの役割は、単に指示を出すことではなく、組織全体を適切に機能させる仕組みをつくることにあります。本章では、組織が円滑に運営され、成果を生み出すために必要な「影響システム」の構築について解説しています。
組織をうまく動かすためには、「管理する」のではなく、「影響を与える」ことが重要です。リーダーが持つ影響力は、組織の構造や意思決定のプロセス、コミュニケーションの仕組みによって大きく左右されます。そのため、本章では、役割と権限のシステム、調整やフィードバックの仕組み、インセンティブの設計といった具体的な方法が紹介されています。
また、組織を効率的に動かすためには、単なる業務の割り振りではなく、メンバーが自発的に動ける環境を整えることが求められます。そのためには、適切な権限の分配や、組織内の調整プロセスが重要になります。本章では、こうした観点から、経営者がどのように組織の影響力を設計すべきかについて具体的な方法が提示されています。

リーダーの役割は、組織を直接管理することではなく、組織が自律的に動く仕組みを作ることにあります。
組織的な影響システムを構築することで、メンバーが主体的に行動し、成果を生み出す環境を整えることができます。
第4章 現場の自己刺激プロセスを活性化する――他人を通して事をなす②
組織の活性化には、トップダウンの指示だけではなく、現場の自発的な行動が不可欠です。本章では、現場が自ら考え、行動し、組織全体の生産性を向上させるための仕組みについて解説しています。
現場の活性化には、リーダーの働きかけが重要です。理念を明確に示し、企業文化をつくることで、社員が自分の仕事に意味を見出し、モチベーションを高めることができます。また、ヨコの相互刺激を生み出す「場」をつくることで、現場のメンバーが互いに学び、成長する機会を増やすことができます。本章では、こうした組織文化の形成や、現場のエネルギーを高めるための方法が説明されています。
また、組織全体の勢いを生み出すためには、単に業務をこなすだけではなく、現場での創意工夫を促す仕組みも必要になります。そのため、本章では、リーダーがどのようにメンバーのやる気を引き出し、組織全体の活力を高めるかについても具体的に説明されています。

組織の現場が活性化することで、従業員は自発的に動き、創造的なアイデアが生まれやすくなります。
リーダーの役割は、現場の自主性を引き出し、成長を促す環境を整えることにあります。
第5章 想定外に対処する
経営の現場では、計画通りに進むことはほとんどありません。どれだけ綿密に戦略を立てても、突発的な問題や予測不能な出来事が発生することは避けられません。本章では、そうした「想定外」の事態に対処するための考え方と手法を解説しています。
想定外の事態に対応するためには、まず冷静に状況を分析し、適切な判断を下す力が必要です。パニックに陥ることなく、客観的に情報を整理し、優先順位をつけて行動することが求められます。また、日頃からリスク管理の仕組みを整えておくことで、トラブル発生時の対応をスムーズにすることができます。
事後的な対応だけでなく、事前の備えも重要です。想定外の出来事が起こった際にどのように対応するのか、あらかじめシミュレーションを行い、組織全体で危機対応の準備をしておくことで、実際の問題発生時に迅速かつ的確な対応が可能になります。本章では、具体的な危機対応の手順について詳しく解説しています。

想定外の出来事は、どの企業にも起こりうるものです。
重要なのは、それに対して適切に対処できる準備をしておくことです。
事前の備えがあるかどうかで、組織の対応力が大きく変わります。
第6章 決断する
経営において、決断は最も重要な仕事の一つです。リーダーは日々さまざまな判断を下す必要がありますが、その決断の質が企業の将来を左右します。本章では、効果的な決断を行うための考え方とプロセスについて解説しています。
優れた決断には、論理的な思考と直感的な判断のバランスが求められます。論理的な分析だけでは時間がかかりすぎることがあり、一方で直感に頼りすぎるとリスクが高まります。重要なのは、情報を的確に収集し、状況を分析した上で、最適なタイミングで意思決定を行うことです。
また、決断を下す際には、自らの価値観や哲学を持つことも大切です。経営においては、短期的な利益だけでなく、長期的なビジョンを持ち、その実現に向けた判断を下す必要があります。決断の背景には、企業の方向性を支える「哲学」が必要であり、それがあることで、より一貫性のある判断が可能になります。
本章では、著者が提唱する「決断の原則」をもとに、実践的な意思決定のプロセスについて説明しています。リーダーが持つべき視点や考え方について、多くの事例を交えながら詳しく解説しています。

リーダーの決断力が企業の成長を左右します。
優れた決断を行うためには、論理と直感のバランスを取り、自らの価値観を持つことが重要です。
第7章 企業という存在の本質
企業とは何か? 本章では、企業が持つ本質的な役割や構造について考察しています。企業は単なる利益追求の場ではなく、価値を生み出し、社会に貢献する組織であるという視点が強調されています。
企業の本質として挙げられるのは、大きく分けて三つの要素です。一つ目は、技術的な変換機能です。企業は、原材料や人的資源を活用し、製品やサービスを生み出す存在です。二つ目は、情報蓄積の場としての役割です。企業は、技術やノウハウ、組織文化などを蓄積し、それを次世代へ継承していきます。三つ目は、資本と人材が結びつく結合体であるという点です。企業は、資本(カネ)と人材(ヒト)が結びつくことで成立しており、この二つのバランスが企業経営の根幹となります。
また、企業の成長には、経営者の倫理観や価値観も大きく影響します。特に、短期的な利益を追求するだけではなく、長期的な視点で企業の持続性を考えることが重要です。本章では、企業の本質を理解し、どのように経営戦略を立てるべきかについて解説されています。

企業は単なる営利組織ではなく、社会の中で価値を創造し、知識を蓄積する場でもあります。
この視点を持つことで、経営の本質をより深く理解できるようになります
第8章 本質と原理の交差点、そして企業統治
企業経営は、単にビジネスを運営することではなく、経営の本質を理解した上で、企業統治(コーポレートガバナンス)を適切に機能させることが求められます。本章では、企業の本質と経営原理の交差点に立つ経営者の役割について解説されています。
企業の本質を考えると、経営者が取るべき行動が見えてきます。しかし、企業の本質には矛盾が内在しており、利益追求と社会的責任のバランス、短期的な成果と長期的な成長のバランスなど、さまざまなジレンマが生じます。本章では、これらの矛盾にどのように対処し、適切な経営判断を下すべきかについて議論されています。
また、企業統治の仕組みについても詳しく説明されています。企業統治とは、経営者が適切な意思決定を行うための仕組みであり、株主や取締役、従業員など、さまざまなステークホルダーとの関係が重要になります。本章では、企業統治のあり方や、経営者がどのように自己を律し、健全な経営を行うべきかについても具体的に解説されています。

企業は、利益だけでなく、社会的責任や組織の健全性も考慮しながら運営する必要があります。
経営の意思決定には、複数の視点を持つことが欠かせません。
終章 経営を考えるための一六の言葉
本書の最後では、経営を考える上で重要な視点を整理し、16の言葉としてまとめられています。これらの言葉は、経営者やリーダーが直面する課題に対して、指針となるものです。
本書を通じて、経営は単なる管理業務ではなく、未来を描き、組織の活力を引き出しながら、意思決定を行っていくプロセスであることが強調されてきました。終章では、その考え方をより深く理解し、実際の経営の現場で活かすためのヒントが提示されています。

経営には、明確な答えがあるわけではありません。
だからこそ、自分なりの考えを持ち、経験を積みながら成長していくことが大切です。
本書の内容を活かしながら、実践の中で学び続けることが求められます。
対象読者

本書『経営学とはなにか』は、経営学を体系的に学びたい人だけでなく、実際に組織を運営する立場の人々にも役立つ内容が詰まっています。
特に以下のような人々にとって、本書は経営に対する理解を深め、実践に活かすための示唆を与えてくれる一冊となるでしょう。
- 経営学を学ぶ学生
- 企業の経営者
- 管理職・マネージャー
- 起業家
- ビジネスパーソン
それぞれの読者層に向けた本書の魅力を詳しく見ていきます。
経営学を学ぶ学生
経営学を学び始めたばかりの学生にとって、本書は経営学の基本的な考え方を理解するのに最適な一冊です。学問としての経営学は、単なる理論の積み重ねではなく、実際の企業経営に応用できる知識を学ぶことが重要です。本書では、経営の原理を明快なフレームワークとして整理し、初心者でも理解しやすいように解説されています。
また、経営学は単なる知識の習得ではなく、実際に経営の現場でどのように活用されるのかを知ることが大切です。本書には、企業の実例や著名な経営者・学者の考え方がコラムとして紹介されており、理論と実践のつながりを意識しながら学ぶことができます。

経営学の知識を学ぶだけではなく、それをどのように活かすかが重要です。
本書を読むことで、経営の現場で実際にどのように考え、行動するべきかを具体的に学べます。
企業の経営者
企業のトップに立つ経営者にとって、日々の意思決定は非常に重要な仕事です。組織のビジョンを描き、それを実現するために社員を導きながら、環境の変化に適応しなければなりません。しかし、経営の判断には常にリスクが伴い、確実な正解があるわけではありません。本書では、経営者がどのような視点を持ち、どのように意思決定を行うべきかについて、具体的なフレームワークを提示しています。
また、企業は単に利益を追求する組織ではなく、社会の中で役割を果たす存在でもあります。本書では「企業とは何か?」という根本的な問いにも触れながら、経営者が持つべき視点について詳しく解説されています。企業の方向性を見直したい、経営の基本に立ち返りたいと考えている経営者にとって、本書は示唆に富んだ一冊となるでしょう。

管理職・マネージャー
企業の中間管理職やマネージャーは、経営層と現場をつなぐ役割を担いながら、チームの成果を最大化することが求められます。しかし、部下のモチベーションを高める方法や、組織全体の方向性に合わせた業務の進め方について悩むことも多いのではないでしょうか。本書では、組織の動きをスムーズにし、社員の行動を生産的なものにするためのフレームワークが詳しく解説されています。
また、「他人を通して事をなす」ことの重要性にも触れられています。管理職は自分一人で成果を上げるのではなく、チーム全体を活性化させることが仕事です。そのためには、単に指示を出すだけでなく、適切な環境を整え、社員が主体的に動けるようにする工夫が必要になります。本書を読むことで、効果的なマネジメントの考え方を学ぶことができるでしょう。

管理職の役割は、単なる業務管理ではなく、チーム全体のパフォーマンスを向上させることです。
本書を通じて、組織を動かすための具体的な方法を学びましょう。
起業家
新たに事業を立ち上げる起業家にとって、経営の知識は必要不可欠です。起業を成功させるためには、単に良いアイデアを持っているだけでは不十分であり、ビジョンを実現するための戦略や組織運営の方法を理解しておく必要があります。本書では、事業の方向性を決め、組織を構築し、変化に対応しながら成長させるための具体的な考え方が紹介されています。
また、起業家にとっての大きな課題の一つが「決断」です。市場環境が変化する中で、どのタイミングで何を選択すべきかを判断するのは容易ではありません。本書では、決断のプロセスや、優れたリーダーが持つべき視点について詳しく解説されており、起業家が経営判断を行う際のヒントが得られます。

起業家にとって、経営の知識を身につけることは、事業の成功確率を高める重要な要素です。
本書を活用して、事業を成長させるための戦略を学びましょう。
ビジネスパーソン
経営者や管理職だけでなく、一般のビジネスパーソンにとっても、本書は非常に役立つ内容が含まれています。普段の仕事の中で、経営の視点を持つ機会は少ないかもしれませんが、企業の仕組みを理解することで、より戦略的に働くことができるようになります。本書では、組織の中で自分の役割をどのように考え、成果を上げるために何が必要なのかを学ぶことができます。
また、想定外の事態に対処する力や、適切な判断を下すための考え方についても詳しく解説されています。ビジネスの現場では、計画通りに物事が進むことは少なく、柔軟な対応が求められる場面が多々あります。本書を読むことで、変化に適応しながら仕事を進める力を身につけることができるでしょう。

経営の視点を持つことで、日々の仕事の意義をより深く理解することができます。
本書を通じて、自分のキャリアをより戦略的に考えるきっかけを得ましょう。
本の感想・レビュー

経営学の基礎として最適な一冊
この本を読み終えて、経営学の本質とは何なのか、改めて深く考えさせられました。経営というものは単なる知識の蓄積ではなく、実際に組織を動かし、人を導き、想定外の出来事にも柔軟に対応する力が求められるものだと感じます。本書では、「経営学とはなにか?」という問いに対して、単なる理論の説明にとどまらず、経営の現場で直面するリアルな課題に焦点を当てながら、学問としての経営学の全体像を丁寧に整理しているのが印象的でした。
特に、経営学を学ぶうえで重要な概念やフレームワークを網羅的に扱っており、初心者にとっても体系的に理解しやすい構成になっています。経営学に初めて触れる人でも、経営とはどのような営みなのか、なぜ学ぶ価値があるのかが明確に伝わってきます。実際に企業経営に携わっている人はもちろん、これから経営を学ぼうとしている人にとっても、最適な入門書だと感じました。
また、経営学の枠組みが単なる理論ではなく、実際の経営者の視点を交えながら説明されている点も魅力的でした。経営学が「現場の悩みに応える実学」であることが、この本を通じて強く伝わってきます。これまで「経営学=難解な理論」と思い込んでいた人も、この本を読むことで経営の実践的な側面に気づき、興味を持てるのではないでしょうか。
実践に活かせるフレームワークが魅力
本書の魅力は、単なる理論の説明ではなく、実際の経営に役立つフレームワークが豊富に紹介されていることです。経営学を学ぶ上で、「理論と実践の橋渡し」は非常に重要なポイントですが、本書ではその点が非常に意識されており、読者が実際の経営の現場で活用できるように構成されています。
印象的だったのは、経営行動の基本として挙げられている「未来への設計図を描く」「他人を通して事をなす」「想定外に対処する」「決断する」という4つの行動原則です。このシンプルな枠組みがあることで、経営という仕事の本質が明確になり、どのように行動すればよいのかの道筋が見えてきます。
また、本書ではそれぞれの行動に関して、具体的なケースや経営者の視点が紹介されており、単なる理論ではなく、実際の経営の現場でどのように活かされるのかがわかりやすく説明されています。特に、「他人を通して事をなす」という考え方は、経営者にとって最も重要なスキルの一つであると感じました。どれだけ優れた戦略を持っていても、実際に動くのは組織のメンバーであり、彼らが力を発揮できる環境を作ることが、経営者に求められる最も大切な役割なのだと実感しました。
このように、本書は単なる知識のインプットではなく、読者が経営の実務に活かせる具体的なフレームワークを提供してくれる一冊だと感じました。
読みやすく、初心者にも理解しやすい
経営学の本というと、専門的な用語や難しい理論が並んでいて、初心者にはとっつきにくい印象があります。しかし、本書はそうした壁を感じさせず、スムーズに読み進められるよう工夫されています。難解な言葉や専門用語が少なく、著者の語り口が非常にわかりやすいため、経営学を初めて学ぶ人でも無理なく理解できる内容になっています。
また、各章の構成が明確で、「経営学とは何か?」という基本的な問いから始まり、それを具体的なフレームワークや実例と結びつけながら解説しているため、全体の流れが非常にスムーズでした。特に、各章の最後に設けられている「経営者コラム」や「学者コラム」は、経営に関する知識をより深めるための良い補助となっており、単なる教科書的な説明だけでなく、リアルな経営の現場に即した視点を提供してくれます。
経営者に必要な意思決定の重要性を強調
経営者にとって最も重要な仕事の一つが「意思決定」です。本書では、意思決定とは単なる選択ではなく、時には大きな飛躍を伴うものであり、それが企業の未来を左右することを強調しています。
意思決定には「論理的な判断」と「直感的なひらめき」の両方が必要であり、それを支えるのが経営者自身の経験や哲学であることが本書を通じてよく伝わってきました。特に、意思決定の際に求められる「跳躍のための哲学」という考え方は非常に印象的で、経営者が持つべき視座について深く考えさせられました。
本書を読んで、経営者の意思決定は単なるデータ分析や戦略立案だけではなく、長年の経験や価値観に根ざしたものであるべきだと改めて実感しました。
想定外への対応力が鍛えられる内容
本書の中で特に印象的だったのは、「想定外への対処」というテーマが経営学の枠組みの中でしっかりと位置づけられていたことです。経営の現場では、計画通りに物事が進むことの方が少なく、予期しないトラブルや環境の変化に直面することが多々あります。本書では、そのような状況にどう対応すべきかについて具体的な視点を提供しており、経営者やマネージャーにとって非常に実践的な内容になっています。
特に、「想定外は必ず起こる」という前提に立ち、事前の準備や事後の対応の仕方について考えさせられる部分が多くありました。何か問題が起こったときに慌てるのではなく、冷静に判断し、適切なアクションを取ることの重要性が強調されており、危機管理能力を高めるためのヒントが随所に散りばめられています。
また、想定外に対応する力は、単なるスキルではなく、組織全体の文化や仕組みと密接に結びついていることも本書を通じて学ぶことができました。経営者だけでなく、組織全体が柔軟性を持ち、変化に対応できるような体制を整えることが重要であると改めて感じました。
学者・経営者のコラムが学びを深める
本書の特徴の一つとして、各章の終わりに経営者や学者のコラムが掲載されている点が挙げられます。これらのコラムは、単なる知識の補足にとどまらず、著者が実際にどのように彼らから影響を受けたのかという視点が含まれているため、読者にとっても非常に示唆に富んだ内容となっています。
特に印象的だったのは、著名な経営者や学者の考え方が、経営の実践とどのように結びついているのかが具体的に語られている点です。経営学の理論を学ぶだけではなく、それを実際に実践した人々の視点を知ることで、経営というものが単なる理論ではなく、生きた学問であることを実感できました。
また、著者自身がどのように経営の知見を深めてきたのか、そのプロセスを垣間見ることができるのも興味深かったです。理論と実践の両方をバランスよく学ぶことで、経営というものをより立体的に理解できる構成になっていると感じました。
企業統治とリーダーの役割について考えさせられる
本書の中で特に印象に残ったのは、企業統治とリーダーシップに関する考察です。経営者は単に会社を運営するだけでなく、社会的な責任を果たしながら、組織を適切に統治していく必要があります。本書では、そのためにどのような考え方が求められるのかが詳細に論じられています。
企業統治のあり方については、ステークホルダー資本主義の視点からの考察もあり、経営者が誰のために意思決定を行うべきなのかについて考えさせられました。株主だけでなく、従業員や顧客、社会全体に対して責任を持つことの重要性が強調されており、現代の経営者にとって避けて通れない課題であることがよく伝わってきました。
また、リーダーシップの在り方についても、単なる権限の行使ではなく、組織に影響を与え、メンバーの力を引き出すことが重要であるという視点が貫かれていました。経営者としての役割を改めて見直し、どのように組織を導いていくべきかを深く考えさせられる内容でした。
経営戦略のヒントが詰まっている
本書には、実際の経営戦略に活かせる具体的なヒントが多く詰まっています。経営学を単なる学問として学ぶのではなく、実践に活かすための視点が随所に散りばめられている点が魅力的でした。
特に、「未来への設計図を描く」というテーマでは、企業がどのように成長していくべきかを考える際の視点が詳細に解説されています。立ち位置のコンセプト設計や、製品・顧客構造の設計など、企業の方向性を決める上で必要な要素が具体的に述べられています。
また、「イノベーションプロセスの構造設計」や「需要を大きく育てるための構造設計」など、成長戦略に関する具体的な方法論も学ぶことができました。企業が新たな市場を開拓する際にどのようなアプローチを取るべきか、どのように情報を蓄積し、活用していくべきかが論理的に整理されており、実務に直結する内容だと感じました。
これまでの経営書の中には、成功事例を紹介するものの、それをどのように自社に応用すればよいのか分かりづらいものも多くありました。しかし、本書は経営戦略の基本原理を解説しながら、それを具体的にどう活かすべきかが示されており、実践的な視点で学ぶことができました。
まとめ

本書『経営学とはなにか』は、経営の基本原理を分かりやすく解説しながら、実際のビジネスに活かせるフレームワークを提供する一冊です。
ここでは、本書を読むことで得られるメリット、読後に取るべきステップ、そして本書の総括について紹介します。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれ詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
本書は、単なる経営理論の解説にとどまらず、実践的なフレームワークや具体的な事例を交えて、経営の本質を深く理解できる内容になっています。
この本を読むことで得られるメリットを以下のように整理しました。
経営学の体系的な知識を学べる
経営学は幅広い分野を扱う学問ですが、本書では「未来への設計図を描く」「他人を通して事をなす」「想定外に対処する」「決断する」といった具体的な経営行動の流れに沿って、経営学を体系的に学ぶことができます。バラバラな知識を詰め込むのではなく、一連の流れの中で理解できるため、初心者でもスムーズに学習を進められます。
実際の企業運営に役立つフレームワークを学べる
本書では、企業経営の実践に役立つフレームワークが豊富に紹介されています。例えば、「未来への設計図」を描く際の判断基準や、組織を動かすためのインセンティブシステムの設計など、実務に応用しやすい知識が詰まっています。企業経営に携わる人にとっては、すぐに実践に活かせるヒントが満載です。
リーダーシップと意思決定の重要性を学べる
経営者や管理職にとって、的確な意思決定を行うことは非常に重要です。本書では、決断のプロセスを「直感」「論理」「哲学」という視点で整理し、より良い意思決定を行うための方法を提示しています。経営の現場では、論理的な分析だけではなく、時には直感を信じて決断することも必要です。本書は、そのバランスを取るための考え方を学ぶ上で大いに役立ちます。
実際の経営者の考え方や経験から学べる
本書の各章には、著名な経営者や学者に関するコラムが掲載されています。例えば、小倉昌男や本田宗一郎など、実際に成功を収めた経営者の思考プロセスや決断の背景を知ることができます。これらのエピソードを通じて、経営者のリアルな判断基準やリーダーシップのあり方を学ぶことができます。

本書は、経営学を体系的に学べるだけでなく、実務に活かせる実践的な知識が詰まっています。
経営者や管理職だけでなく、ビジネスの現場で活躍するすべての人にとって有益な一冊です。
読後の次のステップ
本書『経営学とはなにか』を読み終えた後、得た知識をどのように実践に活かしていくかが重要です。
経営学は単なる理論ではなく、実際のビジネスシーンで応用できる知識です。
本を読んで満足するだけでなく、学んだことを活かすことで、経営者や管理職、ビジネスパーソンとしてのスキルを高めることができます。
ここでは、本書を読んだ後に取るべき具体的なステップを紹介します。
step
1本書の内容を振り返り、自分の課題と照らし合わせる
まず、本書で学んだ内容を振り返り、自分のビジネスや職務において、どの部分が最も関係が深いのかを考えてみましょう。例えば、「未来への設計図を描く」というテーマが重要であれば、現在の事業やプロジェクトがどのような立ち位置にあるのかを改めて整理し、方向性を明確にすることが求められます。
step
2実際の経営や仕事において活かせるポイントをリストアップする
本書には、企業運営やリーダーシップに関する実践的なフレームワークが多く紹介されています。その中で、自分の仕事に直接応用できるものをリストアップし、日々の業務に落とし込んでみましょう。たとえば、チームを動かす仕組みとして「影響を与える」ことの重要性が説かれていましたが、それを実際にどのように実践するのかを考えることが重要です。
step
3経営学の知識を日常業務の中で意識的に活用する
経営学の知識は、一度読んで終わりではなく、日々の業務の中で意識的に活用することが重要です。例えば、本書で紹介されている「決断する」というテーマを意識して、日常の小さな意思決定の場面でも論理的思考や直感の活用を意識することで、より実践的なスキルとして定着させることができます。
step
4経営学を実践するための研修やセミナーに参加する
書籍を読むだけではなく、実際に学びを深める場に参加することで、より実践的な知識を身につけることができます。企業が開催するマネジメント研修や、経営学を学ぶためのオンライン講座、MBAプログラムなどを活用するのも一つの方法です。こうした場での学びは、書籍では得られない実際の事例や、他のビジネスパーソンとの交流を通じて新たな視点を得るきっかけになります。
step
5成功事例や失敗事例を記録し、振り返る習慣をつける
経営学を実践する上で、成功事例や失敗事例を記録し、定期的に振り返ることも大切です。本書を読んで学んだ知識を実際に活かしてみた結果、何がうまくいったのか、どこに課題があったのかを分析することで、より実践的な理解を深めることができます。

本書を読んで終わりにするのではなく、実際に学びを仕事に活かすために、小さな行動からでも始めてみることが重要です。
一歩ずつ実践することで、経営学の知識がより深く身につき、実際のビジネスで成果を上げることにつながります。
総括
『経営学とはなにか』は、経営の本質を深く掘り下げながら、実際のビジネスの現場で活かせる知識を提供する一冊です。本書は、経営とは単なる管理ではなく、組織の中で人を動かし、未来を設計し、想定外の事態に対応しながら意思決定を重ねることであると説いています。著者の伊丹敬之氏は、長年の研究と実務経験をもとに、経営学を単なる理論ではなく「生きた知識」として示しており、実際の経営現場に携わる人々にとって貴重な指南書となっています。
本書の魅力は、単なる学問的な知識を提供するだけでなく、実際の企業経営の中でどのように意思決定をすべきか、どのように組織を動かすべきかといった実践的な視点を豊富に盛り込んでいる点です。特に、経営の要素を「未来を描く」「組織を動かす」「想定外に対応する」「決断する」という4つのステップに整理し、それぞれを具体的なフレームワークとして解説している点は、非常にわかりやすく、読者がすぐに実務に応用できる内容となっています。
また、本書は初心者にも理解しやすい構成になっている一方で、経営の経験がある人にとっても新たな気づきを与える内容となっています。経営の現場では、理論だけではなく、経験や直感、そして時には哲学的な思考が求められます。本書は、そうした「知識と実践」の橋渡しをしてくれる貴重な一冊です。企業の経営者はもちろん、管理職や起業を考えている人、そして経営学を学ぶ学生にとっても、多くの学びを得られるでしょう。

経営に関する知識をさらに深めるためには、他の経営学書を読むことや、実際のビジネスの現場で実践してみることが重要です。
また、経営者やビジネスリーダーがどのように意思決定を行い、組織を運営しているのかを観察することで、よりリアルな経営の感覚を身につけることができます。
本書を通じて、経営に対する理解を深め、実際のビジネスの場で活かしていくことで、より良い経営者、リーダーへと成長できるでしょう。
経済学に関するおすすめ書籍

経済学に関するおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 経営学について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 世界標準の経営理論
- ゼミナール経営学入門(新装版)
- 経営学とはなにか
- 今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」
- 図解 人的資本経営 50の問いに答えるだけで「理想の組織」が実現できる
- サクッとわかる ビジネス教養 経営学
- 実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた

