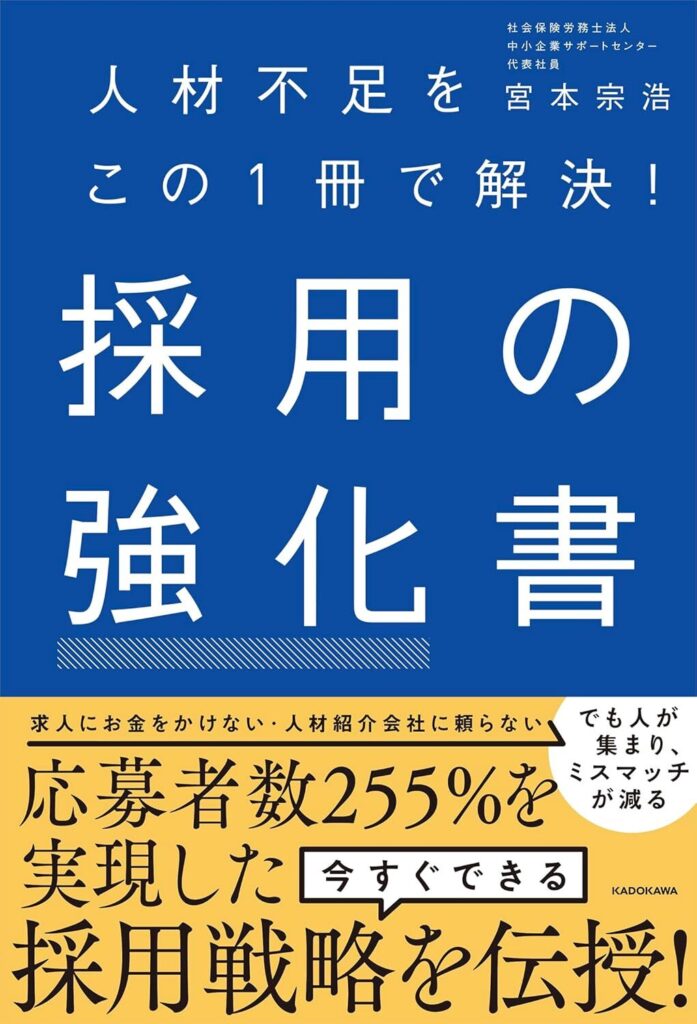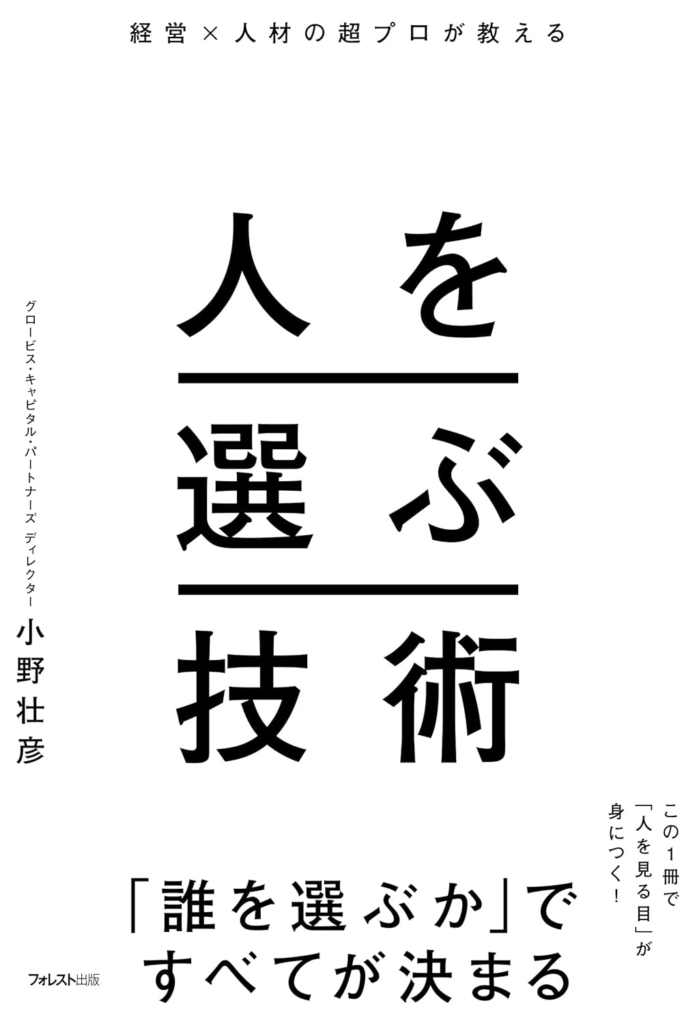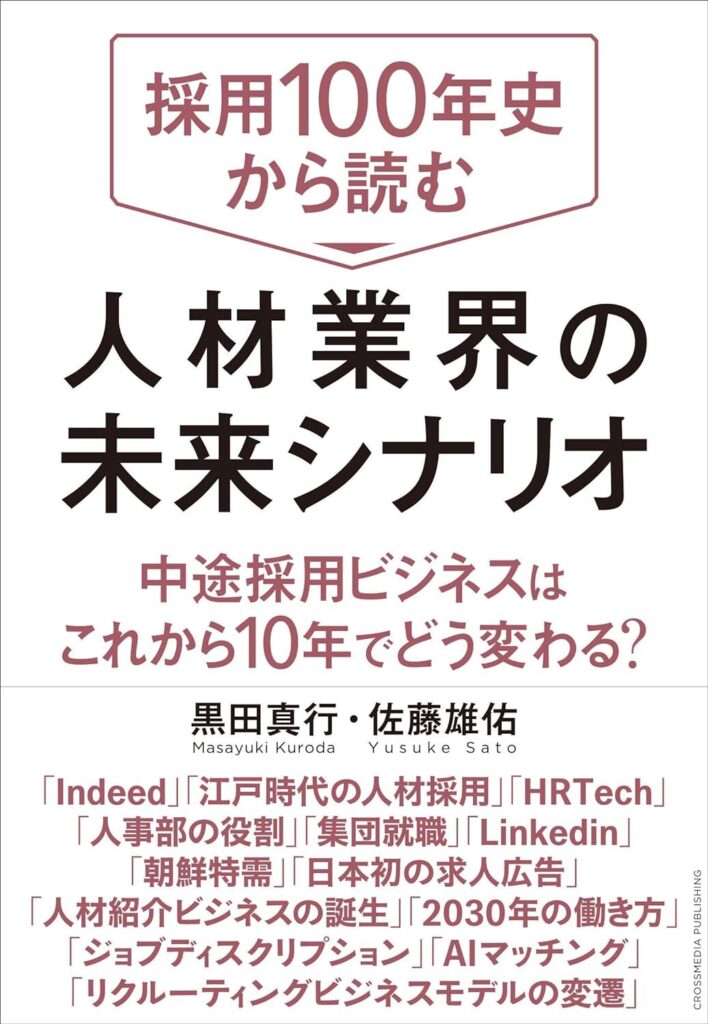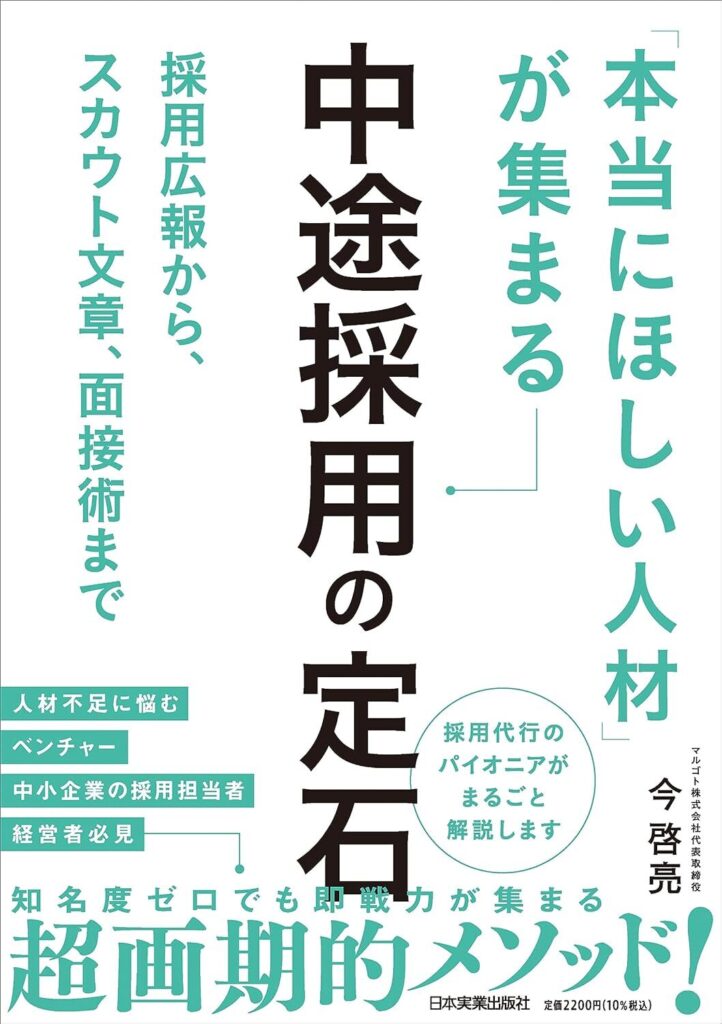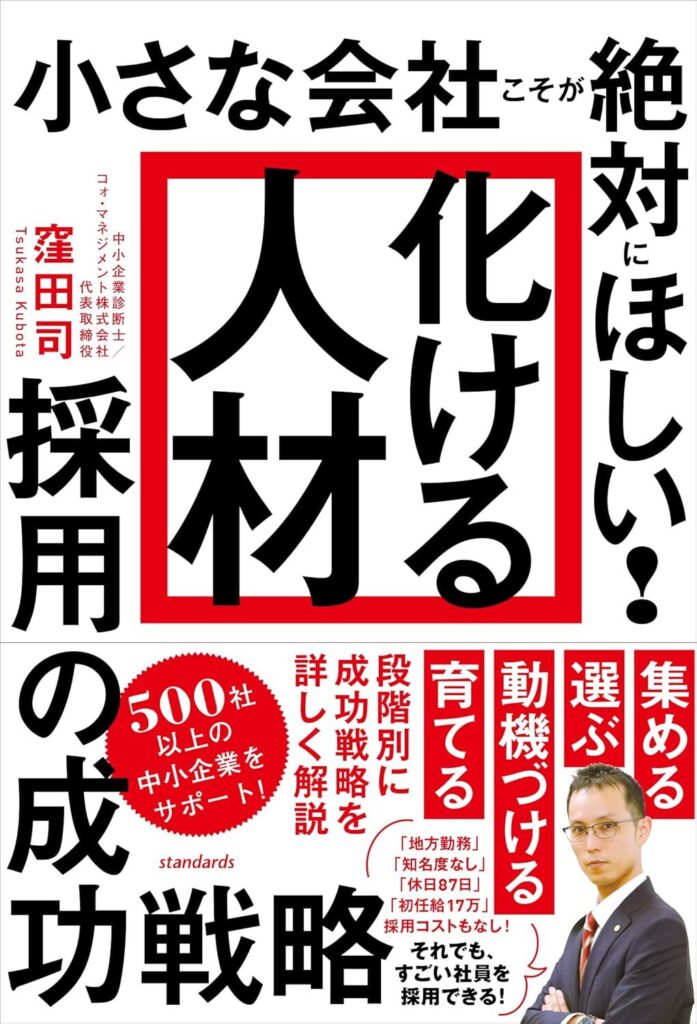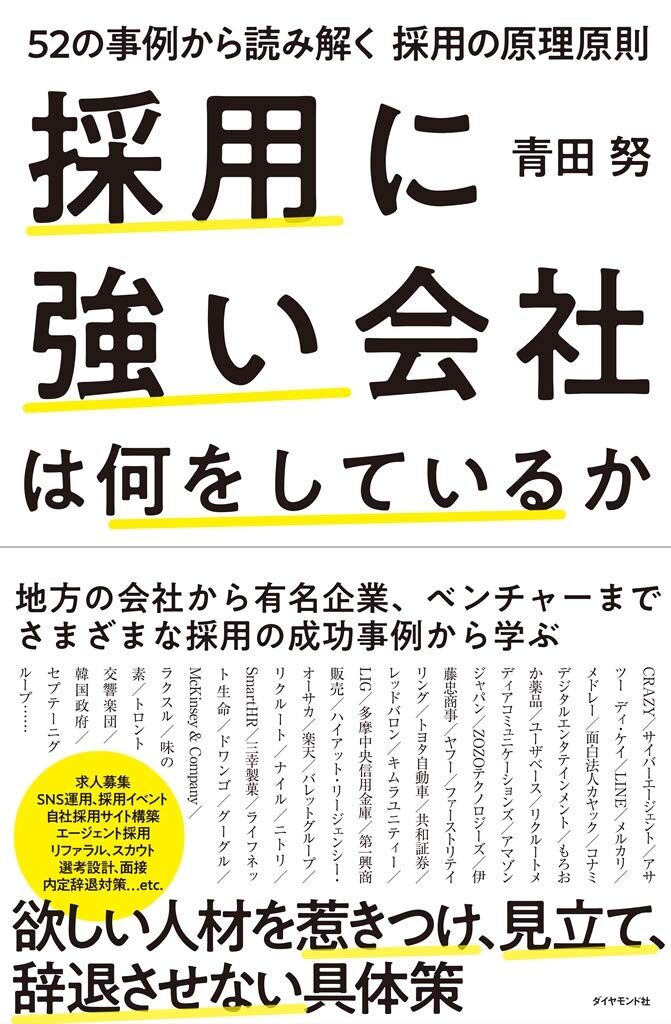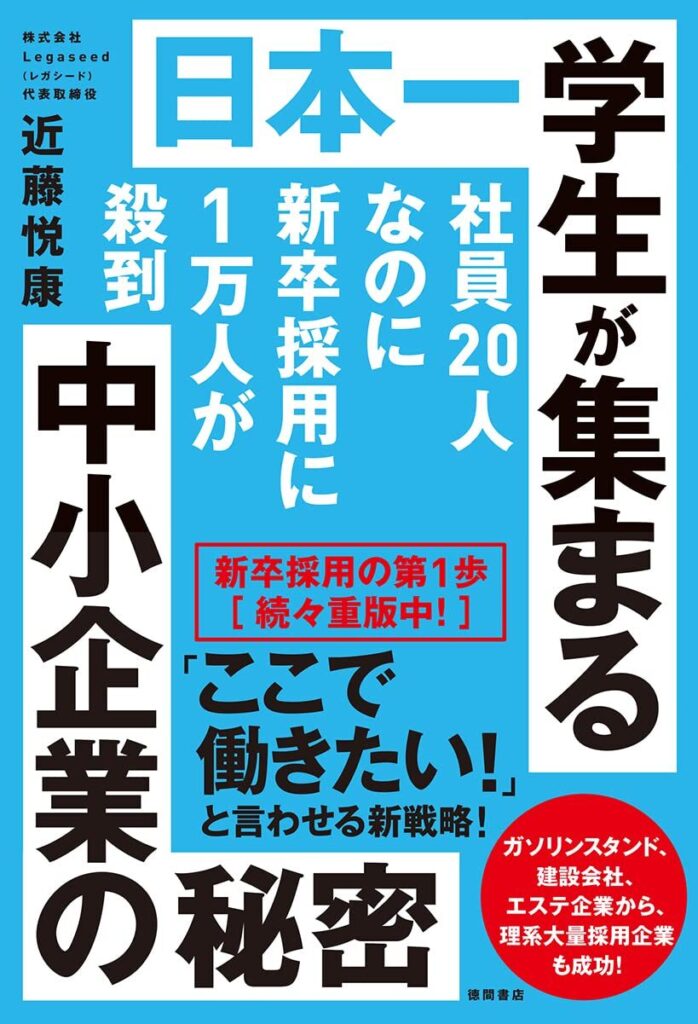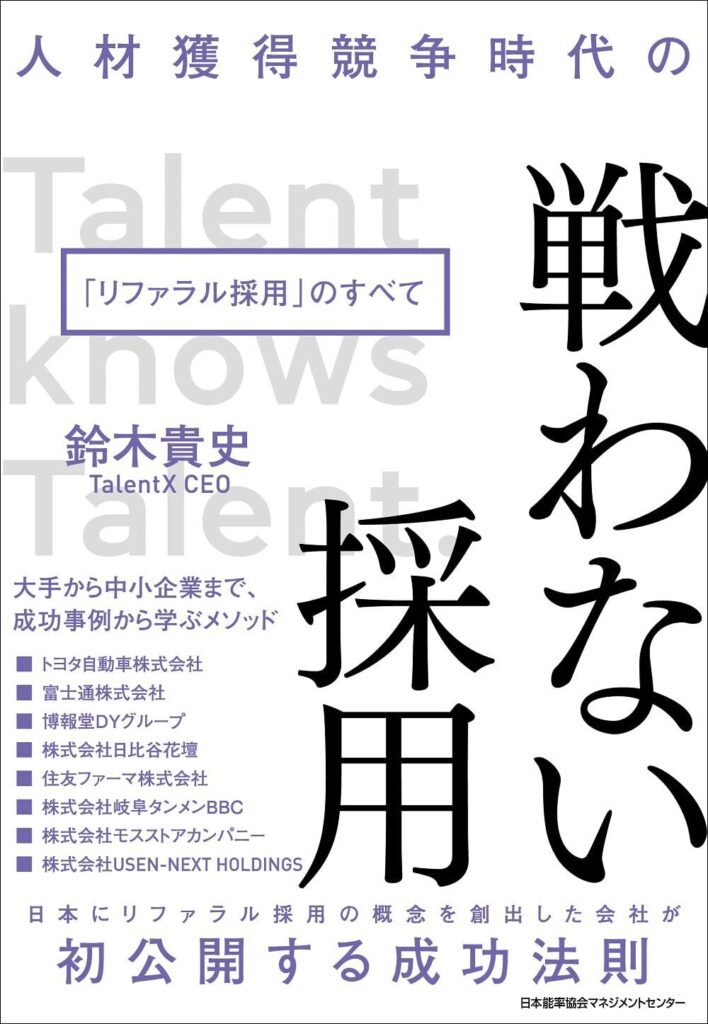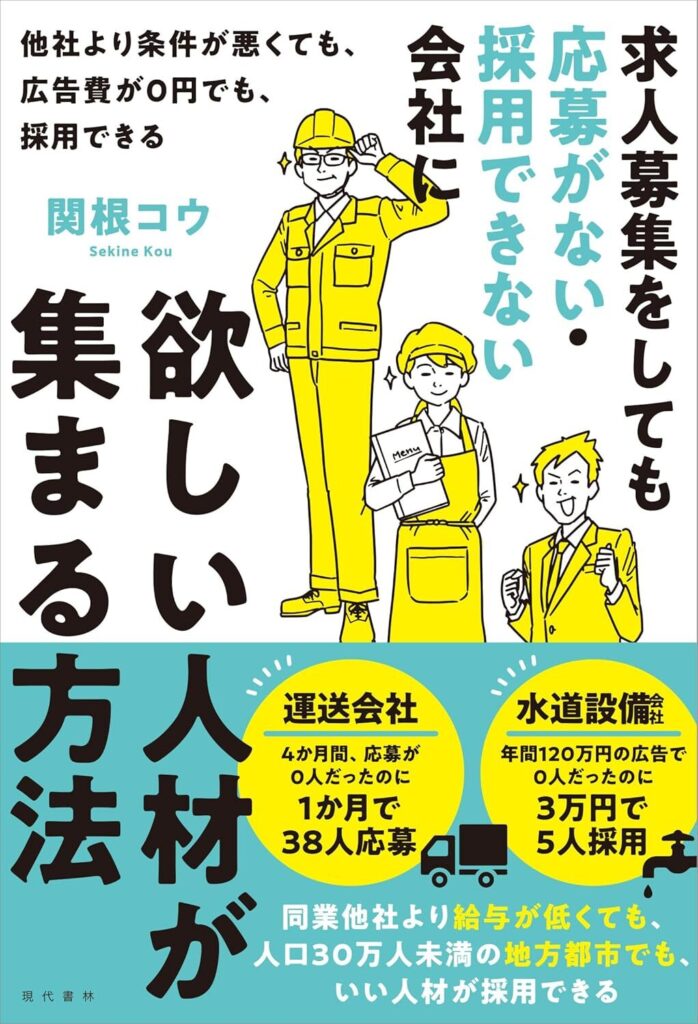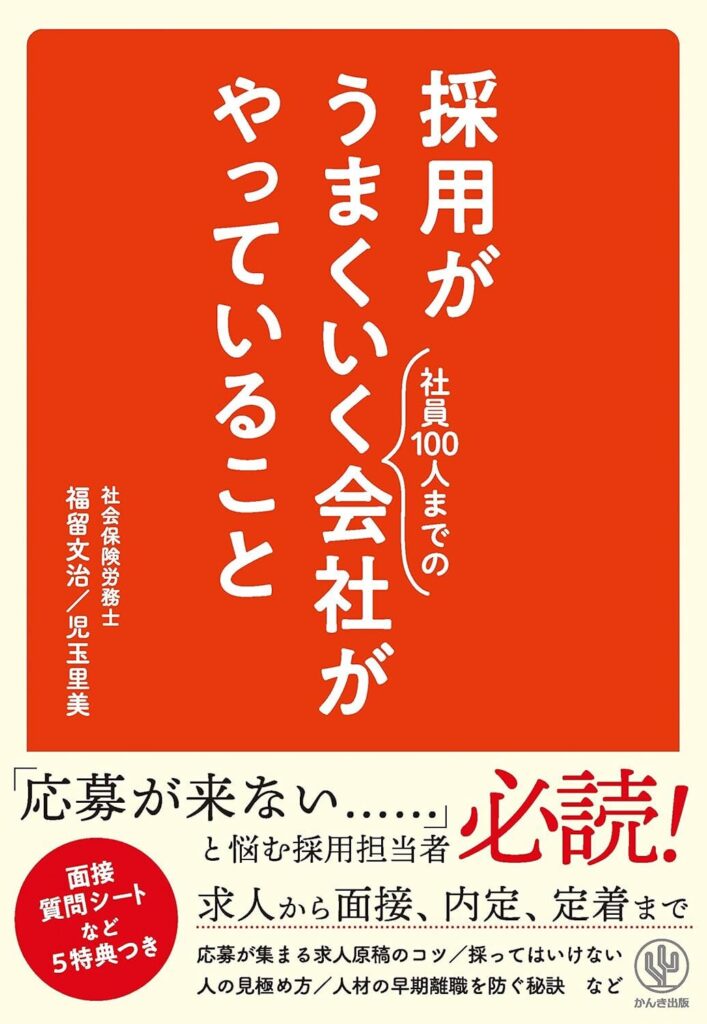企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。
しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者も多いのではないでしょうか?

ガイドさん
採用の成功には、戦略的なアプローチや面接のスキル、そして市場や候補者を理解する力が求められます。
そこで役立つのが、採用力を高めるための本です。
採用の基礎から最新のトレンド、実践的なノウハウまでを学ぶことで、より効果的な人材獲得が可能になります。
本記事では、優秀な人材を採用できるようになるためのおすすめ書籍をランキング形式でご紹介します。
採用活動の課題を解決し、自社にぴったりの人材を見つけるために、ぜひ参考にしてみてください!

読者さん
1位 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書
「求人を出しても全然応募が来ない……」「やっと採用できても、数ヶ月で辞めてしまう……」——そんな採用の悩みを抱えていませんか?
中小企業の経営者や人事担当者にとって、「人を採る」という行為は、単なる業務のひとつではなく、事業の成長を左右する極めて重要な課題です。にもかかわらず、昨今の日本では採用環境がますます厳しさを増しています。パーソル総合研究所の予測によれば、2030年には労働人口が約644万人も不足すると言われており、企業間での人材獲得競争は今後さらに激化することが避けられません。
そんな“採用難”の時代にあって、多くの企業が「求人を出しても人が集まらない」「採ってもすぐに辞めてしまう」という悪循環に悩まされています。しかし、その一方で、同じような環境の中でも、着実に人材を集め、育て、定着させている企業も存在します。では、両者の違いはどこにあるのでしょうか?
その答えが詰まっているのが、本書『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』です。
続きを読む + クリックして下さい
本書は、社会保険労務士として1,000社以上の中小企業を支援してきた著者・宮本宗浩氏が、自身の豊富な現場経験をもとに、「人材が集まり、育ち、定着する仕組み」を体系化した一冊です。特に中小企業における採用現場の“リアル”に寄り添いながら、すぐに実践できるノウハウを具体的に紹介しています。
注目すべきは、単に「採用活動」のテクニックを解説するのではなく、採用そのものを「組織戦略」「マーケティング」「セールス」といった視点から捉えている点です。
たとえば、求人票の書き方を見直すことで応募者数が255%増加した事例。自社の弱みも開示する「リファレンスリクルート」によるミスマッチ防止。組織内分析からスタートし、キャリアパスの整備や評価制度を通じて「人が辞めない職場」をつくる仕組み。さらには、採用広報を通じて自社の価値を社会に発信し、「選ばれる企業」になるためのステップまで、理論と実践のバランスをもって丁寧に解説されています。
特に、採用活動を営業活動と同様に「顧客=求職者にどう伝えるか」という視点で再構築する発想は、従来の採用常識を覆す新しい気づきを与えてくれます。
本書は、決して一部の大企業やスタートアップだけが実践できる高尚な理論ではありません。資金も人手も限られている中小企業こそが活用できる、現場目線で編み出された現実的で実行可能なノウハウばかりが詰まっています。

ガイドさん
もし今、あなたが「なぜうちは採用に苦戦しているのか」と悩んでいるのなら、本書がきっとその答えと、そして次に進むための地図を示してくれるでしょう。
採用は、単なる“人集め”ではありません。会社の未来を担う“仲間を迎え入れるプロセス”です。そして、強い組織は、強い採用から始まります。
この一冊が、あなたの会社の「採用力」を根本から変えるきっかけになることを願ってやみません。
本の感想・レビュー
私は中堅の製造業で人事を担当している者です。これまで「採用=選別する作業」だとどこかで思い込んでいた節がありました。ですが、この本を読んで「採用は営業活動そのもの」だと書かれていた部分に、衝撃を受けたんです。これって、よくよく考えれば当たり前の話なのに、意外と現場では実感できていない視点じゃないでしょうか。
求職者は、自社の魅力をしっかり伝えられなければ動きません。本書では、求人広告の出し方から応募者との接点の持ち方まで、まるで商品を売るときのように“惹きつけて、納得させる”技術が求められると説明されていました。私はそれを読みながら、「いま自分がしている採用活動って、ちゃんと“売り込めてる”のか?」と自問しました。
これまでの反省と、これからの方針がくっきり見えたような気がします。まさに目から鱗の一冊でした。
他7件の感想を読む + クリック
うちは社員30人ちょっとの小さなIT会社です。大企業向けの人事ノウハウ本は山ほどありますけど、結局「うちには合わないよなあ…」と読み終えることが多くて、少し食傷気味でした。そんな中でこの本に出会って、ものすごく救われた気持ちになりました。
実際に取り上げられているのは、まさに“うちみたいな規模感の企業”ばかり。しかも、現場のリアルな悩みと、それに対する改善プロセスが順を追って丁寧に書かれているから、自分事として読めるんですよ。「人が集まらない」「定着しない」「仕組みが弱い」といった、日々感じていた課題が、“具体的に何をすれば良いのか”に変換されていく。読んでいて、希望が湧きました。
一番ありがたかったのは、「大きな変革じゃなくて、できることから始めていい」というスタンス。本当に背中を押されました。
経営者として採用面接に出ることも多い私にとって、リファレンスリクルートという手法は非常に興味深かったです。「求職者が企業を評価する材料」を積極的に提示するという発想、正直最初は面食らいました。でも、読み進めるうちにその重要性が腑に落ちてきたんです。
求職者だって人生をかけて応募してくるのだから、企業も誠実に“自分たちの実像”を開示しないといけない。情報の透明性を高めることで、入社後のミスマッチを防ぎ、ひいては離職率も下げられる。これは一見地味ですが、実は最も効果的な方法だと感じました。
私もこれまで「企業が選ぶ側」という視点ばかりでしたが、本書を読んで価値観が変わりました。対等な関係づくりが、これからの採用のスタンダードになるのだと思います。
私は管理部門の責任者です。正直これまで「採用=求人媒体をどう使うか」くらいにしか考えていませんでした。でも本書は、まず“組織の中を見直せ”と言います。外へ情報を発信する前に、会社の内側の問題を整理して、強みや課題を把握することが大事だという内容には納得しかありませんでした。
特に「組織内分析」のパートは実用性が高く、チェック項目や進め方も具体的で、すぐにでも自社で取り入れられそうだと感じました。採用活動は一時的なイベントではなく、組織全体の運営と密接につながっていることを再認識させられました。
これまで採用がうまくいかなかったのは、求人の出し方以前に、会社の中身に問題があったからかもしれません。本書はその事実に気づかせてくれる一冊です。
私は人事制度の設計にも関わっている立場なのですが、この本で改めて痛感したのは、キャリアパスと評価制度の整備が“定着率”に直結しているという点です。人が辞める理由って、単に給料や労働時間だけじゃなく、「自分はこの会社でどうなれるのか」が見えないことが大きいんですよね。
本書では、その“見える化”の方法が非常に具体的に書かれていて、特に「将来像を提示できる制度設計」がいかに人の安心感を生むかが丁寧に解説されています。私はこの部分を読んで、自社のキャリアマップを見直すきっかけを得ました。
評価制度も同様で、あいまいな評価基準では社員のモチベーションは上がらない。明確な基準を示し、納得感のある運用をすることで、「この会社にいたい」と思ってもらえる。そんな土台づくりの重要性を再確認できたのは、大きな収穫でした。
私はマーケティング畑出身の人事担当です。そんな私にとって、本書が語る「採用=マーケティング」という視点は、まさに腑に落ちるものでした。
これまで「人事」と「マーケティング」は別の領域とされがちでしたが、本書では明確にそれを統合して見せてくれました。応募者数を増やすにはどうすればいいのか、求職者の「行動心理」や「選ばれる理由」をどう作るのか。企業のブランディングだけでなく、求人の出し方やターゲットの絞り方にまで踏み込んで解説されていて、「これ、まさにプロモーション戦略じゃん!」と感心しながら読みました。
今や人材も「集める時代」から「選ばれる時代」へ。その現実にどう立ち向かうかを、論理的に理解できた一冊でした。
うちの会社では、求人票のテンプレートがもう10年くらい変わっていませんでした。でもこの本を読んで、まず手をつけたのがそこ。求人票って、ただ条件を羅列すればいいと思っていたけど、それが大間違いだったんですよね。
「どう伝えるか」「誰に向けて書くか」、つまり情報の設計そのものが問われているという視点をもらいました。特に、求職者が企業に対して抱く「不安」や「期待」をどう読み取るか。その上で、安心感や共感につながる情報をどう表現するか。このあたりの考え方は、自分には完全に欠けていた視点でした。
おかげで、求人票を“人を惹きつけるツール”として再定義できた気がします。次に出す求人票は、これまでと全然違うものになると確信しています。
経営企画の立場から「採用広報」の見直しを考えていたところ、この本に出会いました。読んで感じたのは、採用広報って「単なる会社紹介じゃない」んだということ。むしろ、候補者との“最初の接点づくり”として、どう信頼関係を築くかが問われているんですね。
本書では、採用広報を「情報戦」と位置づけていて、その中でどんな媒体を使うべきか、どのようなストーリーを発信すればよいかが丁寧に書かれていました。中小企業がリソースに限りがある中で、どう戦略的に発信していくかという視点が、とても参考になりました。
単なる露出ではなく、「相手の心に届く情報発信」にシフトしていくヒントをたくさん得ることができました。自社の採用サイトも、今すぐにでも見直したくなりました。
2位 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
あなたは「人を見る目」に自信がありますか?ビジネスでもプライベートでも、誰を選ぶかは人生を左右するほど重要な決断です。優れたアイデアや十分な資金があったとしても、実行するのは最終的に「人」。どんなに魅力的なビジネスモデルでも、どれだけ整った組織体制でも、「適切な人材を選べるかどうか」によって、成功と失敗は大きく分かれます。
「期待して採用したのに、思ったように成果を上げてくれない」「チームワークを重視していたのに、雰囲気を悪くする人物を選んでしまった」「優秀だと思って抜擢した人が、組織の足を引っ張ってしまった」——こうした問題は、企業経営だけでなく、人間関係全般においてもよく見られるものです。人材採用の場面では、多くの企業が候補者のスキルや経験を重視するものの、その人の本質的な能力や将来性、組織との相性を正しく見極めるのは非常に難しいものです。実際、従来の採用プロセスや評価基準だけでは「本当に優秀な人材を見抜くことはできない」という課題を、多くの企業が抱えています。
本書『経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術』は、世界最高峰のヘッドハンティングファームの共同経営者として、5,000人以上のハイクラス人材を見極めてきた著者・小野壮彦氏が、その膨大な経験を体系化し、「人を見る技術」としてまとめた一冊です。
続きを読む + クリックして下さい
本書の特徴は、単なる「直感」や「経験則」に頼るのではなく、再現性のある理論と実践的なフレームワークを用いて、「人を見る力」を鍛える方法を徹底的に解説している点にあります。これまで「人の見極めは才能のようなもの」と考えられてきた領域に、明確なロジックと具体的な手法を持ち込み、誰でも「人を見抜く力」を鍛えられることを証明しています。
本書では、採用や人事評価においてありがちな「認知バイアス」による誤判断を防ぐ方法、候補者の「地上階(スキル・経験)」だけでなく、「地下階(ポテンシャル・胆力・使命感)」を正しく見極める方法、さらには「優秀ではあるが組織に悪影響を与えるEVIL人材」を特定し、回避する手法など、極めて実践的な内容が紹介されています。特に、面接や評価の場で使える「カット・インの技術(質問の掘り下げ方)」や、「相手の話を深掘りして本音を引き出す方法」など、すぐに実践できるテクニックも豊富に掲載されており、経営者・採用担当者・マネージャーはもちろん、これからキャリアアップを目指す人にとっても非常に有益な情報が詰まっています。
さらに、本書は単なるビジネス書にとどまらず、私たちの「人間関係のあり方」そのものを見直す機会を提供します。人を正しく見極める力は、単にビジネスの成功を左右するだけでなく、人生の質そのものを向上させます。友人、パートナー、同僚、上司、部下——私たちは日々、多くの人と関わりながら生きています。その中で、「この人と本当に信頼関係を築けるのか」「この人は自分の成長にどのような影響を与えるのか」といった視点を持つことで、より良い人間関係を築くことができるのです。

ガイドさん
「人を見る目」は、先天的な才能ではなく、後天的に鍛えることができるスキルです。
本書で紹介されているフレームワークを学び、実践することで、誰もが「人を見る力」を磨くことができます。
そして、その力を活用することで、あなたのビジネスや組織、さらには人生そのものをより良い方向へ導くことができるでしょう。
あなたが「信頼できる人材を見極め、適切な人を選ぶ力を身につけたい」と考えているなら、本書はそのための最良のガイドとなるはずです。
本の感想・レビュー
本書の中で、特に実践的で役立つと感じたのが、「面接や対話の場面でどのように相手を見極めるか」という具体的なテクニックです。これまで私は、面接をする際に、事前に考えた質問をそのまま投げかけて、相手の答えを聞くという方法をとっていました。しかし、本書では「相手の本音を引き出すためには、単なる質問ではなく、適切な聞き方が重要である」と述べられています。
特に印象的だったのは、「それで?」「どうして?」と深掘りしていくディープ・ダイブの技術です。これまでの私は、「この人はこういう考え方をしているのか」と納得した時点で会話を終えてしまうことが多かったのですが、本書では「その人の考えがどこから生まれたのか」を探ることの重要性が強調されていました。
また、「アイスブレイクの重要性」についての説明も非常に参考になりました。私自身、面接の場で「形式的な会話」しかできておらず、相手が緊張したまま本音を語れない状態になってしまうことがありました。本書を読んで、「相手がリラックスできる環境を作ることが、良い面接の第一歩である」と理解し、これからの面談や面接に取り入れていきたいと感じました。
他6件の感想を読む + クリック
本書の中で特に印象に残ったのは、「私たちは無意識のうちにバイアス(偏見)を持っている」という指摘です。これまで私は、「自分は公平な目で人を見ている」と思っていましたが、本書を読むことで、実際には「学歴」「経歴」「見た目」といった要素に左右されていたことに気づかされました。
例えば、「学歴の高い人=優秀」と思い込んでしまうハロー効果や、「一度良い印象を持った人を過大評価してしまう」確証バイアスなど、私自身が無意識のうちに持っていた偏見が具体的に説明されており、非常に納得感がありました。特に、「優秀で無害な人を高く評価しすぎてしまう」「逆に、少しでも欠点があるとそればかり気にしてしまう」という心理的な傾向についての説明は、まさに自分に当てはまるものでした。本書を読んで、「本当にその人を正しく見ているのか?」と自問自答する習慣を持つことが重要だと感じました。
本書を通じて、人を見る際のバイアスに気づき、それを少しでもコントロールできるようになりたいと思いました。人の本質を見抜くためには、まず自分自身の偏った見方を正すことが大切なのだと、改めて学ぶことができました。
本書の中で、もう一つ非常に実用的だったのが、「有害な人材を見分けるためのポイント」についての解説です。組織の成功には、優秀な人材の確保が重要ですが、それと同じくらい「組織の足を引っ張る人物を見極めること」も大切だという指摘には深く共感しました。
本書では、有害な人材の典型的なパターンとして、「マウント型」「ナルシスト型」「突発的にEVILな行動をとるタイプ」などが紹介されています。これらの特徴を持つ人は、一見すると優秀に見えることもありますが、組織全体の士気を下げたり、チームワークを乱したりする危険性があるため、見極めが必要だと説明されています。
これまでの私は、「人を見る目がある」と自負していたものの、実際には「この人と一緒に働くことで、組織全体にどのような影響があるのか」を深く考えたことがありませんでした。本書を読んで、「単に優秀かどうかではなく、その人が組織にとって本当にプラスになる存在かどうか」を判断することの重要性を改めて認識しました。
これまで私は、採用に関わることはほとんどありませんでした。しかし、本書を読んで「人を見る目を養うこと」は、採用担当者だけの仕事ではなく、組織に関わるすべての人が身につけるべきスキルなのだと気づかされました。組織の成長には、単に優秀な人を採用するだけではなく、チームや会社全体の方向性に合った人を見極めることが不可欠なのです。
本書では、「採用の現場では、表面的なスキルや経歴ではなく、その人の本質を見ることが重要である」と繰り返し述べられています。例えば、面接では「あなたの強みは何ですか?」という質問をしがちですが、この質問に対する答えはほとんどの人が準備しており、言葉だけではその人の本当の姿を見抜くことは難しいと書かれていました。代わりに、その人が過去にどのような行動を取ってきたのか、どんな困難を乗り越えてきたのかといった具体的なエピソードを聞き出すことが重要なのだと説明されています。
私はこれまで、「採用は専門家に任せるもの」と考えていました。しかし、本書を読んで、採用は会社の未来を決める最も重要なプロセスであり、誰もがその意識を持つべきだと感じました。たとえ直接面接に関わらなくても、「どんな人と働きたいのか」「どんな人が組織に必要なのか」を常に考えることが、自分の職場をより良くするために必要なのだと理解しました。
この本を読んで、これまで自分が持っていた「人材育成」という概念が大きく揺さぶられました。私は長年、部下や後輩の育成に関わってきましたが、「どのように教え、どのように導くか」という視点が中心でした。しかし本書では、人材育成において最も重要なのは、「誰を選び、どのように見極めるか」だというのです。これは、私にとって衝撃的な気づきでした。
本書では、「人を選ぶ力こそが、その後の育成の質を決定づける」と繰り返し強調されています。どんなに優れた教育プログラムを用意しても、最初の段階で適切な人材を選べなければ、その後の成長は限定的になってしまう。逆に、ポテンシャルのある人材を見極めることができれば、多少の環境の違いがあっても大きく成長していくのだと書かれていました。
この視点に立つと、これまでの自分の育成方法にも改善の余地があることを痛感しました。部下を育てる際、「なぜこの人は思うように成長しないのか」と悩むことがありましたが、それは単に育成方法の問題ではなく、そもそもの人材選定の段階で適切な判断ができていなかったのかもしれません。部下の可能性を引き出すためには、最初に「人を選ぶ力」を磨くことが必要なのだと、本書を読んで初めて理解できました。
「人を見る目は先天的な才能ではなく、鍛えることができる」という本書の主張は、私にとって非常に励みになるものでした。正直なところ、私はこれまで「人を見る目がある人」と「ない人」は生まれつきの違いだと思っていました。しかし、本書では、人を見る力は「経験と学習によって伸ばせるスキルである」と明確に述べられています。
本書では、具体的なトレーニング方法も紹介されていました。その一つが「観察力を養う」という方法です。人のしぐさや話し方、言葉の選び方に注意を払うことで、その人の思考や価値観が見えてくると書かれていました。また、「相手の行動の背景を考える」ことも大切であり、なぜその人がその選択をしたのかを考えることで、本質的な部分を見抜く力が鍛えられるのだと説明されていました。
人を見る目を養うことは、一朝一夕にできるものではありません。しかし、本書を読んで「意識的に観察し、考えること」を続けることで、確実にスキルを向上させることができると確信しました。これからは、日々の会話や出会いの中で意識的に人の本質を見抜く訓練をしていきたいと強く思いました。
本書を読んで、面接官の役割が単なる採用の判断者ではなく、相手の本質を引き出す「ナビゲーター」のような存在であるべきだと感じました。これまで私は、面接は応募者が評価される場であり、面接官は「見極める側」として主導権を持つべきだと考えていました。しかし、本書では「良い面接とは、応募者が本来の自分を自然に表現できる場であるべき」と述べられています。この視点は、私にとって新鮮なものでした。
特に印象的だったのは、「面接官自身がリラックスしていなければ、応募者も緊張し、良いパフォーマンスを発揮できない」という指摘です。面接は単なる選考の場ではなく、組織と応募者の相性を確認する機会であり、応募者が自分を偽ることなく自然に話せる環境を作ることが重要なのだと本書は強調しています。そのためには、面接官は事前に準備を整え、リラックスした状態で臨むことが求められます。
また、「質問の仕方によって相手の回答が変わる」という点も非常に興味深かったです。たとえば、抽象的な質問をすると応募者は事前に用意した一般的な答えを返しがちですが、具体的な行動を問う質問をすると、その人の本質が表れやすくなると書かれていました。これは、日常のコミュニケーションにも応用できる考え方であり、相手の本音を引き出すための問いかけ方を工夫することの大切さを改めて実感しました。
この本を読んだことで、面接官の役割についての認識が大きく変わりました。単なる評価者ではなく、相手の能力や価値観を引き出し、最適な選択をするための「伴走者」であるという視点を持つことで、より質の高い採用ができるのではないかと感じました。
3位 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ
「採用が変われば、企業も変わる。そして社会も変わる。」
かつては「会社に入ったら定年まで勤め上げるのが当たり前」とされた時代がありました。転職者は“脱落者”というレッテルを貼られ、新たな一歩を踏み出すことは後ろめたさを伴うものでした。ところが今、私たちは真逆の時代に生きています。終身雇用は崩れ、キャリアは自らデザインするものとなり、転職は「前向きな選択肢」として受け入れられるようになりました。
この大きな価値観の転換の裏には、情報の可視化やテクノロジーの進化、人材サービスの発展がありました。そしてその流れは今なお加速を続けています。AIによるマッチング、自動化された求人配信、ソーシャルリクルーティング、クラウド型採用管理。現場では次々と新たなテクノロジーや仕組みが生まれ、採用の“当たり前”は日々塗り替えられています。
本書『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』は、そんな激変する人材業界の今とこれからを、100年というスパンで捉え直す試みです。
続きを読む + クリックして下さい
江戸時代の「職業」のあり方から始まり、戦後の高度経済成長とともに育まれた終身雇用制度、新卒一括採用という日本独自のモデル、求人広告と人材紹介の誕生、バブル崩壊後の転職ブーム、インターネットとWebメディアの登場、そしてAIやデータドリブンな採用マーケティングの現在まで。人と仕事をめぐる仕組みがどのように形成され、そしてどう変化してきたのかを、歴史的かつ構造的に読み解いていきます。
本書の魅力は、過去の出来事を単に列挙するのではなく、それぞれの時代において採用支援ビジネスが担ってきた社会的な役割を掘り下げ、今後の進化や分岐点をリアルに予測している点にあります。事例にはIndeedやWantedly、OpenWork、LinkedIn、NewsPicksなど、現代を代表するリクルーティングサービスも取り上げられ、いま何が起きているのかを具体的に把握することができます。また、採用活動の現場で直面する「誰を採るべきか」「どう口説くべきか」「どのチャネルを選ぶべきか」といった実務的な悩みにも寄り添っており、戦略と実践を架橋するガイドブックとしての価値も兼ね備えています。
執筆者は、求人広告・人材紹介・Webサービスなど、複数の領域において第一線でキャリアを積んできた黒田真行氏と、HR領域に精通した編集者・研究者として活躍する佐藤雄佑氏。だからこそ、現場感と俯瞰性の両方が備わった構成になっており、読み手に「知識」だけでなく「洞察」ももたらしてくれます。

ガイドさん
この本は、採用に携わるすべての人、そして人材業界の変化を経営戦略や社会課題の視点から捉えたい人にとって、大きなヒントを与えてくれるはずです。
過去を知り、現在を深く理解し、未来を構想する。そのために必要な“地図”が、この1冊に凝縮されています。
本の感想・レビュー
人材業界で十数年、私自身もリクルートで採用支援に携わってきた身として、本書を読んでまず感じたのは「この視点は中の人にしか書けない」という深い納得感でした。黒田真行さんが語る一つひとつのエピソードや歴史の裏話には、現場を歩いてきた実感が滲んでおり、決して机上の空論ではない「生きた知識」が詰まっていました。
特に印象的だったのは、求人広告と人材紹介、それぞれのビジネスがいかに異なるロジックで動いてきたかという説明です。単なるビジネスモデルの違いではなく、関わる人々のマインドやスキルセットにまで踏み込んでいて、私自身がかつて現場で感じていた違和感の正体が明確になった思いがしました。
また、著者がキャリアのなかで数多くの転職メディアやエージェントサービスに携わってきた経験が、そのまま読者の羅針盤になっていると感じました。この本は、現場を知っているからこそ描ける、業界の過去・現在・未来をつなぐリアルなドキュメントです。
他5件の感想を読む + クリック
人材系スタートアップでプロダクト開発に携わっている者として、ずっと感じていた疑問がありました。それは「なぜ人材業界はこんなにも複雑で、似たようなサービスが乱立しているのか?」ということです。本書は、その問いに対して極めて明快に答えてくれました。
求人広告と人材紹介、さらに派遣やRPO──それぞれがまったく異なる起源と進化の道筋を持っていること。その中で、どのようにして収益モデルや現場オペレーションが形成されてきたのか。まさに業界の裏側に光を当てるような一冊でした。
とりわけ「分業制」や「KPIマネジメント」など、実務に根ざした仕組みの変遷が詳細に書かれている点は、スタートアップの事業設計にも応用できそうな示唆に富んでいました。人材業界のビジネスモデルを知ることは、単なる知識習得にとどまらず、戦略構築にも直結する。そう感じさせる本です。
私は現在、中途採用を担当する人事として働いていますが、実は10年前まで「転職=ネガティブ」というイメージを持っていました。本書を読んで、かつての社会に根づいていたその価値観が、どれほど強く、どれほど根深かったのかをあらためて実感しました。
「途中でケツを割って逃げ出すのは負け犬」──。そんな言葉がまかり通っていた時代から、今や転職はキャリア戦略の一環として当然視されるまでに変わった。その変化の背景には、社会の意識変化だけでなく、人材業界そのものの進化があったのだと、本書は丁寧に教えてくれます。
特に1980年代以前の「三行広告」や「委細面談」といった、求職者がほとんど情報を得られなかった時代の描写には驚きました。私たちが今、当たり前に活用している求人メディアが、いかに時代を経て変化してきたのか、その過程を知ることで、今の仕事の価値がより明確に見えてきます。
私はテック業界のHR部門で働いており、日々の業務でAIやRPAを活用する場面が増えてきています。本書を手に取ったのは、「人材紹介の未来」に漠然とした不安を抱いていたからでした。読み進めるうちに、まさに今私たちが直面している変化の本質が、過去の延長線上にあることに気づかされました。
特に印象深かったのは、HRテクノロジーが単なる業務効率化ではなく、リクルーティングの根幹を再定義し始めているという指摘です。AIが介在することで、従来のマッチング手法では見えなかった人材の可能性が可視化され、RPOなどの外部委託型モデルも、より戦略的な活用へと進化しています。
本書には、テクノロジーによって「人が選ばれるプロセス」そのものが変わることへのリアルな予感が込められていました。未来を見通すヒントを求めている方には、これ以上ない一冊です。
私はキャリアチェンジを考え始めた30代後半の会社員です。これまで営業職一筋だったこともあり、「人材業界」という言葉に、正直ひとくくりのイメージしか持っていませんでした。でもこの本を読んで、実はHRビジネスの世界には想像以上に多くの業態があり、それぞれに役割と成り立ちがあるのだということを初めて知りました。
求人広告と人材紹介の違いはもちろん、RPOやアグリゲーション型求人検索エンジン、ソーシャルリクルーティングなど、これまで耳にしていたけれどよく分かっていなかった仕組みや背景が、歴史的経緯とともに丁寧に解説されていて、すっと理解できました。
単に「採用の仕組み」を学ぶだけでなく、人材業界全体がどれだけ複雑かつ戦略的な構造を持っているのかが分かり、あらためてこの領域の奥深さに感心しました。これから人材ビジネスに関わろうと考えている人だけでなく、私のように異業種から関心を持っている人にも強くおすすめしたいです。
私は現在20代後半で、まだ人材業界に足を踏み入れて数年の若手です。正直、「採用の歴史」や「業界の構造」などという言葉には、最初はどこか堅苦しさを感じていました。しかしこの本は、そんな私のような若手にも驚くほど読みやすく、かつ理解がスムーズに進む構成になっていました。
読み進めるうちに、「今自分が携わっている仕事が、どんな歴史の上に成り立っているのか」「今後どのような方向へ進んでいくのか」が、線でつながる感覚がありました。特に、新卒一括採用や転職市場の移り変わりといった話題は、自分がこれまで何となく“常識”と思っていたものの背景を知る機会にもなり、仕事に対する見方が少しずつ変わっていくのを感じました。
著者の文章は専門的でありながらも丁寧で、読者への配慮を感じます。情報量は多いのに、無理に背伸びをさせられている感覚がない。歴史の流れをなぞるように読むうちに、自然と未来のビジョンへ導かれる構成は、若手にこそ薦めたい内容です。
4位 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石
「どうすれば、うちの会社に“本当に来てほしい人”が応募してくれるのか?」
この問いに明快な答えを提示する一冊が、『採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石』です。
中途採用の難易度が年々高まる今、従来型の採用活動ではもはや通用しなくなっています。求人広告を出せば応募が集まる時代は終わり、企業が「選ぶ側」ではなく「選ばれる側」として、戦略的かつ総合的なアプローチを求められる時代に突入しています。採用活動は、単なる人材募集ではなく、企業の未来を左右する「経営そのもの」と言っても過言ではありません。
続きを読む + クリックして下さい
本書の著者である今啓亮氏は、2015年に創業した採用代行会社「マルゴト株式会社」の代表を務め、これまでに累計350社以上の中途採用支援に携わってきた実績を持ちます。著者自身も、決して人が集まりやすい業種とは言えないアウトソーシング業界の中で、札幌を本拠地にしながら、たった5年で社員150名体制を築き上げるという成果を上げてきました。その過程で試行錯誤を重ね、実際に成果が出た「再現性のあるノウハウ」だけを抽出し、詰め込んだのが本書です。
本書の特徴は、「戦略立案」「職場づくり」「広報活動」「スカウトライティング」「面接設計」など、中途採用に必要なすべての要素を網羅している点にあります。さらに、すべての章において具体的な手法や事例が盛り込まれているため、読者は「考え方」だけでなく、「やり方」までを手に入れることができます。専門用語を使わず、誰にでもわかりやすい表現で書かれているため、採用に不慣れな経営者や現場責任者でも安心して読み進めることができるのも、本書の魅力のひとつです。
たとえば、採用広報においては、求人票だけでは伝えきれない「働く現場の空気感」をどう発信すべきかを具体的に解説し、スカウトメールではテンプレートを使い回すのではなく、個別の「特別感」をどう表現すべきかにまで踏み込みます。また、面接においても「評価する場」ではなく、「魅力を伝える場」として捉え直し、どのように設計すれば求職者から「この会社に入りたい」と思ってもらえるのかが丁寧に示されています。

ガイドさん
このように、本書は単なるテクニック集ではありません。
採用活動に対する考え方そのものをアップデートし、自社の魅力を再発見し、最適な人材を迎え入れるための「採用の教科書」として、多くの企業にとって有益なヒントを与えてくれる一冊です。
本の感想・レビュー
経営者歴10年目になる者です。これまでは売上やプロダクトの開発ばかりに目を向けていて、正直「採用」は事務作業の一部だと考えていました。求人媒体に出稿して反応があればラッキー、くらいの感覚だったと思います。本書を読んで、その認識が根底からひっくり返されました。
著者が語る「採用は企業の総合プロデュース」という言葉が、何よりも印象に残っています。単に人を増やす行為ではなく、会社の未来を形づくる戦略であり、経営と不可分のものだと痛感しました。採用数値を“後ろ”から見て改善するという視点も、これまでにはなかったアプローチで、新鮮な驚きがありました。
読み終えた今は、採用担当任せにするのではなく、自分自身が前面に立つべきだと強く感じています。この本に出会っていなければ、きっと今も「採用=広報任せ」の感覚から抜け出せていなかったと思います。
他6件の感想を読む + クリック
これまでスカウトメールといえば、エージェントから来るテンプレートに近いものを、少しカスタマイズして送るくらいでした。返信がなくても仕方ないと割り切っていたところがありました。
ところが、本書を読んで、スカウト文の設計そのものが採用の成否を左右するという事実に驚きました。特別感を込める、網羅的にしすぎない、相手のメリットを簡潔に伝える――こうした原則が一つひとつ、非常に納得できる形で解説されていて、気づけば夢中になって読み込んでいました。
特に「返信率が低いときの対処法」まで丁寧に触れてくれているのがありがたかったです。いまは本書を片手に、自社のスカウト文を一から見直しています。もっと早くこの本に出会いたかったです。
従業員10名ほどの小さな製造業を経営しています。これまでは人が集まらず、応募が来てもマッチしないということの繰り返しでした。大企業には敵わないと、どこかであきらめていたんです。
でもこの本には、採用代行の会社自身が、札幌に本社を構えながら、メディア露出もせずに1万人以上の応募を集めたというエピソードが書かれていて、心底勇気づけられました。オフィスの立地や派手な実績ではなく、いかに自社の魅力を言語化して伝えられるかが重要なのだと理解できたのは大きな収穫でした。
ページをめくるごとに、「うちでもできるかもしれない」という希望がふくらんでいき、読み終える頃には前向きな気持ちになっていました。今は、まず自社の魅力を4つの観点から整理しようと、社員と話し合いを始めたところです。
普段は人材紹介会社のテンプレートをベースに原稿を作っていたのですが、思うように応募が集まらず、ずっと悩んでいました。
そんなときにこの本に出会い、「職種名の工夫」や「応募理由を想定して書く」といった実践的なアドバイスに出会いました。特に、主観と客観のバランスを意識するという部分は、これまで感覚で書いていた自分にとって大きな気づきでした。
本書を読んだ後、原稿を思い切ってリライトしてみたところ、明らかに応募者の質も量も変化しました。ちょっとした言葉の選び方や構成の順番で、ここまで違うのかと実感しています。この本があれば、これから先の原稿作成にも迷いがなくなりそうです。
前職では「広報=ブランディング」だと思っていたのですが、本書を読んで「採用広報」という独自の概念に出会い、まさに目から鱗が落ちました。
採用広報とは、職場の情報を求職者に対して分かりやすく、戦略的に伝える活動であるという説明があり、従来の広報とは明確に異なる目的と視点が必要なのだと理解できました。とくに、選考フェーズごとに伝える情報を変えるというアイデアには驚きました。応募前から内定後に至るまで、一貫して「どんな職場か」を伝え続けるという姿勢が重要なんですね。
採用広報というと大企業の専任チームがやるものと思い込んでいましたが、この本では中小企業やベンチャーこそ取り組むべきと書かれていて、大いに納得させられました。今後、自社の情報発信にもこの視点を取り入れていきたいと思っています。
正直、これまでは「人材が集まらないのは条件が悪いから」とばかり思っていました。でも本書を読んで、自社サイトの写真や見せ方が、応募者に与える印象に決定的な影響を与えているということを知って、愕然としました。中でも、社長や社員の写真ひとつひとつが、候補者の心を動かす「ビジュアルメッセージ」になっているという指摘は、本当に目から鱗でした。
自社ホームページが「ダサい」「古い」「人の顔が見えない」といった要素だけで、応募をためらう人がいる現実。これを聞いたとき、自社サイトのトップページを見返してみて、背筋が凍るような気持ちになったんです。言葉では「フラットな社風」と言いながら、そこに写っている写真が硬くてよそよそしいままでは、まるで説得力がありません。
読了後、すぐに制作会社に連絡をして、採用ページの刷新を進めています。写真という、ある意味で「無言の語りかけ」が、採用における第一印象を大きく左右する。これは、もっと早く気づくべきだったと痛感しています。
私は人事担当として10年以上面接に関わってきましたが、本書で語られていた「面接官もまた見られている存在」という視点には、正直なところ驚かされました。これまでは「見極める」ことが最優先で、候補者にどんな印象を与えているかまでは深く意識してこなかったんです。
特に印象に残ったのは、カジュアル面談や複数フェーズでの設計を通じて、段階的に相互理解を深めていくという考え方。これは、単なる選考ではなく「関係構築」なんだというメッセージが伝わってきました。また、企業側のネガティブな要素も、隠さずに共有することで、ミスマッチを防ぐという姿勢も非常に現実的でした。
読み進めるうちに、面接の場とは一方的にジャッジを下すものではなく、お互いの未来をすり合わせる「対話の場」なんだと気づかされました。この本は、面接という言葉の意味をもう一度根本から見直すきっかけをくれました。
5位 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)
「人が集まらない」「応募が来ない」「内定辞退される」――
それは、本当に“会社の魅力がない”からでしょうか?
実は、採用がうまくいかない理由は「伝え方」と「見つけ方」にあるかもしれません。
本書『「化ける人材」採用の成功戦略』は、「知名度がない」「条件も平凡」「地方勤務でアクセスも悪い」といった“中小企業のリアル”に真っ向から向き合い、それでも人材を集め、育て、会社の未来を担う存在へと変えていくための具体的な方法を提示する、実践的な採用バイブルです。
続きを読む+ クリックして下さい
著者は、これまで全国500社以上の採用支援に携わってきた中小企業診断士・窪田司氏。大企業とはまったく異なる戦いを強いられる小さな会社のために、「どうすれば資金や知名度に頼らずに、“本当に必要な人材”を採用できるのか?」という問いに、徹底して答え抜いています。
本書が描くのは、即戦力でもエリートでもなく、やがて大きく伸びる可能性を秘めた“化ける人材”を見極め、迎え入れ、育て上げるための戦略です。
採用活動を「母集団形成」「情報提供」「選考」「入社動機形成」という4つのプロセスに分け、それぞれの段階でどんな考え方を持ち、どんな行動をすれば成果につながるのかを、事例と理論、両面から丁寧に解説。ナビサイトやSNSの活用法、学校連携や0次面接といったユニークな施策、さらには内定辞退や早期離職を防ぐ方法まで、すぐに実行に移せるヒントが詰まっています。
注目すべきは、「採用手法」ではなく「採用設計」に重きを置いていること。つまり、どこで告知するか、どんな媒体を使うか以前に、“誰に、何を、どのように伝えるか”という企業のメッセージ設計こそが、採用の明暗を分ける――という、核心に迫る内容です。

ガイドさん
「採用はうちには無理」「有名企業じゃないと人は来ない」――そんな思い込みを捨てて、一歩踏み出したい中小企業にこそ手に取ってほしい一冊です。限られた条件だからこそできる、戦略的で誠実な採用のかたちを、この本がきっと教えてくれます。
本の感想・レビュー
正直に言えば、この本を手に取る前の私は「どうせうちみたいな小さな町工場には人なんて来ないよ」と諦めモードでした。社員は十数名、採用に使える予算も限られていて、応募があってもミスマッチばかり。採用はずっと悩みの種で、どうしてもうまくいくイメージが持てなかったんです。
でもこの本を読んで、その考えが根本から覆されました。小さな会社には小さな会社なりの戦い方がある。それをちゃんと知って実践すれば、ちゃんと届く人には届くんだ、ということが、具体的な事例や戦略を通してリアルに伝わってきたんです。
読み進めるうちに、「無理」と思っていたのは、やり方を知らなかっただけだったのかもしれないと気づきました。自社の強みを見つめ直すこと、求める人物像を絞ること、そして何より「化ける」可能性を見抜く目を持つこと。それが、今までの漠然とした採用活動と決定的に違う点でした。
他6件の感想を読む + クリック
私は以前から「中小企業は大企業には勝てない」と心のどこかで思っていました。ブランド力、福利厚生、給与水準、どれをとっても勝ち目がないと感じていたからです。でもこの本を読んで、自分の考えがいかに一面的だったかを痛感しました。
大企業にはない「小さな会社」ならではの強み、たとえば社長と社員の距離の近さや、仕事の幅広さ、チャレンジのしやすさ、そういったものに価値を感じてくれる人材もいるという視点が、自分には欠けていたのです。
本書の中で語られる「ニッチ戦略」は、まさに中小企業にとっての羅針盤です。大企業と同じ土俵で戦わず、自分たちの土俵を築くという発想に触れたことで、初めて前向きに採用活動を考えることができました。
私は大学生向けの採用説明会を毎年開催しているのですが、どうしても学生の参加率が低く、悩んでいました。事前エントリーが必要な形式だったため、そもそもハードルが高かったのかもしれません。
この本を読んで驚いたのは、説明会の設計そのものに「学生の心理」に立った工夫が多く盛り込まれていたことです。たとえば、参加前から個別に声をかけるアプローチや、説明会の中に動画や物語性を盛り込む方法、エントリーシートではなく「説明会参加シート」という形でハードルを下げる工夫など、今まで気づけなかった視点が満載でした。
今後は、こちらの都合だけでなく、参加者の気持ちや行動の流れに合わせた説明会設計を意識していこうと思います。まさに「相手に伝える」ことの本質を再確認させられました。
これまでの採用では、「今できる人」「学歴がある人」を重視していました。けれど、実際に入社後に活躍するのは、そうした「条件の良い人材」ではないケースも多かったことに、うすうす気づいていました。
本書で紹介されている「伸びしろ」で見るという選考の視点は、目から鱗でした。即戦力ではなく、入社後に育つ可能性に目を向ける。そうすることで、今まで見落としていた人材に目が向くようになるのです。
この考え方を取り入れてから、面接での質問の内容も変わりました。過去の実績よりも、考え方や学ぶ意欲に焦点を当てるようになったんです。実際に、今までだったら見送っていたような応募者の中に、「化ける」可能性を感じられる人がいることに気づけるようになってきました。
私は地方で小規模な製造業を営んでいます。正直、これまで「リファラル採用」なんて都会の話だと思っていました。けれど本書を読んで、その考えが一変しました。なぜなら、本書に出てくる実例の一つひとつが、まさに「うちでもできる」レベルで語られていたからです。
特に印象に残ったのは、社員の紹介によって採用がつながったケース。単なる紹介ではなく、「誰に紹介してもらうか」「紹介してもらう相手にどんなメリットがあるか」といった視点まできちんと掘り下げて説明されています。つまり、紹介制度をただ導入するのではなく、制度として機能させるための仕組みづくりにまで踏み込んでいるんです。
私はこの本を読み終えてから、社内で社員に向けて「紹介ってどういうときにしやすいか?」を話し合う時間を設けました。結果的に、社員の知人が一人、応募してくれることになり、今面接を控えています。リファラル採用が絵に描いた餅でないこと、本当に現場レベルで使えるノウハウだということを、実感しました。
せっかく内定を出しても、辞退されてしまう。これが、毎年のように繰り返されていた私たちの悩みでした。特に、地方の企業ということもあって、東京の企業に流れてしまうことが多く、正直モチベーションが下がることもありました。
この本では、内定後のフォローにおいても具体的な方法が示されており、まさに私たちのような企業の悩みに直球で応えてくれる内容でした。なかでも印象的だったのは、「保護者への情報提供」の視点です。家族の理解を得ることで、求職者の決断を後押しするという発想は、実際にすぐ取り入れたいと思えるものでした。
他にも、定期的な接触や内定者同士の関係づくりなど、実務にすぐ活かせるフォロー方法が紹介されていて、読後には「これならできる」という気持ちになれました。今では、内定辞退が減るだけでなく、入社後のモチベーション維持にもつながっています。
人材育成に関してはずっと試行錯誤してきましたが、本書の終盤で紹介されていた「入社前教育」にまつわる考え方は、まさに私の課題に直撃でした。特に印象深かったのが、「自責思考」を入社前から伝えるという発想です。
これは、入社後に主体性をもって動ける人材を育てるための重要な視点だと思います。従来の「育ててから考える」というやり方ではなく、「迎える前から土台をつくっておく」という考え方は、育成コストやミスマッチ防止にもつながると感じました。
内定から入社までの期間をどう活かすか、何をどう伝えておくべきか――これまで曖昧にしてきた部分にこそ、大きな差が生まれるのだと知ることができました。
6位 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則
「求人を出しても応募が来ない」「書類は通過しても面接でピンとこない」「内定を出しても辞退されてしまう」――採用の現場で、こうした悩みを抱えている企業は少なくありません。人材を求める企業側と、仕事を探している求職者側。双方にニーズが存在するにもかかわらず、その接点はなかなか合致せず、採用活動はしばしば“運頼み”のような状態に陥りがちです。
そんな中で、「なぜあの会社は、いつも良い人材を採れているのだろう」と感じたことはないでしょうか。限られた情報、限られた時間、限られたリソースの中でも、確実に成果を出している企業が存在します。では、彼らはどんな工夫をしているのか。その答えが詰まっているのが本書『採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則』です。
続きを読む + クリックして下さい
本書では、サイバーエージェントやメルカリ、トヨタ自動車、リクルートといった著名企業から、地方の中小企業、さらには海外企業に至るまで、採用で成果をあげている52社の取り組みを一つひとつ丁寧に掘り下げながら紹介しています。そして単なる成功事例の寄せ集めではなく、「出会う」「見立てる」「結ばれる」という三つの採用プロセスに沿って、それぞれに共通する考え方と実践手法を解説。誰でも再現可能な“採用の型”として体系化されているのが大きな特徴です。
特に、候補者との接点をどのようにつくり、興味を引き、エントリーへ導くのか。選考を通じて「自社と合う人」をどう見極めるのか。そして、オファーを出した人材に辞退されずに入社してもらうためには、どのようなコミュニケーションが必要なのか。本書は、それぞれの段階において起きがちな失敗とその原因を明確にしながら、読者に具体的な改善策を提示してくれます。
また、著者・青田努氏自身がリクルート、Amazon、PwC、LINEなど、複数の組織で人事・採用の責任者を歴任してきた実務家であることも、本書の説得力を支えています。現場での成功も失敗も経験してきたからこそ書ける、生々しさと現実味を伴ったアドバイスの数々は、机上の空論にとどまらないリアルな視点に満ちています。

ガイドさん
採用は「人と会社の未来をつなぐ入り口」であり、その設計力と実行力が、組織全体の成長を左右すると言っても過言ではありません。
本記事では、本書の内容構成と各章の要点を整理しながら、「採用に強い会社」が実践している知恵と原理原則を丁寧に紹介していきます。
もし、採用活動をもっと良くしたい、今のやり方に限界を感じている、他社の取り組みから刺激を受けたい、そう感じているのであれば、きっと本書から多くのヒントが得られるはずです。
本の感想・レビュー
この本を読んで一番強く印象に残ったのは、「見立てる」というフェーズに対する考え方でした。これまでの採用活動では、いかに多くの応募者に出会えるかという「母集団形成」に意識が偏っていたように思います。しかし本書は、出会ったあとにどう見極めるか、つまり本当に自社とマッチした人材かどうかを丁寧に見立てるプロセスの大切さを説いています。
「人材要件は業務とカルチャーの両面から定義すべき」とする提言は、自社での経験と照らし合わせても深く納得できるものでした。スキルが合っていても組織文化と相容れない場合、長期的に定着しないケースを私自身も何度か目の当たりにしています。本書では、そのようなミスマッチを防ぐための設計・選考の具体策が示されており、形式的な選考を超えた「対話的な見立て」の重要性を実感させられました。
他○件の感想を読む + クリック
本書に掲載されている52の成功事例は、どれもリアリティと工夫に満ちていて、読み進めるほどに意欲が湧いてきました。特定の業種や規模に偏ることなく、地方の中小企業からグローバル企業に至るまで、実に幅広い取り組みが紹介されている点も印象的でした。
それぞれの企業がどんな思考で施策を立て、どんな困難を乗り越えてきたかが丁寧に描かれており、まるで企業訪問をしているような感覚で読み進められます。どの会社にも共通しているのは、採用活動に“必勝パターン”などなく、仮説と検証を積み重ねながら、自社なりの形をつくりあげているということでした。
結果だけでなく、その過程に至るまでの葛藤や工夫が記されているからこそ、自分たちにも実行できるというリアリティがありました。読後には、自社の採用活動も新たな視点で見直したいという前向きな気持ちになれました。
日々スカウト業務に携わっている中で、本書に出会えたのは大きな転機でした。特に印象的だったのは、「スカウト文面に必要な5つの要素」を具体的に挙げ、構造的に整理してくれていた点です。相手に届く、ということがいかに難しく、そして技術が必要かを痛感しました。
以前は、スカウトの文面をある程度定型的なテンプレートで対応していたため、相手の心に響くようなメッセージになっていなかったのだと、振り返って思います。この本を読んでからは、個々の候補者に合わせた一通一通のメッセージ作成に対して、考え方がまるで変わりました。
特に「なぜあなたに声をかけたのか」を具体的に伝えることの大切さは、自分自身が逆の立場だったとしても納得できることでした。ほんの数行のメッセージに、熱意と論理の両方が宿るように、という著者の言葉がずっと心に残っています。
採用におけるメディア戦略の重要性について、ここまで体系的に解説している書籍にはなかなか出会えません。本書では、チャネル選定やベネフィット訴求といった表面的なテクニックに留まらず、その裏にある「読み手の感情設計」まで掘り下げている点が特に印象的でした。
とりわけ、「振り向かせるためには、自分のことだと感じさせる表現が必要」という視点は、求人原稿を制作するうえでの本質を突いています。応募者は常に多くの求人情報に触れています。その中で、自社の情報が目に留まり、さらに「ここで働きたい」と思わせるには、圧倒的な“読まれる工夫”が求められるのだと再認識しました。
これまで、自社の採用ページや募集文面には惰性で手を入れてきた部分がありましたが、本書を読んでからは、それらを戦略的に組み直す必要があると強く感じるようになりました。
「内定辞退の7つの失敗+1」という章に触れたとき、自分たちの採用プロセスを反省せずにはいられませんでした。とくに、「勝負は内定前から始まっている」という一文には、深く頷かされました。私たちはこれまで、選考を終えて内定を出した時点で安心してしまっていたのです。
しかし、本書では候補者の感情の流れに着目し、内定通知が出る前からどのような関係構築をすべきかが細かく解説されていました。また、フォローの重要性についても丁寧に語られており、ただ“連絡を絶やさない”だけでは不十分であることに気づかされました。
実際の運用では、選考段階の応対や内定通知の伝え方、さらには社内の複数メンバーによるクロージング体制など、見直すべき点が多くあります。本書を読んでからは、辞退が起きるたびに本の該当部分を読み返すようになりました。
私は地方の製造業で採用の仕事に携わっています。どうしても都市圏の大手企業に人材が集中してしまい、採用活動の難しさを日々痛感していました。そんなときに本書に出会い、心から励まされた思いです。
この本が素晴らしいのは、大手企業だけでなく、中小企業や地域企業の事例も数多く紹介されていることです。派手な施策ではなくても、企業の姿勢や本気度をいかに伝えるか、その工夫の積み重ねがいかに重要かという点が繰り返し強調されていました。それは、リソースの限られた中小企業にとって大きなヒントになります。
また、社員の声を活かした求人コピーや、SNSを用いた双方向的な情報発信など、実行可能な手法が具体的に紹介されていて、自社でもすぐ取り入れられるという実感を持てました。「自分たちには無理だ」と思い込んでいたことを、やり方次第で乗り越えられると教えてくれる一冊でした。
人事部に異動してまだ半年ほどの自分にとって、採用の仕事はとても奥が深く、何から学べば良いのか分からない状況でした。そんな中で本書と出会い、採用活動の全体像を体系的に理解できたことは大きな安心感につながりました。
「出会う」「見立てる」「結ばれる」という3つのプロセスに分けた構成は、初心者でも理解しやすく、各フェーズで必要とされる視点や実践方法が丁寧に解説されています。具体的な用語の説明や、事例との結びつけも分かりやすく、採用の基礎を学びたいという段階にある人にとって最適な入門書だと思います。
また、単なる教科書的な記述ではなく、著者自身の経験をもとにした言葉の一つひとつが説得力をもって伝わってくるため、安心して読み進めることができました。読み終えた今は、もう一度最初から読み直して、自社の実務にどう活かせるかを考えているところです。
7位 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密
少子化と売り手市場の加速によって、新卒採用は年々厳しさを増しています。特に知名度の低い中小企業にとっては、学生から見向きもされない現実が続き、「どうせ大手にしか人は来ない」と諦めかけている経営者や採用担当者も少なくありません。しかし、そんな常識を根本から覆す一冊が登場しました。それが、近藤悦康氏による『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』です。
本書は、社員わずか20名の中小企業が、1万人以上の学生を集め、その中から厳選された数名を採用するという驚異的な実績をいかにして実現したのか、その全貌を余すところなく明かしています。単なる成功談ではありません。地方のガソリンスタンド、建設業界、エステ企業など、知名度や規模にハンディを抱えながらも新卒採用に成功した中小企業の事例も数多く紹介され、誰でも実践できる「再現性のあるノウハウ」が丁寧に解説されています。
続きを読む + クリックして下さい
本書の最大の特徴は、「学生に選ばれる会社」になるための思考法と戦略に重点を置いている点です。単なる求人広告や説明会の工夫にとどまらず、経営者自らが採用の最前線に立ち、企業のビジョンを本気で学生に語りかける重要性を説いています。さらに、採用活動を単なる人材確保の手段と捉えるのではなく、会社そのものをイノベーションさせるプロジェクトと位置づけている点も非常にユニークです。新卒採用を通じて組織改革を促し、社員一人ひとりの意識を変え、企業全体を成長させる。そんな壮大なビジョンに裏打ちされた採用戦略が、本書にはぎっしりと詰まっています。
「3億円の投資」というキーワードにも象徴されるように、本書は新卒採用を単なるコストではなく、未来を担う人材への本気の投資と位置付けます。人材への本気の覚悟がなければ、優秀な若者は集まらない。だからこそ、採用のあり方そのものを抜本的に見直し、会社の存在意義や理念を学生に真正面から問いかけるべきだと、著者は強く訴えます。
これからの時代、企業にとって最大の差別化要素は「人」そのものです。商品でも価格でもない。だからこそ、どんなに小さな企業でも、大手と同じ土俵で戦えるのが「新卒採用」という舞台。本書は、そんな厳しい時代を勝ち抜くために、中小企業が取るべき本質的な戦略を、情熱と実践例を交えて余すところなく示してくれます。

ガイドさん
人手不足に悩む中小企業の経営者、人事担当者、そしてこれからの組織づくりに真剣に向き合いたいすべてのビジネスパーソンにとって、本書は確かな指針となるでしょう。
学生に選ばれる会社へ、そして社員に誇られる会社へ。本気で変革を起こしたいと願うすべてのリーダーに、必読の一冊です。
本の感想・レビュー
私は中小企業の採用担当をしているのですが、この本を読み進めるうちに、胸の奥に灯る希望のようなものを感じました。これまで「うちみたいな無名の会社では優秀な学生なんて来てくれない」と、どこかで諦めていた自分がいたからです。けれども、社員20人規模のレガシードが、わずか5年で1万人以上の学生から応募を集め、そこから厳選して人材を採用しているという事例を知り、「ああ、やっぱりできるんだ」と思わず本を握りしめていました。
特に印象的だったのは、「規模や知名度ではなく、いかに学生に未来を見せられるかが勝負」という一貫した姿勢です。会社の規模に関係なく、学生に夢や成長のイメージを与えられるかどうか。そこに採用の成否がかかっているという考え方が、私の中の固定観念を吹き飛ばしてくれました。地方のガソリンスタンド会社や建設業、エステ企業などの成功例にも触れ、中小企業であっても十分に戦えるのだと、心から確信を持つことができました。
他6件の感想を読む + クリック
読み進めるうちに、経営者としての「覚悟」というものの重さを、これほど痛感した本はありませんでした。本書では、新卒一人を採用することは「3億円の投資」であると語られています。その一文を読んだ瞬間、私は大げさではなく椅子に座り直しました。
たった一人を採用するだけで3億円。それは単なるコストではなく、未来にわたって続く企業の価値そのものへの投資だということ。このスケール感を真剣に受け止められるかどうかで、採用活動の質がまるで変わってくるのだと、本書は繰り返し伝えてきます。そして、その本気度は、必ず学生に伝わる。中小企業だからと妥協するのではなく、むしろ大企業よりも深い覚悟をもって一人の人間と向き合う。それこそが、これからの時代の採用だというメッセージが、ひしひしと胸に突き刺さりました。
採用活動にマーケティングの視点を持ち込むべきだという主張に、私は大きな感銘を受けました。本書では、「ターゲットを定め、戦略的に魅力を伝えていく」という採用のあり方が、非常に具体的に描かれています。これまで私は、採用活動はどちらかといえば「受け身」のもの、つまり求人広告を出して待つだけの活動だと思い込んでいました。しかしこの本は、その考えを根底から覆しました。
「ピンポイントマーケティング」や「囲い込みマーケティング」「攻め型マーケティング」など、各手法の説明はどれも理にかなっていて、実践的でした。会社側が学生に対して積極的に働きかけ、出会いを設計し、ファン化させる。そんな能動的な採用活動を通じてこそ、本当に会社の価値を理解してくれる人材と巡り会えるのだという事実に、私は深く納得しました。採用も一つの「市場開拓」だという視点は、これからの時代に必須だと痛感しました。
私はリファラル採用について、正直なところ「社員に負担をかけるやり方ではないか」と、どこか否定的に捉えていた部分がありました。でも、この本を読んで、その考え方は根本的に間違っていたと気づかされました。
著者は、リファラル採用とは「社員に紹介を強制するものではなく、社員自身が『この会社を紹介したい』と思える環境を作ることだ」と語っています。つまり、採用活動の前に、まず社員満足度を高め、社員が自然に「この会社、いいよ!」と言いたくなる状態を作ることこそが本質なのだと。これには目から鱗が落ちました。
単に紹介数を求めるのではなく、会社のあり方そのものを問う。リファラル採用とは、社員満足度のバロメーターであり、会社の本当の魅力を測る指標でもある。そう考えると、リファラルは最も「正直な採用方法」だということが分かりました。この考え方に出会えて、本当に良かったと思います。
人材採用を「投資」と捉えるべきだという指摘には、非常に大きな衝撃を受けました。本書では、新卒一人の生涯にかかる給与・福利厚生費・教育費などを含めると、3億円に達する可能性があると述べられています。この数字の現実味に、思わずページを何度も読み返しました。
普段、採用活動を「コスト」としてだけ捉えていると、いかに目の前の人材を安く確保するか、あるいはスピード重視で採用数を確保するかという視点に陥りがちです。しかし、もし3億円もの投資だと考えたなら、採用の質を徹底的に追求しなければならないはずです。少しのミスマッチも許されないし、短期的な視点ではなく、40年後の未来を見据えて選ばなければならない。この意識改革なしには、持続的な企業成長はあり得ないと、強く感じました。
オープンカンパニーの取り組みについて読んだとき、私は自然と「これだ!」と声を上げてしまいました。学生たちに実際のオフィスを丸一日開放し、社員たちとリアルに交流できる場を設けるという発想は、単なる説明会とはまるで次元が違います。これまでの採用活動では、会社の良さを伝えるためにパンフレットを作ったり、スライドショーを用意したりと、情報を一方通行で届ける手段がほとんどでした。
しかし、オープンカンパニーでは、学生が自分の目で見て、自分の感覚で社風を体験できる。これこそが、本当に会社と学生双方にとって納得できる採用活動だと強く感じました。2000人以上もの学生がこのイベントに参加しているという実績も、やはりリアルな体験の力の大きさを物語っていると感じます。採用における「本音と本音のぶつかり合い」を生み出す場作りの重要性を、心から実感しました。
本書で特に感銘を受けたポイントの一つが、「採用基準を具体化することの重要性」でした。レガシードが実践している「五つの採用基準」は、単なる理想論ではなく、明確な行動基準にまで落とし込まれており、極めて実践的です。これにより、誰が面接官になっても一定の質で評価ができ、ミスマッチを防ぐことができる仕組みが構築されていることに、深く感心しました。
多くの企業では、「人柄重視」「やる気重視」といった抽象的な評価軸に頼りがちですが、それでは合否判断に一貫性が持てず、ミスジャッジも頻発してしまいます。本書で示されているような採用基準の具体化こそが、採用活動における最大の成功要因だと、改めて認識しました。採用基準を明確にすることは、単に学生を選ぶためだけではなく、企業自身が目指すべき未来像を社員全員で共有するための重要なステップなのだと強く感じました。
8位 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて
人材の確保がますます難しくなっている今、企業の採用担当者や経営者は、従来のやり方に限界を感じ始めています。求人広告を出しても応募が集まらない。ようやく採用できてもすぐに辞めてしまう。条件や待遇だけで他社と競っていては、採用の質もスピードも上がらない。そんな行き詰まりの中で、新たな突破口として注目されているのが「リファラル採用」です。
本書『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』は、そのリファラル採用を日本で先駆けて実践し、800社以上への導入支援を行ってきた株式会社TalentX代表・鈴木貴史氏による、理論と実務を兼ね備えた一冊です。単なる「社員紹介制度」とは異なり、「社員が自発的に会社を薦めたくなる仕組み」をどう作るか、その仕組みをどう広げていくかを、具体的なステップと豊富な事例を交えながら解説しています。
続きを読む + クリックして下さい
本書が特徴的なのは、リファラル採用という一つの制度を語るだけにとどまらず、採用という営みそのものを「企業文化を伝える行為」として捉え直している点にあります。社員は単なる採用協力者ではなく、企業の魅力を最もリアルに語れる存在であり、その言葉やつながりが、競合とは無縁の独自の採用チャネルを生み出していきます。採用を「外注」ではなく「内発的な行動」として設計し直すことで、コストを抑えながら、文化にフィットする人材を確保することができるのです。
さらに本書は、「なぜ採用がうまくいかないのか」という根本原因に切り込みながら、「どうすれば紹介される会社になれるのか」「社員の心を動かすには何が必要なのか」など、実際の現場で直面する問いにも具体的に答えてくれます。第3章では制度導入の準備方法を、第4章では社員が自発的に動くためのフレームワークを、そして第5章では富士通、博報堂、USEN、モスバーガーなど、導入に成功した企業の実例を紹介。リファラル採用の活用が、どのように採用の成果だけでなく、社員エンゲージメントや企業価値向上にもつながっていくのかを、多角的に解き明かしています。
また、制度を導入した企業が次に目指すべき応用編として、「アルムナイ活用」や「タレントプール形成」など、より中長期的な戦略に踏み込んだ提案も豊富です。そして最後には、採用活動の最前線で求められる新たな役割「採用マーケター」の姿を描き、これからの採用担当者の未来像まで提示しています。

ガイドさん
「紹介される会社」になることは、「信頼される会社」になること。――本書は、採用手法のテクニック本ではなく、企業の在り方そのものを見直すための戦略書であり、組織に本質的な変化をもたらしたいと考える人にこそ手に取ってほしい一冊です。
人材獲得の競争から抜け出し、社員とともにファンを増やしていく採用へ。あなたの会社が“戦わない”選択をする、その第一歩がここにあります。
本の感想・レビュー
私は地方のサービス業で人事をしています。規模も知名度も限られた中で、求人を出しても反応が鈍く、どこか行き詰まりを感じていました。この本で紹介されている、飲食業や中小のSIerがリファラル採用を活用して成果を上げている話は、本当に励まされました。
特に印象的だったのは、社員が「紹介したくなる仕組み」を整えることで、無理なく協力が得られるという点です。私たちも、制度やインセンティブの設計だけでなく、社員が心から「この職場を紹介したい」と思えるような職場づくりをしなければと、改めて思いました。
小さな企業だからこそできる、温度感のある紹介。それを大きな強みに変えるリファラル採用の可能性を、この本は丁寧に示してくれました。今の現場で何ができるか、もう一度前向きに考えるきっかけになりました。
他5件の感想を読む + クリック
私は広報部門で採用ブランディングを担当しています。本書を読んで何より驚いたのは、リファラル採用が「採用」の枠を超えて、企業文化の醸成にまで寄与するという点でした。特に、従業員体験(エンプロイ・ジャーニー)を軸にしたフレームワークの部分には、多くのヒントが詰まっていました。
共感を生むストーリーの設計、ファン化までを含めたステップの中で、社員一人ひとりがどのように会社を体感し、語れるようになるか。これはまさに、組織内に文化を根づかせる営みそのものだと感じました。
採用を点ではなく線、そして面として捉える。そのための考え方と実践例が詰まった本書は、採用担当だけでなく、広報や経営企画の視点からも極めて重要な資料だと思います。
マーケティングの視点から採用を考えることの重要性は、ここ数年感じていましたが、本書はその先の「共感」にまで踏み込んでいます。単に知ってもらうだけでなく、なぜこの会社に入りたいと思ってもらえるのか。その理由を求職者の心に届ける方法を、非常に実践的に解き明かしてくれました。
ストーリーや透明性のある情報の重要性、そして「数字よりも共感」という構造は、自分が目の前で悩んでいた課題を見事に言語化してくれたように思います。特に、紹介を促す際に必要なのは、金銭的インセンティブではなく「語りたくなる体験」だという提言は、目から鱗が落ちる思いでした。
採用を“惹きつけ”の活動ととらえるなら、本書で語られる内容は、その最前線で必要とされる知恵の結晶だと感じます。
これまで、「社内広報」や「従業員満足」といった言葉にはなんとなく距離を感じていましたが、本書を読み終えてみると、「社員がメディアになる」という考え方が、いかに現代的で有効なアプローチかを実感しています。単に社員に紹介をお願いするだけでなく、その社員自身が企業のストーリーテラーとして機能するようにするにはどうすればよいか。そこに深い設計と継続的な仕組みづくりが求められることを、本書は丁寧に示してくれました。
従業員が自社の魅力を自然と語りたくなるためには、業務そのものや働く環境がその語りを支えるものでなければならず、言葉だけでなく、経験に裏打ちされたものが必要なのだと強く感じました。「社内の声が外に届く」――このシンプルで力強いコンセプトに、採用の未来がある気がします。
人材獲得を「競争」や「効率」として捉えがちななかで、本書が提示する「信頼関係をベースにした採用」の考え方は、まさに目から鱗でした。自社で働く社員が、信頼できる人材を推薦する。その関係性こそが、もっとも企業にとっても候補者にとっても負荷の少ない採用の形だという主張には、大きな説得力があります。
リファラル採用が広がることで、企業と社員の関係性そのものも変わっていく。つまり、ただ採用数を追うのではなく、社員の信頼が企業ブランドとなり、その結果として人が集まる構造へとシフトしていくのだと思います。人事担当者としてだけでなく、組織全体の文化に関わるテーマとして読める点が本書の深みです。
人事に関わっていると、「とにかく今月中に人を採らなければ」という焦りと圧迫感が常にあります。本書の中で語られる「戦わない採用」のコンセプトに初めて触れたとき、心の底から救われる思いがしました。なぜなら、これまでの採用活動はまさに“戦い”だったからです。
競合と広告枠を争い、応募者の確保に追われる毎日。そのなかで、リファラル採用は「戦うのではなく、共に歩む」という提案に聞こえました。社員の信頼とつながりの中から候補者が生まれるなら、採用担当者はもっと創造的な仕事に集中できる。そんな未来が描かれているように感じました。
9位 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法
「求人広告を出しても、まったく反応がない」「応募が来ても、面接前に辞退されてしまう」——そんな悩みを抱えている採用担当者の方は少なくないはずです。人材不足が深刻化するなか、特に中小企業や地方の企業では、給与や待遇で大手と勝負することが難しく、「人が集まらないのは仕方がない」と諦めてしまうケースも見られます。
しかし、実は“条件が悪くても”“広告費がゼロでも”応募が集まり、優秀な人材を採用できる手法が存在します。その具体的なノウハウを詰め込んだのが、関根コウ氏による実践書『求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法』です。
続きを読む + クリックして下さい
著者は、全国30か所以上の地方都市で中小企業の採用支援に携わってきた“現場主義”の採用コンサルタント。求人広告の制作・添削は1万件以上、2023年だけで4077人の応募を生み、598人の採用につなげるという圧倒的な成果をあげています。注目すべきは、その多くが「知名度が低い」「給与が高くない」「人が集まりづらい」とされる人口5万〜30万人の地域で成し遂げられているという点です。
本書では、そのような厳しい条件下でも結果を出すための、極めて実践的な採用ノウハウが惜しみなく開示されています。単なる“書き方テクニック”ではなく、「企業の魅力をどう言語化するか」「面接で辞退を防ぐにはどうすべきか」「応募者が共感する情報とは何か」といった、求人全体の設計思想を深く掘り下げており、どのページにも“明日から使える知恵”が詰まっています。
「応募が来ないのは、うちに魅力がないからだろうか?」と感じている方こそ、本書を手に取ってほしい理由がここにあります。著者はこう述べています。「魅力がないのではなく、魅力をうまく伝えられていないだけかもしれません」。その言葉どおり、たった1行のキャッチコピーを変えただけで、応募がゼロだった税理士事務所に25人のエントリーが集まった例など、説得力ある実例が多数収録されています。
「採用がうまくいかない」と悩む企業のほとんどは、必ずしも待遇で見劣りするからではなく、求職者との「情報の接点」が間違っているか、もしくは「伝え方」が不足しているだけなのです。だからこそ本書は、採用の経験が少ない担当者であっても、誰でも読み進めながら具体的に改善に取り組めるように構成されています。

ガイドさん
この一冊には、「採用に困っている会社」が明日からやるべきことがすべて詰まっています。もし今、求人に悩んでいるなら、そしてこれまでのやり方に限界を感じているなら、本書を読むことから新しい一歩が始まるはずです。会社の規模や条件に関係なく、採用は変えられる――その確信とともに、行動に変化を起こすきっかけになることでしょう。
本の感想・レビュー
広告費をかけずに採用なんてできるはずがない。そう思っていた自分の常識が、完全に覆されました。
この本で紹介されている事例の多くは、大都市の話ではありません。地方の、採用が難しいと言われるような場所で、限られた予算でもしっかり人材を集めている。その事実が、何よりも希望になりました。
私は小さな製造業の採用を一人で担当していて、予算がなくなると「もうどうしようもない」と思い詰めていました。でもこの本には、無料でできる方法がたくさん書かれている。しかもそれが机上の空論ではなく、実際に成功しているという事例とセットで書かれている。
これからの採用活動、まずは「お金がないからできない」という言い訳をやめて、目の前の現実を変えていく意志を持とうと、そう思える一冊でした。
続きを読む + クリック
私は現在、九州のとある地方都市で中小企業の人事を担当しています。
応募が来ないのは地方だから仕方がない、そう思っていた自分を恥ずかしく思いました。
この本には、私のような地方で働く人間にとって、希望とも言える事例がいくつも紹介されています。人口が限られたエリアでも、言葉を工夫し、発信方法を見直せば、人はちゃんと集まる。待遇や知名度に頼らなくても、応募者に響く原稿は作れる。そのことを、現実の数字とともに示してくれています。
何より嬉しかったのは、机上の理論ではなく、泥くさい現場に根差した工夫や視点が詰まっていたことです。都会では通用しても、うちのような地域では無理だろうと思っていた。でも、そうではなかった。読んでいるうちに、思わずペンを取って自社の原稿を見直したくなったほどです。
採用の担当になってまだ1年も経っていません。
前任者からの引き継ぎも不十分で、何が正解か分からないまま日々求人媒体に情報を流していました。
そんな私にとってこの本は、まさに「現場で迷う人の手を取ってくれる存在」でした。とくに助かったのが、「社内インタビュー33の質問」です。何を聞けば求人原稿の材料になるのか、それが分からずいつも悩んでいましたが、これを活用すれば自然と話が引き出せる。
また、抽象的な表現ではなく、言葉の一つひとつが現実の場面に根ざしているので、自分の業務にすぐ取り入れられるという実感がありました。経験が浅くても、自信を持って採用に取り組んでいいんだと、そんな気持ちにさせてくれた一冊です。
この本は、いまこの時代に読むべき一冊だと、心からそう思いました。
私たちのような中小企業にとって、採用はもはや「ついでの業務」では済まされません。人口減少や若者の都市集中など、外部環境の変化に翻弄されるなかで、いかにして“人”を確保するかは、企業の存続に直結する課題です。
だからこそ、「採用のために何ができるのか」を正面から考えさせてくれるこの本に出会えたのは大きな意味がありました。書かれている内容は、どれも現実に根ざした具体的な方法論ばかり。企業規模やエリアに関係なく、すぐに実践できる手段が明快に提示されています。
「どうせうちには無理だ」と思っていた気持ちが、「少しでもやってみようか」に変わっていった感覚があります。困難な時代だからこそ、希望を持たせてくれる本でした。
私は長年、人材紹介会社に頼って採用を行ってきました。正直、自力で人を集めるのは無理だと思っていたからです。
ところが、この本を読んでその考えが根本から覆されました。
印象に残っているのは、「紹介に頼るのではなく、自社の魅力を自分たちで言語化して届ける」ことの重要性です。言われてみれば当然のように思えるけれど、これまでやってこなかった。媒体や外部に依存していたことで、かえって自分たちの強みや価値が伝わらない状況を招いていたのだと気づかされました。
なかでもリファラル採用の具体的な進め方はとても参考になりました。社内にいる既存の社員が“次の採用の鍵”になるという考え方は、紹介会社では絶対に得られない視点です。自社で採用を回す力を育てる——それが今後の鍵になると感じました。
この本は、求人や採用に関わるすべての人に手に取ってほしい一冊だと、心から思います。
内容がとにかく実践的で、しかも理論だけではなく、地方や中小企業の実例が豊富に紹介されている。だからこそ、現場で働く私たちにとって「自分ごと」として読み進めることができました。
どんなに規模が小さくても、知名度がなくても、人は採れる。その確信を持てたのは、この本に出会えたおかげです。そしてそれは、決して特別なスキルやツールが必要なわけではなく、採用の考え方を少し変え、自社をきちんと見つめ直すことで実現できるのだとわかりました。
「条件が悪いから応募が来ない」という言い訳をする前に、できることはまだまだある。そんな前向きな気持ちにさせてくれる内容で、読み終えた後には清々しさすら感じました。これから採用に関わるすべての仲間に、ぜひ勧めたい一冊です。
10位 採用がうまくいく会社がやっていること
中小企業の採用は年々難しさを増しています。求人を出しても応募が集まらない、ようやく採用できても早期に辞めてしまう、そんな悩みを抱える経営者や採用担当者は少なくありません。人手不足、価値観の多様化、働き方の変化といった時代背景が重なり、採用はもはや「人を募集するだけ」の作業ではなく、企業の未来を左右する重要な経営課題となっています。
そうした現実を真正面から捉え、「中小企業が今すぐ実践できる採用の具体策」を体系的にまとめたのが、書籍『採用がうまくいく会社がやっていること』です。本書は、社労士として数多くの中小企業の採用を支援してきた著者が、実務の現場で培ったノウハウを惜しみなく公開した一冊であり、理論だけでなく現実に即した方法論が丁寧に整理されています。
続きを読む + クリックして下さい
現代の求職者は、応募前に企業や業界の情報をインターネットで細かく調べるのが当たり前です。良い情報だけでなく、悪い情報も含めて比較検討したうえで応募先を決めるため、企業側がどれだけ誠実に情報を発信できているかが、応募数や人材の質に大きな影響を与えます。本書は、こうした情報環境の変化を前提に、採用活動をどのように組み立て直すべきかを具体的に示しています。
また、独立志向の高まりや働き方の多様化により、「会社に勤めたい人」が減っているという厳しい現実にも触れられています。その一方で、中小企業だからこそ発揮できる強みや、大企業とは異なる戦い方があることも、本書では明確に語られています。採用市場の不利な状況だけを嘆くのではなく、視点を変えることで活路が見えてくる点が、本書の大きな特徴です。
本書では、求人原稿の作り方、求人媒体の使い分け、面接時の見極め方、内定から入社前後のフォロー、入社後の定着支援まで、採用の流れを一貫して学ぶことができます。採用活動を部分的に改善するのではなく、「採用から定着まで」をひとつの流れとして捉え直すことで、企業と人材のミスマッチを減らしていく考え方が貫かれています。

ガイドさん
採用に対して苦手意識を持っている経営者や管理職、初めて人を雇う立場の人にとって、本書は「何から手をつければいいのか」を明確にしてくれる道しるべのような存在です。
採用を運や偶然に頼るのではなく、きちんとした取り組みとして積み上げていくことの大切さを、静かに、しかし力強く伝えてくれる一冊だといえるでしょう。
本の感想・レビュー
これまで採用というものを、求人を出して、面接して、良さそうなら採る、という極めて断片的なイメージで捉えていました。この本を読み進めるうちに、採用は思っていた以上に多くの工程で成り立っていて、それぞれの段階に意味と役割があるのだと気づかされました。第1章で採用の土台となる考え方が示され、第2章で求人、第3章で面接、第4章で内定後のフォロー、第5章で定着までと、流れが非常に整理されているため、頭の中でバラバラだった採用業務が一本の線としてつながっていく感覚がありました。
採用に関する情報はネットにも溢れていますが、たいていは「求人の書き方」や「面接のコツ」など、一部分だけを切り取った内容が多い印象でした。その点、この本は採用活動の全体像を一冊で俯瞰できる構成になっているため、「今、自分がどの段階にいて、何が足りていないのか」が自然と見えてきます。採用がうまくいかない理由を、感覚や運任せで片付けずに、構造的に理解できるようになったのは大きな収穫でした。
読み終えた後、これまで場当たり的にやっていた採用が、実は順番や準備を大きく間違えていたのかもしれないと感じました。採用活動を「作業」ではなく「設計されたプロセス」として捉え直せたことで、これから何から手をつけるべきかがはっきりした点が、この本を読んで最初に感じた一番の価値だったと思います。
他5件の感想を読む + クリック
世の中にある採用本の多くは、大企業や人事部がある会社を前提に書かれているものが多く、読んでも「うちの規模では無理だな」と感じることが正直ありました。しかし、この本は最初から一貫して中小企業の現実を前提に話が進みます。採用にかけられる予算、やれる人手、知名度の低さなど、理想ではなく現実に寄り添っている点が非常に印象的でした。
求人媒体の使い分けや、ハローワーク、無料求人媒体、人材紹介会社、社員紹介などの扱い方も、中小企業が無理なく使える範囲に絞って解説されています。限られた条件の中でどう戦うか、どう工夫するかという視点で書かれているため、「小さい会社だから仕方ない」と諦めていた部分に、まだ改善の余地があるのだと感じられました。
中小企業向けの採用ノウハウは意外とまとまった形で学べるものが少ない中で、この本はまさに「中小企業専用の採用教科書」のような存在だと思いました。自社の状況と重ねながら読み進められる実用性の高さは、他の採用書籍にはなかなかない魅力だと感じます。
読み始める前は、「結局、大企業には勝てないのではないか」という諦めのような気持ちがどこかにありました。しかし、第1章を読み進めるうちに、その考え方自体が大きく揺さぶられました。小さな会社には小さな会社ならではの強みがあり、それは大企業には簡単に真似できないものであるという視点が、非常に説得力を持って語られています。
環境、コスト、価値観という三つの視点から採用を考えるという考え方も印象的でした。給与や知名度だけでは勝負できなくても、働く環境の整え方や、会社の考え方の伝え方次第で、十分に求職者に選ばれる存在になれるのだと感じました。「勝てる方法がある」と理屈で理解できたことで、採用に対する姿勢そのものが前向きに変わった気がします。
小さな会社だから不利なのではなく、小さな会社だからこそできることがある。そのことを具体的な視点で教えてくれた点で、この本は単なるノウハウ本ではなく、採用に向き合う姿勢そのものを変えてくれる一冊だと感じました。
最もありがたかったのは、求人の出し方だけでなく、面接、内定、入社後のフォローまで一貫して学べる点でした。採用の本というと、どうしても「応募を集めるところ」だけに焦点が当たりがちですが、この本は採った後のことまでしっかり視野に入れて構成されています。「採用は入社がゴールではない」というメッセージが、章構成そのものから伝わってきました。
内定後の書類の扱い方や、入社前面談の意味、さらには入社初日の対応やその後の面談まで、定着につなげるための段階が細かく整理されています。採用と定着が分断された別の問題ではなく、一本の流れとして連続しているのだということを、この本を通して初めてしっかり理解できました。
求人で集め、面接で見極め、内定でつなぎ、入社後に育てて定着させる。この一連の流れを一冊で俯瞰しながら学べるところに、この本の総合力の強さを感じました。採用について体系的に学びたい人にとって、最初に手に取る一冊として非常に相性が良いと感じます。
採用に関わるようになってから、私はずっと漠然とした不安を抱えていました。これで本当に合っているのか、失敗したらどうなるのか、自分の判断で人の人生を左右してしまうのではないかという怖さもありました。この本を読んで、その不安の正体は「何を基準に考えればいいのかが分からないこと」だったのだと気づきました。
本書では、採用が厳しくなっている社会背景や、求職者の心理、大企業と中小企業の採用の差といった現実が、はじめにの章で丁寧に整理されています。その上で、「それでも中小企業にはできることがある」というメッセージが繰り返し伝えられます。ただ不安をあおるのではなく、「構造を知ることで怖さは小さくなる」という感覚が自然と芽生えてきました。
読み終えたとき、不思議と採用に対する緊張感はありながらも、「やることが見えている安心感」を持てるようになっていました。不安そのものを否定せず、どう向き合えばいいのかを教えてくれる点で、この本は採用担当者の心を支えてくれる存在だと感じました。
これまで求人が集まらない理由を、外部環境のせいだと考えていました。しかし本書を読み、「環境を整える」という視点が、こんなにも採用に直結しているのかと衝撃を受けました。給与、労働時間、休日数、作業環境、人間関係、アクセス――これらの要素がどれだけ求職者に影響しているのかを、著者は非常に分かりやすく整理しています。
特に、自社が「当たり前」だと思っている条件が、求職者にとっては応募をためらう大きな理由になり得る、という説明が心に刺さりました。改善できる部分を見ずに、「応募が来ないのは景気のせい」と思い込んでいた自分を反省しました。環境を整えることは、決して贅沢ではなく、採用活動の前提そのものなのだと理解できました。
読み終えたころには、「人が来ない会社」ではなく「人が来たくなる会社」に変えていくために、自社がどこまで具体的に改善できるのかを真剣に考えるようになりました。本書がなければ、この視点は一生持てなかったと思います。